1996年12月、南米ペルーの首都リマで発生した在ペルー日本大使公邸占拠事件は、日本と世界を震撼させた国際的テロ事件である。過激派組織トゥパク・アマル革命運動(MRTA)が日本大使の公邸を襲撃し、要人や外交関係者を含む数百名を人質に取って立てこもったこの事件は、最終的にペルー軍の強行突入作戦「チャビン・デ・ワンタル(Chavín de Huántar」によって幕を閉じた。
日本とペルーは歴史的、文化的に非常に重要なつながりを持っている。当時の首相はアルベルト・フジモリ。日系ペルー人であった。
現地での人質保護の主導権はあくまでペルー当局にあったものの、この事件の背後では、日本政府も重大な判断を迫られていた。日本の警察庁も事態の推移を注視し、一時は日本側も突入部隊(SAT)の派遣を検討していたという報道があったのだ。
本稿では、事件の概要とともに、ペルー側特殊部隊の突入に使われたP90という火器の特性、日本警察が現実に行動を起こす可能性はあったのか――その事実と推測を分けて検証する。
1996年に発生した「在ペルー日本国大使公邸占拠事件」に関連して
1996年末、在ペルー日本大使公邸での祝賀会の最中に、武装勢力MRTAのメンバーが押し入り、600人を超える要人や外交官を人質にとるという事件が起きた。この事件は4ヶ月以上にわたり続き、最終的にペルー政府は、1997年4月22日午後3時23分(日本時間23日午前5時23分)、ペルー軍の特殊部隊による「チャビン・デ・ワンタル作戦」を敢行し、突入が実行された。
軍特殊部隊約140人を大使公邸に突入させた結果、人質72人のうち、ペルー最高裁判事1人が死亡したが、日本人24人を含む残る71人は、事件発生から127日目に救出された。一方、銃撃戦の末、ペルー軍の特殊部隊の隊員2人が死亡し、犯人グループは、14人全員が死亡した。
日本警察が国内で突入シミュレーションを実施
本事件は在外公館での武力テロという極めて異例の状況であったが、日本警察も全くの傍観者ではなかった。1997年版の警察白書によれば、事件発生後、外務省を中心とした関係省庁間での危機対応会議が開催され、警察庁もそこに加わって情報共有や治安対応策を協議していた。
そして、事実上の解決策として、警視庁SATが原寸大の模擬日本大使館を造り、人質救出訓練と突入シミュレーションを極秘裏に実施していたと伝えられている。また、神奈川県警察SATも隊員をドイツに派遣し、GSG-9から訓練を受けたという。
これは、現地の情勢が長期化する中で、日本の警察力による解決を図りたいという思惑もあったとされ、国内でも万一の事態に備えた訓練が必要と判断されたことによるもの。現地警察・軍による対応が不十分である場合や、交渉決裂・強硬突入の必要が生じた場合を想定し、SAT(特殊急襲部隊)や銃器対策部隊の海外派遣を検討していたことは衝撃的な事実だが、これは主権国家内での作戦となるため、非常に慎重な手続きと外交交渉を要する。しかし、「最悪のシナリオ」に備えるという意味では現実的なオプションの一つだったと考えられる。
ただし、あくまで作戦指揮権はペルー政府にあり、日本側の直接介入は外交的にも困難とされた。結果として、日本の警察コマンドが実際にリマへ派遣されることはなく、あくまで突入計画は「想定レベル」でとどまった。

なお、平成9年警察白書によれば、同事件で日本警察が行った活動は、情報収集のための現地対策本部への要員(オブザーバー)派遣、警察病院の医師、看護師の派遣および医療支援活動、人質解放後の現場検証支援のための職員および資機材派遣といった後方支援にとどまっており、警察庁の公式発表にSATが現地で作戦に直接参加したという情報はない。
【出典】
-
警察庁『平成9年 警察白書』第1節 国際テロ情勢 1 在ペルー日本国大使公邸占拠事件
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h09/h090101.html - 伊藤鋼一『警視庁・特殊部隊の真実』大日本絵画(警視庁特殊部隊の元隊員)
ペルー特殊部隊とP90
「チャビン・デ・ワンタル作戦」で注目されたのは、ペルー軍が使ったベルギーFN社のP90(5.7×28mm弾を使用するPDW)であった。当時、先進諸国の対テロ部隊ではMP5が主流であり、ペルー軍特殊部隊もサプレッサー仕様のMP5SDを携行していた。
FN P90(エフエヌ・ピーナインティ)は、ベルギーのFNハースタル社が開発した個人防護火器(PDW:Personal Defense Weapon)である。
当時としては世界的にも最先端の火器であり、事実上、P90の大々的な対テロ作戦投入は今回の事件が初とされる。ペルー軍がいかに「最短時間で制圧する」というコンセプトを徹底していたかがわかる選択である。
1980年代末から1990年代初頭にかけて、「従来の拳銃弾ではボディアーマーを貫通できない」という問題に対処すべく設計され、5.7×28mm弾という高速・小口径の弾薬を使用することで、防弾チョッキ越しでも有効な貫通力と制圧力を両立した。
実際、今回のテロ事件の首謀者である過激派組織トゥパク・アマル革命運動(MRTA)は防弾チョッキを着用しており、通常の9mm弾を使うMP5では作戦遂行が困難とされた。
P90の最大の特徴は、水平装填の50連トランスバースマガジンと、ブルパップ構造による極端なコンパクトさにある。これにより、狭い建物内部や車両内などの閉所での取り回しが抜群によく、近接戦闘(CQB)における理想的な装備とされてきた。

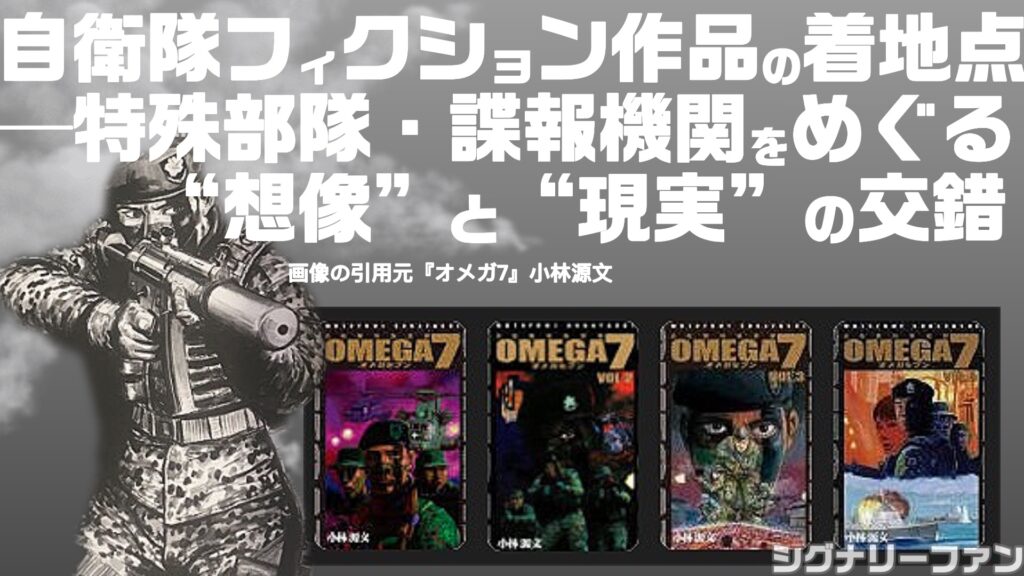
未遂に終わった日本警察特殊部隊の“海外実戦展開”
在ペルー日本大使公邸占拠事件は、海外在留邦人保護に関する日本の危機管理体制を大きく揺さぶった事件であった。その後、政府は国際テロ対策の強化に踏み切り、SATをはじめとする特殊部隊の装備・訓練も高度化していくこととなる。
結果として、日本の警察部隊がリマで実戦投入されることはなかったが、「警察特殊部隊の国外作戦」構想が内部で真剣に議論され、実戦想定の訓練まで実施されていたことは見逃せない事実である。
また、作戦に投入された「P90」に関しては、日本警察が関心を持った可能性もあるが、少なくとも当時の警察部隊にP90の実戦配備は確認されていない。SATや銃器対策部隊において、同種の「連射できる火器」の導入が初めて公開されたのは、ずっと後の2002年である。

参考資料・出典
-
FN Herstal(製造元公式) – P90 標準モデル紹介ページ
https://fnherstal.com/en/defence/portable-weapons/fn-p90/ -
FN America(米国版公式) – PS90 民間モデル紹介
https://fnamerica.com/products/rifles/fn-ps90-standard/ -
Wikipedia(英語) – FN P90 の全体解説
https://en.wikipedia.org/wiki/FN_P90 -
Modern Firearms – FN P90 詳細解説(構造・運用・背景)
http://modernfirearms.net/en/submachine-guns/belgium-submachine-guns/fn-p90-eng/ - SOFREP – 特殊部隊視点での開発と戦術評価
 The FN P90: A Special Operations and Personal Defense PowerhouseLearn about the FN P90, a compact and powerful weapon designed for versatility and reliability in military and law enfor...
The FN P90: A Special Operations and Personal Defense PowerhouseLearn about the FN P90, a compact and powerful weapon designed for versatility and reliability in military and law enfor... -
Hyperdouraku – 東京マルイ製「P90」レビュー(エアソフト)
https://www.hyperdouraku.com/airgun/p90/index.html
















































































































