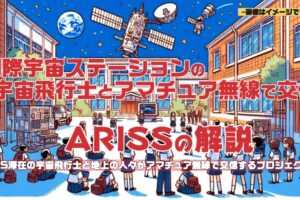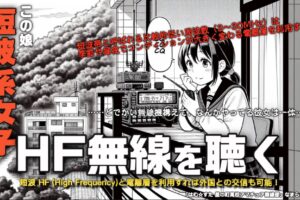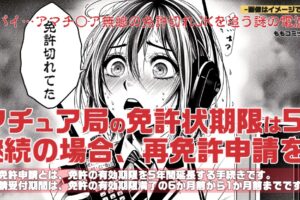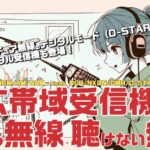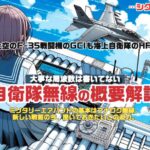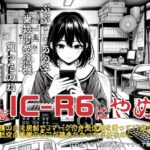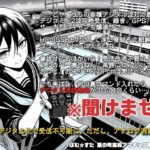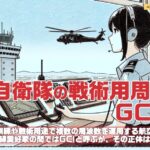Contents
2011年3月11日に発生した東日本大震災は多くの方々が津波や建物の崩壊等により亡くなり、避難の方法や救援の呼びかけ方など、防災における多くの教訓を私たちに残しました。多くの専門家の方々、その道のプロの方々、各方面が防災や減災に努めようと弛まぬ研究をされている現状です。
そして万が一の災害発生時に携帯電話等での救援要請が行えなくなってしまった場合、私たち一般のアマチュア無線局も、その立場から減災に貢献できるボランティア活動があります。それが本項でご紹介する『非常通信』です。
非常通信とは?
無線局は原則、電波法第52条により、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない決まりです。アマチュア無線局であれば、本来許されているのは『アマチュア業務』のみとなっており、令和5年現在、総務省が認めているアマチュア無線で行える行為は通信実験および、地域ボランティアなど社会貢献活動等での活用です。
ただし、同法第52条の第4号の規定に基づく非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信)等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用ができます。
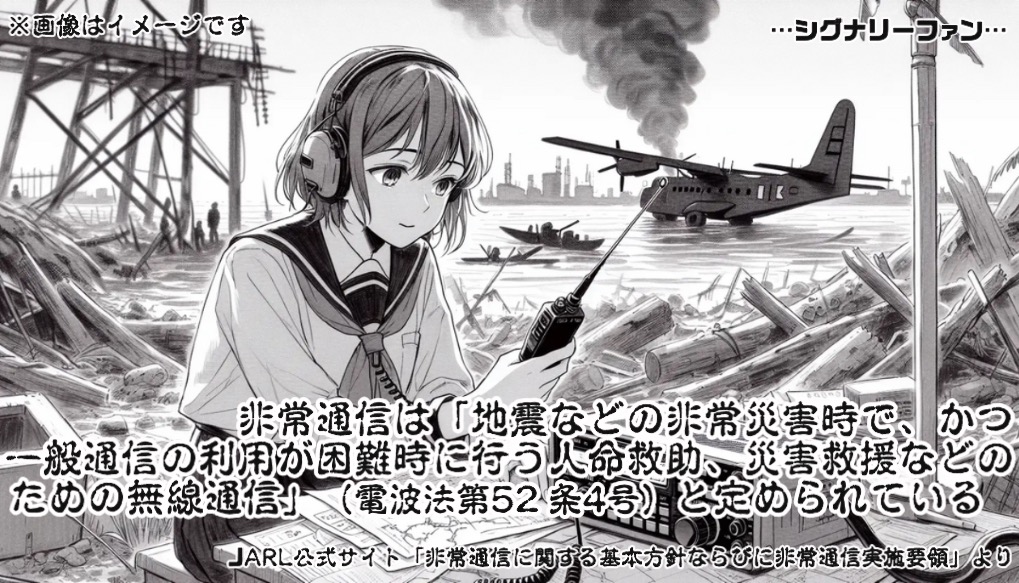
これがアマチュア無線を使って非常通信ができる根拠となっています。JARL公式サイトでは『アマチュア局の非常通信マニュアル(PDFファイル)』として、その詳しい手順を示しています。
アマチュア無線が災害時に有用である理由
通信インフラが強固
2008年に公開されたスタジオジブリのアニメーション映画『崖の上のポニョ』は、子供向けのファンタジー映画でありながら、災害や緊急時の対応についても考えさせられる要素が含まれています。
基本的に携帯電話回線やモバイル通信などの通信インフラは基地局を介した中継通信です。地震や台風などの災害が発生すると、設備の損傷、電力の供給が不安定になるなどして基地局の機能が停止し、通信が行えない場合があります。
一方、アマチュア無線局のうち、自宅等の固定局は通常、家庭用のコンセントからの電源供給で運用される場合が多いものの、前述のアニメ映画同様、発電機があれば停電時でも稼働でき、ハンディ無線機や自家用車に備えられたモービル無線機であれば、通常は独立した電源を使用するため、充電池や車の燃料が続く限りは災害が発生しても通信を維持することができます。
さらに、アマチュア無線では基本的に相手の無線機と直接交信(レピーターを介した中継通信も可能です)しますから、大災害発生時においては全国に38万局(令和2年度時点)あるアマチュア無線局の大きなネットワーク特性を活かし、地域を超えた救援の通信を行うことができます。これらが災害時にアマチュア無線が有用である理由であり、広域かつ速やかな情報伝達手段として優れていると言えます。
これまで95年1月の阪神大震災、2011年3月の東日本大震災ではアマチュア無線が被災地からの通信、人命救助に貢献しています。
非常通信の性格は『ボランティア精神』
総務省によれば、実際の非常時において、非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用できないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断は、アマチュア局の免許人が判断するものであり、非常通信は状況に応じてアマチュア局が柔軟に行えるものとしています。ただし、その際アマチュア局の免許人はあくまでボランティア精神で行うものとしています。
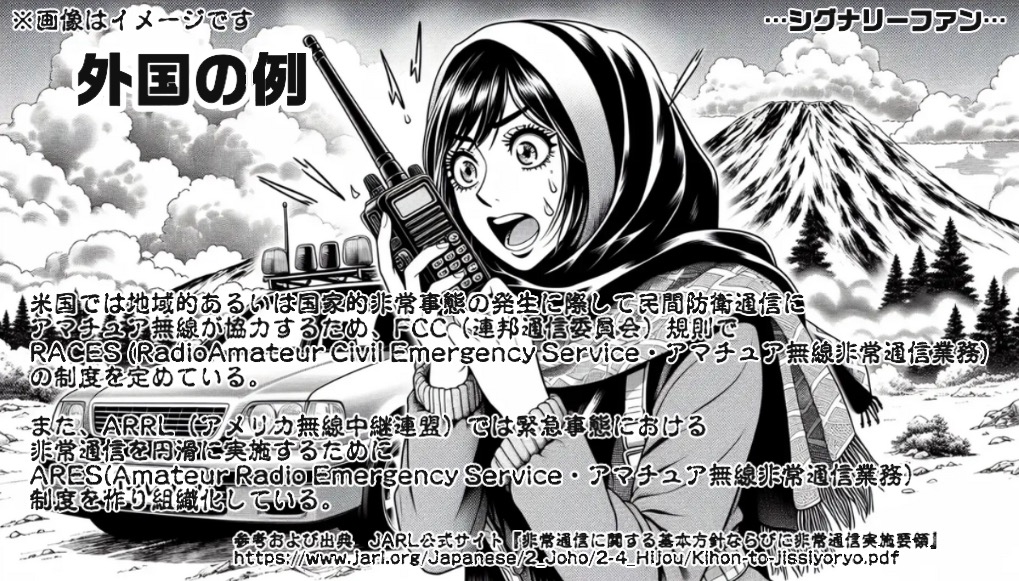
非常通信に準じた制度は外国でも同じく、実施されています。
社会貢献活動等によるアマチュア無線の活用が可能になったことで「非常通信」は変わる?
総務省の方針は『今後も非常通信の制度に変更なし』
今般、民間ボランティア、公務員などによる地域活動など、社会貢献活動によるアマチュア無線の活用が認められましたが、総務省では災害時等における非常通信について、今後も制度に変わりはないとしてます。総務省では社会貢献活動によるアマチュア無線の活用により、非常通信であるかどうかにかかわらず、非常災害時(事前・直前準備、訓練含む。)から災害復旧時まで、継ぎ目のない支援がアマチュア無線により行うことが可能となったとしており、アマチュア無線の社会貢献活動等の範囲内の運用であれば、非常通信の報告(電波法第80条第1項)についても不要となるとしています。
※出典 総務省電波利用ホームページ アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方
非常通信の際は呼び出し周波数または非常通信周波数を使用
非常通信はアマチュア局に認めらたアマチュアバンド内において通常行われますが、その際はHFからUHFの各帯域ごとに定められた呼び出し周波数または非常通信周波数を使用します。例えば、VHFの144MHz帯では145,00MHzは呼び出し周波数兼非常通信周波数となっているほか、145,50MHzが非常通信周波数となっています。
参考サイト 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟『アマチュアバンドプラン(PDFファイル)』 https://www.jarl.org › bandplan20200421 PDF
当サイトでも、一般的な非常通信用周波数や災害時に活発になる無線の周波数を以下の記事でまとめています。
万が一の非常通信に備え、あらかじめの資格取得と局免を
電波法を基にした一般論ですが、平時におけるアマチュア無線の運用で従事者免許証(資格)と無線局免許状(局免)が必要であるように、万が一の災害発生時にアマチュア無線で非常通信を行う場合に備えて無線機を自宅や車に設置しておく場合でも、必ずあらかじめ資格を取得し、開局申請して局免交付を受けるようお願いいたします。
『非常通信』と類似する通信に『遭難通信』があります。『遭難』という言葉のイメージから、山岳地帯で登山者が陥った非常事態を連想させますが、本来、遭難通信は船舶の海難ならびに航空機の重大な危機が発生した場合に行われる緊急の通信です。したがって、山岳での遭難などは前述の『非常通信』を行うこととなります。
普段からの電波のコンディションチェックや、どの場所から送信した場合に遠距離と交信できるかの確認のためにも、平時からコミニュケーションと訓練を兼ねた運用がおすすめです。
非常通信について参考になるサイト
非常通人における公的機関やJARLの考え方は下記URLを参考にされてください。
総務省アマチュア局による非常通信の考え方
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/amahijyo/JARL
アマチュア無線局の非常通信マニュアル
http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-4_Hijou/index-manual.htm
また、http://www.cosmos.zaq.jp/cosmos/team7043/kanham2013_bou_jarloo.pdfではJARLの職員で元電波監理局職員の方の防災シンポジウムにおけるアマチュア局の非常通信訓練のあり方に関する発言録ですが、非常通信の実際の実施と実施後の総務省への対応などが事細かく記載されていて大変興味深いです。
この中で、実際の非常通信においては「”非常”は三回でなくてもいい」とか「非常通信を行ったからといって、総務省にあとで怒られることはありません。むしろ人命を救助すれば電波の日に表彰されます」など興味深いお話がいっぱいです。このようにアマチュア無線による非常通信は万が一の災害時、人命救助にも活用されています。
2014年、熊本県で震災をきっかけにお坊さんグループが防災チーム結成
災害時、このようなボランティアで非常通信を行うため、全国各地にはアマチュア無線家で構成された協力団体がそれぞれ設置され、普段から自治体や消防などと合同で訓練を行っています。熊本県で2014年に編成された僧侶らの防災チーム「浄土真宗本願寺派熊本教区アマチュア無線リーグJKAL」では、アマチュア無線を使った災害時の情報収集と人命救助を活動目標としています。JKAL設立に携わったのは浄土真宗本願寺派熊本教区の10人の僧侶ならびに6人の門徒だそうです。中でも正元寺の寺添和南住職は若いころのエピソードとして、交通事故の現場に遭遇し、アマチュア無線による救助要請を行ったことでアマチュア無線は『命綱』であると認識されたそうです。寺添住職はメンバーとともに愛車に何本もアンテナを立てて車載無線機を積み込み、非常事態に備えています。
典拠元 https://www.asahi.com/articles/ASLBH3CGYLBCTLVB004.html
まとめ
以上のように、非常通信は災害時にとても重要な役割を担っている通信として、過去の災害でも行われてきました。アマチュア無線は通信手段としては最古のテクノロジーですが、災害時に最も力強い通信手段であり、アマチュア無線家は被災時の通信確保に頼りになる存在です。この信頼性の最も高い防災通信拠点が日本の全国いたるところにすでに広く点在するわけですから、アマチュア無線は我々が今後も後世に残していかなければならない文化ですし、減災技術であります。

- 電波法第52条に「非常通信」が定められ、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生した場合、その通信が認められている
- 非常の事態が発生し又は発生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用できないか又はこれを利用することが著しく困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの判断はアマチュア局の免許人の柔軟な判断に委ねられている
- アマチュア局の免許人はあくまでもボランティアで非常通信を行う
- 非常通信であっても、あらかじめ無線従事者資格と局の免許状を取得していなければ使用はできない
このようにまとまりました。
なお、テレビアニメ『ミームいろいろ夢の旅』の第73話(1984年)にて、まさにアマチュア無線と非常通信について言及されており、非常に興味深いため、下記ページにて詳しく解説しています。


![CQ ham radio (ハムラジオ) 2009年 08月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/517gVsvKyqL._SL500_.jpg)