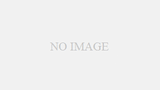画像は米国マサチューセッツ州警察の配備例 出典 The MP5SDs of the Massachusetts State Police. In around 5/1/2003.
安全保障系のブロガー界隈では、小林源文作品を好む方も少なくない。
その中でも、90年代の初冬に発表された『自衛隊特殊部隊オメガ7』は、架空の自衛隊特殊部隊や非正規戦を非常に早い時期からリアルに描写した点で、現在も一定の評価を得ている。
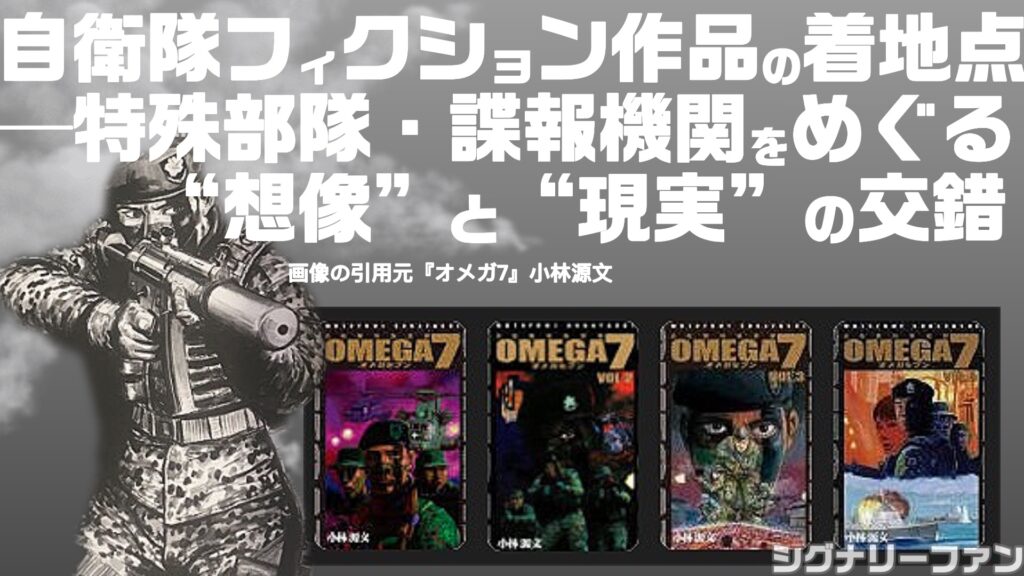
劇中でオメガ部隊に初期配備されていたのが、圧倒的な静穏性を誇るサプレッサーを標準搭載したHeckler & Kochのサブマシンガン「MP5SD6」である。
敵勢力の背後に密かに忍び寄る特殊部隊の象徴として運用されていた。
今回は、その「MP5SD」シリーズが日本の警察当局に、早い段階から実際に配備されていたという衝撃の事実をお伝えし、その性能を解説してみたい。
日本警察におけるMP5とMP5SDの配備
すでに当サイトで解説している通り、「MP5」は日本の警察庁が「警察白書」において、その性能を高く評価し、全国の機動隊や特殊部隊SATに配備している9mm口径の「機関けん銃(サブマシンガン)」である。

MP5系の標準的ローデータとして約 800発/分程度のサイクルを持ち、近接戦・室内戦(CQB)向けの安定した制御性が評価されている。
狙撃銃にも匹敵する命中率を誇り、世界各国で運用されるMP5。
中でも国際的に注目されたきっかけの一つが、1977年のルフトハンザ機ハイジャック(Lufthansa Flight 181/「Landshut」)における、西ドイツ対テロ特殊部隊GSG9による人質救出作戦「Operation Feuerzauber(ファイアーザウバー作戦または マジック・ファイア作戦)」だ。
このオペレーション マジックファイアこそ、ヘッケラー&コッホ MP5が実戦投入された最初の作戦であり、この成功によってMP5の銃としての評価は一気に高まった。
出典 アームズマガジン公式サイト https://armsweb.jp/report/1786.html
この作戦ではMP5が戦術的に用いられ、その後の対テロ部隊装備と運用に大きな影響を与えた。
MP5SD含め同系統の採用は、密室での火力制御や静粛行動を重視する部隊に評価された。
ただし、現代では9mm口径の貫徹力不足が指摘されていることに留意が必要だ。

米国の警察機関やFBIの特殊部隊などではM4系へ装備更新する事例も多く、それまでパトカーに搭載されていた備え付けのMP5やショットガンもパトロールライフルとしてM4が多くなっている。

日本でのMP5SDの配備事例
日本では警察庁が、ほぼオリジナルのMP5A5の配備を公に認めたのが2002年の、いわゆる「警視庁SAT訓練ビデオの公開」だ。
その背景には、2002年のFIFAワールドカップ日韓大会を控え、テロの抑止を高める狙いがあったが、日本が特殊部隊の装備に関する情報を公にすることは、秘密主義の過剰な警察当局において非常に珍しい出来事だった。
ただし、実際には95年のSAT正式発足発表後、90年代後半のミリタリー・タクティカル系フィクション作品などのブームにより、SATの装備と部隊概要は、米国のSWATに準じたものであると、広く世間一般に知られていたと考えられる。
ところが、驚くべきことに、日本の警察特殊部隊では1970年代からMP5が配備されていたという証言がある。
これは元・警視庁警察官である伊藤鋼一氏の著書『警視庁・特殊部隊の真実(大日本絵画、2004年)』からの情報である。
元・警視庁SAP隊員であった伊藤鋼一氏のインタビュー記事は当サイトでも、「SATになれる条件」の事例として紹介している。

当時、警察の特殊部隊は非公然とされていたが、警視庁では「SAP」、大阪府警では「零中隊」と呼ばれていた。

そして、部隊にはサプレッサーが標準装備されたMP5SDが一部配備されていたという。
一方で、実在の自衛隊特殊部隊では「MP5SD」が使用されたことを裏付けるような資料や関係者の声は皆無に近いものの、陸上自衛隊がSNSで公開している動画で以下のようなものがチラリと映っている。

画像の出典 陸上自衛隊公式SNS
手前の熊撃ちライフルではなく、その奥に見える銃である。これは明らかに、MP5SDの特徴である。
今回はMP5SDの特徴と性能に迫ろう。
サプレッサーを標準搭載したMP5SDシリーズ
MP5SD シリーズは、ドイツのヘッケラー&コッホ(Heckler & Koch)が、成功したMP5シリーズの派生として開発したサプレッサー(サイレンサー)一体型(integral suppressor)モデルである。
伸縮式ストックのMP5SD6、固定ストックのMP5SD5が知られている。
製品説明やメーカー資料ではサプレッサーにより、マズルフラッシュ抑制され、夜間暗視装置下での視認性低下を防ぐ点が強調されているほか、発砲音低減で優位になり、夜間および密室での奇襲性を高めるとしてる。
MP5SDシリーズは作動信頼性と相まって、CQB(近接戦)での射撃が容易だ。
サプレッサーの仕組み
最も重要な点であるMP5SDのサプレッサーとはどのような仕組みになっているのか、改めて検証してみよう。
技術と基本性能
MP5SDは一体型消音機構により、短い銃身と消音ユニットを組み合わせ、バッフル(隔壁)構造などにより発射ガスを銃内部で拡散・冷却し、膨張・噴出を抑えことで弾丸の音(ソニックブーム)とマズルフラッシュの双方を低減する。
MP5SDは通常弾(必ずしもサブソニック弾を要求しない)でも顕著な静音化効果が得られるのが特徴である。
MP5SDはポーテッドバレルの効果により、必ずしもサブソニック弾の使用を前提としない。
つまり標準的な9×19mm弾薬でも一定の静音効果が期待できるが、弾速や弾着性能は使用弾薬に依存するため、運用上は静音効果と弾道性能のトレードオフを考慮する必要がある。
MP5SDの消音性能は
短く結論を先に言うと、「当時の警視庁特殊部隊などが配備していたMP5SDの消音(正確には低騒音化)性能は一般的な9mm短銃器より明らかに高いが、「完全無音」ではない。
さらに言えば、使う弾薬で、その発射音は全く変わるのが実情だ。
ある解説ではピークノイズで約70 dB(大声と同レベル)と記載される例もあるが、別の実測やフォーラムでは125〜128 dB程度という値も報告されている。
これは(A)使用した弾薬(完全にサブソニックか否か)、(B)測定距離とマイクの仕様(ピーク値か等価値か)、(C)屋内/屋外など環境、(D)消音器の型や整備状態で大きく変動するためである。
したがって単一の数値で「非常に静か」と断定するのは誤解を招きやすい。
測定条件や弾薬で聴感上の差が大きく、報告される数値には測り方で幅がある、というのが事実といえる。
また短所としては、消音器内部に炭素やカーボンが堆積しやすく、清掃・整備を怠ると性能低下や「固着(ロック)」の問題が生じる点(過去の設計・運用で指摘された)。また周囲の反射や近距離での聴感は依然“鋭い音”を伴うため、完全な秘匿は期待できない点などがある。
まとめ
MP5SDをオリジナルのMP5と比べた場合、静音性はあるが、使う弾種に依存するのが実情である。つまり、現実的に言えば銃の発射音を抑えるためには、サプレッサーだけでは不足するのである。
では、どんな弾丸を使うのか。
次回の記事では、サプレッサーと組み合わせて使う特殊な弾丸『サブソニック弾』について考察してみよう。