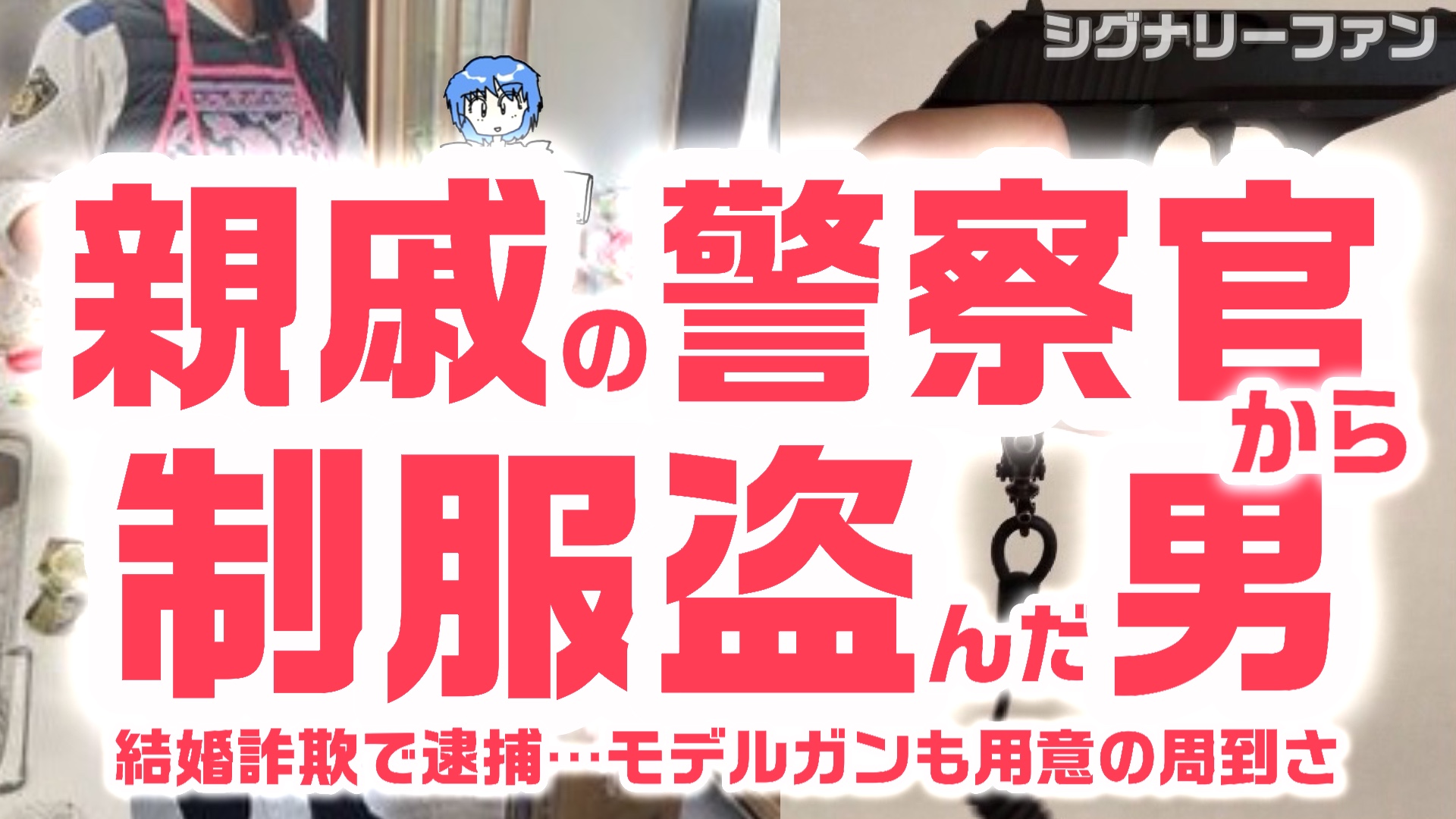「警官」という言葉に、実は警察当局が強い違和感を抱いている──。
普段の会話やニュースでもよく耳にする「警官」という表現。しかし福岡県警察本部は、ある事件報道でのこうした呼び方に対して「やめてほしい」と異例の要請を行っています。「警察官」と「警官」、この二つの言葉の背後には意外な温度差が存在しているようです。その理由とは何なのか、探っていきましょう。
「警察官」と「警官」——その呼び方に、意味の違いはあるのか?
広辞苑では『警官』は警察官の“通称”となっており、このため、『警官』という言葉は単に警察官の一般的な略であると考える人が多いのではないでしょうか。
ところが、一見、言葉の短縮に過ぎないように思える『警官』は、当事者からすれば「蔑称」として受け取られています。

「警察官に対する蔑称」と聞くと、あからさまに侮辱的な表現を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし、そうした極端なケースに限らず、一般的には差し障りのないと思われている「警官」という呼称が、実際にある警察本部の正式な訂正要求の事例を見る限り、現場に立つ警察官にとっては限りなく屈辱的に響くこともあるということがわかります。
また、元警察官からも、「軽んじられているようだ」といった声もあります。
調べていくと、単に呼びやすく便利な略称として、警察官の“通称”である『警官』を簡単には使えない背景がありました。
その理由を見ていきましょう。
なぜ報道では「警官」と言わないのか?——言葉に宿る“敬意”のかたち
日本国内の事件や事故に関する報道において、警察官のことを「警官」と表現することは、メディアの現場ではあまり見られないのが通例です。普段、新聞記事を丁寧に読み進めても、「警官」という表記にはなかなかお目にかかれません。紙面では「警察官」「署員」「捜査員」このような表現が多いのではないでしょうか。
この点について、読売テレビアナウンサーの道浦俊彦氏がご自身の連載『道浦TIME』において、報道現場の立場から詳細に解説されています。
出典 : 『道浦TIME』:新・ことば事情6398「警官か?警察官か?」 | (ytvアナウンサー:道浦俊彦)https://www.ytv.co.jp/michiura/time/2017/07/post-3730.html
道浦氏によれば、「警官か、警察官か」という議論の出発点は、ある事件で逮捕された福岡県警警察官の事件報道において、福岡県警察本部が報道機関に対し、「警官は蔑称なので使用を控えてほしい」と要請したことがきっかけだったといいます。
この要請を受けて、各報道機関では対応が分かれたようですが、もともと各報道機関ではそれぞれ自社の基準や考え方があるようで、以前から対応はまちまちだった様です。

たとえば、共同通信社は「決まりは設けていない」としつつも、国内ニュースでは「警察官」、海外の事件報道では「警官」と表記するのが慣例であると説明しています。実際に過去の記事を調べてみると、「警官」という表現は「外信記事」、すなわち海外ニュースに多く見られるとのことです。
また、フジテレビでは入局時の教育で「警察官」が正式名称であることを教えられ、基本的には正式名称ではない「警官」は使わないとしています。一方、不祥事を起こした警察官の場合は、敢えて警官と呼んでいるとのこと。
さらに、テレビ東京では、福岡県警と同様に「警官」は蔑称であるという認識を持っており、国内ニュースにおいては「警察官」と表記する姿勢を取っています。
このように、テレビ局も「報道」と「ドラマ」などの娯楽分野ではスタンスを分けており、報道では「警察官」、ドラマなどでは「警官」という呼び方が一般的となっているようです。
興味深いのは、洋画の日本語吹き替えにおいては、ほとんどと言っていいほど「警察官」という言い方を聞かない点です。こうした場面では、「警官」という表現が定着しているのが現状です。
つまり、「警官」と「警察官」は、単なる言い換えの違いというだけでなく、文脈や媒体、立場によって「敬意」が変わってくる言葉なのです。
言葉には、時に思ってもみない意味や感情が含まれていることがあり、一人歩きすることもあります。報道という公的な言葉の場においては、より丁寧で誤解のない表現を選ぶ配慮が求められているのかもしれません。
『警官』が蔑称に当たる理由とは
報道の世界や公的な文章において、「警察官」という表記が基本とされ、「警官」という略称が避けられる背景には、単なる言葉の短縮にとどまらない“意味の違い”があるようです。
では、なぜ「警官」という略称が、時として警察組織、警察官から“蔑称”と受け取られてしまうのでしょうか。
この点については、元警視庁捜査一課長の久保正行氏の見解が参考になりました。久保氏は次のように語っています。
「警察官」は「警官」と略して呼ばれることがありますが、当の警察官たちはこの略称を嫌います。というのも、警察の『警』には『いましめる』という意味が、『察』には『人の心を察する』という意味が込められています。『察』が抜けてしまえば、高圧的にいましめるだけの存在ということになってしまうからです。
(出典:JBpress「元警視庁捜査一課長が語る現場のリアル」https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55881)
つまり、「警察官」という言葉には、単に法律を厳しく適用するだけではなく、状況や人の心情を読み取る、“公衆への奉仕者としての姿勢”が込められているのです。
「察」が抜け落ちた「警官」では、“人の心を理解しようとする姿勢”が感じられず、命令的・一方的な官吏を想起させてしまう——。これが、福岡県警察本部のみならず、全国の警察官の間で「警官」が蔑称とされるゆえんのようです。
『警察官』と『警官』の呼称のまとめ
言葉は無意識に使われるものであると同時に、時にその選び方が相手の心を強く揺さぶることがあります。「警察官」という言葉が今なお丁寧に使われ続けている背景には、そうした“言葉の重み”に対する深い理解と配慮があるようです。
もちろん一般の人々にとっては、単なる略語としての認識で使っているケースも多いと思われます。しかし、公的な職務を担う立場の人々にとっては、その言葉に込められた「使命」や「理念」がときに否定され、職業的な誇りを奪われかねないと考えているのかもしれません。
これは、呼び方一つで職業に対する敬意の有無が伝わってしまうという、言葉の持つ繊細さを示す一例とも言えるでしょう。
日常の中でちょっとした言い換えを意識することが、相手に対する礼節や思いやりに繋がるのかもしれません。