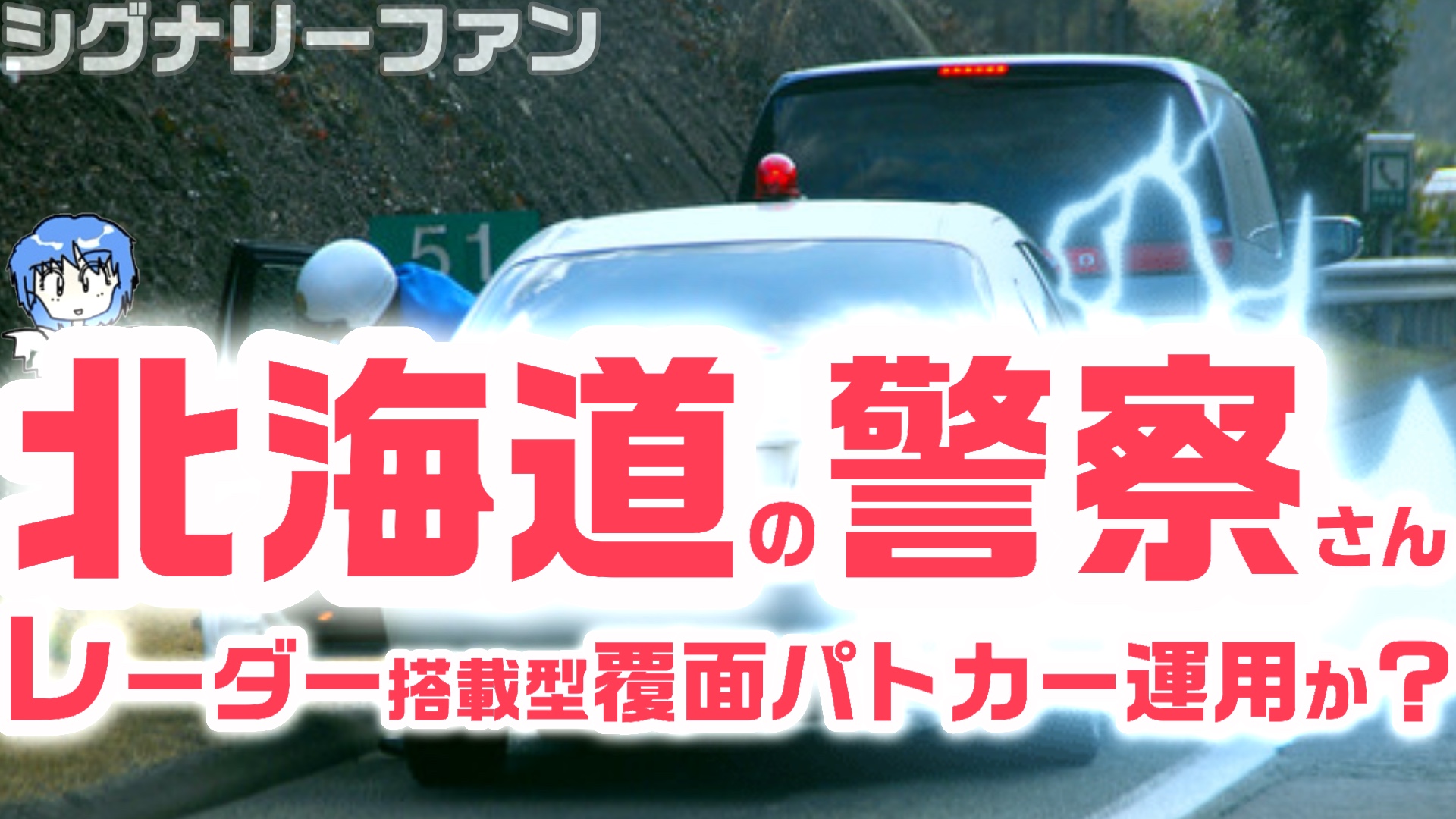世界的に見ても、回転式けん銃(リボルバー)は構造上、手動安全装置(マニュアル・セイフティ)を持たない設計が標準となっている。
マニュアルセーフティはダブルアクションリボルバーのほとんどに備えられておらず、内部にあるオートマチックセーフティによって安全が確保されている。
引用元:アームズマガジン公式サイト 知れば知るほど奥が深い! 「リボルバー」を基礎から徹底解説 意外と知らないリボルバーの基礎知識 https://armsweb.jp/report/5576.html
アメリカの警察機関で広く用いられてきたS&W社製のKフレーム・リボルバー、コルト・ポジティブなど、あるいはヨーロッパ諸国で一部採用されてきたトーラス社製リボルバーなどにおいても、手動の安全装置を持たないものが圧倒的に多い。

これは、リボルバー特有の内部構造による安全性が理由とされる。たとえば、撃鉄(ハンマー)が完全に引き切られた状態でしか撃針(ファイアリングピン)に力が伝わらない設計、あるいはハンマーブロックやトランスファーバー(撃鉄の動力を撃針に伝える中間部品で、トリガーが適切に引かれた時だけ介在する)といった撃発遮断装置が標準的に組み込まれており、落下や衝撃による暴発リスクは極めて低いとされている。
日本の警察で長年配備されてきたS&W M37エアウェイト、国産のニューナンブM60、さらに現行のM360Jサクラも、この国際的な設計思想に準じており、手動安全装置を持たない構造である。

しかし、日本の警察においては、世界でも見られない回転式けん銃の特殊な運用を長らく行っている。
今回はこの日本独特の運用について解説する。
日本警察独特の暴発対策「安全ゴム」とは
その独自運用とは「安全ゴム」である。日本警察では拳銃管理の安全対策として、物理的な暴発防止策「安全ゴム(セーフティ・ゴム)」を独自に追加し、半世紀にわたって運用されてきた経緯がある。
安全ゴムとは、引き金後部にゴム片を挿入し、トリガーを引き切る動作そのものを制限する仕組みである。
この「安全ゴム」は諸外国の警察機関ではほとんど例を見ない、日本独自の管理文化を反映した安全措置と位置付けられる。使用者の故意・過失を問わず、警察署の貸与段階で銃を物理的に封じるという性格が強く、管理責任の所在を明確にする側面、つまり実戦的というより、誤射・誤作動防止に特化した文化的な安全管理と言える。

もっとも、現在ではこの安全ゴムの運用も全国一律ではない。たとえば神奈川県警における運用例ではM37、ニューナンブM60、サクラいずれの制式拳銃においても、安全ゴムが装着されていない事例が複数確認されている。逆に、地方の警察本部では依然として安全ゴムの標準運用が継続されているところが多い。
京都新聞でも以下のように取り上げられている。
ルールは時代によって変遷してきた。滋賀県警察史によると、警察官の採用下限年齢には変遷があり、それに伴い、拳銃を所持できる年齢にも変化がある。近年では2001年、警察官に危害を加えられる事件が相次いだため、全国的に威嚇射撃なしで発砲できるよう、新ルールが定められた。引き金にゴム製の安全装置を付けるかどうかも、都道府県によって微妙に取り扱いが異なっている。
引用元 京都新聞 https://web.archive.org/web/20181113141614/https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180515000127
この“日本警察特有の安全ゴム”が劇中で描写された作品として知られているのが、1988年公開の映画『リボルバー』。

トリガーに安全ゴムが仕込まれていることに気づかず「奪ったニューナンブの引き金が引けない」という滑稽な描写がされている。
【実例】銀行強盗、警察官から奪った銃の安全ゴムに気がつかず
つまり、安全ゴムの存在は、万が一けん銃が強奪された場合に即座に使用される危険を低減する役割も担っている。こうした措置が実際に一定の抑止効果をもたらしたとされる事例として、1979年に発生した「三菱銀行人質事件」が挙げられる。
同事件では、犯人の梅川昭美が猟銃を手に大阪市の三菱銀行北畠支店に立てこもり、42時間に及ぶ人質事件となった。初動で現場に駆け付けた大阪府警の楠本正己警部補は、威嚇射撃を行ったが、梅川に撃たれ殉職。
その後、梅川は楠本警部補や他の警察官からけん銃を奪取したが、報道によれば、奪ったけん銃の引き金を引いた際、梅川は「故障している」旨の発言をして銃を放棄したという。実際には、奪われたけん銃には安全ゴムが装着されており、引き金が引き切れない状態にあったとされている。
この暴発防止措置が結果的にさらなる被害拡大を防いだ可能性があるとして、安全ゴムの存在意義を評価する声も出ている。
まとめ……安全装置の多層化 ― 日本警察におけるけん銃暴発対策
こうした追加的な安全装置や、前述の「安全ゴム」による物理的なトリガーロックは、日本警察におけるけん銃運用上の安全対策の一端を示すものといえる。中でも「安全ゴム」は、日本独自の発想による極めてアナログながら有効性の高い措置として、多くの警察本部で長年採用されてきた。
安全ゴムが装着されていれば、万が一けん銃が強奪された際にも即座の発砲を防ぐ効果が期待できる。この点は、暴発防止のみならず、犯罪抑止上の副次的な安全策とも位置付けられている。
一方で、この「安全ゴム」の存在が広く知られる契機となったのが、2018年に発生した富山県内での交番襲撃・けん銃強奪事件である。
事件報道の中で、安全ゴムの仕組みや運用実態が詳しく紹介されたことにより、これまで主に警察関係者や一部の専門的な層に知られていた情報が、広く一般にも認知されることとなった。結果として、対策の周知が進む一方で、秘匿性の低下によるリスクも指摘されている。
こうした背景を踏まえ、警察ではさらなる強奪防止策の強化も進めている。2019年からは全国の警察で、けん銃の強奪を防ぐ機構を備えた新型の樹脂製ホルスターの配備が開始されている。

これにより、けん銃の抜き取りがより制限されるようになり、仮に警察官が襲撃された場合でもけん銃を奪われるリスクを物理的に低減させる構造が導入されている。