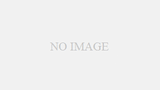警備業者および警備員の役務は、1972年に制定された「警備業法」という法律によって定められています。
すべての警備会社では、請負契約を通じて警備員を各企業に派遣していますが、警備員はこの警備業法を根拠として業務を遂行しています。
また、1980年には業界団体である「全国警備業協会」が設立され、警備業者が事業に取り組む際の活動指針が定められることになりました。
警備業法が制定されるまでの日本の警備業界
日本の警備業界の始祖とされるのは、現・セコムの前身であり、1962年に設立された「日本警備保障株式会社」です。
同社の機械警備システムは、それまでのアナログな警備保障業務を一変させました。また、凶悪犯の逮捕に貢献するなどの実績により、警備保障業者の社会的役割が一挙に国民へ認知されるようになりました。
一方で、警備業法が制定されるまでの日本では、一部の警備業者によって違法行為や不祥事が横行していたことも事実です。特に、チッソの警備を受注していたことで知られる「特別防衛保障」は、水俣病患者やその支援者に対して暴力を振るっていました。
さらに、この会社は自社の労働争議においても「警備」と称して社員や一般人に暴行を加えていたほか、市民運動を妨害する行為も公然と行っており、社会問題として国会でも取り上げられるほどの事態となっていました。
特別防衛保障株式会社(昭和四十四年四月設立)は、警察当局がは握しているところでは、昭和四十五年以降株式会社報知新聞社(東京都)、株式会社細川鉄工所(大阪府)、株式会社教育社(東京都)、チッソ株式会社(大阪府)及び株式会社本山製作所(宮城県)における労使紛争に関連して不法事案を起こしている。
出典 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b074003.htm
現在、各警備会社は警備業法に則って業務に従事していますが、警備業法は細部に至るまで明文化されており、これに違反した場合には、会社名が管轄の警察に公表される行政処分を受けることになります。その理由は、一般市民や一般企業が、法律を守らない悪質な警備会社を利用しないようにするという、明確な公益目的に基づいています。
警備会社と契約を結ぶ際には、その会社が警備業法を順守しているかどうか、また過去に行政処分を受けたような業者ではないかを確認することが重要です。契約を行う企業側にもコンプライアンス上の責任が問われる可能性があるため、十分な確認のうえで契約を行う必要があります。
また、警備業法第3条に規定されている「欠格事由」には、以下のような項目が明記されています。
「禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 、また 最近5年間にこの法律の規定、この法律に基づく命令の規定もしくは処分に違反し、または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者」
出典 警備業の要件に関する規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F30301000001.html
つまり、犯罪者は警備員になることができないと明文化されており、公務員と同様に、警備員も表向きには犯罪歴がある者は就くことができない職業であるということです。
そもそも、この警備業法が定められた背景には、前述の特別防衛保障による暴力的かつ無法な行為が大きく影響しています。
警備業法では、前科のある者を排除する規定が設けられており、特に同社では、社長自身が犯罪歴のある人物、つまり警備業者として欠格に該当する者であったため、警備業法が施行される直前に経営から退いています。
とくに交通誘導業務を除くすべての警備業務においては、警備会社が犯歴の確認に厳重な注意を払っています。ただし、法律に明記されているとおり、前科のある者であっても、刑の終了または執行の免除から5年を経過していれば就業は可能とされています。
日本の警備業界は大別して業務は4つ
日本国内で警備員が従事できる業務は、警備業法によって次の4つに大別されています。すなわち、1号警備にあたる施設警備、2号警備にあたる交通誘導(雑踏)警備、3号警備にあたる貴重品輸送警備、そして4号警備にあたる身辺警備(警護)です。
| 1号警備 | |
| 施設に常駐し管理および警備を行う施設警備、店舗内などの巡回を行う保安警備、契約先のセンサーが発報すると警備員が駆けつける機械警備などがある。 | |
| 2号警備 | |
| 交通誘導。警察の交通規制と違って一切の権限はないが、誘導をミスって事故を起こした警備員に賠償命令や、有罪判決が下った判例もある(※後述)。 | |
| 3号警備 | |
| 現金輸送。正式名称は貴重品運搬警備業務。警送中は路上でけが人を見つけても、止まってはならないと会社から至上命令を受けている。 | |
| 4号警備 | |
| 身辺警護、いわゆるボディーガード。大臣などの公職の場合は警視庁のSPが警護を行うが、民間企業の重役などを警護するのは民間警備員となる。ほとんどが元警察官。 |
現在、業界団体は警備業務の適正化に向けて努力を続けており、多様なサービスが企業だけでなく一般家庭にも売り込まれるようになっています。
警備員が持つ権限について
警備員は警備会社に雇用されている「会社員」ではありますが、警備業法を根拠とする警備の専門職として、知識と技術を活かし、第三者からの依頼に基づいてその生命・身体および財産の保護を目的とした業務に従事しています。
しかしながら、警備員がこれらの業務を遂行するにあたって、特別な権限が与えられているわけではないという点に留意する必要があります。
警備員が有するのは、あくまで一般の私人としての現行犯逮捕の権利や、施設管理者からの委任による施設管理権にとどまります。
したがって、明確な現行犯に対しては私人として逮捕が可能ですが、それ以外の場合には、施設内からの退去を要請する、制服の存在による無言の抑止効果を期待する、あるいは警察へ通報するといった手段によって対処します。
また、警備員が店内で万引き犯を確保した場合であっても、取り調べに類する行為を行うことは禁止されています。保安員が万引きした女子高校生に対して説教をすることは、社会通念上、ある程度認められる場合もありますが、これが取り調べに該当するような行為となれば、直ちに違法行為となります。
このように、警備員とはいえ、警備業法によって特別な公的権限が付与されているわけではないという点を十分に理解しておく必要があります。
警備員が駆け付ける「機械警備」

※努力義務として明記されている。
警備業界においては、1960年代から大手警備会社が侵入検知型アラームを用いたサービスを開始し、これを一般企業がこぞって導入したことにより、警備業界における一大革命となりました。
近年では、一般企業にとどまらず、「ホームセキュリティ」と銘打って一般家庭向けの防犯アラームの導入が進んでおり、売り上げを伸ばしています。
これらのサービスは、いわゆる1号警備に分類される「機械警備」に該当するものであり、留守中の住宅や事業所に侵入感知型の各種センサーを設置し、窓の破損や不審な侵入があった際にはその信号が警備会社の監視センターに送信され、警備員が現場に車両で急行するという仕組みになっています。
なお、警備員が通報を受けて現場に駆けつけるまでの時間については、「25分以内」とすることが警備業法において努力義務として定められており、これを超過する場合には公安委員会から厳重な指導が入ることがあります。
特例的な対応として、広大な面積を有する北海道においては、「30分以内」というローカルルールが設けられており、地域の事情に応じた運用が行われています。
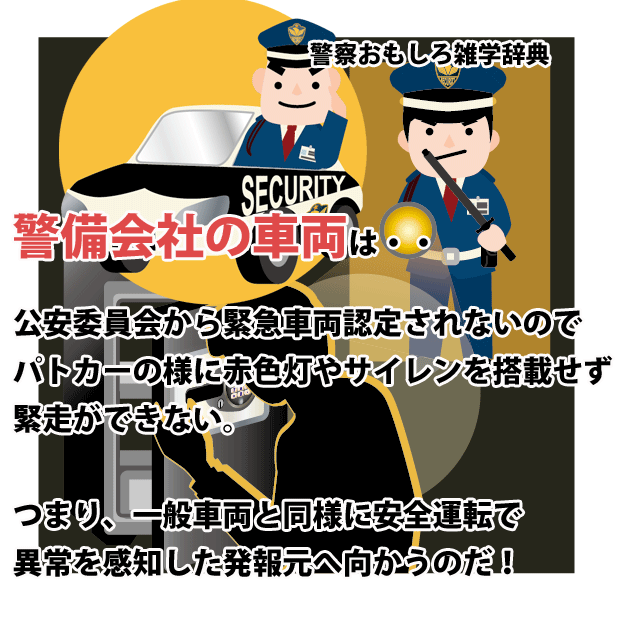
ただし、警備会社の車両には公益性が認められておらず、ガス会社や電力会社のように緊急自動車としての指定は一切受けられません。
道路交通法上および警備業法上においても、警備会社の車両はあくまで一般の業務用車両と同じ扱いとされており、緊急走行や優先通行といった特別な権利は付与されていません。
一部の警備会社の車両に赤色灯やサイレンが装備されている場合がありますが、これは警備業務の一環として血液の緊急搬送業務を委託されているためであり、通常の警備業務での使用を認められているわけではありません。
日本の警備員の武装
警備員には特別な権限が付与されていないとはいえ、日本の民間企業の社員としては例外的に、法律上明確に護身用具の所持が認められている職種であることは事実です。
これは警備業法に基づき、必要最低限の範囲で警棒や盾、防護服などの護身装備を携行することが許可されており、警備員が自身および警備対象の安全を確保するために限って使用が認められているものです。

現在、日本の警備員が例外的に所持を認められている護身用具の代表が「警戒棒」、いわゆる特殊警棒です。
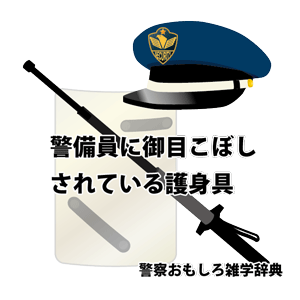
この特殊警棒については、近年では警察官が使用しているものと同様にツバ(鍔)が取り付けられた、防御性の高いタイプの使用が可能となっています。たとえば、ALSOK(アルソック)の現金輸送業務においては、サンリキ製の「ジストス警棒」が採用されています。
なお、日本では警備業法が施行された当初から、警備員に対して銃器による武装は一切認められていません。このため、銃を所持した武装強盗に襲われて現金を奪われるという事件もたびたび発生しています。

一見すると頼りない印象を持たれるかもしれませんが、たとえ現金を奪われたとしても、警備会社が加入している保険によって損失はカバーされます。むしろ、警備員が無理に抵抗して負傷した場合には、後に警察か
ら「なぜ抵抗したのか」と注意されることもあるため、警備員には「給料以上の仕事はするな」と会社からも明確に指導されています。
また、銀行などの施設において、稀に現金輸送車の近くで長い木製の棒を持った警備員を見かけることがあります。この棒は「警杖(けいじょう)」と呼ばれるもので、もともとは警察で古くから使用されていた武具ですが、現在では警備員にも一部使用が黙認されています。
加えて、さすまたやポリカーボネート製の盾も、一定の条件下で所持が可能となっています。
ただし、スタンガンや催涙スプレーといった攻撃性の高い器具については、現在のところ警備員による所持は認められていません。
警備員はどうして警察官と似ている服を着ている?
警備員は、施設の管理権限を持つ職員として、一般の利用客や職員と異なる服装、すなわち制服の着用が求められる場面が多くあります。制服は警備員が施設管理の職務を担っていることを視覚的に示すためのものとして、非常に重要です。

とはいえ、警備員が制服を着用しなければならないという法的な義務はありません。実際、1号警備における万引き保安員や、4号警備のボディーガード業務では、目立たないよう私服を着用するのが一般的です。
一方で、多くの警備員が警察官の制服に似たデザインの制服を着用しているのは、外見上の影響力を意識したものであると考えられます。つまり、警備員が権限を持っているように見せかけることで、一定の抑止効果を狙っているとされます。もっとも、警備員は実際に「施設の管理権限」という明確な立場に基づいて行動する場面が多く、これは単なる演出ではありません。
法律上は、警備員の制服が警察官や海上保安官の制服と酷似することは明確に禁止されています。それにもかかわらず、実際には多くの警備会社が警察官に近い紺色やブルー系の制服を採用しており、その類似性がしばしば指摘されています。
ただし、皮肉なことに、こうした制服デザインの多くは、警備会社が先に採用し、その後に警察側が制服を変更したという経緯も一部に存在します。
また、制服のデザインは会社ごとに自由度があり、中にはカラフルで一見すると警備員には見えないようなスタイルを採用している企業もあります。
さらに一部では、北海道のパチンコ店を母体とする警備会社が、予備自衛官(自衛隊を退職後、民間で働きながら予備役登録している者)を多数採用し、彼らに警備にあたらせているケースも見られます。そうした現場では、警棒を腰に下げた警備員が店内を堂々と巡回しており、威圧感を高める手段として機能していると考えられます。
お店で緊急事態が発生した場合、太陽ミリタリーセキュリティに招集がかけられます。不正遊技を行うゴト師の背後に警棒を持った本格的な隊員が並び、無言の圧力をかけます。ゴト師は逃げたくとも退店すると自らの不正行為を認めてしまうので動けません。そうすることで、これまで幾度となくゴト師を取り押さえてきました。
引用元 https://taiyogroup.jp/about/military/
交通誘導警備で誘導した車両が事故を起こすと、警備員も責任を問われる

交通誘導警備とは、警備業法第2条第2号に定められた「2号警備(雑踏警備)」に分類される業務であり、主に道路工事現場などで交通の円滑な流れと安全を確保するために行われる警備活動です。現場では、交通誘導警備員が片側交互通行の規制に従って、車両や歩行者の安全な誘導に従事しています。
ただし、交通誘導警備員は、警察から委託を受けた「駐車監視員」などとは異なり、公務の一部を代行する「みなし公務員」ではありません。そのため、交通誘導において法的な強制力や公的な権限は持っておらず、あくまで「お願い」という形でドライバーに協力を求める立場です。
責任の所在について
インターネット上では、「警備員の誘導に従って事故が起きたとしても、すべて運転手の責任になる」という趣旨の情報が散見されますが、これは事実とは異なります。実際には、交通誘導警備員の誘導ミスによって事故が発生した場合、その責任が警備員や警備会社側に問われるケースも存在します。
もちろん、運転者としての注意義務は常に前提となるため、ドライバーが責任を負う場面は多いものの、誘導の内容や状況によっては、警備員に対して刑事責任や民事責任が問われることもあり得ます。
過去の裁判例では、女性交通誘導警備員の誘導の結果、歩行中の幼児が事故に巻き込まれて死亡したという痛ましい事例において、裁判所が警備員側の過失を認定し、責任を認める判決を下しています。
このように、交通誘導警備は社会の安全を支える重要な業務である一方、業務中の判断ミスが重大な結果を招く可能性があります。
あんたが誘導したんだろう!!
典拠元 http://keibihosho.blogspot.jp/2013/08/blog-post_6381.html
「あんたが誘導したんだろう!!」という言葉は、女性の交通誘導警備員による誘導が原因とされるこの事故の直後に、加害ドライバーがその女性警備員に向かって発したものです。
この裁判では、運転手だけでなく警備員側にも過失が認められるという判決が下されました。
女性警備員の交通誘導ミスが原因となった事故について、警備員にも有罪判決が下されたことが報じられています。
典拠元:http://response.jp/article/2013/03/08/13103.html
この判決において、裁判官は運転手に対し「警備員の誘導を妄信した運転手に第一の過失がある」と指摘しました。一方で、女性警備員に対しても「交通警備員の交通誘導が起因となって事故が発生したのは明白である」と述べ、「したがって交通誘導警備員にも運転者に準ずる責任がある」との主旨を言い渡しています。
その結果、女性警備員には「執行猶予4年つきの禁固1年」という有罪判決が下されました。
典拠元: http://www.kurumaerabi.com/car_news/info/73167/
このように、誘導を行った女性警備員側も起訴され、実際に有罪判決が出たことは当時、世間を驚かせました。
つまり、ネット上でよく見かける「警備員の誘導によって事故が起きた場合、その責任は警備員ではなく運転手のみに課せられる」という考え方は誤りだったのです。
誤解されている方も多いかもしれませんが、警察官の「交通規制」と交通誘導警備員の「交通誘導」はまったく別物であり、強制と要請という立場の違いから、公道上において両者に権限や義務に共通点は一切ありません。
警備業者は保険に加入していますが、その保険を使用せずに会社負担とする場合もあります(自動車保険と同じ理屈で、使うと保険料が上がるためです)。
中には、違法であるにもかかわらず、警備員個人に給料から保険料を支払わせる会社もあるということです。
しかし、ほとんどの警備員はそのような知識を持たず、組合やユニオンなどのバックボーンもなく、泣き寝入りしているのが現状だと思われます。
各地に警備業協会というものがありますが、これは警備会社を守るための組合であり、警備員個人の権利を守るための労働組合ではありません。
その警備業協会に加入していない会社も存在します。実際、前述の裁判で被告となった女性警備員が所属していた会社は、警備業協会に未加入だったと言われています。
裁判で被告となった元警備員の女性は、法廷で終始泣いて自分の犯した罪の重さに肩を震わせていたと言います。そして、判決後には以下のような言葉を残しています。
生活は苦しいけれど、警備員のような人の命に関わる仕事はもうしたくありません
典拠元 http://keibihosho.blogspot.jp/2013/08/blog-post_6381.html
女性が控訴したかどうかは不明ですが、彼女の消極的なコメントを見る限り、警備員のような業種では日銭を稼いで生きるのに精一杯であり、月給18万円程度の警備員の給料では、50万円や100万円もの弁護士費用を捻出して法廷闘争を続ける気力はなさそうに思えます。
判決を受けた女性警備員は、公判中、終始肩を震わせて泣いていたと言われています。そして、判決後には「生活は苦しいけれど、警備員のような人の命に関わる仕事はもうしたくありません」とコメントを残しています。
引用元
http://keibihosho.blogspot.jp/2013/08/blog-post_6381.html
http://response.jp/article/2013/03/08/193103.html
さらに2017年6月には片側交互通行の工事現場において、バイクが行ったのに警備員が無線で連絡を取り合わなかったために、衝突事故が発生。この事故でも警備員および現場代理人の3人が書類送検されています。
警備会社の新サービスが続々。「ネット炎上監視サービス」も登場
現代では、社員やアルバイト従業員の悪ふざけのツイートやブログ記事一つで、会社の企業スタンスや品性が疑われることもよくあります。先日、大手警備保障会社「セコム」が公式Twitterで大炎上したことも話題になりました。一方で、競合の大手「アルソック」では、2014年12月から「情報警備」と銘打って、ネット炎上監視サービスを提供し始め、月額10万円の料金が話題になっています。
炎上と言えば、徳島県の警備会社「四國中央警備保障」も忘れられません。同社は2002年に女子中学生のブルマ写真集を発売しようとしたことがネットで炎上し、批判が殺到しました。実際、四國中央警備保障には批判的な電話が鳴り止まず、社長に対する脅迫電話もあったと言われています。最終的に同社は解散し、その後写真集がどうなったかは不明です。
このように、警備業界では次世代型のサービスを提供することで生き残りをかけている企業が増えてきています。
福島第一原発警備員「仕事を辞めたい」と言い出したら、ハケン会社の幹部社員が豹変した!
福島第一原発で働く作業員たちは、拉致されたりどこかから無理やり連れてこられたワケアリの人たちです。
実はフクイチだけの問題ではないようで、古くから日本では原発ビジネスに組織暴力がかかわってきており、組がホームレスや借金のカタに売られた人を危険な炉心作業員としてかき集め、全国の原発に送り込んでいるとされています。
作業員のほか、福島第一原発の警備員もまた違法に集められた人材が多いようで「辞めたい」と言い出した24歳の警備員が派遣元の人夫屋の役員からバットでボコボコにされたといいます。
犯人の人材派遣会社の役員(36)ら2人は監禁、傷害容疑で逮捕されましたが、軽作業で高収入と言われてホイホイついていったら福島の放射能汚染地域だった……という恐れもあり、モームリです。
典拠元
http://wjn.jp/article/detail/2349568/
http://www.minyu-net.com/news/news/0619/news12.html