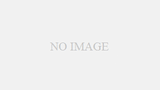以前、三才ブックスの「警察の本シリーズ」で、次のような主旨が紹介されていました――
「日本警察のけん銃には照星(フロントサイト)はあるが、照門(リアサイト)はない。なぜなら、日本警察は銃の使用目的を“攻撃”ではなく“防御”に置いているためである」と。
この話を読んで以来、ずっと印象に残っています。

ニューナンブM60で射撃訓練を行う警察官。画像の出典 北陸朝日放送公式ページ 『警察官が射撃の技術競う 2018.10.9放送』
一般的に、照星(フロントサイト)は銃身前方に設置され、照門(リアサイト)は銃の後方に取り付けられ、二つが揃って初めて照準器として機能します。
確かに、散弾銃の中には照星のみを搭載するタイプもあります。これは、弾を散らす設計のため、精密な照準を必要としないからです。照星と照門を重ねる手間を省くことも、野生動物を相手にする場面では理にかなっています。
しかし、その用途が主として対人用の警察用けん銃となると話は別です。

たとえば、日本警察が制服警察官に配備しているリボルバー――ニューナンブ、エアウェイト、サクラの御三家。刑事部向けのP230やM3913、SITで使用されるベレッタ92、警護任務用のP2000やグロック、特殊部隊用のP226。さらにはMP5などの特殊銃に至るまで、いずれも照星と照門がセットで装備されています。
リアサイトが「無い」という情報は、元警察官の著書や専門書籍、また報道写真などでも確認されておらず、むしろ、ベレッタやMP5の一部には、精密な射撃を可能にするダットサイト(光学照準器)すら搭載されています。

つまり、「あえてリアサイトを外して納入されている」などという説は、その本以外では聞いたことがありません。
実際、日本の警察がけん銃を使用する目的の一つは、被疑者の制圧にあり、照準器がなければ、その役目を果たせないはずです。
では、なぜライターは「照星はあるが照門はない」と書いたのでしょうか?
考えられる理由のひとつに、ニューナンブやその元となったスミス&ウェッソン製の回転式けん銃のデザインが挙げられます。
たとえば、M37エアーウェイトを真横から見ると、確かにフロントサイトは目立ちますが、リアサイトは「無いように見える」ことがあります。
しかし実際に構えてみれば、照準用の溝がきちんとリアサイトとして設けられていることがわかります。もしその“溝”をリアサイトではないと見なすのなら、それはもう定義の問題でしょう。
もし、ニューナンブやM36、M10にコルト社の回転式けん銃のように大型のアジャスタブル(調整式)リアサイトが備わっていれば、このライターが映画などでけん銃を真横から見たことしかなかったとしても、「日本警察のけん銃には照星はあっても照門はない!なぜならば」などとは書かなかったかもしれません。
一方、警視庁SITのような特殊部隊が使用するベレッタ92には、レーザーサイトやダットサイトなど、より高度な照準器が搭載されています。
ですが、一般警察官が携行するけん銃にはそうした装備は許されておらず、カスタムもできません。したがって、銃本体のアイアンサイトを使って正確に狙う必要があります。
日本の警察は、自衛隊と違い、銃に関する情報公開をあまり行っていません。そのため、実態は見えにくいのが現実です。ただし、各県警の警察学校の紹介ページでは、射撃訓練の様子が写真で紹介されていることもあります。
そこには、足を大きく開いて腰を落とし、両手でけん銃を構える警察官の姿が映っています。これは、近年主流となっているアメリカ式の射撃スタイルで、より正確な射撃を目的としたものです。
そうした訓練の様子を見れば、「日本の警察官がけん銃を防御のためだけに撃っている」というのは、やや実情とズレているのではないか――と感じずにはいられません。
誤解してほしくないのですが、この記事は誰かのように揚げ足取りをしたり、皮肉ったり、批判する趣旨ではありません。
むしろ、子供の頃に読んだ「警察の本」を、今でも大切に覚えている――そんな純粋な気持ちから、この話題を取り上げたもので、今でも大好きなネタのひとつです。

他の関連記事もぜひご覧ください。
















































































































![ストライクアンドタクティカルマガジン 2021年 11 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51gFpAb7LAL._SL500_.jpg)