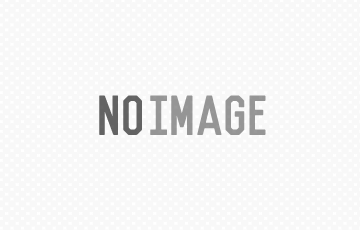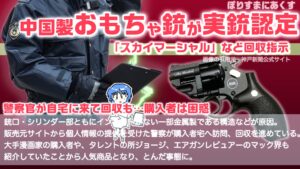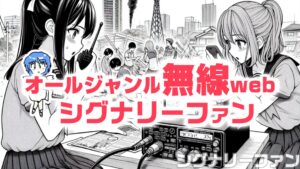警察官に採用された者は警察学校に入港し、専門の教育を受けるという。今回、各種オープンソースや広報資料を閲覧し、警察学校の教育について理解を進めたいと思う。
香川県警察の採用案内を例に見ると、筆記および論文試験、体力検査、第1次身体検査が行われたのち、集団面接試験に進むことが許される。ここまでが第1次試験である。さらに第1次試験に合格すると、第2次試験として適性検査、第2次身体検査が行われたのちに口述試験(自己PRおよび個別面接)が行われ、身辺調査を経たうえで最終的な合否が判定される。
いずれの警察本部の場合でも、最終合格して成績順に採用候補者名簿に登載されると、欠員が出るごとに上位者から採用され、警察官を拝命する。
警視庁の場合、採用される男性警察官は年間2000人あまり、同女性警察官は200人あまりだという。
そして採用時教養のため、入校するのが全寮制の各警察学校である。採用時教養の第一段階となる『初任科』を、大卒採用で6か月、それ以外の採用区分で10か月間にわたって受けるのだ。
警察学校に授業料はなく『条件付き採用の警察官』として毎月の給与と賞与が支払われる。条件付き採用とはいえ、入校時に『巡査』の階級を拝命しており、学生の身分は警察官に変わりはない。
一般に、採用時教養の複数段階の中でも、基礎となる初任科教養は警察官としての素養を身に付けるものであり、精神的にも肉体的にも限界まで追い詰められるのではないだろうか。
しかし、卒業配置後の実務はもっとつらいのだから、その素養ができていなければ務まりはしないのでは。
だからこそ、それに見合った俸給、有給、ボーナス、各種手当てなど、ほかの公務員よりも俸給が高い公安職公務員としての福利厚生が約束されていると言えるのではないだろうか。
この論評はオープンソースを基に執筆しています。筆者は一切、警察の内部事情を知る立場にありません。ご了承ください。
Contents
警察官志願者と警察学校の中のリアルとの乖離
ある県では警察学校での扱いがひどすぎて訴訟が起きた。
採用後に入校する警察学校では、厳格な教育訓練が実施されるが、その過酷さゆえに途中退職する学生も少なくない。ビズジャーナルの報道によれば、2013年度における全国の警察学校の中でも、兵庫県警察学校は退職率が25.1%に達し、ワースト1位となっていた。実に4人に1人が脱落する計算である。この厳しさを巡っては、2015年、兵庫県警察学校を退職した元学生が、退職に追い込まれた経緯を理由に県警を提訴する事案も発生している。一方で、同じ年の統計では、退職率が最も低かったのは大分県警察学校で1.1%にとどまった。次いで、宮崎県警察学校2.2%、富山県警察学校2.4%、皇宮警察学校2.6%、山梨県警察学校2.9%、新潟県警察学校3.1%、沖縄県警察学校3.2%、山口県警察学校3.4%、愛媛県警察学校3.9%、島根県警察学校4.4%、群馬県警察学校5.0%、山形県警察学校5.0%と続いている。
警察学校の退職率には地域差があり、訓練の厳しさ、指導方法、学生の適応状況など、複数の要因が影響しているとみられる。
警察学校の教育は、同じ階級社会で上命下達の徹底が求められる自衛隊、消防、海上保安庁などと比しても、決して遜色のない厳しさを持つとされる。全寮制の生活の中で、学生巡査たちは教官(通常は警部補)や助教(巡査部長)に加え、半年先に入校した先輩学生(いわゆる「指導員」)に対して絶対的な服従を求められる。階級社会の一員として、初任科に着任した瞬間からすでに組織の一部としての自覚と責任が課せられるのだ。
訓練の厳しさに耐え切れず、自ら教場(クラス)を去る学生も決して少なくはない。前述のように、退職率が二桁に及ぶ警察学校も存在する。その厳しさは、単なる学生生活とは異なる、実戦的な組織教育の色合いが強い。
さらに、教官や助教からの指導のみならず、同期生同士の集団規律も重要視される。集団行動に適応できない学生に対しては、時に同期生からの無視や貸与品の隠匿など、現代の価値観から見れば「いじめ」と評されかねない同調圧力も働くことがある。これは、日本の集団主義文化の中で長らく体育会系組織に根付いてきた「伝統」と言えなくもない。
連帯感と規律を養う訓練の中では、集団の一人が規律違反を犯せば、連帯責任の名の下に同期全員で罰として腕立て伏せなどの体罰的指導が行われる例も報告されている。こうした経験を経てこそ、現場配属後に待ち受ける厳しい職務に耐え得る警察官としての素養を身につけるというのが、警察学校教育の一つの理念とも言えよう。
警察学校の厳しさは各都道府県警の公式採用案内には記されないことが多い。しかし、志願者とのミスマッチを防ぐため、近年は一部の警察本部であえて現実的な教育現場の様子を紹介する『情報公開』の取り組みも見られるようになってきている。
中でも、千葉県警が志願者に対して行っているバスツアーの取り組みは、他の都道府県警に先駆けた先進的な試みと評価されている。警察組織と志願者との間に、より現実的な相互理解を築こうとする姿勢がうかがえる。
千葉県警では2015年から、警察官志望の高校生とその保護者を対象にした『警察学校バスツアー』を実施している。志願者は保護者とともに警察学校の教場や寮内、さらには機動隊の訓練風景などを見学し、入校後の生活を具体的にイメージできる機会が設けられている。もちろん、見学の場で披露される内容が警察教育の全てではなく、あくまで「表の顔」に過ぎない部分もあろうが、それでもなお現場を事前に体感させる意義は大きいのではないか。
千葉県警によれば「採用3年以内に離職する者のうち、過半数は警察学校在籍中に退職している。学校の現実を知った上で志願してもらい、後のミスマッチを防ぎたい」としており、志願者に対して現実の厳しさを隠さず伝えようとする姿勢は、一定の評価を得ているという。あらかじめ覚悟を促すことで離職率の低下を目指すこの取り組みは、警察学校教育の厳しさが全国的に議論となる中で、一つの模索の形とも言えよう。
採用時には気づかれなかった適性の欠如が、わずか数週間の警察学校生活の中で白日の下に晒されてしまう……。
警察学校を題材にした小説、長岡弘樹『教場』(小学館文庫)が近年注目を集めている。夢を抱いて警察官を目指した若者たちの前に立ちはだかるのは、教官・風間の冷徹な審査である。「警察学校は優秀な警察官を育成する場ではない。適性のない人間をふるい落とす場である」と断言する風間の言葉が、本質を突いていると感じる読者も多いのではないだろうか。なぜか全国の書店員たちの支持も集め、ベストセラーとなり、ドラマ化されたのも、そこに警察学校の実態を仄めかすリアリティがあるからなのかもしれない。
では、こうして入校した若き夢追い人たち――すなわち「学生巡査」たちは、警察学校でどのような寮生活を送り、どのような教育を受けていくのだろうか。
警察学校の初任科と入校中の学生生活
入校早々、彼らを待ち受けるのは、警察官としての基礎的素養を身につけるための新任教育、いわゆる「初任科」である。採用時教養とも呼ばれ、警察官人生の第一歩はここから始まる。
警察学校の敷地は、講堂、本館、教場棟、術科棟、グラウンド、学生寮(学生棟)などで構成される。さらに実務訓練用の模擬住宅が敷地内に設置されていることも多い。購買部も併設されており、日用品や簡単な食品も手に入るが、基本的に外出は制限されるため、ここが学生生活のライフラインとなる。
学生の一日は早い。午前6時半、起床ラッパのように響く点呼の声で始まる。学生たちはジャージにスポーツ帽を着用し、まずは日朝点呼を受ける。続いて警察体操、ランニング、教場と居室の清掃が行われ、ようやく朝食となる。食事も時間厳守、素早く済ませて授業の準備に取り掛かる。制服に制帽を着用し、午前8時半前には中庭に小走りで集合。国旗掲揚の後、学校長らによる朝礼・訓示を受けるのが毎朝の儀式だ。その後、各自の教場――たとえば丸越教官が担任なら「丸越教場」――に入室し、20分間の学級活動(ホームルーム)を経て、午前8時50分から本格的な授業が始まる。
警視庁の場合、1教場は概ね40名編成であり、正担任(教官)と副担任(副教官または助教)が学生たちを直接指導する。
初任科で行われる教育
座学では法律、警察実務、倫理規範など、警察官として最低限必要な知識が叩き込まれる。体育・武道は体力・護身術の基礎を養い、射撃訓練では拳銃の安全な取扱いを習得させられる。さらに警察業務に欠かせないのが無線通話の訓練であり、交通整理の実技訓練も頻繁に行われる。
とりわけ通信業務に必要な国家資格「第2級陸上特殊無線技士(通称2陸特)」の取得は必須とされ、授業内の養成課程と修了試験によって全員に資格を取らせる。無線機自体は3陸特でも扱えるが、警察官は速度違反取締りで『陸上のレーダー』を扱うので、2陸特が必要だ。
警察官の職務は日常的に車両運転と密接に関わっており、採用後すぐに現場で即応できるよう、一定の運転技能が求められている。警察庁も「入校前に普通自動車免許または普通自動二輪免許を取得しておくことが望ましい」としており、多くの警察本部もこれを踏襲している。しかし、実際に警察学校内で免許取得の機会が用意されているかどうかは、各都道府県警察学校ごとに対応が分かれているのが現状だ。
たとえば神奈川県警察学校では、授業の一環として二輪車操法の実習こそ行われるものの、免許自体は「警察学校内で取得することはできない」と明言している。やむを得ず未取得で入校した学生は、休日を利用して外部の教習所に通い免許取得を目指すケースもある。
一方、広島県警察学校では、入校内定者に対して「普通自動二輪車免許(小型限定以上、AT限定は不可)の取得を必須」と、公式に厳格な方針を示している。高知県警察でも「業務で免許が必要となるため、入校までに各自で取得しておくこと」と事前取得を原則としており、間に合わない場合は授業終了後に教習所通学を命じている。愛知県警察学校もまた「運転技術の訓練は学校で行うが、免許自体は各自で取得」との立場を取っており、入校前取得を強く勧めている。
こうした各地の警察学校の対応の差はあれど、警察官を志す者にとって、運転免許はもはや採用試験突破と並ぶ「事実上の必須資格」となっているのが実情である。
中でもやはり、体力を使う警察官の資質を養うメインの授業は実技。体育では剣道、柔道、合気道、逮捕術といった実務に必要な武道が徹底的に教え込まれ、卒業前にはほぼ全員が初段を得る。
警視庁の場合、男性警察官は柔道または剣道、女性警察官は柔道、剣道、合気道から授業を選ぶ選択制となっている。学生の大半が初心者で礼法と基本技からの技術習得となる。
基本的な訓練メニューは授業中に行うが、柔道、剣道、逮捕術、体育の4つは必修となっている。その他にも授業後の自主トレと称して、半ば強制的なメニューでグラウンドでの走り込みをやる。
警察学校に入校した学生らは、まず数週間にわたり外出禁止の寮生活を強いられる。これはいわゆる「シャバの誘惑」を断つためであり、警察官としての基本的な規律・心構えを徹底的に叩き込む時期とされている。おおむね三週間程度が経過すると、週末や祝日に限り、外出が許可されるようになる。
もっとも、外出といっても「警察官である自覚を持った行動」が当然のように厳命され、外出時の服装は原則としてスーツにネクタイ、革靴の着用が義務付けられている。いわば学生というより、すでに社会人警察官としての公式な立ち居振る舞いが求められるようだ。立ち寄り先も事前に届け出た店舗や施設に限定され、自由奔放な行動など許されない。
万一、外出先で酒を飲み過ぎて市民とトラブルを起こすようなことがあれば、それは即ち「不適格」と判断される。
ただし、こうした厳格な管理も時代の変化とともに徐々に緩和されつつある。たとえば千葉県警察学校では、2018年から外出時の服装にカジュアルなジャケットやチノパンなども認められるようになり、飲食店での飲酒も節度を守れば可能とされるようになった。とはいえ、これはあくまで例外的な運用であり、多くの警察学校では今なお「学生巡査は常に公務員である」という前提のもと、私生活においても厳格な規律が貫かれている。
けん銃操法と射撃訓練
警察学校の射撃場は警察官だけでなく、刑務所の刑務官も射撃訓練に訪れる。厚生労働省の麻薬取締官は「警察とは別の射撃訓練場」が用意されているので、使わないという。
なお、千葉県警など、一部の警察本部では新規に設置される警察署には最初から射撃場を署内に設けている署もある。
班別討議
警察官として現場に立つ以上、冷静な判断力と説得力ある言葉の力は不可欠だという。犯罪捜査の現場で被疑者と対峙する時も、あるいは市民対応で苦情処理にあたる時も、必要なのは「弁の立つ警察官」であれと、厳しい指導が待つという。こうした素養を身に付けさせるため、多くの警察学校では「班別討議」という科目が必修となっている。これは少人数に班編成した学生同士が、決められたテーマに沿ってディスカッションを行う訓練である。
討議にあたっては、まず相手の主張を丁寧に聴取し、必要に応じて質問や確認を行いながら自らの意見を述べる。相手の主張に賛同できない場合でも、感情的に反論するのではなく、論点を明確化し、具体的な根拠を示して対話を重ねていく。最終的には互いに妥協点を見いだし、建設的な結論を導くことが求められるという。Xで「パワーワードでマウントを取って即論破」など論外であり、あくまで現実社会に通用する実務的な議論能力の養成が目的である。
討議のテーマは警察業務に限らず、国内外の時事問題や社会課題など幅広く設定される。いわゆる中高生の発表会にありがちな、一方通行の自己満足的スピーチ「わたしの主張」とは次元を異にする本格的訓練であり、特にコミュニケーション能力に不安を抱える学生にとってはかなりの試練となるという。
【朗報】警察さん、情操教養で理性や教養を身に付けていた
とはいえ、警察学校が単なる「ふるい落としの場」であるだけではないことも確かである。現場で力任せに振る舞う野獣警察が多く生み出されると市民感情もすこぶる低下し、“警察改革”につながりかねない。そこで多くの警察学校では、倫理観と人間性を涵養する「情操教養」の科目も重視されている。外部講師による茶道や華道の実習、職業倫理の講義、あるいはボランティア活動などを通じて、バランスの取れた円満な人格形成を目指している。
また、ユニークな研修も行っている警察学校もある。北海道警察学校では卒業の近い学生に対し、札幌市内のスーパーで店員として「いらっしゃいませ!」「ありがとうございました!」 と店頭で野太い声を送出させる研修や、介護施設にて介助体験などを行う研修も過去に行われた。
警察官とは単なる法の執行者ではなく、地域社会における信頼される公僕でなければならない――警察学校の教育課程には、そうした建前も確かに存在しているようだ。
初任科程を修了後は卒業配置
警察学校の初任科課程を修了すると、新任警察官は各所属先への配属を迎える。高卒者は約10か月間、大卒者は約6か月間に及ぶ厳格な初任科教育を経て、ようやく現場に立つ準備を整えるのだ。しかし、これで警察官としての養成は完結しない。採用時教養はさらに複数段階の実習と教育を伴う体系で構成されている。
職場実習(卒配)
まず、警察学校を卒業した新任巡査は、各警察署の交番等に職場実習生として配属される。これを「卒業配置(卒配)」と呼ぶ。実習期間中は、職場実習指導員の下で交番勤務の基本実務を学ぶとともに、制服の着装、所作、装備品の扱い、勤務態度に至るまで細かな指導を受ける。指導は生活面にも及び、日常生活の細部に対する助言や改善指示が行われることも珍しくない。地域実習のほか、交通実習、生活安全実習、刑事実習(捜査実習)など複数の部門も経験する。各実習の内容は、実習記録表に逐次記録される。
初任補修科生として再入校
この職場実習を終えると、再び警察学校に戻る。次は「初任補修科」と呼ばれる再入校期間である。高卒者は約3か月、大卒者は約2か月間、警察実務の知識や技能の定着を図るとともに、警察官としての心身の充実を目的とした教育を受ける。
実戦実習
補修科修了後は再度現場に戻り、今度は「実戦実習」に臨む。実戦実習では原則として単独勤務が始まり、実習指導員は常時付かなくなる。高卒者で約4か月、大卒者で約3か月の間、交番勤務を中心に日常業務を単独でこなしながら、実務適性の確認と最終的な技能の熟練が図られる。
こうして一連の採用時教養が完了し、正式な警察官としての自立が認められる流れとなっている。
管区警察学校と警察大学校
なお、警察官としての基礎教育を実施する警察学校のほか、警察庁の付属機関として、全国の都道府県警察の幹部警察官や警察庁採用のキャリア警察官を育成する警察大学校(東京都府中市)もある。稲葉元警部の著書の中には警察大学校の話もあり「1000億円の税金を使って作られた」こと、「警察大学校の中に居酒屋まで入っている」ことが書かれており、オドロキだ。ただしあくまで研修機関であり、警察学校とは異なる。
また、管区警察局の機関のひとつで、専門実務の運用に関する教育を行う管区警察学校もある。
警察学校のまとめ
この記事を執筆するにあたり、多くの都道府県警察警察学校の公式ウェブを参考にしたが、共通点として、「使命感を持った警察官の養成」「精神的強靭さの育成」といった表現が目立ち、その役割についても、警察学校は単なる知識習得の場というよりも、精神力と使命感を徹底的に鍛え上げる訓練所というニュアンスの説明が非常に多いと感じた。
新任の学生らがインタビューで口にする「教官のご指導・ご鞭撻」への感謝の言葉は、警察学校特有の厳格な上下関係や規律文化を象徴していると言える。良くも悪くも、日本の一部上場企業や官庁では体育会系の価値観が敷かれている。それに適応できるかどうかは、早い段階で見極められる。
警察学校の教官が採用時の面接官を兼務しているのかは不明だが、採用試験に通っても、中高時代に部活動で上下関係を経験してこなかった若者や、注意力に課題を抱える者、あるいはそれ以外の理由で、その後の経験豊富な教官による警察学校での厳しい訓練と指導の中で早々に適性を判断されることが多いのではないか。結果として、警察学校入校後に保護者同席のうえで退職を勧告されるケースも珍しくなく、ときには退職の強要が行われたとする報道も出ている。
警察学校が「悪に立ち向かう法の番人を育成する場」と位置付けられている以上、職務を遂行できる高い適応力と精神的耐性が求められるのは必然とも言える一方で、こうした厳格な訓練文化が一部では高い離職率や訴訟に至る事例も生んでいる。上下関係を重視する体育会系文化の警察組織のあまり、現代の若年層の気質と乖離を見せている側面も指摘される。
こうした実態は、決して単なる職業訓練校ではない警察学校の性質を浮き彫りにする。
「公務員」や「警察官」という職業を論じる場合、歌手の宇多田ヒカルが引き合いに出されることが多い。
「公務員になりたい」という幼い子どもを揶揄する宇多田ヒカルの曲が物議を醸した際、宇多田は以下のように違和感と職業選択の重要性を訴えた。
テレビで幼稚園児が「公務員になりたい」って言ってるのを見て、「先生」「警察官」みたいに具体的な職種を言わないあたり、この子は親に入れ知恵されてるだけじゃないのかなって思ったの。「パン屋さんになりたい」とは言うけど、「飲食店経営したい」っていう園児なかなかいないから。
引用元:宇多田ヒカル X公式 アカウント https://x.com/utadahikaru/status/6928803523731456
親の入れ知恵で公務員を選ぶ青少年の例もあるのだろうが、少なくとも、そのような考えで「警察官」を選ぶと後悔することになりそうだ。