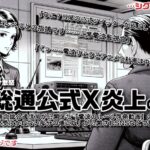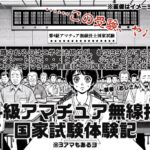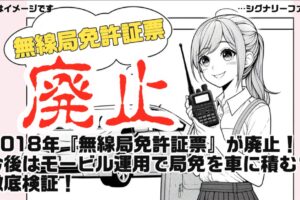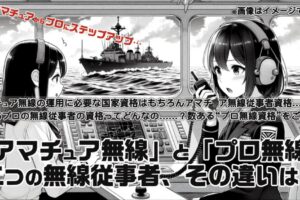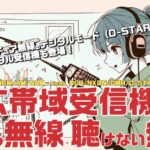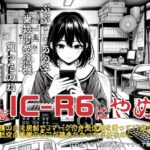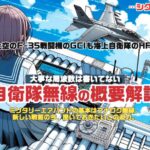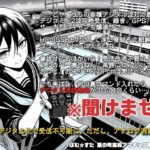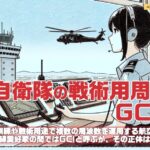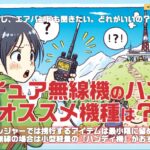Contents
『短波放送』という言葉を聞いたことがあるかもしれません。3~30MHzまでの低い周波数を『短波帯(HF /High Frequency)』と呼びますが、短波放送は季節、それに昼と夜でコンディションが大きく変わる電離層に対応するため、周波数を使い分けて放送されるのが特徴です。日本国内ではとくに『ラジオNIKKEI』のほか、北朝鮮国内にいるとされる日本人拉致被害者に対する日本政府からの情報提供を目的とした『しおかぜ』が有名です。
夜間になれば、HF帯の周波数は電離層で反射しやすくなって非常に遠くまで飛ぶことから、世界各国の短波放送が聞こえてきます。これら短波放送の受信趣味をBCL(Broadcast Listening)と呼び、日本では70年代にブームとなりました。
もちろん、短波帯(HF /High Frequency)はラジオ局の短波放送のほか、アマチュア無線をはじめ、各種業務無線、漁業、気象、航空通信、軍事系通信など公共の情報伝達を含む広範な無線通信の領域でもあり、一部は国家の情報戦や非合法な活動にも利用されるなど、BCLよりさらにアンダーグラウンド的な側面もあります。
後述しますが、HFの通信にはAMのほかSSBモードが多用されており、SSBモードはIC-R6では復調できませんが、IC-R6の約半額で比較的簡単にHFのSSBモードを復調・受信できる『中国製SSB対応短波ラジオ』という機材をご紹介しています。
アマチュア無線のHF帯域
さて、アマチュア無線局もそれぞれの級ごとに短波帯の複数の帯域で利用が許可されており、これら低い周波数を使ったアマチュア無線の運用を『HF運用』または単に『HF』と呼んでいます。
4アマが手軽に運用できる144MHz帯や430MHz帯はアンテナを短くできる利点があるものの、Eスポが発生でもしない限り、数百キロ程度の交信範囲が限界です。それでも電波の異常伝播経路(ラジオダクト)が生成されることによって、144MHz帯でも外国と交信できるチャンスが訪れることもあります。しかし、ラジオダクトの発生は希で、日常的にというわけにはいきません。これでは国外のアマチュア局と交信したい場合には不便です。
そこで、周波数が低ければ低いほど遠くへ飛ぶ電波の性質を利用するHF運用となります。理論的には周波数は低ければ低いほど電波が電離層で反射されるため、見通し距離の交信に比べて数倍から数百倍も遠くへ飛んでいきます。さらにHF運用で使用されるSSBやCW(モールス)といった各種モードは通常のFMやAM変調の搬送波に比べ、電波の減衰が少なく、地球の裏側までも飛んでいきます。
SSBはAM同様、振幅変調による電波ですが、SSBは搬送波のエネルギーと変調波のエネルギーの半分をカットして信号を送ります。通常のAMやFMに比べると音声品質がよくないなどの欠点がありますが、無信号時に不要なエネルギー送信しない点や占有帯域幅が狭い点(3kHz)などが利点です。
このSSBには変調波のうち、搬送波と搬送波より低い周波数成分をカットするものをUSB(UpperSide Band)、搬送波と搬送波より高い周波数をカットするものをLSB(Lower Side Band)と呼んでいます。アマチュア無線では7MHz帯以下のバンドではLSB、14MHz帯以上のバンドではUSBを使用します。
このSSBのうち、USBモードは航空無線の『洋上管制』でも使用されています。
アマチュア無線のHFは7MHzが人気
HF帯域ではサイクルピークが比較的良好で安定していることから、7MHz帯(波長から40mバンドとも呼ばれます)が人気となっており、国内局によるコミュニケーションや、効果的な遠距離通信などの技術実験が1年中盛んです。つまり、HF帯のアマチュアバンドとしては、7MHzがもっとも”人が多い”バンドであり、もっとも人気と言っても過言ではありません。また、7MHzは第4級アマチュア無線技士から運用が許可されており、ビギナーのHF入門バンドでもあります。
通常、HF帯は夜間がピークですが、7MHzバンドは日中でも開けており、早い時間から遠距離との交信が可能です。ロングにQSOするのも良いのですが、できるだけ全国の多くの局と交信したい人も多く、1局あたりの交信を短時間で切り上げる局も多くみられます。
以下に7MHz帯の一般的な特徴と特記事項を記載します。
- 帯域範囲:
- 日本国内での7MH帯は7.000MHzから7.200MHzの範囲に許可されています。※日本国外では異なる場合があります。
- HF帯アマチュアバンドとしては許可範囲が狭いため、比較的容易に運用中の局を見つけることができます。
- 通信モード:
- SSB(単一側波): SSBモードの下側を使うLSBモードによる音声通信が主流です。
- CW(連続波): モールス信号による通信も盛んで、QRP(低電力運用)に適しています。
- デジタルモード: パソコンを利用したPSK31やFT8などのデジタル通信も利用されています。
- 時間帯の特徴:
- 日中でも比較的安定しています。
- 夜間になるとD層が消失し、さらに遠距離交信が可能です。そのため、40mは夜間に特に活発になります。
- DXに最適:
- ビギナーでもDX(外国局との遠距離通信)が比較的容易に行えます。
- QRP運用:
- 7MHzは低電力運用(QRP)により、効果的な通信が可能です。
- キャンプやアウトドアとの相性が良い:
- HF帯域のため、建物や障害物の影響を受けにくく、山中でのキャンプなどアウトドア運用との相性が抜群です。
- ポータブル無線機と簡易なアンテナでOKです。
このようなHF運用で国外アマチュア局と行う遠距離交信を『DX』と呼び、自宅に大きなタワーアンテナを立てて、7MHzや14MHz帯などの低い周波数と電離層を使って外国局との交信を楽しむベテランハムが多くいます。中でも40mバンドはDXを狙いたいアマチュア局にとっては重要かつ魅力的なバンドと言えるでしょう。
HF運用をしたい場合、アンテナの設備が大掛かりになり、またHF無線機も比較的高価のため、初心者にとってはやや飛び込みづらさもありますが、もちろんビギナーが多い4アマでも、SSBとAMモードにて豊富なHF帯域が許可されており、外国局との交信も夢ではありません。またHFのモービル運用も可能です。その際は海岸にでも出かければ2メートル程度のHF用アンテナでアメリカとも交信が可能です。
現在、4アマに許可されているHF帯は7MHzのほか、3.5MHz、3.8MHz、21MHz、24MHZ、28MHzの各バンドとなっており、JARLのビギナーズガイド(PDF)を参照してください。ただ、もっとも電波の飛びの良いモールス(CW)の利用は4アマでは許可されておらず、3アマからとなっているので注意が必要です。
レビュー総数100件超え!HF用受信アンテナのベストセラー!ApexRadioの長中短波受信用アンテナ『303WA-2』
HF運用ではアンテナがより重要となり、一般的には大きなタワーアンテナがあると、送受信効率も良いものです。HFアンテナは費用が安く、設置が簡易な自作のワイヤーアンテナ(全長10m程度)とオートチューナー、V型ダイポール、より大型の八木アンテナまで幅広く、さらに付け加えるならばHF用のアンテナを立てられる自宅環境があれば最適です。
しかし、送信を伴わない受信環境のみであれば、それほど神経質にアンテナを設計、設置する必要はなく、タワーアンテナのような大型アンテナを必ずしも作る必要はありません。HFであっても屋根やベランダ設置のVHF帯モービルアンテナでも、深夜ともなれば太平洋上を飛行する航空機からの電波を十分に受信してくれます。
でも、快適なHF受信を求めるならば、やはり高性能な受信用アンテナの設置を考えたいところです。
レビュー総数100件超え!アパマン受信家の間で人気が高く、HFバンドの受信用アンテナとしてベストセラーなのがApexRadioが製造販売する長中短波受信用アンテナ『303WA-2』です。
HF受信の定番アンテナとしてロングセラーの303WA-2は、2023年10月現在、総合評価が4.62 (106件)となっています(楽天市場)。約1.8mの垂直型で、自宅設置でも省スペースで運用可能。メーカーによれば『30kHz~30MHz を混変調や相互変調の心配なく、低雑音で受信するために開発設計されたコンパクトな受信アンテナ』とのことで、とにかくノイズの少なさが多くのユーザーに支持される所以です。30MHzまでなら大抵のHFで良好な受信環境を構築できるので、ノイズの多い環境の方は一度試してみてはいかがでしょう。
アンテナ取付金具一式、同軸ケーブル(約10m MP-BNCP装着済)が付属し、お買い得です。
HFで運用されるモールス通信
日本では1854年、ペリー(マシュー・カルブレイス・ペリー)が2度目に来日した際、持参した「エンボッシング・モールス電信機」にて江戸と横浜間の電信に成功させ、これが国内初の電信通信となりました。日本のアマチュア無線制度では3アマに合格して初めて打鍵器を使った電信であるモールス(CW)が運用できます。
通常の音声での通信に比べた場合、消費電力は10分の1程度と非常に省電力で通信が行えることが利点です。またモールス通信は弱い出力でも周波数が低ければ低いほど、地球上のあらゆる場所にまで電波が到達するので、驚きと面白さがあります。アマチュア無線技士においては3級から運用が許可されるモールス通信ですが、民間の業務局では使われなくなりました。しかし、自衛隊ではいまだに運用されているほか、日本政府が電波法施行規則第12条第13項で「無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA1A電波4,630kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない。」と規定し、自衛隊のほか警察も常に傍受している非常通信用の周波数4630kHzはモールス通信(A1A)が基本となっています。
HF用各種アンテナの種類
HF用アンテナは通常、低い周波数の無線通信(通常は3MHzから30MHzの帯域)に使用されるアンテナです。これらのアンテナは長いワイヤーや導体を使用したり、釣り竿状の形状を持つタイプもあります。VHFやUHF用アンテナに比べると比較的大型になります。になる場合もあります。以下はHFアンテナの一般的な種類です。
- ダイポールアンテナ:
- ロングワイヤーアンテナ: 「ロングワイヤーアンテナ」は一般的に、長いワイヤーを水平に張り、その一端を高い場所に取り付けることで構成されます。
- 単純な構造:
- ロングワイヤーアンテナは、単純な構造で作成できます。ただし、適切な長さと配置が重要です。
- 多くの周波数帯域で適用可能:
- 適切な長さと配置を選択することで、多くの周波数帯域で効果的に動作します。一般的には、短波からHFバンドに使用されます。
- 長距離通信が可能:
- ロングワイヤーアンテナは、高い場所に設置されるため、遠距離通信に適しています。長いワイヤーが信号をより遠くまで送信できます。
- 指向性が制御しやすい:
- ロングワイヤーアンテナの指向性は、ワイヤーの方向や高さを調整することで制御できます。これにより、特定の方向に信号を送信または受信することが可能です。
- コスト効率が高い:
- ロングワイヤーアンテナは比較的低コストで製作できます。特に自作する場合、素材費が安価で済む場合が多いです。
- 単純な構造:
これらのHFワイヤーアンテナは、アマチュア無線のみならず、軍用分野などでも使用されています。
電離層の種類
電離層とは大気中の酸素分子が赤外線や波長の短い紫外線により、原子へと分解され、その原子が自由電子とイオンに分解され小さな粒状となって浮遊しており、低いほうからD、E、Fと各層から成り立っています。地上から約50キロから数100キロ上空にある各層に電波が当たると反射現象が起こりますが、それぞれ電子密度によって反射や吸収率が違い、一般的に密度が高くなるのは太陽活動が活発な夏場で、とくに前述した短波帯の電波が影響されます。
D層
地上約50キロから80キロと比較的低い位置に発生する層です。昼がもっとも電子密度が高くなりますが、夜は消えてしまいます。短波は反射しませんが、長波はこの層によって比較的広範囲に伝わります。
E層
地上約100キロ上空に発生する層です。朝から発生し昼の時間帯がもっとも電子密度が高くなります。
F層
F層は約200~400kmの高度に形成される電離層です。外国の短波放送が深夜によく聞こえてくるのはこのF層が理由で、アマチュア無線のHFで主に利用されるのもこの層です。
電離層により引き起こされるさまざまな現象
フェージング
夜間のHFで見られる現象で、受信している電波が強くなったり弱くなったりすることがあります。このような電波のゆがみがフェージング現象です。地表波と電離層波が互いに干渉しあうために起きます。
Eスポ
春から夏にかけて、主に昼間、地上から上空約100km付近に局地的かつ突発的に発生する電離層のこと。これに電波が反射することで普段では届かない地域に電波が届き、通信が可能。つまりこれが発生すると遠距離通信が狙えるのだ。ただし、発生は突発的であり安定しない。
デリンジャー現象
太陽フレアによる一種の短波障害です。電子密度が増大したD層で短波が吸収されることにより短波が遠距離へ到達しなくなります。
磁気あらし
こちらも太陽フレアの発生で起きる現象です。