デジ簡(登録局)の申請方法は書類申請と電子申請の2種類
デジタル簡易無線(登録局)を使う場合は最寄りの総合通信局へ登録申請をして、登録状の交付を受ける必要があります。登録申請手続きには電子申請と書類申請の二種類があります。 絶対に書類申請(郵送)をお勧めいたしま…
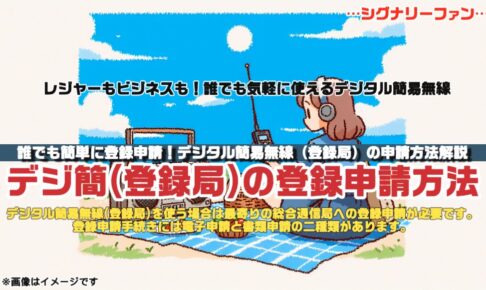 ライセンスフリー無線
ライセンスフリー無線
デジタル簡易無線(登録局)を使う場合は最寄りの総合通信局へ登録申請をして、登録状の交付を受ける必要があります。登録申請手続きには電子申請と書類申請の二種類があります。 絶対に書類申請(郵送)をお勧めいたしま…
 受信機は無線を聴くことができる
受信機は無線を聴くことができる
地上のアマチュア局が宇宙空間の国際宇宙ステーション(ISS)に設置されたレピーターを介して交信……それはISSが日本上空を通過する一瞬だけの奇跡。 宇宙空間を利用したアマチュア無線の運用はとても楽しく神秘的な体験になるか…
 ライセンスフリー無線
ライセンスフリー無線
デジタル簡易無線(登録局)にはAMBE方式とRALCWI方式の二種があります。これら二つの方式の注意点について考えてみましょう。 アルインコの独自通信方式『RALCWI方式』とは? AMBE方式とRALCWI方式では異な…
 資格と免許の取得
資格と免許の取得
アマチュア無線の運用で必要となるのが「アマチュア無線技士の国家資格」、すなわち従事者免許証の取得です。2023年現在、1級を除くアマチュア無線技士の資格の取得方法には「国家試験(国試)」、そしてこの記事でご紹介する「養成…
 ライセンスフリー無線
ライセンスフリー無線
タイトル画像の出典 映画『ロードキラー』より インターネット黎明期、男性が女性のフリをして、ある特定の趣向に好奇心の強い男性を掲示板上で”釣る”行為が流行った。顔が見えない匿名性を利用した、ある種のネット文化とも考察でき…
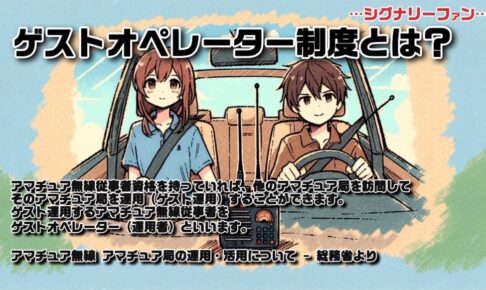 アマチュア無線
アマチュア無線
アマチュア無線のゲストオペレーター制度とは、1997年2月24日から開始された『アマチュア局の開設の有無にかかわらず、無線従事者資格のみで、他のアマチュア局を訪問して運用ができる制度』です。 具体的には、すでに開局をして…
 資格と免許の取得
資格と免許の取得
2023年9月25日、総務省ではアマチュア無線従事者資格の国家試験合格や養成課程修了から、アマチュア無線局の開設・運用までの期間が大幅短縮できるように「アマチュア無線従事者免許」と「アマチュア無線局免許」を同時に申請でき…
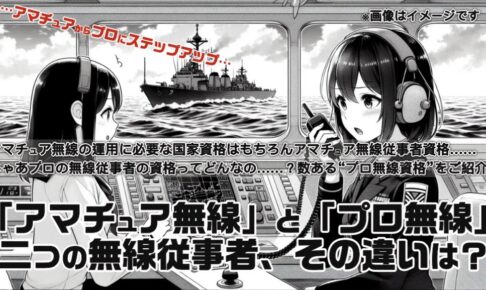 アマチュア無線
アマチュア無線
現在、アマチュア無線で行うことが許されているのは「アマチュア業務」です。電波法(第1条第78項)に明記されているその「アマチュア業務」の内容とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可…
 受信機は無線を聴くことができる
受信機は無線を聴くことができる
周波数の基本的な考え方として、周波数には既知の周波数と未知の周波数の二つがあります。 したがって、周波数の調べ方は大きく分けると以下の2つの手法があります。 1、web上で調べる web上で周波数を調べる手法は以下の3つ…
 アマチュア無線
アマチュア無線
局免が交付されると、そこにはあなただけのコールサインが記載されています。局免と同時にもらえる「呼出符号」とは? アマチュア無線では自局のコールサインを明示しての交信が定められていますから、正規に免許を受けたアマチュア無線…