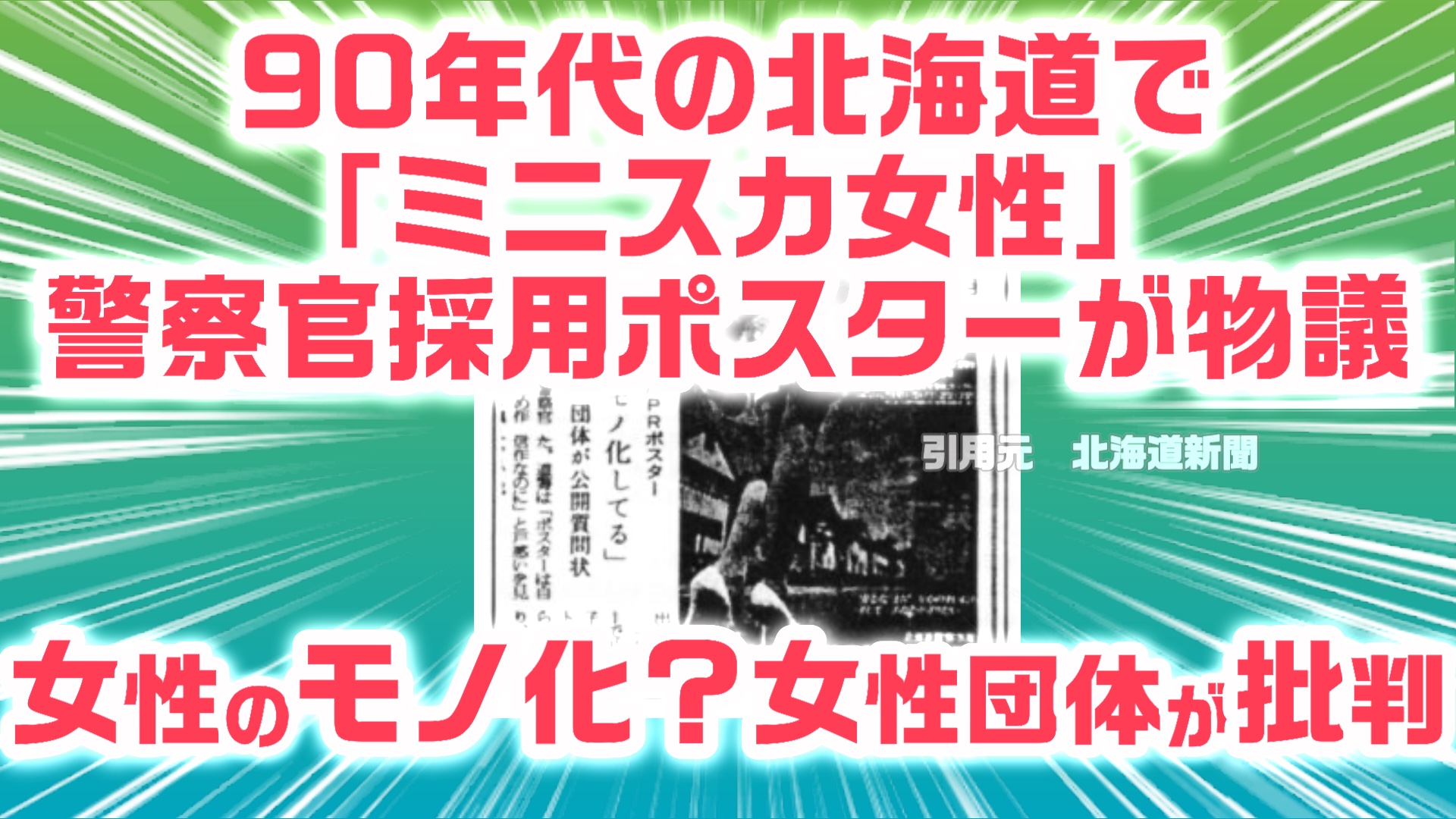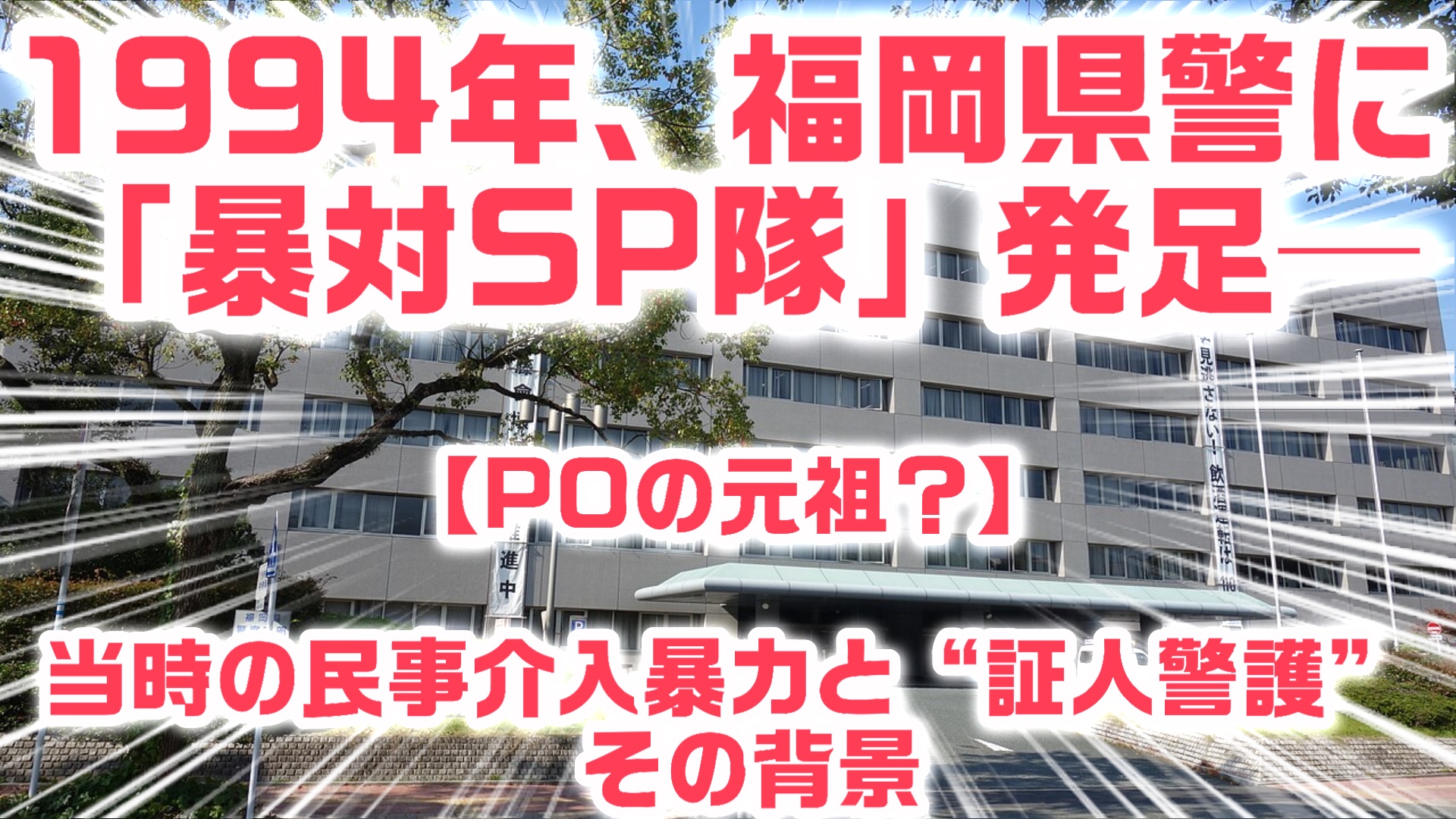バナー画像の引用元、90年代の北海道新聞紙面から
北海道警察の90年代ポスターに対する批判とその背景―ジェンダーと表現の自由、そして警察PRのあり方を巡って
2024年、日本の警察庁は「女性警察官のスカート型制服を廃止する」と47都道府県警察へ正式に通達を出した。
半世紀以上にわたって続いた「女性警察官のスカート」という警察装備品のひとつが、今その役割を静かに終えたことになる。

警察庁は今回の決定を「機能性の向上」として説明するが、この決定は、単に衣類の機能を更新したというだけではなく、その背後には、「スカート=女性」という単純な図式は、もはや現代社会の価値観とは整合しない、という認識があるのだろう。
多様性や選択の自由、性別による役割分担の解体が求められる時代において、性別と服装を単純に結びつける考え方そのものが、今の社会では見直されつつある。
ステレオタイプの打破、多様性の尊重といった流れは、警察組織においても例外ではないのだ。
「警察とフェミニズム」「行政とジェンダー平等」といった本質的な問題については、一般に深く論じられる機会は少ないが、当サイトでは、こうした「警察装備品とジェンダーの関係」にも注目している。
たとえば、日本の一部警察では、女性警察官向けに男性用よりも細身のグリップを備えた特殊警棒が導入されている。あるヨーロッパの国では、制式拳銃のグリップが女性警察官の手には太すぎるという理由で、運用に苦労しているという例もある。
こうした装備面の工夫や課題を掘り下げていくと、警察という組織の構造的な設計思想が見えてくる。
そうした中で、「スカートは女性のアイコンなのか?」という問いに向き合った過去の出来事がある。1990年代、北海道警察が作成したある警察官募集ポスターが、一部局所的に議論を巻き起こしたのだ。
「女性をモノとして描いている」――1990年代警察官募集ポスター騒動
90年代初頭、北海道警察は警察官・女性巡視員の採用にあたって、広告代理店に依頼して約1万1千枚のポスターを制作した。
全道の交番や警察署に掲示されたそのポスターは、制服姿ではない私服の若い女性が、短めのスカートとハイヒールを着用し、地面すれすれのローアングルから撮影されたものであった。
人物の顔は写っておらず、カメラは彼女の脚とスカートに視線を集中させていた。
このポスターに対して、当時の北海道新聞では札幌の女性団体「あごら札幌」が公開質問状を提出した一連の動きを次のように報じている。
道警の来春採用PRポスター 「女性をモノ化してる」 札幌の団体が公開質問状
北海道警が来春採用の警察官と女性巡視員募集のため作成したPRポスターに対し、札幌の女性団体「あごら札幌」が「なぜ女性の下半身をクローズアップしたポスターを使用しなければならないのか」と公開質問状を8月初め提出した。北海道警は「ポスターは自信作なのに」と戸惑いを見せている。
引用元 90年代の8月12日付けの北海道新聞紙面より
同団体は、図柄が「若者の目を引きつける」理由や、「警察がどんどん変わっている」こととどのように関係するのかについて道警に問うた。
また、団体のメンバーは「ミニスカート姿の女性の下半身を下からのアングルで撮っており、不自然。人物の顔が見えず、脚を強調する撮り方は女性を人格としてではなく“モノ”として扱っている」と批判した。
さらに「このポスターに類するもの、もっとひどいものは私たちの周りにあふれており、女性をモノ化していることに慣れてしまっているのかも。これも性差別の一環であることをわかってほしい」ともしている。
この批判に対し、北海道警察本部警務課は当時次のように説明した。
「この図柄は『夕暮れの新興住宅街でも、若い女性が一人歩きができる社会を北海道警察が作る』というイメージで『安心な”まち”安心のまいにち』というコピーを入れた。広告代理店に作製を依頼、1万1千枚を製作し、全道の警察署、交番で掲示した」
「若い年代の女性職員にも感想を聞いた結果、さわやかで若々しいと好評である」(北海道警察本部警務課)
記事によれば、北海道警察本部警務課によると、募集受付は同年8月7日で終了し、ポスター掲示の効果もあってか、女性警察官の応募率は前年より35%増加したという。
つまりこのポスターは、批判を受けながらも、一定の効果を上げていたことになる。
また、記事によれば、同課では「趣旨が理解されていないなら会員に会ってポスターの趣旨を伝えたい」として、対話の意向も示していた。
では、次のページで実際のポスターを見てみよう。もし興味がある場合は、次のページへと読み進めて欲しい。