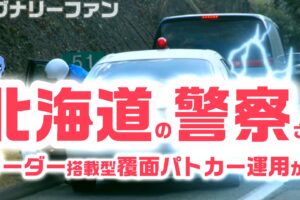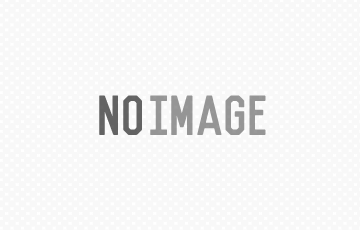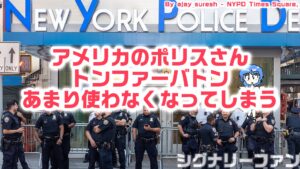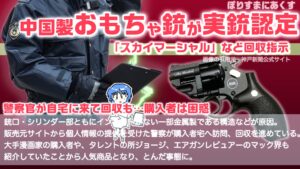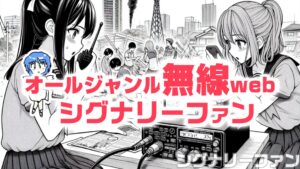各警察本部警備部に編制される機動隊。機能ごとの部隊も編成される機動隊では、多様性とニーズに応じた各種の特殊車両が配備されている。
機動隊が運用する特殊車両は多岐にわたる。集団警備には金網付きの遊撃車、暴徒排除には放水車が投入される。さらに、銃眼付きで装甲を強化した特型警備車も存在する。
災害現場ではレスキュー車や爆弾処理車が用いられ、人命救助や危険物の処理に対応する。任務の長期化に備え、トイレカーやキッチンカーなど後方支援車両も自前で運用されていることが興味深い。
これらの車両は、機動隊の多様な任務を下支えする装備である。
各種放水車

警視庁警備部第一機動隊(1機)の高圧放水車。通常型放水車とは水圧(法執行能力)が違う。 出典:警察庁ウェブサイト(当該ページのURL)
放水車は、車両上部または後部に放水砲を備えた特殊車両であり、主にデモ警備や暴徒鎮圧に投入される。
我が国を含め、諸外国の警察においても集団警備時の実弾使用は極めて稀であり、あくまで最終手段とされている。暴徒制圧に用いられるのは、催涙ガスやゴム弾などの非致死性装備である。
2020年7月、札幌市内で発生した立てこもり事件では、北海道警察SITがPepperball VKSを装備して出動しており、非致死性兵器の運用実態が注目された。
さらに、非致死性である水(放水)を用いた鎮圧手段は集団警備における多数の暴徒排除に、きわめて有効である。この放水機能を車両に備え、暴徒に対する実力排除の手段としたのが『放水車』である。
日本警察の機動隊が暴徒対策で配備する放水車には複数の種類があるが、その改良発展の歴史は、ある意味では学生ゲバルト(暴力)との戦いの歴史でもある。
遊撃放水車

警視庁の現行配備型遊撃放水車。小型の車体で機動性が高い。撮影/Ypy31氏
とくに成田デモ事件をはじめとする学生運動での警備における暴動鎮圧で出動した遊撃放水車。小回りの利く車体が活用された。高圧放水の直撃を受けた者は4,5メートル吹っ飛び、機動隊員に警棒で直接殴られるのと同等のダメージを受けたはずだ。
警備車兼放水車
遊撃放水車よりもやや大きい車体が特徴で、常駐警備車と放水車の機能を併せ持った車両。70年代安保当時の”カマボコ”タイプの三菱ふそうザ・グレートがベースのタイプはすでに旧型だが、現在は同社のスーパーグレートをベースとしたタイプが配備されている。
高圧放水車

機動隊が用いる実力排除手段には、盾を用いた突撃、警棒による制圧、ガス銃からの催涙ガス水平発射、そして放水がある。中でも放水は象徴的な手段だが、必ずしも万能ではない。
1950~70年代の安保闘争期、バス型の警備車兼放水車が暴徒に対し威圧的に放水を行っていたが、多勢に無勢となり、車両が持ち上げられ横転させられる事態も発生。
この教訓から、より強力な高圧放水能力が求められ、特定部隊にのみ配備されたのが「高圧放水車」である。警視庁や神奈川県警の一部機動隊に導入され、4000リットルの水槽を搭載。約2分間の連続放水が可能で、射程は100メートル以上に及ぶ。
警視庁第一機動隊に所属する高圧放水車は、1995年のオウム真理教施設捜索時、ならびに2011年の福島第一原発事故においても投入された。後者では、機動隊員が高圧放水車を操作し、東京消防庁のスーパーポンパーや自衛隊の大型消防車とともに炉心冷却作業に従事した。
朝日新聞の2011年3月17日付報道によれば、当時、警視庁の高圧放水車は全国で1台のみの配備であった。
警察幹部によると、使用が検討されているのは、警視庁が全国の警察で1台だけ保有する「高圧放水車」とみられる。通常の放水車は警視庁の各機動隊に数台ずつ配備されるが、高圧放水車は第1機動隊(千代田区)だけが持つ。タンクに入る水の容量は4千リットル。消防車両を大きくしのぐ12気圧の水圧で、100メートル近い距離を飛ばす能力があるという。
出典 朝日新聞社 2011年3月17日1時7分付け 当該URL
しかし、高圧放水車は本来、暴徒鎮圧用のため、消防車のように放水ノズルの仰角がとれないため、このような任務には困難であったのも事実。
ただし、この高圧放水装置は対人(暴徒)用としてはすこぶる高い制圧能力を持っており、放水搭は車中からリモコン操作が可能で、凶器を持った暴徒の動きを封じ込めるには非常に有効な車両である。
高所放水車

高所放水車。撮影/Ypy31氏
現在は用途廃止になっているが、警視庁のみに配備された大型車両で、高所への高圧放水を可能とした特殊車両。
各種警備車
「特型警備車」とは、我が国の警察において装甲車両の制式名として採用されているものである。この車両が実際の暴徒鎮圧の前線に投入されたのは、1970年の第2次安保闘争においてである。
その登場の背景には、1950年代から激化した学生運動がある。初期の学園紛争では投石が主だったが、次第に火炎瓶などを用いた過激な行動へと移行。当局はこれに対応するため、大型バスに簡易装甲を施した即席の装甲車を導入した。
しかし、大型バスをベースとしたことで小回りが効かず、また構造上の問題から活動家らによじ登られるといった脆弱性も露呈した。この反省を踏まえ、70年安保を控えた警察当局は新型装甲車の開発に着手。その結果として誕生したのが「F-3型 特型警備車」、通称「コマンドカー」である。全長は7.36メートル、最大乗員は14名におよぶ。機動性と防御性を兼ね備えた専用設計であり、以後、各地の機動隊に配備されている。
旧世代の特型警備車
特型警備車が登場した背景は学生運動が激しかった50年代にさかのぼる。当時の学園紛争は投石から火炎瓶へと過激化。それに対処する当局側では大型バスに簡易な装甲を施した即席の装甲車両を投入して暴徒鎮圧警備を実施。
しかし、大型バスを流用したために車体が大型過ぎて運用には難があった。よじ登る者も出た。そこで70年安保闘争を控え、新たに開発されたのが全長7.36 m、最大乗員14名の「F-3型 特型警備車」通称コマンドカーであった。
| 名称 | F-3 |
| 全長 | 7.36 m |
| 全幅 | 2.49 m |
| 全高 | 2.2 m |
| 重量 | 11.16トン |
| 主要装備 | 放水砲 |
| 乗員数 | 14名 |
『F-3型』特型警備車はまさに軍用装甲車を意識した物々しいスタイルだが、”武装”は非致死性の放水銃を備えた砲水塔を備えるのみで、銃器は搭載されておらず、機動隊員の携行する短銃、ガス銃などを使用するための銃眼が車体側面と前後部の計6箇所に設けられている。
また、暴徒がよじ登れないよう斜めにカットされた車体デザインと全面シルバー色が、体制へ牙を剥く者へ威圧感を与える。また車体側面の下部にも工夫があり、暴徒が持ち上げて横転させないようにノコギリ状にされている。
あの、あさま山荘事件にて出動した実績がある。
この特型警備車、近年では東京都の排ガス規制に引っ掛かるため、警視庁から栃木県警察へと移籍したのち、用途廃止になった。
またF-3型を小型化、4WD化して走破性と機動性を高めたF-7型も配備されたが、こちらも現在は全車、用途廃止となっている。
現行配備の特型警備車
近代以降配備される特型警備車はアメリカの装甲現金輸送車のようなスタイルに変更され、ブルーを基調としたカラーリングになっている。

前方に可動式防弾板やカメラ、側面には銃眼を備えた特型警備車PV-2型。ルーフ中央には機動隊員が身を乗り出せるように開口部が設けられ、装甲板を起こして盾代わりにも出来る。
こちらもまた、ゾンビが車両に手や足をかけてへばりつくのを防ぐため、車体は全面的に突起をなくした伝統のスムージング加工。側面2連銃眼設置済み。
常駐警備車

撮影/Ypy31氏
現場常駐型警備に投入される車両。金網防護の遊撃車よりも防御力が高い。
小型警備車

撮影/Ypy31氏
銃器対策警備車
側面3連銃眼を設置した銃器対策警備車。当然、使用者は日本警察の持つ『最後のカード』こと特殊部隊SAT。
各種遊撃車
一方、遊撃車は放水などの直接的な実力手段を持たない車両だが、一部装甲化されている車両もあり、いわば簡易的な盾や小隊の展開手段として使用される車両だ。
部内では『マル遊』と呼ばれる遊撃車にはI型からIV型、そして小型、特型まである。
遊撃車I型
マイクロバスベースの車両。車体防護は金網のみ。

撮影/Ypy31氏
遊撃車II型

マイクロバスベースの車両。車体防護は金網のみ。
遊撃車III型
別名・ゲリラ対策車。小型のワゴン車ベースの多目的車両。一見、金網のついた”護送車”だが、これは機動隊が警備活動のために使う車両で、重防こと重要防護施設の張り付き警備から人員輸送まで使用される便利な展開手段だ。

ニッサンキャラバンをベースとした遊撃車(III型)。護送車は車内に金網を設置するが、遊撃車は外側だ。
80年代から90年代までは走破性の高い三菱のデリカワゴンだった。この特有の濃紺カラーは現在では旧式となり、2015年からは白と青のストライプデザインとなり、金網も非搭載となった。
警察の表記はないが、フロントの旭日章、ルーフの赤色灯、そして金網が特徴。テロやゲリラ事案での張り付き警戒と警備にはもってこいの車両だ。
遊撃車IV型
機動隊では珍しい覆面パトカータイプのミニバン型車両。主に目立たない警備を要求される現場で活用される。近所のお祭り会場付近で、いかつい顔をしたマツダボンゴ(E-SSE8W)が赤色灯で威圧しながら暴走族に突っ込んでいった夏の日のあの光景を忘れられない。そのあと家に帰って、震えながらちびまるこちゃんをあたしゃ見たんだよ。何歳だよ。
小型遊撃車
200系ランドクルーザーをベースとした防弾・覆面機動車両。街中を銃乱射しながら逃げまわるヤバイやつ対策のために銃器対策部隊に導入、配備された。外見上は真っ黒スモークのいかつい闇金回収車みたいな200系ランクルだが、防弾ガラス仕様のため、窓枠が太くなる。乗ってるのは警備部機動隊の銃器対策部隊員。ルーフにユーロアンテナを設置および前面赤色灯を秘匿搭載。ルーフの赤色灯は着脱式。
特型遊撃車
特型警備車PV-2型から重い防弾装備を取っ払い、機動性を重視した軽装甲タイプ。
爆発物処理車
爆発物の対策にあたる車両を便宜上まとめて爆発物処理車と呼ぶ。以下の各種の車両によって爆発物の解体、運搬などの任務に当たる。
爆発物処理筒車

警視庁の爆発物処理筒車 撮影/Ypy31氏
いすゞエルフなどトラックベースの特殊車両。後部に爆発物処理装置を搭載し、液体窒素などを使って爆弾の起爆装置を急速冷凍で凍結させ、回路等を損傷させることで爆発を防ぎつつ、解体処理のため緊急走行で速やかに安全な場所まで輸送するのが任務。
爆発物処理用具I型

アームを使って爆発物処理筒車の処理筒に模擬爆発物を投入する爆発物処理用具I型(手前)。出典:警察庁ウェブサイト(当該ページのURL)
コマツの民間向け工事用小型油圧シャベル機を警察の要請で爆発物処理用に改修した装備品だ。日立建機製の爆発物処理用具I型双腕タイプもある。
爆発物処理用具運搬車
上記の『爆発物処理用具I型』を専用運搬するのが、緊急走行可能な平型ボディトラックの爆発物処理用具運搬車である。
爆発物処理用具資材運搬車
爆発物処理用具関係の液体窒素、整備用の関連資機材を運搬するための車両。基本的に緊急走行可能なアルミバントラック型車両である。後部にパワーゲートを架装している。
レスキュー系車両
警視庁機動隊の中には主に災害救助活動に従事する機動救助隊(通称・レスキュー110)も編成されている。余談だが「ドーベルマン刑事」にてレスキュー110隊員を主題にした話があり、警察官と救助隊員という二つの立場のはざまで、隊員が犯人の”救助”に奮闘するエピソードがあった。あろうことか犯人は救助に来た110隊員の優しさに付けこんで外道なことをしたために、駆けつけたドーベルマン刑事にスタームルガー・ブラックホークでドゴーッ!と撃たれるというたいへん心に残るエピソードであった。何歳だよ。
レスキュー車

高性能救助車

埼玉県警のウニモグ型高性能救助車
1.2メートルの水深を進み、また、45度の傾斜をものともせず登坂できる高性能4WD「ウニモグ」。『エリア88』ではスーパーローギアで急斜面の険しい崖を一気に駆け上がったため、当時の少年らに激しいウニモグ全地形完全走破幻想を抱かせた。何歳だよ。
ミニレスキュー車

黒豹マークはレスキュー110こと機動救助隊
警視庁の機動救助隊レスキュー110で配備されている軽自動車のレスキュー車。
山岳救助車

警視庁の山岳救助隊で配備されている山岳救助車。
各県警に編成された山岳専門のレスキュー部隊は航空隊のヘリコプターとも連携し、遭難者の救助や捜索に当たる。
水難救助車

警視庁の機動救助隊レスキュー110で配備されている水難救助車。緑色の車体が特徴だ。
全国都道府県警察の機動隊に設置されている水難救助隊に配備されている車両。救助隊員用の資機材が積まれ、災害時は救助活動を行うが、隊員は水難救助専従ではなく、普段は制服で重要施設の警備やデモ・祭礼警備、重点パトロールなど多様な活動にあたっており、水難救助の任務が充てられた際にのみ、水難救助部隊として召集され活動。
平時は事件捜査で水中の証拠物件の捜索にも投入される。
資材運搬車

機動隊に配備されている小型のトラック。主に機動隊用の資機材の輸送に活躍する。トヨエースなど車種は複数あり、写真のアルミパネルタイプから平型ボディタイプもある。緊急走行に対応できるが、キャビン上の警光灯は高いアルミパネルのため、後部からは見えにくくなっている。
このため、別途アルミパネルの後部およびサイドにもフラッシュ式の警光灯が搭載されている。

ユニック搭載型も配備されている。撮影/Ypy31氏
また、県警によっては着脱式の赤色灯を必要に応じて装着し、車体に警察の表記の入らない『覆面』タイプもある。
化学防護車両
毒物などを使用したテロ事件に対応するため、警視庁特科車両隊などでは化学防護車を配備している。
化学防護車

警視庁警備部機動隊特科車両隊の化学防護車。撮影/Ypy31氏
警視庁の化学防護車には警備部(機動隊)用の救助を目的とした車両と、公安部公安機動捜査隊の捜査用車両がある。
除染車

警視庁特科車両隊の除染車。撮影/Ypy31氏
NBC対策車

警視庁、神奈川、千葉県警などに配備される対化学テロ特殊車両。地下鉄サリン事件に代表される都市における大規模な化学、核、生物といったNBCテロに出動する。同種の車両に化学防護車もある。
放射線防護車
警察庁が2013年4月に福島県警へ導入した一両、一億五千万円の大型車両。全長10メートル、重さ22トンのバス型車両でガラスには鉛を使い、車内の気圧も完全に調整され、放射性物質の流入を防止する構造。福島などの放射能汚染地区における対テロ作戦や、原子力災害時、住民救出に投入されるという。同じく警視庁にも一台配備された。
後方支援系の特殊車両
最前線で活動する機動隊員の団結力を強め、士気や鋭気を養うのに必要なものは部隊長の激、そして隊員に分け隔てなく供される温かい食事であるはずだ。
いわば、縁の下の力持ちとして、後方支援を務めるのがこれらの車両。
キッチンカー

警視庁のキッチンカー。撮影/Ypy31氏
恒常的な常駐警備では、おべんと担当者が外部の仕出し屋に弁当の発注を折衝するが、突発的イベントにおける集団警備でもメシに困らない頼もしい車両が、機動隊が自前で保有するキッチンカー。
あの有名な『あさま山荘事件』では、支給された弁当も苛酷な真冬の環境ではすぐに凍った。コレでは士気もがた落ち。そこで急遽、機動隊員に配給されたのが、当時発売直後の温かいカップヌードルだったというエピソードは余りにも有名。
警視庁のキッチンカーは自衛隊の野外炊具のような本格的車両ではなく、電子レンジと湯沸かし機、それに炊飯器といった必要充分にして基本的なキッチンセットのみ搭載。すぐ美味しい、すごく美味しい温食を供給できるの。
トイレカー
こちらは出すものの処理に使用される車両。警備事案など多くの警察官が動員される場合に活躍。張りつき警戒中の排出作業は極めて困難。付近に公共施設のトイレが無い場合にはこの移動式のトイレ車が出動。ベンツ製。
機動隊の特殊車両まとめ
このように、機動隊の車両は警察車両の中でも異彩を放つ特殊車両がずらりと揃っている。どれも機動隊が集団警備を実施するために必要な車両である。
また警備部の機動隊車両のカラーリングは警察車両の中でも特異。警察の車両はアンマークの覆面パトカーを除けば白と黒のツートンだけでなく、多様なカラーの車両があり、とくに警備部の車両では古くはグレー、近代では濃紺、さらに昨今では青と白のツートンの新デザイン。また警視庁機動隊の救助系部隊ではグリーンなど多様。
なお、この項目を作成するにあたり、警察庁公式ウェブサイトが国民向けに公表している広報資料『警察白書』のほか、Ypy31氏がwikipedia上にてパブリックドメインで公開されている各車両の写真を利用した。この場を借りてお礼を申し上げたい。