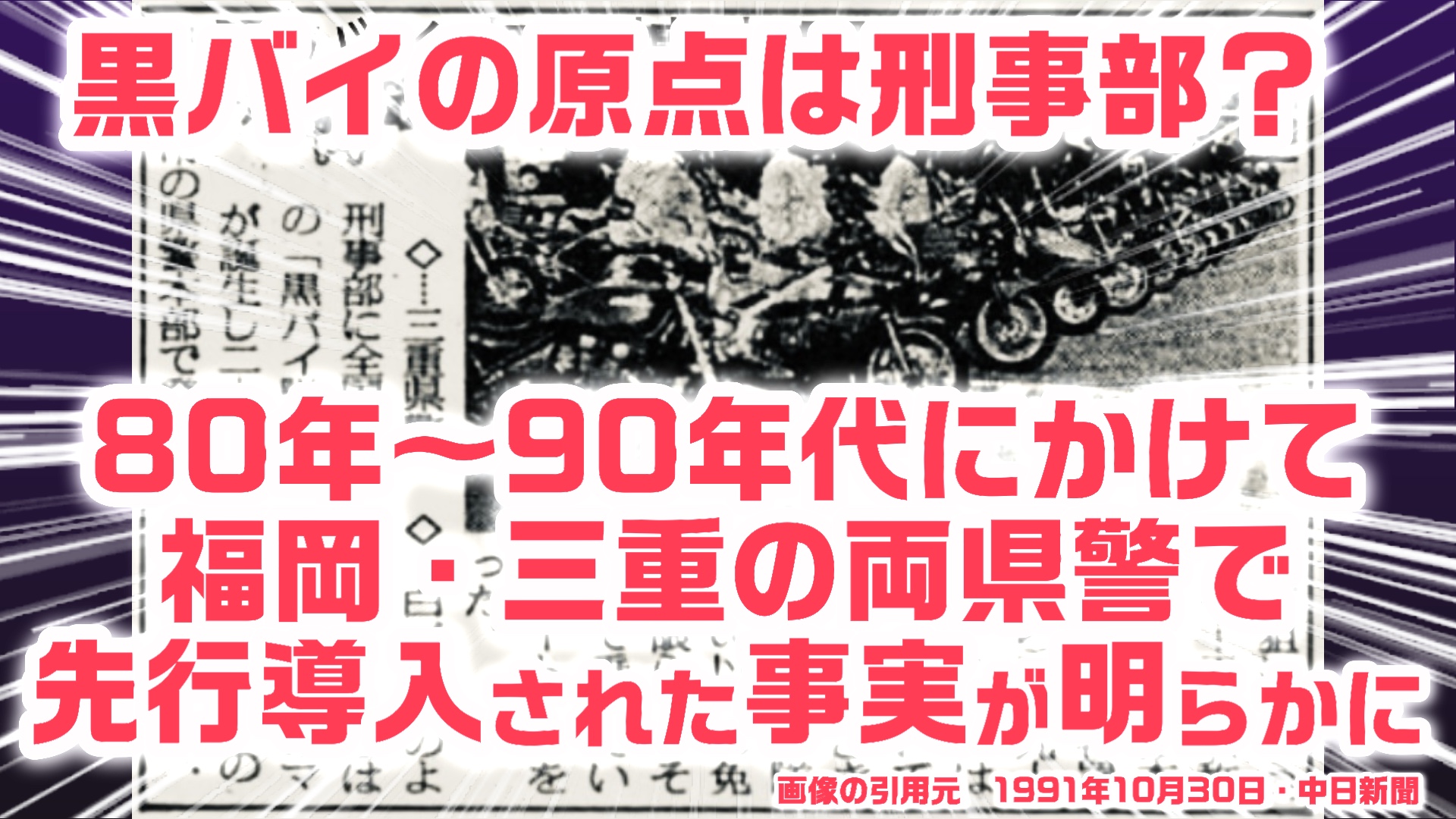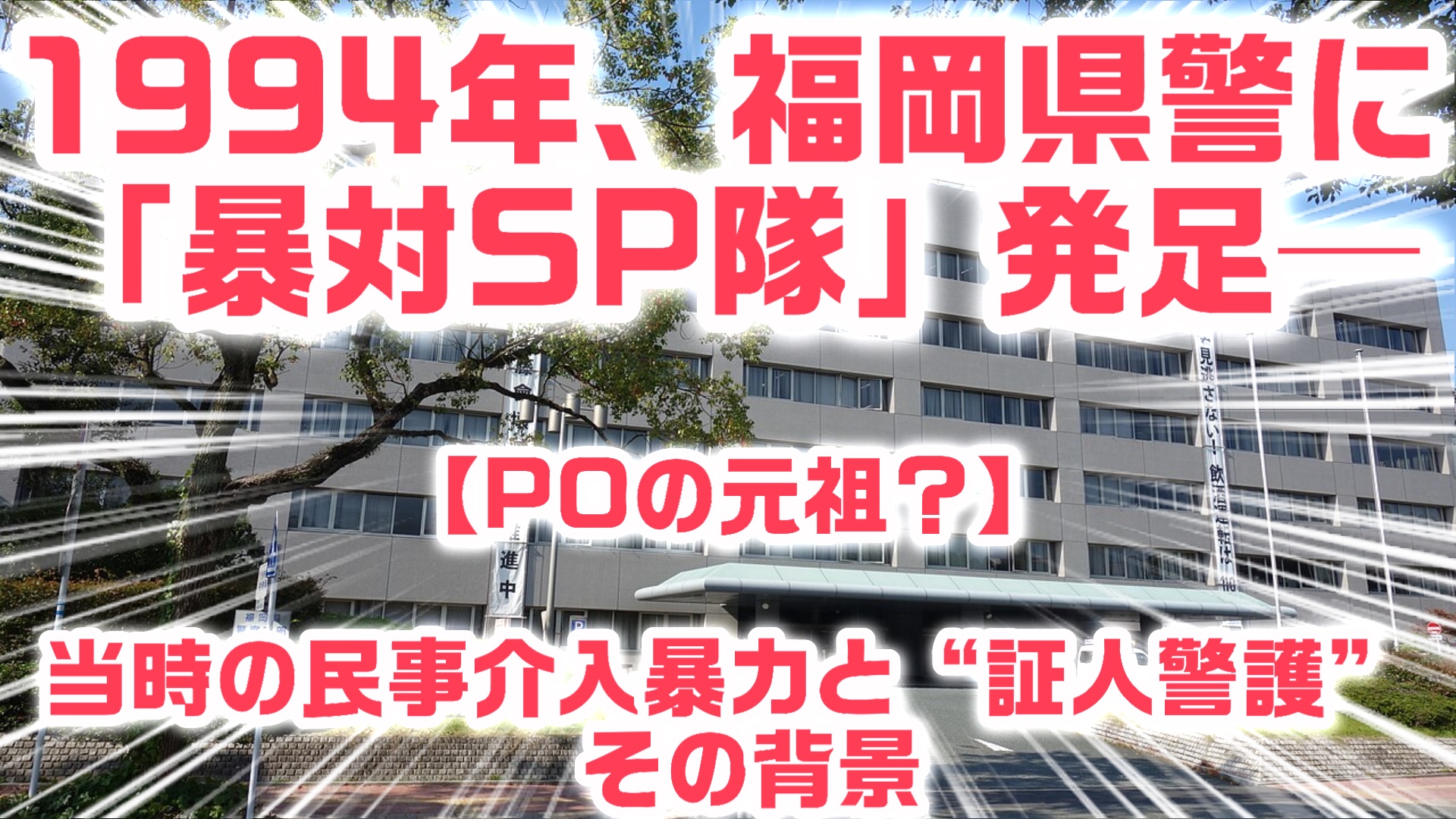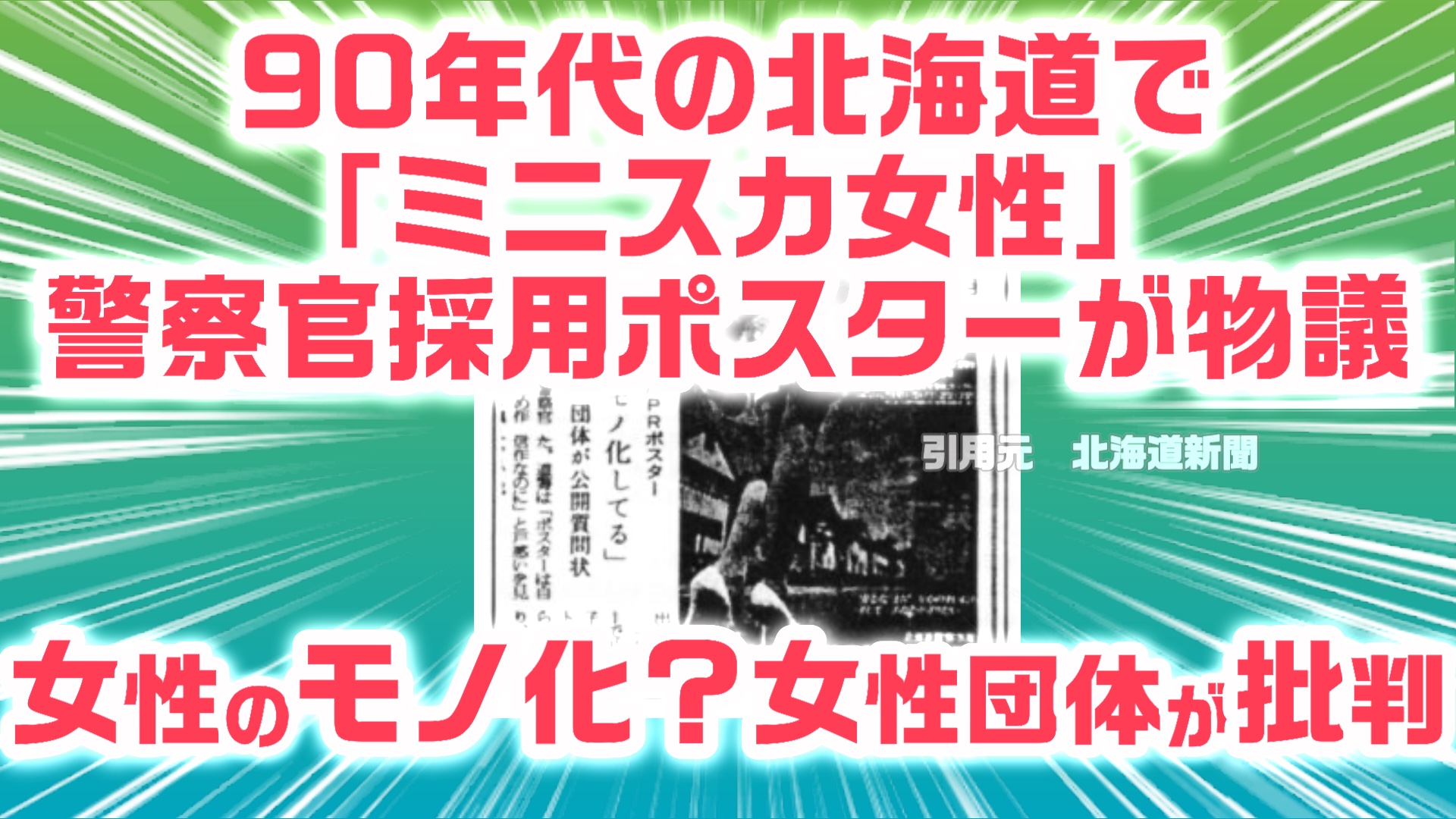福岡県は11日、暴力団総合対策委員会を開いて決め、正式名称は「暴力団事件における被害者等保護対策専従員」(通称・暴対SP隊)となる。
福岡県警捜査4課が本部と各警察署から、柔道2段以上で30歳未満の「士気旺盛(おうせい)」な精鋭を選び、隊員として登録する。隊員は、ふだんは所属する課や署で仕事をするが、暴力団事件で証人などの護が必要となった場合、専従のSPとして動く。
証人の自宅などを管轄する警察署員が中心になって数人でSP隊の1班を編成、自宅や職場周辺で暴力団に目を光らせる。3交代、24時間態勢で本人に張付いたり、家族などをガードしたりもする。県警のプロから響護方法を学び、射撃訓練も定期的に実施。教官として警視庁のSPを招くことも検討している。
映画監督の伊丹十三さんが「民事介入暴力」をテーマにした映画を製作したことがきっかけで組員に襲撃された事件では、捜査に協力した関係者が「暴力団からいやがらせを受けた」と公判で証言した。
福岡県警でも1986年5月、暴力団組長を告訴した福岡市の金融業者が配下の組員に刺され、死亡している。
企業幹部が襲われるケースも各地で目立つ。今年2月には、以前、総会屋対策の責任者だった富士写真フィルムの専務が東京・世田谷の自宅前で何者かに刃物で襲われ、殺された。
6月には株主総会シーズンがピークを迎えることもあり、福岡県はより徹底して関係者を守ろうと、体制を充実させることにしたという。県警捜査4課長は「従来も守ってきたが、一層市民が安心して被害を訴えることができるようになり、暴力団捜査の障害も除かれると期待している」と話している。
引用元 1994年5月12日付 朝日新聞より
暴対SP隊の発足背景には、当時の福岡県内における暴力団抗争や組織犯罪の激化があったようです。
とくに、1990年代初頭に社会問題化した暴力団による民事介入の増加が挙げられるでしょうね。いわゆる「みかじめ料」や不当要求、さらには市民生活に介入する形での恫喝行為「民事介入暴力」が横行し、企業や市民が暴力団からの報復を恐れて声を上げにくくなる状況が続いていました。
こうした流れの中で、1992年には「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)」が施行され、社会全体として反社会的勢力に対する規制を強化する機運が高まっていきました。
また、記事でも触れられている通り、その象徴的な文化的事件として挙げられるのが、1992年公開の伊丹十三監督作品『ミンボーの女』です。
同作品は、暴力団による民事介入を題材にしており、暴力団に目をつけられたホテルを舞台に「ミンボーの女」こと弁護士の井上まひるが「男の僕たちでさえ怖いのに…」と恐れ慄くベルボーイたちに奮起を促しつつ、暴力団の不当な要求に立ち向かっていく社会派の風刺劇です。
ところが、同年5月、映画公開直後に伊丹監督は暴力団員によって襲撃され重傷を負う卑劣な事件が発生し、表現の自由と反社会的勢力の実態が世論の注目を集める転機となりました。さらに翌1993年5月30日には次作映画『大病人』が公開中の映画館で、上映中に暴力団組員がスクリーンを切り裂く嫌がらせも起きています。
このように暴力団による自分たちの存在誇示、捜査協力者への報復、企業への恫喝的手法が目立ち始める中、警察の側が積極的に保護と警護を行わなければ、被害者が沈黙することになり、暴力団の影響力が社会に浸透する危機感があったのです。
そこで、これまでの暴力団摘発作戦と同時並行的に行われたのが、暴力団に狙われている市民や関係者の身辺保護という、福岡県警の新たな任務です。
暴対SP隊の主な警護対象となるのは、暴力団の脱退者や内部告発者、企業のコンプライアンス担当者、さらには事件で証言を行うことを決意した市民らです。
また、隊員たちは普段は所轄の業務をこなし、事件が発生し証人や企業関係者に危害が及ぶ可能性がある場合には、速やかに警護任務に就く兼務制となっているのも、のちの「PO」とそっくり。
そして、この制度は単発で終わらず、その理念は2011年に警察庁が定めた新たな任務体系「PO(プロテクション・オフィサー)」制度に継承されています。
かつての福岡県警暴対SP隊同様、PO制度は暴力団事件のリスク対象者への警護が任務です。民間人を暴力団等の脅威から守るという任務が全国的に体系化された形であると言えるでしょう。
とくに福岡県警察は、2011年に改正された県の暴力団排除条例の成立を受け、同年12月21日に「暴力団対策身辺警戒隊」を新設。警戒隊は、県警組織犯罪対策課などに所属する数十人の警察官が兼務する形で編成され、県内に数百人いるとされる警護対象者以外でも、必要があれば臨機応変に出動する体制が取られていました。
その後、2013年3月には、警戒隊を発展的に改組し、「保護対策室」が設置されました。
保護対策室は約110人の体制で、全国でも最大規模の専門部隊です。
室内には、警護対象者の選定を担当する「保護企画係」や、実際に警護活動を担う「襲撃抑止対策係」などが設けられ、より体系的で機動力ある活動が可能となりました。
この保護対策室は、警護活動にとどまらず、暴力団内部から得た情報をもとに、過去の脅迫や傷害事件などの捜査にも取り組んでいます。
また、福岡県内では、民間人だけでなく、暴力団関連事件に関わった司法関係者も警護対象に含まれており、福岡県知事や福岡市長といった公人も、必要に応じて警護対象となっています。
このように、「暴力団対策」という枠組みは、単なる摘発や取締りといった「壊滅作戦」だけでなく、市民社会を構成する個人の“安心”を守る制度へと進化してきたのです。
その端緒となった94年発足の福岡県警の「暴対SP隊」の存在は、警察制度史における重要な転換点のひとつといえますね。
余談ですが、警察の新任務や装備を福岡県警が先行導入する例は、他にも「黒バイ」があります。