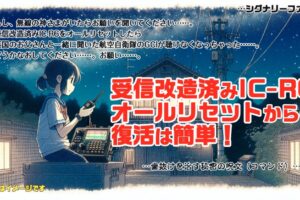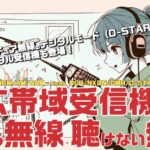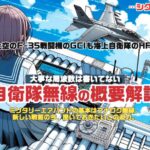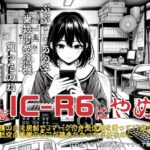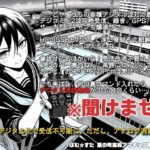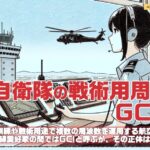Contents
日本の漁船や旅客船、プレジャーボートなど各種船舶および海岸局が行う海上無線通信には国際VHF、漁業無線など複数。これらをまとめて本稿では「船舶無線」と呼称する。
国際VHF(船舶共通通信システム)
手っ取り早く船の無線を聞きたいのなら、国際VHF(船舶共通通信システム)の16チャンネルが最もベストだ。世界各国の船舶で最も普及している世界共通の標準的船舶通信システムであるからだ。
大海原を航行する大型タンカー、貨物船、豪華客船、海上保安庁や海上自衛隊、各国海軍の各種船舶、そして海岸局と呼ばれる港湾の管理事務所の無線局。これらはVHF帯の150MHzから160MHz(FMモード)に割り当てられた世界共通の計57チャンネルを使う「国際VHF(船舶共通通信システム)」にて、互いに航行安全上の通信を行うことが定まっている。
国際VHF(船舶共通通信システム)とは?
■船舶の航行のための通信に使用する国際的なシステムです
150MHz帯を使用し、船舶において遭難・安全通信・港務通信、電気通信業務、水先業務等に使う無線通信システムで、全世界的に使われているため「国際VHF」と呼ばれています。総務省では、船舶のより安全な航行を実現するため、小型船舶等に任意で設置することができる安価な国際VHF機器の普及を図るべく、平成21年に「船舶共通通信システム」として制度の整備を行いました。国際VHFは、航行の安全に関する重要な通信を行うものとして多数の船舶に利用されています。
出典 日本マリン無線協会 https://marine-vhf.jp/marine-vhf.html

57チャンネルのうち、156.800MHzは16チャンネルと呼ばれ、航行中は必ず聴取が義務付けられているのと同時に、呼び出しと応答専用ともなっており、遭難安全通信用にも使用される。ここで呼び出して、他のチャンネルに移って交信をするのはアマチュア無線やデジ簡と同様。つまり16チャンネルを聞いていれば、即座に大海原を行く船の無線、航行案内を行う海岸局からの送信をワッチ可能だ。チャンネルによっては海上保安庁の船舶局、海岸局、航空機局との通信に使用するものもある。
総務省による国際VHFの説明(pdfファイル)を参考にしてほしい。
前述したとおり、これは世界共通の通信システムで大型船舶は設置が義務。

国際VHF用の無線機各種。画像引用元 https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/life/technique/navigation/vhf.html
2018年に発生した日本の自衛隊機に対する韓国駆逐艦レーダー照射事件でも、日本のP1哨戒機側は国際VHFの16ch、それにVHFとUHFの二つの国際緊急周波数を使って、韓国艦艇側にレーダーによるロックオンの意図を繰り返し問い合わせたが、国際的に取り決められた安全航行のための周波数や緊急事態用の周波数による問い合わせを韓国海軍は一方的に無視ている。
というわけで、手っ取り早く「船の無線」を聞きたいのであれば、国際VHFの16chをワッチしてみよう。毎朝、16チャンネルで航空無線とはまた違うハッキリした英語で「プリーズ、チャンネル、ワン、フォー」などと、海岸局と各船舶との交信を聴取できるはずだ。
なお、実務としてこれらの通信に携わる業務局の職員が国際VHFを使用するためには第一級から第三級総合無線通信士、第一級から第四級海上無線通信士、第一級から第三級海上特殊無線技士のいずれかの無線従事者資格を取得していなければならない。
また、この国際VHFのシステムの中には、我が国の沿岸海域のみを航行する国際VHFや、漁業無線なども設置していないレジャー船、プレジャーボート用として、日本独自の「マリンVHF」という制度がある。1988年(昭和63年)に発生した自衛隊潜水艦と釣り船との衝突事故「なだしお事件」が導入契機となっており、緊急時の連絡体制をいかに確保するかということであるが、マリンVHFには国際VHFと違い、聴取義務はないのが特徴だ。ただし、マリンVHFも国際VHFを使用する大型船舶や海上保安庁との直接通信が可能だ。
漁業無線
一方、漁船は所属漁協や僚船との通信を1.7MHz、2MHz、4MHz、8MHz、27MHz、39MHzといったHF帯で行なっている。無線局免許は漁協か漁業無線組合に交付されるのが通例で、各漁協に割り当てられている周波数一覧は総務省公式サイト(PDFファイル)で公開されておりチェックしたい。なお、J3E、H3EはSSB、A1Aはモールス、A3EならAMだ。8MHzは韓国の海岸局も使用しており、日本国内でも受信可能。また、日本の民間プロ無線からは廃れてしまったモールス(電信/CW)が漁業無線では今なお生き残ってもいる。

漁業無線の使う27MHz帯では27.524MHzが呼び出し周波数となっている。ただし、早朝の定時放送を除けば、交信頻度自体は少ない。驚くことに漁業無線では秘話も使う。27MHzはCB無線(市民ラジオ)の帯域としても割り当てられていて、ご存知の通り、夏ごろにダクト現象やEスポが出れば、遠距離でも受信可能。
電波モードはSSBを使うことが多いので、SSB対応の比較的高価な広帯域受信機の上位機種か、HFアマチュア無線機があると良い。筆者はIC-R30で傍受しているが、”受信機を選ぶ無線通信”である点については同じくHFバンドかつSSB(そのうちのUSB)モードを使う航空無線の洋上管制同様で、残念ながら当サイトでおすすめしているIC-R6や同価格帯のハンディ型受信機では漁業無線の受信に適さない。その理由は二つあり、以下の洋上管制の記事で解説している。
なお、HFかつSSBモードを手軽に受信したいならば、高価なHFアマチュア無線機がなくとも、1万円前後のSSB対応BCLラジオでも受信可能。以下の記事にて人気機種を解説している。
基本的には各地の漁協ごとに周波数が割り当てられており、海岸局である各漁協無線局(コールサインは○○ぎょぎょう)と、漁協所属漁船との交信が主なもの。交信内容は主に海水温、気象情報など。当然、漁獲高や良好な漁場などの情報をやり取りすることもあるため、平文のほか暗号を使った交信がなされたり、FURUNO社の秘話装置を使った秘話通信を使うこともあり、非常に興味深い交信と言えそうだ。この秘話は民間船に妨害を与えることもあるとしており、必要最低限の使用が漁協より推奨されている。
常に交信されてはおらず、海岸局からの定時放送のほかは閑散としたものだ。ところが北朝鮮からミサイルが発射された場合は自動音声でセキュリティが発報され、安否確認が行われることもある。
北朝鮮がミサイル発射 太平洋で操業中の県内漁船に被害なし
4日朝、北朝鮮が弾道ミサイルを発射したことを受け、日南市にある油津漁業無線局では、東北沖など太平洋で操業中の県内の漁船に対して情報を伝えるとともに、安否の確認を行いました。
引用元 https://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/20221004/5060013826.html
上述のEスポ発生時はモービルホイップでもいけるが、やはりHF用アンテナを立てられる環境が最高だ。ワイヤーアンテナも可。大掛かりなアンテナでなくとも、ベストセラーのHF用受信専用アンテナがあればいい。
船舶無線のまとめ
航空無線にHFの洋上管制があるなら、漁業無線にもHFのマグロ無線があるわけだ。エアバンドや一般業務無線の受信に飽きたら、これら船舶無線にチャレンジしてみよう。
「ボクんちの近所に海なんかないよ!」なんて嘆くなかれ。海から離れた内陸部に住んでいるから船の無線なんて聞けそうにない……なんて諦めの声も聞こえてきそうだが、大丈夫。国際VHFに関して言えば、海面反射により意外と遠方まで聞こえている。海岸から山を挟んで100キロは離れた内陸部でもコンディション次第。まずはダメもとで国際VHFの呼び出し周波数である156.800MHzを受信機にメモリーしておこう。
一方、HF帯の電波も電離層に反射するため、夏場のEスポ発生時には受信のチャンスが多くなる。ただし、HFの場合はSSBも使うので『SSB対応BCLラジオ』があると良い。
なお、フライトレーダー24同様に船舶のリアルタイムな動向がわかるサイト・MarineTrafficもあるので、日本のほか世界中で漁船や貨物船、旅客船、漁業監視船など、おおまかな船舶のリアルタイムな位置を知ることができる
漁協、各種船会社、さらには国立高専に割り当てられた周波数は総務省で公開されているので、目を通しておこう。
総務省公式サイト https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/06.pdf