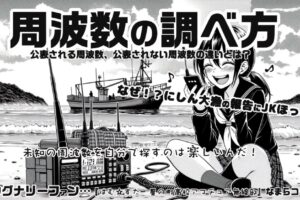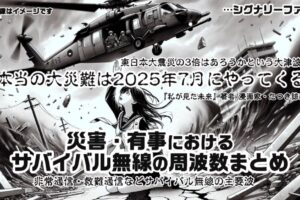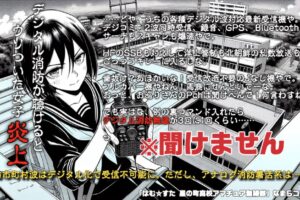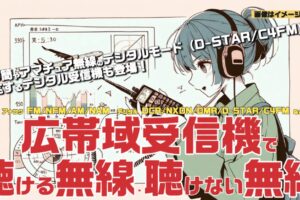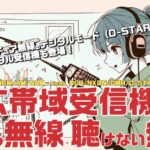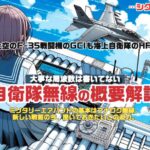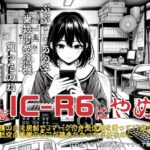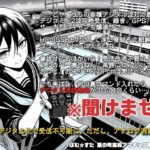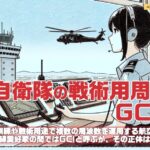高空を音もなく飛行機雲を流して飛んでいる国と国を行き交う3万フィート上空の国際線の大型旅客機、貨物機。そして約3000フィートの低空域では自衛隊や警察、防災、報道、各機関のヘリ、民間のセスナ、田植え時期には農薬散布のジェットレンジャーと、航空機は多彩です。
これらの航空機が飛行中に使用するものと言えば、もちろん航空無線。高高度を飛行する航空機から送信される電波は広範囲で受信できるので、空港が近くになくても気軽に受信が楽しめるのが魅力です。

これらアナログの航空無線はほぼ全て、市販の広帯域受信機で傍受が可能です。資格も免許も不要です。
航空無線の周波数と種類
では航空無線を趣味として受信する人が主に受信する各周波数の概要を確認しましょう。航空無線に使用される周波数は国や地域によって異なりますが、日本国内ではVHF帯である118.000 MHzから137.000 MHzまでのVHFが主に使用されていますが、自衛隊などの一部では140MHz帯も使用されます。
- 航空交通管制(ATC)
- 日本の航空路管制は計器飛行方式(IFR)で航空路を飛行中の航空機に対する航空交通管制で、実施するのはACC, Area Control Centerです。
- 札幌、東京、福岡及び那覇航空交通管制部それぞれの管轄する管制空域内を飛行する航空機に航空路管制業務、進入管制業務等を実施します。
- 最も一般的な航空無線であり、航空路を飛行中の航空機と地上の管制との通信に使用されます。
- VHF帯 : 118.000 MHzから137.000 MHzでセクターごとに主用波と副用波の二種が割り当てられています。
- 洋上を飛行する国際線旅客機はHF帯である2.000 – 22.00 MHzの「洋上管制」が使われます。
- 太平洋上空の洋上管制区は航空交通管理センター (ATMC) が管轄しています
- 飛行場管制(aerodrome control)
- 飛行場管制では管制塔から目視等で航空機の位置を確認し、滑走路や離着陸の順番や時機等の管制指示を発出しています。
- 空港や飛行場から離陸し,または飛行場に着陸する航空機,空港周辺を飛行する航空機に対してタワー(管制塔)から目視によって指示を与える管制です。
- 計器飛行の航空機に対する承認(クリアランス 略号:CLR)や、誘導路やエプロン上の航空機に対する指示(グランド 略号:GND)などがあります。
- そのほか空港内の走行区域内における人や空港内作業車両に対する管制も担当します。
- 管制塔にもレーダー装置がありますが、基本的にはタワーの管制官の目視および、ターミナル・レーダー管制を行うレーダールームの管制官と綿密に連絡を取り合い業務を遂行します。
- 北海道では運が良ければロシア側の管制やロシアの空港管制塔と交信する旅客機側の電波も聞こえます。
- ターミナル・レーダー管制
- 管制塔で管制官が目視を中心として行う飛行場管制に対し、ターミナル・レーダー管制は空港から出発・到着する高度1万4,000フィート以下の航空機を管制官がスクリーンの画面上で監視し、飛行経路や高度等の管制指示を発出します。
- 航空機が着陸する際には「ターミナル・レーダー管制」から「飛行場管制」へ、逆に離陸の際は「飛行場管制」から「ターミナル・レーダー管制」にリレーされます。
- 気象情報
- VHF帯: 通常はATIS(Automatic Terminal Information Service)やAWOS(Automated Weather Observing System)で使用されます。
- ATISは飛行場からの自動放送で、送信元空港名、情報名、視程、雲量、風速、気温などの気象情報、使用滑走路、デパーチャー周波数情報といった内容です。
- これらの内容を録音したものが英語で空港の運営時間中、自動的に繰り返し送信(放送)されます。
- 緊急通信
- VHF帯 : 121.500 MHz、UHF帯 : 243.000 MHz
- 航空機の緊急事態時における通信用周波数で「国際緊急周波数」と呼ばれます。
- 外国や軍事的には「ガードチャンネル」、UHF帯の周波数は「Uガード」とも呼ばれます。
- 航空機相互通信
- 航空機局相互間で気象状況及び航空機の相互の位置等飛行情報に関する通信を行います。
- VHF帯 : 122.600 MHz 123.45MHz (注) 注 この周波数の使用は、航空局のVHF周波数の通信圏外となる遠隔地及び洋上を航行する場合に限ります。
- 飛行中の航空機相互間で航行の安全上必要な際に行う通信です。
- 災害や事件事故が起きた際、ヘリが多数飛来するなどの場合において現場上空の安全を確保するために開局します。
- 滑空場などの管制塔は「飛行援助局」と呼ばれており、自飛行場の所属機への指示のほか、付近を低空で飛行する航空機に対し日本語でアドバイザリーを行います。
- ミリタリーエアバンド
- 軍用機(自衛隊機)向けの周波数として、138MHz~141MHzのVHF帯ならびに、UHF帯である222~253.8、275~322MHzの周波数帯が設定されています。
- 基本的に英語による交信ですが、場合によっては日本語を使用します。戦闘機の訓練では日本語での交信が顕著でしょう。
- 非公開である航空自衛隊のUHF帯のGCIはチャンネル数が数100以上あるとされます。
- これらのUHF帯域のGCIは自衛隊機が訓練や実戦のための交信で使用します。
- 航空会社の内部通信(カンパニーラジオ)
- 航空会社や警察・消防など公的機関の所属機と地上の運行部門が業務連絡を行う無線を「カンパニーラジオ」と呼びます。
- 旅客機では乗客に関することや気象情報、機体の状況、警察や消防・防災ヘリでは飛行位置、残燃料、任務に関する連絡一般です。
- 通常はVHF帯の120.000 MHzから137.000 MHzを使用します。
ご覧のように、空港の管制から空港情報の自動送信周波数、防災ヘリ、警察ヘリ、航空会社それぞれに割り当てられたカンパニーラジオ、自衛隊用の周波数まで、実にさまざまな無線通信の周波数が混在していますが、これら各空港管制、各航空会社に定められたさまざまな周波数が便宜上「航空無線」と呼ばれ、これらがエアバンド受信の中で基本となります。
航空管制はこのように各部署が担当を受け持っており、周波数を変えながら次々にリレーのように引き継いで、航空機に指示を出していきます。もちろん航空機側も周波数の変更を行いながら交信します。ですから、広帯域受信機には複数の空港、複数の管制区の周波数をメモリーしましょう。

付近を飛行中の航空機がいる場合は航空機近接交信用の周波数でお互いがコンタクトをとるほか、カンパニー周波数を使って運行会社の地上局と業務内容の確認、機材の状況や給油の手配など、さまざまな業務連絡を行っています。
これら航空無線の周波数は各国の航空当局や国際航空通信機関(ICAO)が、航空交通や通信の安全性を確保するために国際的な標準や規制に基づいて割り当てています。航空会社の内部通信(カンパニーラジオ)に関しては、各航空会社が独自に設定していますが、詳細な周波数は周波数手帳ワイド2023-2024(三才ムック)など関連書籍にほぼ全て掲載されており、便利です。
ミリタリー周波数は以下に解説しています。
航空無線を傍受するにあたって
さて、このような無線交信を受信することを『傍受(ぼうじゅ)』と呼びます。もし、すでに手元に広帯域受信機(レシーバー)があったなら、上述の周波数帯域をAMモードでスキャンすれば、どなたでもアナログの航空無線を傍受できます。許可、資格、申請などは不要です。まだお求めでないならば、どの受信機を買えば良いか、以下のページで答えを書いています。
とはいえ、このような受信機が市販されているとしても、本当にだれでも自由に航空無線を聴いていいのでしょうか。もちろんです。傍受することに何の問題もありません。どなたでも受信機があれば楽しめる趣味です。国土交通省航空局も公式サイト上にて「エアバンドを聞いてみよう」という題名で下記のように解説しています。
『エアバンドを聞いてみよう』
管制官とパイロットは航空無線を使用して話をしていますが、その内容は「エアバンドレシーバー」という無線機を使えば誰でも聞くことができます。ただし、傍受した通信の内容を漏らしたり、窃用することは電波法で禁じられています。
出典 国土交通省ホーム>政策・仕事>航空>航空管制官 公式
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr14_000016.html
上記の国土交通省公式サイト上にて、電波法という法律が出てきましたが、典拠元のとおり、交信の内容を漏らすこと及び窃用することは法律で禁じられています。これさえ守れば、個人の趣味の中で楽しむのであれば、問題がないものと解されています。
誰もが楽しめる親しみやすい趣味、航空無線
いかがでしょうか。航空無線受信趣味の一端を垣間見ていただければ幸いです。広帯域受信機を手に入れたら、まずは航空路管制を聞いてみましょう。地元に空港が無くったって大丈夫。空を見上げれば、飛行機雲。遥か上空を通過する航空機から地上の空港へ送信される航空路管制は何の不自由もなく誰でも受信できます。
一見、無機質な航空路管制ですが、日本の空域を離れる外国便のパイロットが交信の最後に「サヨナーラ」とか「オヤスミナシャイ」と言ったり、管制官もそれに返すなど、時折垣間見える人間味には頬が緩みます。さらに面白いものには「ウェイポイント」もありますので、興味があれば一読を。