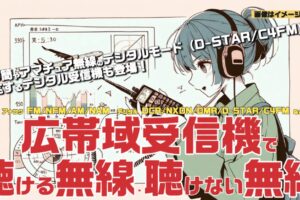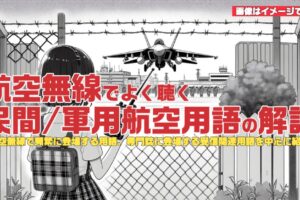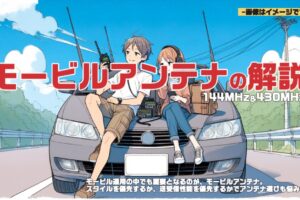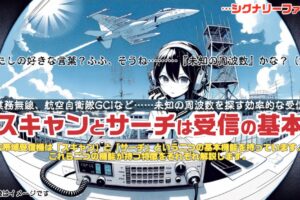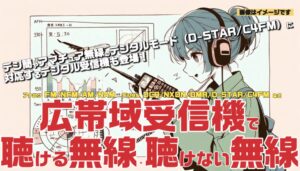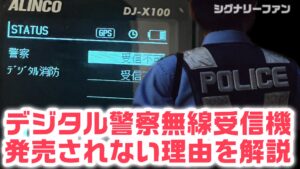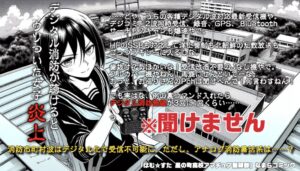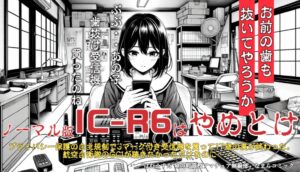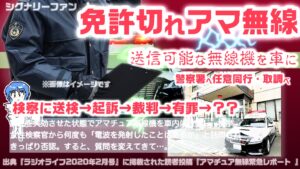民間機、軍用機は安全および効率化のため、管制圏においては常に地上の管制当局から位置・高度や飛行方向、航空路等、もっぱら近距離用のVHF帯の航空交通管制通信で承認を受けて飛行しています。
さらに洋上を航行する航空機との遠距離通信用としてHF帯(洋上管制)ならびに衛星系の周波数を使うこともあります。
つまり、パイロットと管制官のやり取りが、航空交通管制通信(管制波)。
カンパニーラジオは管制波とは違う面白さがあります。見ていきましょう。
各項目に飛べます
カンパニーラジオとは?
カンパニーラジオとは、もともと航空会社などが機体と地上の連絡のために使う業務無線ですが、その使用は大手民間航空会社に限りません。防災ヘリや警察ヘリなどの公的機関も広く利用しており、使用される周波数帯も多岐にわたります。
こうした用途の無線通信全体を、総称してカンパニーラジオ、カンパニー波、あるいは単にカンパニーと呼んでいます。
カンパニーラジオで行われる主な通信
通常は運行管理における確認、打ち合わせ、その他様々な交信をします。
- 運航管理: パイロットや地上の運航拠点との間で、フライトプランの確認や変更、機体の不具合報告など。
- 緊急事態対応: 緊急時に航空機が迅速に地上の運航拠点と連絡を取り、適切な対応をとるために使用。
民間の旅客機の場合、カンパニーラジオは主に以下のような連絡に使われます:
-
気象情報(ウェザー)
-
到着予定時刻の報告
-
機体の状態確認
-
客室乗務員からの要望連絡
-
「行ってきます」といった乗務前のあいさつ
いわば、航空会社の運航部門と機体との社内連絡のためのチャンネルといえるでしょう。
一方、防災ヘリの場合はまさに人命救助の最前線。その交信はより切迫したものになります。
-
現在位置と残燃料の報告
-
天候悪化による一時帰投の判断
-
要救助者のピックアップ開始を告げる連絡
-
状況の急変に即応するためのリアルタイムな指示交換
これらのやり取りには、緊張感が漂い、聞いているこちらも思わず息を呑むような場面がしばしばあります。
特に大規模災害が発生した際などは、このカンパニーラジオとデジタル化されたマスコミ無線を同時に傍受することで、現場の状況をより詳細に把握でき、情報収集の精度とスピードが格段に向上します。
カンパニーラジオは航空無線の入門に最適
カンパニーラジオは、日本語による交信が基本。航空無線初心者の受信入門にはぴったりです。
管制官とパイロットとの交信が非常に端的で早口かつ英語が基本である航空交通管制通信(管制波)。
それに対し、カンパニーラジオは日本語で、比較的ゆっくりとした交信です。
また、空港の近くにいなくても、旅客機やヘリコプターの電波は意外と届きやすいのが特徴です。たとえば、高度1万フィートを飛ぶ旅客機だけでなく、3000フィート以下のヘリコプターからの電波であっても、100km以上離れた場所での受信が、IC-R6(受信改造済み)なら可能です。
当サイトの参考ページ 非・受信改造済みIC-R6を買うと後悔する理由とは?
受信を楽しむためのポイント
-
カンパニーラジオは日本語での交信が基本
→ 初心者でも聞き取りやすい。 -
交信頻度は管制波より少ない
→ 主要な周波数はしっかりメモリー登録してチャンスを逃さずに! -
大手航空会社は「エンルート用」「ターミナル用」の2種類の周波数を使い分ける
→ 両方を登録しておくと、フライト中の連絡も、離着陸時の交信もカバー可能。 -
地元以外の航空会社の周波数も入れておくと、受信のチャンスが広がる
→ とくに連休や大型イベント時には、思わぬ機体が通過するチャンス到来。 -
外国の航空会社は日本国内で独自の無線局免許を持てない
→ そのため、日本空港無線サービスの周波数を経由して業務連絡を行っている。
大手エアラインのカンパニーはターミナルとエンルート用の二種
警察や消防、防災ヘリ、それに小規模な航空事業者の場合、使うカンパニー波は基本的に1波か2波程度。
しかし、大手航空会社では空港内で離陸前に使う「ターミナル」用、航空路まで上昇後に使用する「エンルート」用の二種類。
たとえば、129.850MHzはエアーニッポンのカンパニー周波数(ターミナル用)。
 航空無線ハンドブック 2017 (イカロス・ムック)
航空無線ハンドブック 2017 (イカロス・ムック)
4802202318 | イカロス出版 | 2016-09-28
現在大手ではJALグループとANAグループ、それにスカイマークがこの二種のカンパニー波を使い分けて使用。
当然、空港で使うターミナル用の周波数は空港から遠ければ受信は難しいので、まずは航空機が空の上から発射するエンルート用周波数の受信がベスト。
もちろん、空港に出向いた際に受信するため、ターミナル用周波数も受信機にメモリーしておくとグッド。
また、同じ会社でも地域や空港ごとに周波数が異なります。
例えば、北海道で受信する場合は道内に加えて、青森空港の各社カンパニー周波数をメモリーしておくと、数百kmは余裕で飛ぶVHFの特性上、意外と受信できます。
地元だけでなく、遠方地域の周波数メモリーもベスト。

総務省 電波利用ホームページ内の無線局免許状等情報で公開されている情報によると、新北九州空港‐羽田などに定期便を就航する2002年創立の「スターフライヤー」のカンパニー周波数は128.975MHz。
| 航空会社 | エンルート周波数 | ターミナル周波数 |
|---|---|---|
| ANA系(全日空、IBEX、NCAなど) | 129.650 MHz、129.700 MHz | 129.850 MHz(神戸空港)、129.475 MHz(関西空港) |
| JAL系(日本航空、JAC、JJPなど) | 129.150 MHz、131.900 MHz | 131.850 MHz(伊丹空港)、129.225 MHz(関西空港) |
| スカイマーク(SKY) | 129.250 MHz、123.675 MHz | 123.675 MHz(神戸空港) |
| フジドリームエアラインズ(FDA) | 122.425 MHz | - |
| スターフライヤー(SFJ) | 128.975 MHz | 130.950 MHz(関西空港) |
| ソラシドエア(SNA) | 129.275 MHz | - |
| ジェットスタージャパン(JJP) | 親会社の周波数を使用 | 130.950 MHz(関西空港) |
この周波数も総務省公式サイトのほか、航空無線ハンドブックなどに掲載されていますから一冊あると便利。

地上の整備部門との調整も重要。場合によっては地上職員の不手際に絡む機材運行のトラブルで、パイロットがディスパッチャーに冷静な声で嫌味を言ったり、いらいらが伝わってきて思わず苦笑させられたり、人間味を感じさせます。
気象と到着予定時刻に関する事項
エアラインのカンパニーラジオで最も多い交信が到着先空港周辺のウェザー、つまり気象状況と到着予定時刻の連絡。着陸時に悪天候が予期される場合は、より密な連絡が必要です。
整備に関する事項
エンジンの油圧、ブレードのピッチに起因する異音など旅客機の運航トラブルに直結する機材関連の不具合も、地上クルーとの間で連絡を密にしなければなりません。
乗客に関する事項
やはりVIP、さらにクレーマーが乗り込むとそれに関するやり取りが多くなります。タクシーの手配などの要請が行われます。
これらカンパニーラジオの交信は、当サイトがオススメしているIC-R6(受信改造済)で受信可能です。
警察・消防防災ヘリなどのカンパニーラジオ
都道府県の防災ヘリ、消防局や警察、海保のヘリでも航空隊基地と業務連絡にはカンパニーラジオを使用。
多くの防災ヘリや警察ヘリは135.950MHzを共用しています。
防災ヘリ・消防ヘリなどのカンパニー周波数
| 周波数 | 都道府県または政令指定都市 |
| 129.75MHz | 札幌市、千葉市、川崎市、横浜市、京都市、神戸市、静岡市 |
| 131.15MHz | 東京都、仙台市、名古屋市、大阪市 |
| 131.875MHz | 北海道、秋田県、福島県、千葉県、神奈川県、富山県、福井県、長野県、三重県、大阪府、島根県、愛媛県、福岡県、長崎県、宮崎県、浜松市、岡山市 |
| 131.925MHz | 岩手県、山形県、栃木県、群馬県、石川県、山梨県、愛知県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、徳島県、佐賀県、大分県、鹿児島県、福岡市 |
| 131.975MHz | 青森県、宮城県、茨城県、埼玉県、新潟県、岐阜県、静岡県、京都府、和歌山県、鳥取県、山口県、香川県、高知県、熊本県、沖縄県、広島市、北九州市 |
情報の出典 https://www.habataki.org/dcms_media/other/%E3%81%AF%E3%81%B0%E3%81%9F%E3%81%8D%E4%BE%BF%E8%A6%A72021.pdf
なお、民間航空会社に防災ヘリの運行を委託している自治体の場合、運行会社のカンパニーラジオが使用されます。
また、事件や事故現場の上空でマスコミや行政機関のヘリが数機集まると、通常は122.60MHzローカルが開局し、お互いが位置情報を伝えるなど、安全上の注意喚起を行いますが、相手の会社のカンパニーの周波数に割り込む場合も。
警察ヘリのカンパニーラジオ周波数
| 周波数 | 都道府県警察本部 |
| 135.950MHz | 全国共通 |
全国共通で135.950MHzを使用します。また、90年代の『ラジオライフ』誌には133.700MHzの使用も掲載されていましたが、現在は使用されていないと思われます。
救助事案の場合は救助開始の地点および開始時刻、要救助者の情報などが一般に交わされる警察・消防・防災、海保ヘリのカンパニーラジオですが、警察の犯罪捜査だけは別。
間違ってカンパニー波で警察車両を呼び出すイレギュラーが稀にありますが、捜査情報は基本的にデジタル警察無線でのやりとり。カンパニーでは流れません。
消防でも、地上の消防隊との連絡でデジタル消防無線を使うことも多く、その場合は当然ながら傍受できません。
コールサイン
各機関のヘリのコールサインを覚えておくと、交信が聞こえた際にすぐにどの機関の機体かわかります。
防災ヘリ、警察・消防の各ヘリがカンパニーで使うコールサインはJAナンバーのほか、JAナンバーをもじったコールサイン(北海道警察は”HP”をもじったハッピーなど)、さらに機体の愛称などを使います。
『ヘリテレ連絡波』も聞き逃せないが平時の交信頻度は少ない
現代の消防・防災ヘリや警察ヘリには『ヘリコプターテレビ中継システム』が装備されており、災害時などは災害対策本部などへ14.80GHzなどで映像電送ができます。当然、ヘリテレ用周波数は映像送信用ですから、380MHz台に割り当てられている音声連絡波が傍受対象です。
ヘリテレ連絡波の周波数各種資料 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/Helicopter/shiryo8.pdf

画像出典 日本経済新聞社 https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK29034_Z20C13A3000000/
ただし、これまで電波遮へいの発生によって通信できない空白地帯が全国各地に存在していた問題の解消手段として、2013年からは東京消防庁がヘリテレに代わって新たにヘリサットと呼ばれるヘリコプター直接衛星通信システムを導入しており、ヘリサットが主流になれば将来的にヘリテレは廃止されていくでしょう。
■関連記事■
≫ SSBモードを受信できる受信機材『SSB対応BCLラジオ』は?
≫ 航空無線を受信するためにはまず広帯域受信機を購入しよう!
≫ 広帯域受信機ではスキャンとサーチを使い分けて効率的に受信しよう!
≫ 受信機を買ったら高性能アンテナも絶対に買ったほうが良い理由とは?
まとめ
このように、カンパニーラジオは無線初心者が航空通信の世界に触れる入口としても優れており、日本語のクリアな交信内容から状況を読み解くチャレンジの面白さもあります。
ほかにも、航空系無線は災害時に活発になる周波数の中にもまとめてあります。