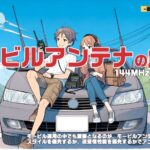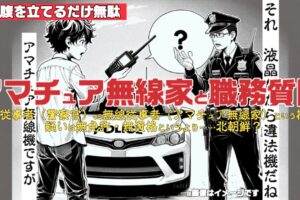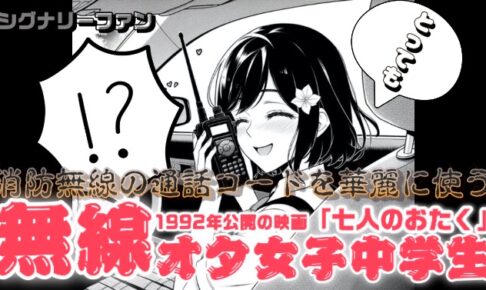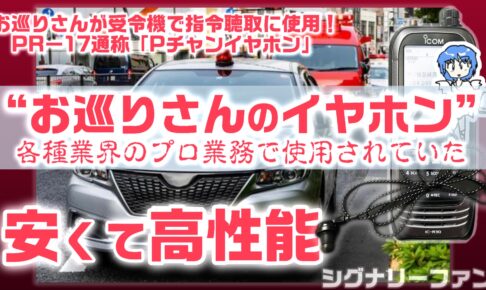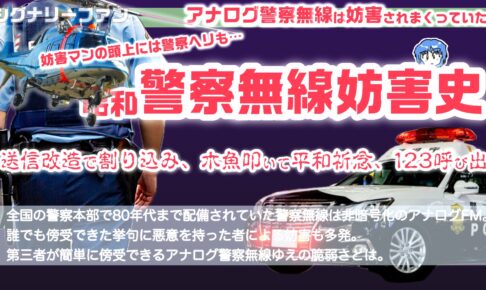各項目に飛べます
アマチュア無線の運用形態のひとつ「モービル運用」とは?
アマチュア無線において、無線設備を通常保管する場所は「常置場所」と呼ばれています。この「常置場所」から運用を行う無線局は「固定局」とされ、固定局に対して「移動局」という対義語があります。
つまり、移動体で運用する場合は、車やバイクにアマチュア無線機を搭載して運用するが「モービル運用」です。
自宅の常置場所から運用するのはもちろん、車やバイクを使って移動しながら行うモービル運用も非常に楽しさがあり、無線愛好者にとっては魅力的な体験です。
![CQ ham radio (ハムラジオ) 2009年 08月号 [雑誌] CQ ham radio (ハムラジオ) 2009年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/517gVsvKyqL.jpg)
CQ ham radio (ハムラジオ) 2009年 08月号 [雑誌]
B002DVBG0M | CQ出版 | 2009-07-18
車に搭載するアマチュア無線機はどのような種類があるか解説いたします。
モービル運用では『モービル機』が最適
ハンディ機のページでも触れましたが、ハンディ機を車に積めば手軽にモービル運用ができます。
しかし、やはり使いにくさは否めません。
モービル運用向けアマチュア無線機
結論として、モービル運用には車載用アマチュア無線機、いわゆる「モービル機」が最適です。
モービル機が主に使用する周波数帯である144MHzや430MHzは、比較的小型のアンテナで運用できるため、自動車やバイクでの運用が非常に簡単です。
モービル機の利点は多岐にわたりますが、セパレート式の液晶表示パネルを運転席の見やすい位置に設置すれば、スイッチ類やボリューム、スケルチのダイヤル操作が楽に行えるのがグッド。
また、モービル機は車のエンジンノイズを極力拾わないように設計されているため、車内で使用する際の雑音が大幅に軽減され、快適な運用が可能です。ハンディ機を車内で使用していると、エンジンノイズでスキャンが止まってしまうこともありますが、モービル機ではその心配が少なくなります。
アマチュア無線の電波形式にはAMやFM、SSBなどがありますが、FMモードは自動車のエンジンノイズに強いため、モービル機を使用する場合には最適です。ほとんどの市販のモービル機はFMモードに対応しており、車での運用には非常に便利です。
さらに、モービル機の大きな利点はバッテリー切れの心配がないことと、送信出力の強さです。ハンディ機が最大1Wから5W程度の出力に対して、モービル機は最大で50Wの送信が可能です。この高出力によって、より遠くまで電波を届けることができます。ただし、安定した作動を望む場合は、走行中に50Wの大出力を常に使用するのではなく、10W程度の出力が望ましいです。過度な出力はバッテリー上がりの原因となることもあるので注意が必要です。
現在、モービル機として販売されているアマチュア無線機は、144MHzと430MHzのデュアルバンド機が人気ですが、28MHzや50MHzのシングルバンド機もあります。さらに、広帯域受信や同時受信機能を持つ機種もあります。ただし、使用する無線機は自分の免許の級に対応したものでなければなりません。
もしモービル機を自宅などで固定局用に使いたい場合、家庭用のコンセントから直接電源を取ることはできません。そのため、「安定化電源」と呼ばれる装置を別途用意する必要があります。
オススメのモービル機は?(2025年版)
FTM-6000Sがおすすめです。

筆者は長らくスタンダードのFT-7900を愛用。使いやすさでベストセラーです。ハンドマイクにボタンがいっぱいついている機種は嫌だったのですが、使いやすさを考えるとこれ以上の選択はありませんでした。
実際、基本性能の高さと使いやすさ、さらには広帯域受信機能つきで、FT-7900は初心者から中級者まで幅広い層に人気となりました。

FT-7900 スタンダード(STANDARD) 144/430MHz帯 FMデュアルバンドモービルトランシーバー 20W
B002N4AV1Y | 八重洲無線株式会社 |
FT-7900の実質的な後継機であるFTM-6000Sが2023年に発売されています。
基本性能の高さは前機種を踏襲、もちろん広帯域受信は108MHz~999.995MHzと心強いもの。
さて、モービル運用で必要なものはもちろん、無線機本体に加え、モービルホイップという車用アンテナ。
また、バッテリーの配線も必要です。この電源を取る作業は素人には難しいかもしれません。

モービル・ハム入門: クルマで楽しむアマチュア無線 (アマチュア無線運用シリーズ)
4789815862 | CQ出版 | 2013-08-24
セパレート式操作パネルのおすすめ
無線機の操作性は、無線機本来の性能に加えて、取り付け方にも大きく左右されます。現在、多くのモービル機では「セパレートタイプ」と呼ばれる分割式の操作パネルが採用されています。つまり、操作パネル部分を運転席の操作しやすい場所に設置し、無線機本体は助手席の下などに設置するという仕組みです。この設置方法によって、スマートに配置でき、利便性が高くなります。
また、モービル機の場合、ハンディ機のようにマイクから音が出るのではなく、無線機本体に内蔵されたスピーカーから音が聞こえます。そのため、本体はできるだけ運転席の近くに設置するか、外付けスピーカーを購入して運転席付近に設置するのが一般的です。筆者は本体を助手席下に設置し、スピーカーから受信音を聞いていますが、明瞭に聞こえ問題ありません。
操作パネルは、付属のブランケットを使わなくても、車内用の強力粘着テープ(例:3M製)を使うことで、コンソールに穴を開けずに強力に固定できます。
車内の無線機を隠すべきか?
モービル機を車に取り付ける際、セパレートパネルの設置場所が問題になります。「車内で無線を使っていることを外から知られたくない」と考える人もいるかもしれません。
特に覆面パトカーなどでは、車内の無線機を目立たないように隠されているのは、ある意味参考になります(!?)。
例えば、無線機本体にカバーをかけたり、最近では無線機をグローブボックス内に隠し、ケーブルとハンドマイクだけをドアの穴から出す方法が採られています。これにより、無線機をよりスマートに秘匿することができます。
とはいえ、正当な免許を持つアマチュア無線家にとって、車内の無線機を隠す必要は特にありません。ただし、車内で無線機を目立たせすぎるのも良くないかもしれません。特に盗難防止の警報装置がない車の場合は、無線機が搭載されていることを隠すほうが安全です。
バックミラーにハンドマイクを吊るすのも格好良いかもしれませんが、個人的にはちょっと勇気がいります。
モービル機のバッテリーはどこからとるの?
さて、初心者が最初に気になるのが、電源の問題ではないでしょうか。無線機はバッテリー直結で配線するのが基本なのですが、素人がやると危険ですし、失敗する可能性が高いでしょう。
ですから、あまり車のメカニズムに詳しくない場合、そう簡単に自分でバッテリーから直結するのは現実的ではありませんから、無線ショップにお願いしましょう。
気軽に別料金で引き受けてくれるでしょう。通販で購入した場合は整備工場で架装してもらうか、地元のOMさんなどの助言や支援を得るなども有用です。
実は、もっとも手軽に電源をとれる方法があります。シガーライターから直接電源を取れるシガーケーブルが発売されていますので、こちらを使用しても良いでしょう。
無線機のT型カプラとシガーケーブルのカプラをつなぎ、シガーソケットにつなぐことで、誰でも簡単かつ安全に電源が取れます。
また、高出力の50w機では使用できませんので、使えるのは20w機までという制約があります。というより、車のバッテリーで50wの無線機を運用するというのは現実的ではないのかなと思います。
多くのリグでは必要に応じて無線機の出力を切り替えることが可能ですので、小出力で使用すれば大丈夫です。その場合もバッテリー上がりなどにご注意ください。
ただ、この方法はとくに年季の入ったOMさんからは幼稚な手法と見られているのが実際です。
無線機の次はアンテナも必要ですが、以下の別ページにてモービル用各種アンテナについて解説します。
次のページではモービル運用と無線局免許、いわゆる職質についてのお話をします。
免許が無くても、無線機からマイクを外した状態なら違法じゃない?
総務省東北総合通信局の公式サイトによれば、以下の説明がありました。
「電源を切っていたり、マイクを無線機から外していても、直ちに取り付けられる場合は不法局となります」
引用元 総務省東北総合通信局公式サイト
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/amateurradio.html
これについては以下のページで詳しく迫ってみました。
そのほかのモービル運用の注意点など
交信が尻切れになる場合がある
モービルハムは常に電波が安定的に届くわけではないので、ビルの谷間に入れば交信の最後が相手に届かない場合もあります。
相手局が固定局でローテーターでアンテナの方向を調整してもらえる場合は、移動局のほうへアンテナを向けてくれるので、比較的安定的な交信が可能ですが、固定式のアンテナですと、やはり距離が離れるにしたがって尻切れになってしまいます。
コールサインの後ろに「ポータブル」か「モービル」とつける
これは法で定められた義務ではありませんが、車で使うときは「ポータブル」とか「モービル」など、コールサインの後ろに付けることで、移動局なのか固定局なのかを明示する慣習となっています。
さらにエリアナンバー(北海道なら「ポータブルエイト」)。さらに現在の市町村名もつけると親切でわかりやすいでしょう。
なお、無線局開局申請時に移動する局として申請しておけば、車のほかに、船や飛行機にだってアマチュア無線機を積んで運用することが可能です。
飛行機にて運用する場合は「エアロノーティカルモービル」、船の場合は「マリタイムモービル」とコールサインの後ろにつけます。
ただ、旅客機などの客室内では保安上の理由から当然、携帯電話や無線機を使うことが許されませんから、個人所有の軽飛行機などの場合を想定しています。大空や、自然の中で楽しいハムライフを。
車のバッテリーの寿命が短くなる
基本的にモービル機はバッテリーを搭載しておらず、通常は車のバッテリーを利用して電源をとります。このため、車のバッテリーの寿命が短くなります。
また無線機のスイッチを切り忘れるとバッテリーあがりも起きえます。
これを防ぐためには無線用のバッテリーを別に用意するなどの方法があります。
運転中にハンディ機をそのまま使うと道路交通法違反になるが、モービル機は?
典拠
http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/041101mobile.htm
運転中の携帯電話が法律で禁止されて久しいですが、実は運転中の「携帯電話」だけでなく、「無線通話装置」自体が禁止されているって知っていましたか?
アマチュア無線機では、据え置き型のモービル機では規制対象になりませんが、ハンディートランシーバーの単体使用が対象となっていますので、ハンディ機をモービル機代わりに使う場合はご注意を。
ただし、ハンディートランシーバー本体にヘッドセットやハンズフリー装置、ハンドマイクなどをつけて使用する場合は規制の対象外になるとJARLさんの公式サイトに記載されています。ハンディ機を車に積んで運用する場合は、ハンディ機を手に持たず、ハンドマイクをつけて運用してください。
そして、JARLさんでは「運転中に交信すると運転が散漫になるので、運転中のQSOはやめるべき」ともアドバイスをされています。
モービル機には、音声を感知すると自動で送信状態になる「VOX」という機能がある機種もあり、手放し通話も可能ですが、安全運転の観点から、やはり筆者としても、停車して交信するほうがスマートだと思います。
なお、これには「傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車などの走行中に緊急でやむを得ずに行うものを除く」という除外規定が設けられていますが、傷病者の救護または公共の安全の維持のための当該自動車とはすなわち、救急車やパトカーなどであり、アマチュア無線は対象とはなりません。
車にアンテナを付けることでパトカーから無線の免許確認をされることが多くなる
何度も言ってますが、嫌ですね職質。もちろん、有効な従免と局免を取得している限り、堂々としていればいいだけですが、煩わしいことです。中には液晶表示だからという理由で「これ違法機だね」と言った北海道巡査もいます。
http://ja8tdl.at.webry.info/201204/article_2.html
地元で一回職質を受けて、正当な免許所持者であることが分かったならば、その後は警察署内で情報共有されて、以後は声かけされることもないのでしょうが、移動運用などで地元以外を走る場合は、やはりその地域の警察のお声がけが待つことでしょう。
ですから、遠出をする場合はトラブルを避けるためにアンテナを外して出かけるというOMさんもいます。
モービル運用と移動運用は違うの?
両者は厳密には違います。移動運用とは良好な電波伝搬を得るため、ロケーションの良い場所に移動して、運用する手法です。
車などに無線機と大きなアンテナを積んで高い山の上で、アンテナを組み上げて運用するのが一般的です。
手間暇がかかりますが、ロケの良さから自宅での運用では出会えない局との交信が可能になるなど魅力がいっぱいです。一方、車で移動しながら無線を楽しむのは一般にモービル運用と言います。
モービル運用のまとめ
このようにモービル運用って、わずらわしいことが多いのですが、とっても楽しいんです。筆者はモービル運用こそアマチュア無線の醍醐味と思います。
一方で144MHzと430MHzは不法無線局の温床ともなっているのが、私たち正当に許可を受けた無線局としては辛いところです。ほぼ毎日、昼間はコールサインも言わない局が交信しています。だから正規の無線局が出てくるのは夕方以降や週末だけ……というツライ現実も。
しかし、モービルハムの楽しさは一度味わえば病みつきになるでしょう。ぜひチャレンジを。