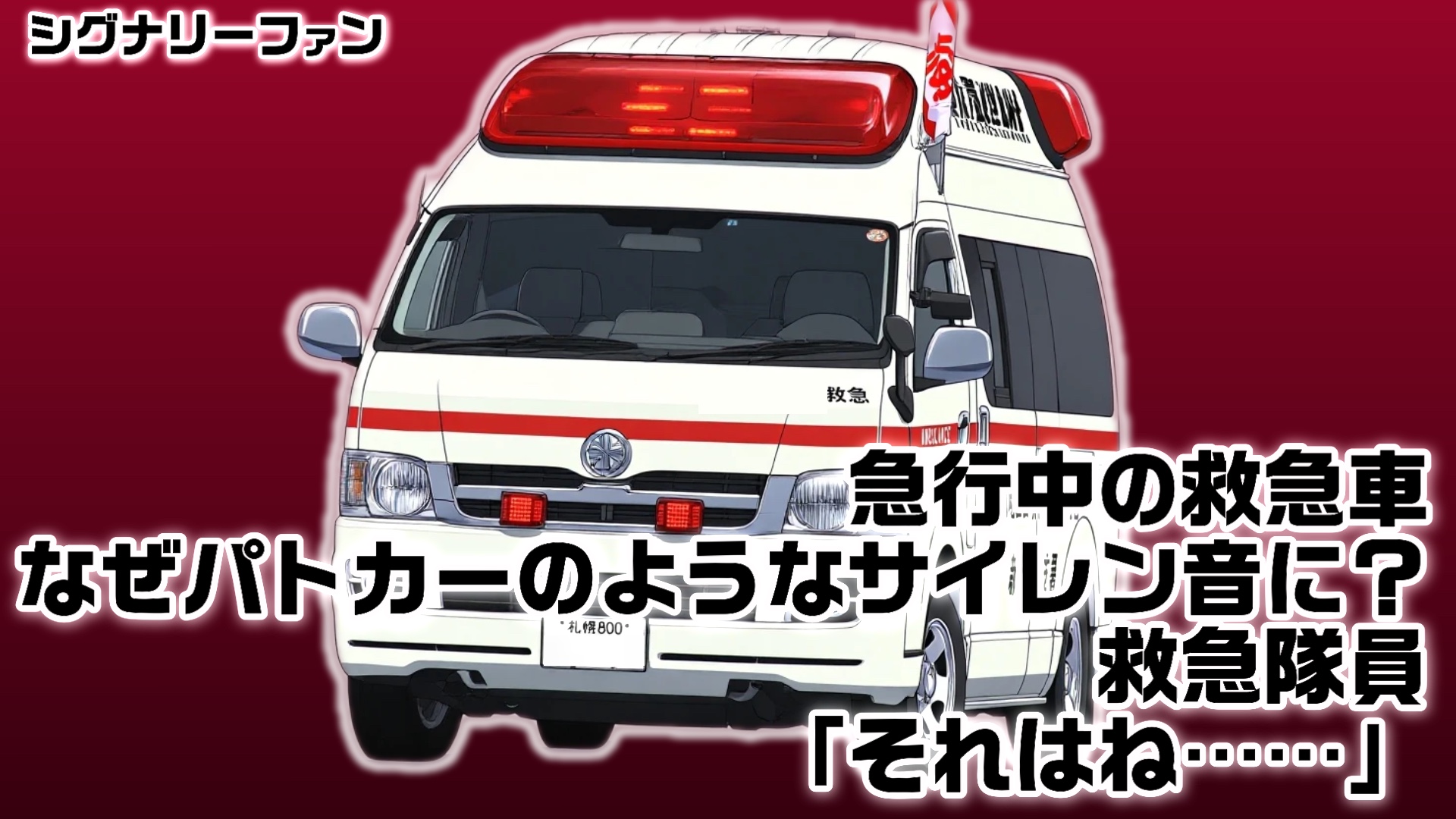「ウーウー音」サイレン、街に響く――救急車が“音色”を選ぶ理由とは?
街中を走る救急車が、あの“パトカー風”の「ウーウー音」を鳴らすようになって何年も経ちますが、皆さんはご存知でしたか。
まだ聞いたことのない方は「えっ、パトカー?」と思って思わず身構えてしまった経験があるかもしれません。
でも、実はあれ、れっきとした救急車のサイレン音なんです。
今回は救急車のウーウーサイレンにまつわる、私たちドライバーのモラルに関する記事を発掘してみました。
なぜ救急車がパトカーのようなウーウーというサイレンを鳴らすようになったのか、その理由を1996年の高知新聞の報道で読み取ることができます。それは非常に興味深い内容でした。
高知県の高知市消防局が救急自動車に取付けているパトカー風の「ウーウー音」型サイレンの使用頻度が増えている。導入直後は注意喚起のため交差点で時折使用する程度だったが、最近は「ピーポー音では待避してくれない」と、渋滞の直線道路などで使用する場面も増えた。
救急隊員は「瞬間的にパトカーと思って待避するのだろう」と“脅し”効果に頼りながらも、「もっと救急患者のことを考えてほしい」と運転モラルの低下を嘆いている。
救急車のサイレン音は、以前は消防車と同様の「ウーウー音」だったが、「火災発生との混乱を防ぐ」「搬送患者にとってもソフトな音色がよい」などの判断で昭和45年の消防庁通達で現行の「ピーポー音」に改められた。
ところがその後、乗用車の遮音性が高まり音色がやや聞こえにくくなったことや交通量の増加、ドライバーのモラルの低下が加わる形でピーポー音の効果が減退。
このため、高知市消防局では現場の救急隊員らが声を上げる形で平成2年ごろ、ウーウー音併用のサイレンに改めた。
隊員の話では、当初は交差点に進入するのに時折、音が通りやすいウーウー音に切替える程度だったが、最近は「なかなか待避してくれない車や、道の中央で止まる車が多い」「救急車を追い抜いたり、平気で並んで走る車が増えた」と、電車通りなど直線の道路でも使う頻度がじわじわ増加。多くの隊員が「道を譲らない車でもウーウー音に切替えた途端によけ始める」と効果を認める。
消防庁は、ピーポー音が主体なら、ほかの音との併用を認めており、自治体の対応はまちまちだが、あるサイレンメーカーによると、すでに自治体への納入の半分以上がウーウー音との併用型になっているという。
救急車乗車歴11年の高知市消防局の救急救命士(42)は「救急車は患者への配慮からパトカーより走行速度は遅いが、乗っているのは一刻を争う患者。自分の家族が乗っていると思って常にすばやく待避して欲しい」と訴えている。
(引用元 1996年7月29日・高知新聞)
本来、救急車のサイレンは昭和45年(1970年)の消防庁通達を受けて、「ピーポー音」が全国的に採用されるようになりました。
これは火災現場へ向かう消防車の「ウーウー音」との混同を避けるため、また患者の心理的負担を軽減するためといった理由が背景にあります。やさしい音色、というわけですね。
ところが、それから半世紀が過ぎた今、事情が変わってきています。
たとえば、現在の自動車は遮音性が飛躍的に高まり、車内にサイレン音が届きにくくなりました。
また、交通量の増加とともに、運転マナーの変化――あるいは低下――も指摘されます。救急隊員が「ピーポー音では待避してくれない」と嘆く声が現場から上がり、高知市消防局では1996年から「ピーポー音」と「ウーウー音」を併用できるサイレンの導入に踏み切りました。
興味深いのは導入当初は交差点での一時的な使用にとどまっていたのですが、近年では直線道路でも多用されるようになったとのことです。
理由は明快で、「ピーポー音」では車がどいてくれない、しかし「ウーウー音」に切り替えると、とたんに道を譲ってくれる――という現場での経験知に基づいています。
まるで“パトカーが来た”と誤認させることで得られる瞬間的な注意喚起効果を活かしているのです。
これは一種の「行動心理学的なサイレン運用」ともいえるでしょう。
実際に「ウーウー音」で緊急性を認知しやすくなったとの研究報告もあり、サイレン音の選択は単なる技術ではなく、認知科学や交通行動理論に基づいた公共心理インターフェースと捉えるべきです。
とはいえ、この“脅し効果”に頼らざるを得ない現実には、やや複雑な思いを抱かざるを得ません。
救急車に道を譲る行動は、本来であれば道路交通法にも定められており、また市民の倫理意識に基づくべきものです。しかし、現場の声は切実です。
11年の経験をもつベテラン救急救命士がこう訴えます。
「救急車はパトカーよりゆっくり走るけれど、乗っているのは一刻を争う患者。あなたの家族かもしれない。だから、すぐに道を譲ってほしい」
人の命を運ぶ車両が、その音色ひとつで扱いの差を受ける――この現象は、私たちの公共意識がいかに“音”に左右されるかを物語っています。
都市の音響設計(アコースティック・アーキテクチャ)と、交通心理の交差点に立つこの問題。今後、さらなる研究と制度設計が必要だと感じます。
そして何よりも、市民一人ひとりの「思いやり」が、ピーポー音を「届く音」に変える最大の鍵であるのかもしれません。
皆さんも後ろから救急車が走ってきた場合は、速やかに道路脇脇に寄せるなど道を譲ることをお願いいたします。
救急車が「ウーウー音」で迫る理由――私たちの無関心が生んだ”威嚇”という選択肢
このように救急車のサイレンがピーポーピーポーのほかに、パトカーのように威圧的で怖いサイレンを鳴らすという、現場の救急隊員がサイレンを“威嚇的”に使わざるを得ない状況に陥っている現実が90年代にあったのです。そして今もそれは続いています。
つまり、「ウーウー音」は、交通法規による注意喚起ではなく、心理的圧力を与える手段として使われているのです。
これは言い換えれば、救急車では譲らないが、警察には譲るという、私たち一般ドライバーの意識のズレとも言えます。
もはや、救急車がサイレンの音色に「威嚇性」を求めなければ通行できない、そんな都市の交通環境は、果たして健全でしょうか。
パトカーと勘違いして譲るくらいなら、最初から救急車のために道を譲れる社会でありたい―救急隊員たちのウーウーサイレンの選択は、私たち一般ドライバーの運転マナーとモラルの“鏡”なのかもしれません。