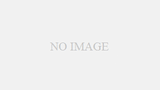警察で短機関銃を配備する部隊というと、SATが話題に上がる。また、刑事部のSITでも一部で単発仕様のMP5を配備している。
しかし、機動隊の中でも、銃器を使用した重大事件が発生した際の対処に出動するSATに次ぐ重武装かつ即応性に優れた部隊がある。
それが「銃器対策部隊」である。
SATと違って、マイナーな部隊だが、その違いは意外と知られていない。
本記事では、それぞれの任務・装備・運用方法を実際の事例とともに解説したい。
銃器対策部隊の任務とSATとの違い
日本警察の銃器対策部隊(銃対)は、警察庁を頂点とする全国の警察機構の中で、銃器や爆発物を使用する犯罪、あるいはテロリズムへの対応を目的に都道府県警ごとに機動隊に編制されている。
銃対は、アメリカやヨーロッパ諸国のSWAT(特殊火器戦術部隊)に相当するが、日本特有の法制度や治安環境に応じて運用されており、その構成・任務・装備にも独自性がある。

一方、警察の最精鋭部隊は警察庁の直轄指揮下にある対テロ特殊部隊である「特殊急襲部隊(SAT)」であり、東京・大阪など全国8の警察本部のみに配備されている。

SATは、9mm特殊拳銃(SIG P226など)や短機関銃(H&K MP5など)を使用し、防弾装備や特殊車両も整備され、主にハイジャック、人質立てこもりなど、特に凶悪な銃器使用事件、テロへの即応を任務とし、国内では最も高い訓練水準と装備を有する。
警察庁では必要に応じて警視庁や神奈川県警のSATを全国へ派遣する運用を行なっているが、全国配備されていないSATの隙間を塞ぐ形で配備されているのが、各県警機動隊の『銃器対策部隊』、通称“銃対”である。
銃器対策部隊は銃器等を使用した事案への対処を主任務とし、重大事案が発生した場合に、SATが到着するまでの第一次的な対処に当たるとともに、SAT到着後は、その支援に当たる。
つまり、SATが未編成の警察本部では、銃器対策部隊が警備警察の「初動対応部隊=SWAT」として機能している。
現在、全国の警察本部機動隊に配備された銃器対策部隊の隊員数は全国で約2,100人(令和元年 警察白書より)。
装備面でも非常に充実しており、SATも配備するMP5サブマシンガン、自動小銃、防弾盾、さらには耐弾・耐爆仕様の特型警備車両(装甲車)まで投入されており、重装備のテロリストや武装グループへの対応も想定されている。

画像の出典ANN
SITは刑事部として、主に立てこもりや誘拐、殺人など重大事件の捜査と初動対処を刑事警察の立場から担う一方、銃器対策部隊は警備部に属し、テロや爆発物事案を含むより武力的対処に重点を置いた訓練と装備を有する。

これらの部隊は通常警察官としての職務を行いながら、必要に応じて招集される即応型部隊として機能している。
-
銃器対策部隊とは特殊部隊でも通常機動隊でもない機動隊の機能別部隊のうちの“銃器事件特化チーム”
-
SITやSATに次ぐ、知られざる第3の警察部隊
- SAT到着までの初動対応が任務
埼玉県警察 RATS
警視庁 銃器レンジャー部隊
警視庁機動隊の中でも特異な存在である「銃器レンジャー部隊」は、第七機動隊にのみ編成されている専門部隊である。
その起源は1969年(昭和44年)に結成された「レンジャー部隊」にさかのぼり、2001年(平成13年)には任務の特性に応じて「銃器レンジャー」と「山岳レンジャー」に再編された。
「レンジャー部隊」と聞くと陸上自衛隊をイメージしがちだが、ロープを多用し、より高度な任務に対応するという定義は同じである。

銃器レンジャー部隊は、高層建築物における強襲突入を専門とする特別高等作戦部隊で、銃器使用が想定される凶悪事件や人質立てこもり事案などに対応し、犯人の制圧や人質の救出任務が主である。
通常の銃器対策部隊同様の任務だが、「レンジャー」の名称の通り、突入戦術に加え、ヘリコプターや高所からのラペリング降下で上階から突入するといった高度かつ機動的な作戦にも対応できるよう、日頃から厳しい訓練を重ねている。
また、降雪下での実戦想定訓練も実施されており、通常の市街地だけでなく多様な環境下における即応力を高めている。
その活動は、警察署との連携による共同訓練の中でも確認されており、災害対応とは異なる「銃器事案への即応」を強く意識した組織となっている。
レンジャー部隊は、警視庁機動隊の中で、第七機動隊にのみ編成されています。昭和44年にレンジャー部隊が発足し、平成13年「銃器レンジャー」と「山岳レンジャー」に再編されました。
※出典:警視庁公式ウェブサイト「第七機動隊 銃器レンジャー部隊」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/katsudo/kidotai/kidotai/dai7kidotai.html
警視庁 緊急時初動対応部隊(ERT)
特筆すべきは、警視庁での独自強化である。2015年4月からは、銃器対策部隊の中に緊急時初動対応部隊「ERT(エマージェンシー・レスポンス・チーム)」というチームが編成され、万が一テロが発生した際には、SATよりも先に現場へ駆けつけ、即応的な初動対応を行う。人員は「銃器対策部隊」から選抜された警察官で編成され、SATと連携しながら大規模事案に対応する。
SAT(特殊急襲部隊)との違い

埼玉県警のRATSや、警視庁の銃器レンジャーの訓練は陸上自衛隊のレンジャー教育課程に委託しており、非常に過酷な訓練を経た精鋭たちによって構成されており、その実力はSATにも劣らぬレベルとされている。

しかし、銃器対策部隊はあくまで「警備警察の中の即応力」として整備されており、特殊部隊(Special Forces)であるSATとは明確に区別されている。

SATは警察庁が主導する全国規模の広域部隊であり、テロリズムやハイジャックといった国家的脅威に対応するための部隊である。
以下の点で、銃器対策部隊と明確な違いがある。
| 区分 | 銃器対策部隊(RATS等) | SAT(特殊急襲部隊) |
|---|---|---|
| 所属 | 各都道府県警察(機動隊) | 警察庁警備局指揮下 |
| 任務範囲 | 主に管内の銃器・暴力事案への初動対応 | 全国規模でのテロ・重大武装犯罪対処 |
| 常設状況 | 常設・専従 | 常設・専従で一部は機動隊から独立 |
| 装備 | 9mm拳銃、MP5、簡易突入装備など | MP5、狙撃銃、小銃等 |
| 特徴 | 初動制圧重視 | 大規模突入、陸海空作戦も対応可 |
■ 補足
銃器対策部隊は、SATの「最後のカード」に先立ち、通常機動隊と異なり、拳銃や自動小銃などの銃器を用いた凶悪事件に即応するため、特別な訓練と装備を受けた機能別部隊である。現場で最初に“対銃器戦闘”にあたる警察力として極めて重要な位置を占めている。
銃対の展開手段「小型遊撃車」
この銃器対策部隊の展開手段として、現在配備が進んでいるのが「小型遊撃車」と呼ばれる特殊車両である。小型遊撃車は、トヨタ・ランドクルーザーをベースに、耐弾ガラスやボディの防弾加工を施した専用車両で、現場における機動性と防御性の両立を図って設計されている。
2022年には、ある事件の被疑者護送にも投入され話題となった。この特殊車両の出動理由は“被疑者奪還”を警戒した警察当局の思惑にある。

実際、国内では過去に自動小銃や散弾銃が使用された重大事案が複数発生しており、一般的な警察車両では対応が困難な状況が想定されていた。たとえば、都市部で突発的に発生する銃撃事件、あるいは施設占拠型のテロ事案などでは、最初に展開される部隊の装備と車両が、初動対応の成否を大きく左右する。
これまでも機動隊には防弾化された各種警備車が配備されていたが、SUVのような機動性は期待できなかった。

小型遊撃車は、こうした危険な現場において、銃対の隊員を安全に展開させるとともに、突発的な逃走事案への備え、現地での持続的な対応を可能とするための移動拠点としての機能も兼ね備えている。加えて、空港や原子力発電所などの「重防対象施設」における防衛任務においても、同車両は防御的・威圧的な存在感をもって配備されることがある。
SATが出動する以前の段階で、まず銃対がこの小型遊撃車を駆って現場に急行し、初期の制圧・封鎖・偵察を担うという構造は、警察の銃器事案対応における合理的な多層構造の一端をなす。言い換えれば、小型遊撃車は「最初の盾」としての役割を果たす装備なのだ。
まとめ
銃器対策部隊は、市民を巻き込む凶悪・銃器事件への第一線対応を担う専門部隊であり、SATに先立つ独立した抑止力として機能している。
1996年以降、テロ情勢の変化に対応しつつ、装備・人員・訓練体制が着実に強化されてきた。
ほかにも、沖縄県警の国境離島警備隊や、海上保安庁の特殊警備隊(SST)、など、状況に応じた銃器・爆発物への対応力をもつ部隊が各所に存在するが、それらとも連携がされる。
日本国内では銃器犯罪の発生件数が欧米諸国に比べて圧倒的に少ないとはいえ、暴力団や密輸組織、あるいは「ローンウルフ型」の個人による銃器使用事件への備えが求められている。
近年はドローンや模倣銃、3Dプリンタによる銃器の製造といった新たな脅威も念頭に置かれ、訓練内容や装備の見直しが続けられている。
このように、日本の銃器対策部隊は、現場主義と法治国家としての制約の中で、高度な専門性と即応性を両立させるよう編成されており、公共の安全維持とテロ抑止の要となっている。

📚 出典一覧(警察庁公式サイト「警察白書」)
-
平成16年 警察白書 第2項 テロへの対処態勢の強化:「」
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h16/hakusho/h16/html/F7002020.html -
令和元年版 警察白書 第2項 警察におけるテロ対策:「イ 銃器対策部隊」
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r01/honbun/html/vf122000.html -
令和4年版 警察白書 第2項 国際テロ対策:「(2)テロ対処体制の強化」
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r04/honbun/html/y6612000.html -
平成14年 警察白書 銃器対策部隊の装備・体制:「(2)テロ対処部隊の活動」
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h14/h140202.html -
平成20年 警察白書 第3節 国際テロ対策:「(2)テロへの対処態勢の強化 〔1〕 テロ対処部隊の充実強化」
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h20/honbun/html/k4300000.html -
平成15年 警察白書 機動隊活動と銃器対策部隊:「2)テロ対処部隊の充実強化」
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E6001020.html -
平成22年 警察白書 第2 国際テロ対策:「〔1〕 テロ対処部隊の充実強化」
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h22/honbun/html/m4120000.html - 平成26年 警察白書 第2 国際テロ対策:「図表6-7 テロ対処部隊の概要」
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h26/honbun/html/q6120000.html