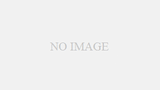フラットビーム・バイザーが下ろされ、艶やかなパンプスがアクセルを鋭く踏み込む。
車内のコンソールにはA社製無線機が搭載されており、「マルモク」「マルヒ」といった警察用語が車載通信系で流れる。
無線通信規定などどこ吹く風とばかりに、自局のコールサインも告げず、女性捜査官は捜査専務系を通じて捜査一課に対し、被疑者データの転送を即座に要請する。
その間にも、17系クラウンアスリート捜査車両は鋭くエンジン音を唸らせ、緊急走行で現場へと向かう。
「……なんだよ、これ。」
わずか40秒あまりのこのシークエンス、筆者はテレビの前で釘付けとなった。観る者の息を呑ませる緊迫感に満ちていたのだ。
そう、これこそが、のちに9年間にわたり続くことになる伝説の刑事ドラマ『アンフェア』の幕開けを告げた、あの“問題の40秒”である。
一人の女性刑事の「アンフェア」な生き様
2006年1月、その初回放送が始まったとき、日本の刑事ドラマの文法が一つ塗り替えられた。雪平夏見という、型破りでありながらも理知的で、そしてどこか壊れたヒロインが、この40秒で鮮烈にその存在を印象づけたのである。
記憶をたどれば、『アンフェア』が初めて放送された当時、「なんだかすげェドラマが始まったなあ……」と感じた視聴者も多かったはずだ。
あれから19年。もはや“近年の刑事ドラマ”と呼ぶには時間が経ち過ぎたが、その余韻と衝撃は、今なお色褪せることがない。
再視聴のたびに思う。「このシーンがすべてを語っている」と。そして、それが『アンフェア』なのだ。
一人の女性刑事を軸に描かれたこの物語は、ただの刑事ドラマではない、リアリズムとスタイリッシュさが同居した作品世界になっており、一気に引き込まれた。
関西テレビ制作による人気刑事ドラマ『アンフェア』が、劇場版『アンフェア the end』で完結してから、早くも5年が経過した。
だが、その熱気は冷めることなく、スピンオフ作品『アンフェア the special ダブル・ミーニング』が公開されると、改めてその根強いファン層の存在を世に示した。スピンオフながらも、本編に劣らぬ緊張感と完成度で構成された同作は、視聴者から高い評価を受けている。
雪平夏見という一人の女自身の過去、信念、そして正義とは何かという命題にまで踏み込んでゆく。続編やスピンオフの公開が繰り返されたのも、そうした深層的なテーマが多くの支持を得た証であろう。
物語はやがて、「公安がらみの案件」へと展開し、「警察組織を揺るがす巨大な爆弾」を、たった一人の刑事である雪平夏見に託すという構図が浮かび上がる。
警察組織と捜査官個人の対立、巨大な陰謀、そして孤独な捜査。その筋立てには、どこか『新宿鮫』の香りが漂う。いずれも警察ドラマの王道領域である。
今後、原作の完結とともに、あの“アンフェアな世界”がもう一度スクリーンやテレビに帰ってくる日は、果たして訪れるのだろうか。
ちなみに余談だが、『新宿鮫』も『海猿』も、フジテレビ版よりNHK版のほうが硬派で質実だったという印象がある。映像表現の“品格”においてNHKはやはり一日の長があるのだろう。
であれば——『アンフェア』もNHKでリメイク、というのはどうだろうか?ドラマファンなら一度は夢想したに違いない、“公共放送による再構築されたnext雪平夏見”。
……いや、やはり無理があるか。それとも、案外悪くないかもしれない——そう思ってしまうのは、きっと筆者だけではあるまい。
ねえっ?だめなの?
リアリズムの追求――『アンフェア』に見る劇用車の考証精度
ドラマ『アンフェア』は、当時としても稀に見るリアリズム志向の刑事作品であった。
劇中の演出やキャラクターの造形、そして小道具のプロップガンにいたるまで、「リアルで行く」という製作陣の気概が全編に漲っていたのである。

170系クラウンアスリート覆面が意味するもの
しかし本稿で注目したいのは、別のリアル――すなわち、劇中車両である。
そう、あのクラウンアスリート(170系)覆面パトカーだ。
警視庁刑事部捜査一課・強行犯係の刑事として登場する雪平夏見。その彼女の足として与えられているのが、17系クラウンアスリート。この車両選定が、しぶい。
というのも、この型のクラウンアスリートは、実際に警視庁刑事部にて捜査車両として配備されていた事実があるからだ。
とくに捜査現場へ指揮官が臨場する際に使用される「指揮用車」と呼ばれる覆面としての採用があったことは、劇用車ファンの間ではもはや常識であろう。
配備数自体は限られていたものの、確かに存在した“実車ベースの劇用車”であり、これは映像考証的にもかなりの再現性を誇っているといえる。
◆巡査部長にしては贅沢すぎる一台?
とはいえ、ここで一つの疑問が生じる。果たして、巡査部長という階級の雪平に、このような高級車が割り当てられることが現実的であるのか――という点だ。
指揮用車という名目からすれば、本来は係長クラスや幹部格の捜査員が乗車するのが自然な構図。つまり、雪平のポジション的にはやや過剰装備とも言えるのだ。
◆大井松田吾郎師匠の記事に見る当時のアスリート捜査覆面事情
ここで参考になるのが、ラジオライフ2003年2月号「警察特集 パトカー巡礼」にて、大井松田吾郎氏が記した一節だ。
師匠によれば、当時の東京ではアスリートGの覆面捜査車が、ブルーバードの覆面と並んで日常的に目撃されていたとのこと。つまり、配備先は幹部に限らず、一般捜査員にも及んでいた可能性が高いというわけだ。
また興味深いのは、アスリートG一台でブルーバード覆面が約4.5台購入可能というコスト面での格差。
にもかかわらず、アスリートが現場に出ていたという事実は、それだけ“威圧効果”や“機動性”が評価されていたことの裏返しでもある。
ちなみに師匠曰く、「アスリートは顔が怖い」ため、緊急走行時には他車両が避けてくれるという利点もあったという。
再びドラマ内のアスリートに戻して考えると、あくまで警視庁刑事部配備の事実がある以上、劇用車としての考証は成立している。むしろ、映像上の演出として“あえてのアスリート”を選んだとも解釈できる。“顔が怖い”この1台こそ、雪平夏見という人物像の冷徹さ、そして芯の強さを映し出していたのかもしれない……!?
ところが、近年の刑事ドラマでは、この“リアルさ”の扱いが極端に分かれつつあるという印象も
最近では、自動車メーカーが全面協力し、実際に警察で採用されているモデルを劇用車として提供するケースも少なくない。たとえばスズキがスポンサーについた作品で、キザシ(※実際に警察庁が採用)を劇用車として使用した例などは記憶に新しい。
一方で、まったく逆方向の措置も。
つまり、捜査車両を模した劇用車のメーカーエンブレムを隠したり、独自に“ありもしないマーク”を捏造して貼り付ける手法である。
たとえば、こちらもリアルな演出で人気の『機捜216シリーズ』のように、劇中の捜査車両の再現度が極めて高い作品においてでさえ、ティアナやレガシィといった実車の前後に、“韓国車風”の意味不明な架空エンブレムを貼り付けるという演出がなされている。
これは、映像としてのクオリティを高めるどころか、むしろ視聴者の違和感を誘発する“演出ミス”とさえ感じられる場面である。
せっかくの細密な捜査車両のディテールも、この不自然な“改変”によって台無しになってしまっては、超気持ち悪く、残念なのよ……。
これは、いわゆる商品名やブランドを出せない制作上の配慮――ないしは、スポンサー不在ゆえの“仕方ない対応”なのだろう。
雪平は“赤色灯ルーフ中央主義”の矜持――アンフェアに見る警光灯のリアリズム
またも、『アンフェア』のリアリズム追求を裏付けるファクターである。覆面の警光灯の扱いにまで、拘っているのだ。
刑事ドラマにおいて、覆面パトカーの赤色警光灯の載せ方など、視聴者の多くが見過ごしてしまうであろう細部にまで“リアリズム”を宿している作品は意外と少ない。
とりわけ興味深いのは、劇中に登場するクラウン・アスリート覆面捜査車の赤色警光灯が、きちんと“ルーフ中央”に設置されている描写が一貫して採用されている点である。

助手席サンバイザーには“お馴染みのフラットビーム”も。赤色灯の搭載位置ひとつで語れるリアル――これもまた、“刑事ドラマの美学”のひとつ。
第7話、安藤が撃たれた現場へ急行する雪平のアスリート覆面に注目してみよう。
ルーフ中央には着脱式の赤色灯、助手席側サンバイザーにはフラットビーム型補助灯が設置され、ヘッドライトも点灯――これはまさに、現実の緊急走行時における標準的な点灯パターンを正確になぞっている。もっとも、緊急走行時のヘッドライト上向き点灯は推奨であり、道交法の義務ではない。刑事ドラマの緊急走行でヘッドライトが点灯されていない場面も多いもの。
ともかく、“顔が怖い”と評されたクラウン・アスリートのフロントマスクも相まって、緊急車両としての存在感を際立たせていた。
◆片手ポン載せじゃない、中央配置へのこだわり
さらに注目すべきは、赤色灯の“載せ方”そのもの。劇中では助手席の相棒が片手で“ポン”と載せるような横着な演出はなく、ルーフの真ん中に正確に配置された赤色灯が、ぴたりと安定して据え付けられている。
シーンとして直接描かれているわけではないが、第1話冒頭での“雪平単独による緊急走行”の際にも、しっかりと中央に赤色灯を設置していた。
これはつまり――「型破りの女刑事」という設定とは裏腹に、警察内部の内規に忠実な人物であることをさりげなく示している描写と捉えることもできる。
さらに興味深いのは、この“中央主義”は雪平のアスリート車両に限った話ではない点である。全捜査車両に共通する“中央設置”の徹底ぶりだ。
劇中に登場する他の捜査用覆面車両も、赤色灯は必ず中央に設置されており、これは一つの作品内ルールとして統一されているように見受けられる。
現実の警視庁においても、式典や合同訓練など、斉一を期す場面では赤色灯は必ずルーフ中央に搭載されると定められており、本作の描写もその原則に則ったものである。
ところで、こうした描写を目にした視聴者の中には、
「え、クラウンアスリートって指揮用車だよね? 赤色灯って2個載せじゃないの?」と疑問を持つ方もいるかもしれない。
その問いはもっともである。
当サイトでは以前、“覆面パトカーにおける赤色灯2個載せの理由”について特集を掲載したが、それをお読みいただいた読者諸氏ならば、この件もご納得いただけることだろう。

要するに、赤色灯2個載せ=指揮官車両、あるいは部隊運用前提の運用仕様であり、劇中の雪平車両はあくまで「単独行動の刑事車両」という演出の範囲内にある。
結果として、1灯搭載+フラットビーム補助という構成が最適解となっている。
覆面パトカーにはイレギュラーな運用がいくらでもある……なんてことを得意げに言うつもりはない。それこそが杓子定規の交通覆面とは違う捜覆の大きな魅力なのだ。
見た目の“かっこよさ”や“ドラマチックな演出”に逃げることなく、現実の運用規定に則った緊急車両描写を積み重ねたことで、視聴者に対し説得力でわからせてくるのである。
『アンフェア』における覆面パトカーのアンテナ考証 ――凛とした“働くセダン”の佇まい
ドラマ『アンフェア』に登場する170系クラウン・アスリートは、その演出面でも細部へのリアリズムが光る。特に無線アンテナの搭載に関しては、覆面捜査車両としてのリアルさを追求したディテールが随所に見られる。

たとえば第9話。雪平と安藤が現場に駆けつけたクラウンのリアウインドウ脇に、TAアンテナがしっかりと確認できる。TAはおそらくパナソニックのアナログテレビ受信タイプ。セイワのTAの実物はヤフオクで10万から20万円でしたからねえ。
このTAアンテナは、おそらくアナログテレビ受信用――警察無線用の外観を再現するための「見立て」だと考えられるが、その存在感は圧倒的。
クラウンの流麗なルーフラインに、鋭く伸びたアンテナがアクセントを加えており、まさに「凛とした働くセダン」の趣だ。

さらに第2話では、TAアンテナに加えてTLアンテナ(トランク右側)も装備されていることが確認できる。

これは当時の覆面捜査車両でしばしば見られた「TA+TLのセット構成」であり、TAが車載通信系ほか、TLが移動警電(WIDE通信)を担っていたと思われる。

この組み合わせは、00年代中盤の警視庁覆面車両の“美学”とも言える仕様で、同様の構成が見られた。
インプレッサ捜査覆面ですらTAとTLセットでつけてましたからね。このTA/TLの併せワザこそが当時の覆面パトの凛々しき姿。まさに「凛として覆面」である。
こうした実在装備の再現をドラマに持ち込んだ制作チームのこだわりは特筆すべきだ。
一方で、劇中で実際にこのアンテナを通じた無線通信の描写は限定的。第1話で無線連絡を取る場面を除けば、以降は携帯電話でのやり取りが中心となっていく。この点については少々惜しいところだが、2005年からは警視庁でポリスモード携帯(捜査員専用端末)の導入と活用が進んでいたことを考えれば、当然とも言える。
また、雪平のアスリート助手席側にはカーロケナビ風端末が確認でき、無人の助手席上にはノートPCも常備。警視庁本部の蓮見杏奈からデータ転送が行われる描写も。劇場版では、雪平がカーロケを用いての位置確認に言及する場面もあり、デジタル化が進む捜査の現場を垣間見せる演出が随所に散りばめられていた。

もっとも、2010年代以降、こうした外装アンテナは「覆面の証」として一般にも認識されすぎたため、いわゆるユーロアンテナの導入、さらには全国的にアンテナの車内秘匿化が進行。特に有名なアンテナ泥棒事件以降は、その動きが一層加速。寂しい限りだ。

それゆえ、あの凛々しき“働く覆面セダン”の姿を拝めるのは、ある意味で『アンフェア』が放送された時代までの名残り。
雪平車両に装備されたTAとTLアンテナのツイン仕様――それは単なる美術ではなく、「機能美」でもあった。
まとめ
というわけで、うーん……アンフェアって捜査車両の選定と再現度において、その志の高さは際立ってるし、イイよなあ、雪平夏見のクラウン・アスリート捜査覆面よきなあ……という記事であった。
登場人物の装備や車両がリアルであることによって、ドラマの世界観そのものが揺るぎない説得力を帯びる。これは刑事ドラマにとって、極めて重要なファクターである。
今後、刑事ドラマがどの方向を選ぶにせよ、ディテールのリアリズムは物語を支える土台。決して、マニアを喜ばせる為だけにあると思うなかれ。
とりわけ、“警察装備品”をリアルに感じさせる要素こそが、視聴者を「警察社会」という虚構と闇の世界に引き込む鍵であり、ドラマとしての骨格を強くする武器になるのである。
『アンフェア』が示したスタンスは一つの理想形とも言えよう。実際の捜査車両に限りなく近い選定、そして無理のない考証。エンブレムも堂々とそのまま、虚構と現実の境界線が、極めて自然に溶け合っていた。
しかし、どこから持ってきたんだよ、この17アスリートモドキ
この170系クラウン・アスリート覆面の劇用車。上に挙げたとおり、その出来が“本物顔負け”で「どこからこんな車両を調達したんだ?」と驚く視聴者も少なくない。
この謎にヒントを与えるのが、エンドロールに記載された「車両 ファン」の文字。
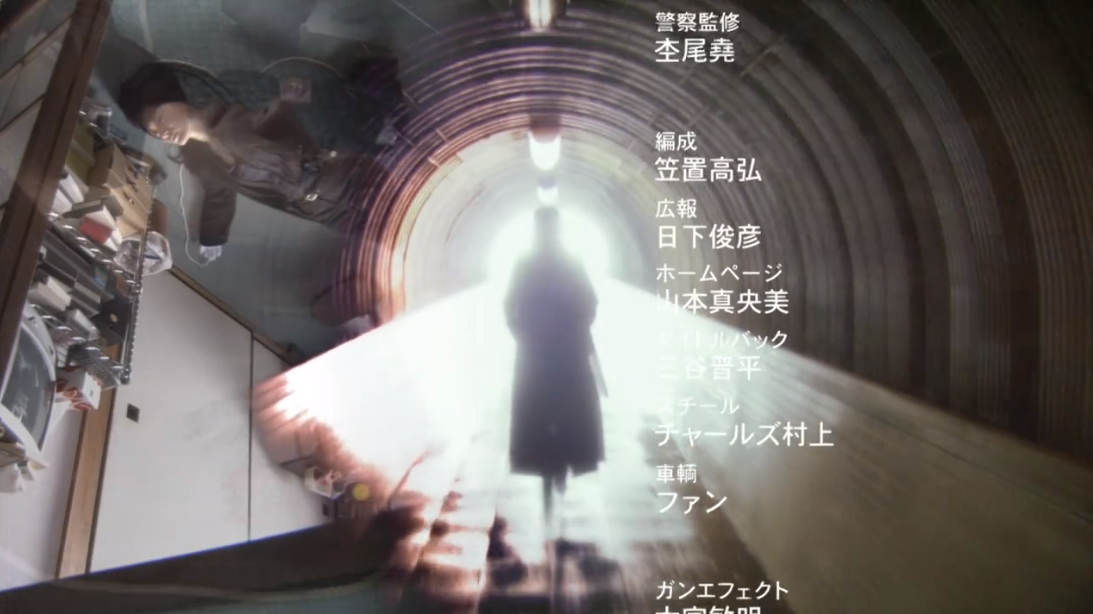
ここでいう「ファン」は、劇用車両の専門会社名とも解釈できるが、それよりも可能性が高いのは「車両マニア(ファン)による私物提供または協力」だという説。
あくまで説であるが、実際に一部のドラマでは、無線マニアや捜査車両再現オタクが劇用車として私有車を提供しているケースがある。これは『アンフェア』においても充分にありえる話だ。
◆ “リアル”が本物に近づきすぎた例:刑事貴族の前例
ちなみに余談だが、ラジオライフ誌に拠れば、90年代刑事ドラマ『刑事貴族(ヒロミ・ゴー版)』にて、実在する覆面車両を模した車両を製作し撮影に使用した結果、番組関係者が警察当局から呼び出しを受けたというエピソードがある。
警察当局からは「なぜここまで似せたのか?」という質問を受けたらしく、警察当局がそれを賛辞・苦言・説諭・警告のどれとして伝えたのかは定かではない。
それでもこのような“リアリズム追求型”の刑事ドラマが、ファンの間で長く語り継がれる理由のひとつでもある。
覆面車内の通信系装備もできるだけ活用するなどの現代の捜査現場では当たり前となった描写もドラマで見てみたいものだ。
そういう意味ではデジ簡の車載機のほうが、アマチュア無線のモービル機より、最新のIPRによっぽど雰囲気が似ており、実例として、2021年に放映されたドラマ『ハコヅメ』ではアルインコ社のDR-DPM60がパトカーの車載無線機として登場している。
パトカーの無線にデジ簡?!#日テレドラマ #ハコヅメ#デジタル簡易無線
DR-DPM60 pic.twitter.com/XUobTuTnWN— miraipipi (@miraipipi) October 9, 2021
タイトルバナーは『アンフェア』第9話より引用。画像は引用の範囲内(研究・批評目的)で使用しており、各作品の著作権はそれぞれの版権所有会社に帰属します。(C)関西テレビ
他の関連記事もぜひご覧ください。