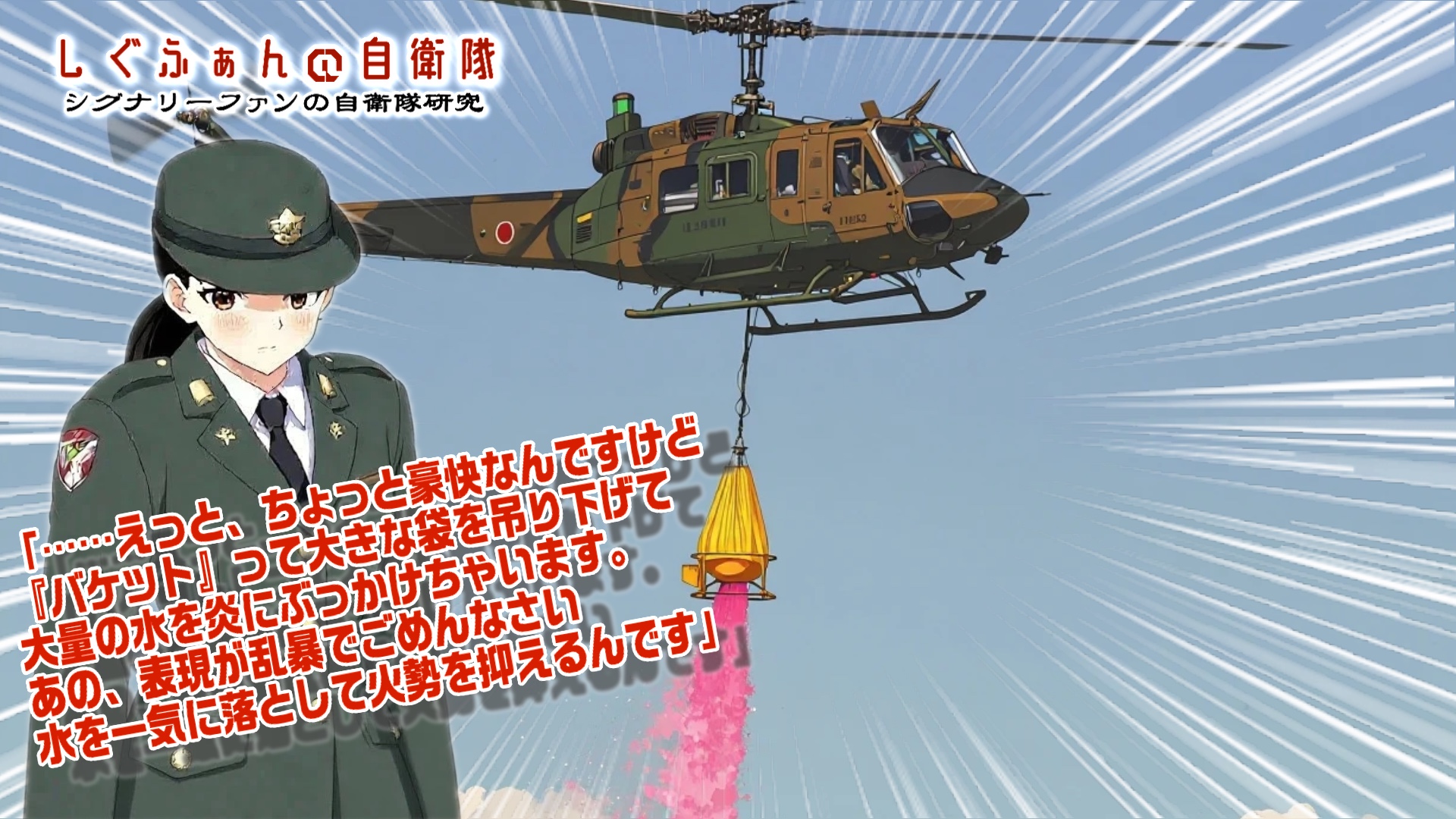88式地対艦誘導弾(通称:SSM‑1/88式)は、冷戦期のソ連艦艇脅威や沿岸防衛の必要性を背景に開発された、沿岸・島嶼防衛における陸上からの対艦抑止力の中核を担う装備です。
従来の艦砲や航空支援だけでは対処が難しい小型高速艦艇に対して、陸上からの抑止力を提供するのが、陸上自衛隊が長年にわたり運用、配備してきた88式。
陸上自衛隊では敵勢力の着上陸を阻止するため、海岸付近に配置した戦車・対戦車・野戦特科火力などを集中させた着上陸侵攻対処を行います。
もちろん、海上の脅威対処は海上自衛隊の任務となりますが、着上陸を防ぐには、陸自や空自の対艦番長とも密接な連携が必要です。

本稿では、88式地対艦誘導弾が「何を目標とするか」だけでなく、「どう使うか」「なぜ重要か」「運用上の長所と限界は何か」を掘り下げます。
(注)公表資料は機密保護のため諸元に幅がありますが、防衛省は同システムの構成要素と運用目的を明示しています。
自衛隊が防衛機密をそのまま公表するとは思えませんが、あくまで自衛隊が公表している公的資料や報道に基づいての整理を基準としています。ご了承ください。
概要と系譜
88式地対艦誘導弾(通称:SSM‑1/88式)は元々、航空自衛隊で使われていた80式空対艦誘導弾(ASM‑1)を地上発射型に改修して発展させた車載型の地対艦ミサイルシステムで、発射機(トラック搭載)、捜索・追尾用レーダー、射撃統制装置などで構成されています。
1988年に陸上自衛隊で制式化され、以降、陸上配備の対艦巡航ミサイルとして沿岸域での艦艇接近阻止を任務に各方面隊へ配備されてきました。陸上から洋上の相手を撃破する能力が、その存在意義です。
車載式(トランスポーター)システムで構成されていることからも分かるように、88式の運用は単純な「置いて撃つ」ではなく、機動展開できることを前提に設計され、沿岸防衛や離島防衛での艦船阻止を目的としています。
発射機は74式特大型トラックの荷台に6連装の発射筒(円筒形のランチャー)を搭載する形が一般的で、車載化されたことで機動的に展開・撤収が可能です。
山間部や内陸の高地から海面へ向けて射出して海上目標を襲う「地形を利用した隠蔽発射」運用が想定されています。
基本的な構成と主要諸元
ミサイル本体は全長約5.0メートル、重量は約660〜661キログラム。ミサイルは円筒形のキャニスターに収められます。
推進は発射直後の加速用に固体ロケットブースターを用い、その後ターボジェット(TJM 系列)で巡航という「ブースト+ターボジェット」方式を採用しています。
誘導は飛翔中は慣性航法で目標付近まで進み、終末段階で搭載するアクティブ・レーダー・シーカーが自律的に捜索・捕捉して最終攻撃を行う、という設計です。
海面低空(シー・スキミング)で飛行して探知を回避します。
88式のシステム構成(運用面)と配備
88式は単体ミサイルだけで運用されるのではなく、指揮統制装置、捜索・標定用レーダー、中継装置、発射機、予備のミサイル装填装置などを含む対艦ミサイル・バッテリーの形で配備されます。
88式は全国の方面隊の地対艦ミサイル連隊に配備されてきましたが、編成や配備は時期により変化しています。
例えば、北部(北海道)・東北・西部方面隊には地対艦部隊が存在し、各連隊は複数の発射機を保有して機動運用を行います。
近年は大規模な新編が行われ、2024年に陸上自衛隊勝連分屯地(沖縄県うるま市)に第7地対艦ミサイル連隊、さらに2025年3月には陸上自衛隊湯布院駐屯地(大分県由布市)に第8地対艦ミサイル連隊が新編されています。
2. 88式は「検知→評価→発射→撤退」のサイクル
陸自における地対艦ミサイル連隊(88式を運用する部隊)は、敵の上陸や艦隊接近を抑止・阻止するため、陣地変換や機動配置を行いながら目標を捕捉して射撃します。
88式の運用では次のようなサイクルが繰り返されます。
-
情報収集・検知:哨戒艦、航空機、地上レーダー、加えて衛星や無人機(UAV)など、多様なセンサー情報を合わせて目標を検知します。
-
目標評価・選別:防衛上のルールと指揮系統に従い、撃破優先度や発射可否を判断します。
-
発射準備・陣地調整:発射位置や角度を計算し、発射機を所定の姿勢に整えます(アウトリガー展開、噴流偏向板等のセッティング)。
-
発射→命中評価:指令に基づきミサイルを発射し、着弾(あるいは修正指示)のために観測を続行します。複数発を連携させることで命中確率を高めます。
-
速やかな撤退:発射後は反撃を避けるために即時離脱します。発射拠点は分散・移動しておき、生存性を確保するのが基本です。
この一連の流れは、「撃って終わり」ではなく「撃って生き残る」というサイクルに重点が置かれています。
発射後に位置が特定されると、敵による反撃(艦砲射撃・ミサイル・航空攻撃)を受ける恐れが高いためです。
飽和攻撃を行う
発射は複数発を用いた飽和攻撃で命中率を高めることが想定され、地形に沿って低空で進入するため、敵の早期探知を回避しやすいという利点があります。
敵海軍側は艦載の防空兵器(短SAM、CIWSなど)や電子防御を備えています。単発のミサイルではこれらを突破しづらいため、複数発を短時間に発射して迎撃能力を消耗させる飽和戦法が用いられます。
連隊規模で複数の発射機を同期させ、同一目標または目標群に矢継ぎ早に攻撃を仕掛けることで、迎撃網を突き崩す戦術です。
発射タイミングの調整や到達時間調整は指揮統制装置側の重要な役割になります。
低空・海面すれすれの飛翔(シー・スキミング)が未来を切り開く
88式を含む多くの対艦ミサイルは海面すれすれに飛ぶ“シー・スキミング”プロファイルを取り、レーダー探知距離を短縮します。
これにより迎撃側の反応時間が削られ、命中の機会が高まります。
一方で、低空飛翔は波や気象、海面反射による誘導ノイズ、終末段階での目標識別の難しさなど技術的課題も伴います。
実戦では海況・気象・電子妨害の状況を精査し、最適な飛翔経路(諸元)を事前にプログラムしておきます。
長い射程の秘密
射程の実務的意味―「百数十km」は何をもたらすか
射程の具体的数値は機密扱いの要素もあり、公開情報に幅があるため、報道や公表値を踏まえて慎重に表現されているのが現状です。
公的説明では88式は「百キロメートル以上」級の射程とされます(報道では100km前後とする説明が一般的です)。
射程が長いことの最大の効果は、敵艦が安全に行動できる“スタンドオフ”空間を狭める点です。
具体的には、敵が沿岸や島嶼の近接海域で自由に艦隊展開できる範囲を限定し、接近自体を抑止する効果があります。長射程はまた、味方の艦艇や航空機と協働して多層的に敵を監視・攻撃する際の戦術的余地を広げます。
誘導方式・精度…終末のアクティブ・レーダー・シーカー
-
88式:慣性航法等の自律中途誘導+終末のアクティブ・レーダー・シーカー(ARH)。海面低空でのシースキミング飛行により探知回避を図る。
-
12式:INS+GNSS(GPS等)併用による航法精度向上と、終末段階のARHによる最終捕捉。現代の電子戦環境を踏まえた耐妨害・高精度化が設計思想に含まれる。
88式の脆弱性
このように、陸上から長距離で艦艇を脅威にできるため、敵の接近を抑止する高い抑止力がある一方で、被探知・反撃リスク:発射拠点は偵察で特定されれば精密打撃を受けるリスクもあります。
したがって撤退と分散が必須で、固定化は致命的です。
また、電子戦・妨害も重要なリスクです。敵のEW(電子戦)により誘導や通信が妨害されるリスクがあります。
そのほか、艦載防空の向上や統合型防空網により、単体ミサイルの有効性は相対的に低下する場合があります。これを補うための信号・センサーの冗長化といった新型ミサイル導入や飽和戦術が求められます。
12式地対艦誘導弾との機動性比較(発射体系・展開性)
88式は有効な能力を提供してきましたが、近年では技術進化や脅威の変化に対応するため、12式地対艦誘導弾(Type‑12 SSM)など新型の導入が進んでいます。
新型の12式は機動性や精度、対艦抑止力を向上させることが狙いであり、結果として88式と12式が一定期間併存しながら、任務と配置の最適化が図られます。
-
88式:トラック搭載の6連装ランチャー等で運用され、機動配置・陣地変換を行う戦術が中心。地形を利用して隠蔽・発射する運用が基本です。
-
12式:専用TELや新設計の機動プラットフォームでの運用が想定され、より機動的かつ分散運用(複数発射位置からの運用)に適合する構成です。部隊編成面でも新設・再編が進められています
近年の動向と試験・公開情報
近年も88式の実弾射撃訓練や試験が行われており、国内での射撃実施や評価が報じられています。メディア報道では、発射レンジや目標への到達、車載型システムの機動性が繰り返し論評されていますが、具体的な運用手順・配備数・発射テンプレート等の細部は安全保障上、公開情報に限りがあります。併せて、後継・補完兵器(12式や艦載型の発展版等)の導入により、運用概念や配備場所は更新されつつあります。
北海道で国内初の実射訓練
陸上自衛隊はこれまで88式地対艦誘導弾の実射訓練は国外で行ってきました。
これは射程の長いミサイルという特性から、訓練実施の理解が周辺自治体から得られなかったのが背景にあるようです。
しかし、中国の海洋進出を念頭に抑止力強化につなげたい考えがあるとされ、2025年6月24日、北海道で国内初となる88式地対艦誘導弾の実射訓練が行われました。南西の海上にある標的船に向けて実習弾2発を発射しました。
参照:https://www.uhb.jp/news/single.html?id=5176
まとめ
88式地対艦誘導弾は、陸上から海上を抑止・阻止する実用的な手段として、日本の島嶼防衛や沿岸防衛の中核を担ってきました。
その有効性は長射程、低空飛翔(sea‑skimming)、そして機動配置という戦術要素に支えられています。
一方で、発射拠点の生存性、敵の電子・防空能力の向上、さらには新型ミサイルの登場という課題に対応する必要があり、これを踏まえた部隊運用・装備更新が継続的に行われています。
また防衛政策的に見れば、地対艦ミサイルの配備は単に軍事能力を高めるだけでなく、抑止政策の要素もあります。
長射程の地対艦能力を沿岸に配備することで、敵にとって「接近しても代償が大きい」という計算を生ませることができます。
それが陸上自衛隊地対艦ミサイル連隊の任務と役割というわけです。
もちろん、海自や空自との多層連携が必須であり、正確・迅速な情報統合(C4ISR):哨戒資産や衛星情報との連動が現代戦の鉄則です。
一方、実弾射撃訓練や配備拡大は地域の緊張を高める面もあり、国際的・地域的な配慮が必要となり、これからも課題が大きいでしょう。
参考(主要出典)
-
陸上自衛隊 装備紹介ページ(88式に関する記載)。https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/1ab/soubi/soubi.html
-
J‑Defense 解説記事:88式運用と訓練に関する分析(実射訓練報道)。https://j-defense.ikaros.jp/docs/commentary/003389.html
-
AP News(2025年6月24日):国内射場での88式実弾射撃試験の報道。https://apnews.com/article/143f17458a6be541997bc5f9e0b817e7
-
三菱重工(Type‑12 関連/後継に関する製品説明)。https://www.mhi.com/jp/products/defense/type12_ground-to-ship_missile_launcher.html
-
陸上自衛隊各方面隊・部隊の活動紹介(演習報告等)。https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/1ab/topic/topiccontent/topic26615kamifuboueidaijin/topic26615kamifuboueidaijin.html