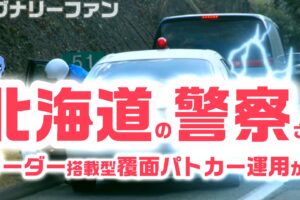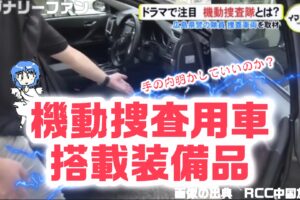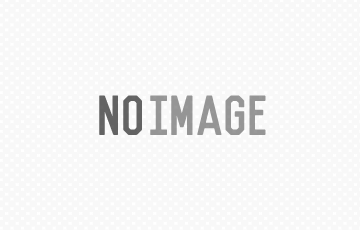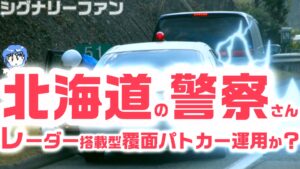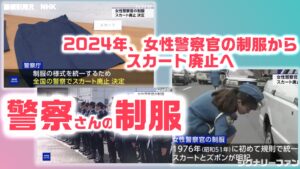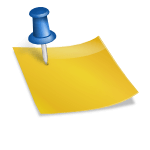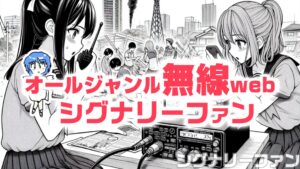このページでは、市街地で最も一般的に見かける白黒ツートンの「警らパトカー」について解説する。
警察車両の配備は、国費調達における調達仕様書(いわゆる入札要項)と、各都道府県警による県費車両の独自採用方針の両方によって決定されている。
街頭で見られるパトカーは、一見するといずれも同じように見えるが、実際には所属や任務によって複数の種類が存在する。具体的には、警察署の地域課や交通課が使用するパトカーのほか、都道府県警察本部に属する自動車警ら隊や交通機動隊など、いわゆる本部直轄の執行隊が運用する車両も含まれる。
これらのパトカーは、所属部門によって車種の選定基準や運用形態が異なっており、それが見た目や装備の違いにもつながっている。
Contents
2025年現在の警らパトカーの主力車種──その1「クラウン・パトロール」

警らパトカーの王道──「トヨタ・クラウン」
現在、街頭で多く見かける警ら用パトカーのひとつが、トヨタ「クラウン」である。クラウンは、長年にわたり警察庁によって国費で調達され、都道府県警察に配備されてきた車種である。主に地域警ら用の白黒パトカーとして運用され、地域の巡回や初動対応などに用いられている。
このクラウン・パトカーについては、インターネット上で「警察が高級車に乗るのは適切なのか」「もっと燃費の良い小型車でよいのではないか」といった意見が一部で見られる。こうした声は、パトカーの調達や装備に関する知識を持たない一般市民からの疑問として、一定の理解は可能である。
クラウンは、「高級セダン」の代名詞とされ、幅広い世代に人気のある車種である。その印象もまたパトカーに対する認識に影響を与えていると考えられる。
警察は、クラウンのモデルチェンジにあわせて歴代のモデルを継続的に採用してきた。なかでも210系と呼ばれる型式のクラウンは、特徴的なフロントマスクを持つことで注目を集めた。市販モデルではピンク色の特別仕様車が話題となったが、警察車両としては白黒塗装が基本である。
また、交通取締りを専門とする交通機動隊などには、クラウン210系アスリートおよび220系グレードが配備されており、高速走行性能を活かして速度違反の取り締まりなどに使用されている。
2022年にトヨタはクラウンセダンの生産を終了し、新型車としてスポーツタイプ多目的車(SUV)のような車形の新型クラウンを投入する方向で最終調整に入った。警察は今後も“セダンの威厳”を固辞するのか、動向が注目される。
警らパトの2強!その2……「BMレガシィ」

警らパトカーとして長年主力の地位を保ってきたのはトヨタ・クラウンであるが、2013~14年、そのクラウンに代わる形で全国の警察に配備されたのがスバル・レガシィ(BM系)である。
このBMレガシィは、2009年から登場した5代目レガシィのセダン型(BM9)をベースとしたもので、警察庁が国費で一括調達し、各都道府県警察本部に配備された車両である。
もともと、警察庁によるパトカーの入札条件には「FR(後輪駆動)」「排気量2500cc以上」「トランク容量」など、クラウンに有利な仕様条件が多く含まれていた。こうした条件のもとでは、クラウン以外の国産セダンが応札可能な余地は少なかった。
しかし、2010年代以降、入札条件の緩和や、FR車に限定しない全輪駆動(4WD)車の容認などにより、クラウンに次ぐ選択肢としてスバル・レガシィが急速に普及。とくに降雪地域を中心に、レガシィのAWD性能は高く評価され、警ら用車両としての適性を認められた。
BMレガシィは、機動捜査用車としても全国に配備されたが、無線警ら車のBMレガシィもまた、2010年代中盤には多くの県警に配備され、クラウンと並ぶ“2強”の一角を占める存在となった。
しかしながら、クラウンが210系(2012年~)以降の新型で再び警ら用として採用され始めたことで、BMレガシィの継続的な配備はされなかった。
伝説の警らパト……「日産クルー」

かつて多くの警察署に配備された代表的な警ら用パトカーのひとつに、「日産クルー」がある。日産クルーは、1994年から製造されたセダン型車両で、もともとはタクシー用途を主とする車両として開発されたが、国費および県費によって警察車両としても大量に導入された。
後期型のクルーでは、現在では標準装備となったブーメラン型の赤色警光灯や、その昇降装置を備えた仕様が初めて本格的に採用され、警らパトカーの基本的なスタイルの一つを確立した。
基本的には地域警ら用としての配備が中心であったが、一部の都道府県警察では例外的に、交通機動隊の覆面パトカーや、速度取締りに特化したレーダー装備の白黒パトカーとしても使用された実績がある。北海道など、一部を除いてほぼ配備されなかった地域もある。
パトカーはなぜ白黒なのか?
現在、日本全国で見られるパトカーの多くは、白と黒のツートンカラーで塗装されている。この配色の由来については、長野県警察が公式に説明している。
典拠元 長野県警察
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/rekishi/pato.html
それによれば、かつて日本国内では、一般の民間車両の多くが白色であったため、警察車両を明確に識別できるようにする目的で、車体の下半分を黒に塗装するデザインが採用されたという。これにより、遠目でも一般車両との区別が容易になった。
こうした塗装の実用的な理由に基づき、昭和30年(1955年)には全国的にこの白黒ツートンカラーが警察のパトロールカーの標準塗装として統一された。
なお、警察車両のカラーリングは用途によって異なる。たとえば、機動隊の車両は白と青のツートンカラーや、濃緑色の塗装を施したものなどもあり、任務や所属部門に応じて多様な配色が用いられている。
機動隊の特殊車両は装甲車だけじゃないぞっ!武骨なフォルムの特型警備車だけじゃなく、レスキュー車や資材搬送車、トイレカーにも萌えろ!
ミニパトおよび小型警ら車の解説
地域警察官、特に交番勤務員が使用する軽自動車や小型乗用車の警察車両は、一般に「ミニパト」あるいは「小型警ら車」と呼ばれている。これらは、排気量660ccの軽自動車や、1000cc前後のコンパクトカーが中心で、地域課や生活安全課の巡回業務などに用いられる。
ミニパトは、クラウンやレガシィといった中大型の警ら用車両よりもはるかに配備数が多く、まさに「警察官の足」として全国で活用されている。
特に東京都内では、警視庁の各警察署交通課が駐車違反の取締りなどにミニパトを活用しており、女性警察官が乗車するケースも多い。都内では、ダイハツ・ミラ(ジーノやイース含む)、エッセ、ハイゼットカーゴ、三菱・ミニカ、スズキ・アルトなど、さまざまな軽自動車がミニパトとして運用されている。
一方、軽自動車ではない小型警ら車としては、スズキ・ソリオやスイフト、トヨタ・パッソなどが全国的に配備されている。これらは軽自動車よりも車内空間や走行性能に余裕があり、狭隘地巡回や人員輸送など柔軟な運用が可能である。
ミニパトにも、警察庁が国費で一括購入し各都道府県警察本部に配分する「国費車」と、各都道府県が独自に予算を使って調達する「県費車」が存在する。自動車販売店のモータープールには、出荷前のミニパトが警察表記なしの状態で多数並ぶ光景も見られ、納車前の準備工程の一端をうかがわせる。
また、警視庁では、白黒塗装の軽自動車パトカーに加えて、外見から警察車両と判別しにくい軽自動車タイプの覆面パトカーも運用されている。
これらミニパトにも赤色灯とサイレンアンプが搭載されており、緊急走行は可能である。ただし、クラウンなどに搭載されている「ストップメーター」と呼ばれる車速測定装置は原則として搭載されておらず、交通取り締まり機能には限界がある。また、車載無線機についても、搭載されていないか、簡易なシステムにとどまることが多い。
ただし、警視庁のミニパトには無線用アンテナを搭載する車両が多く見られる。

高層ビル群の谷間では無線の通信環境が悪化することから、乗車する警察官が携行する署活系無線機と同軸ケーブルを接続して本署との通信環境を改善するためである。同様の運用は通信状況が不安定な一部の地方都市でも見られる。
まとめ
なお、神奈川県警ではスズキ・キザシをベースとした白黒パトカーが一部採用された実績がある。キザシは国費覆面で配備された車種ではあるが、採用例は極めて限られており、現場でも「珍車」として知られている。
えっ?全然解説が足りないって?では、こちらの「パトカーの装備品」についても、よろしければお読みくださいませ。