業務無線局の運用には、法律に基づいた国家資格である「無線従事者資格」が必要です。
なかでも、実務に従事するためのいわゆる“プロ資格”は、陸上特殊無線技士・陸上無線技術士・海上無線通信士・航空無線通信士など、全部で19種類が指定されています。

プロの無線従事者資格は、放送・航空・船舶・警察・消防などで用いられ、業務上の無線通信を行うために不可欠です。
警察実務の基礎である「無線の資格」について
このように、資格ごとに無線設備の操作や監督などの権限が定められており、用途や装置に応じて区分と級が必要です。
もちろん、パトカーや警察署間の通信、災害現場での指揮統制など、多岐にわたる警察職務の遂行に無線は欠かせず、警察官の実務の基礎資格とも言えるのが、やはり無線の国家資格です。

では、“警察官の無線の資格”として、どんな資格が活用され、その資格はどのように取得されるのか見ていきましょう。
警察官は警察学校入校中に「警察無線の資格」を取得する
警察官が普段の職務遂行に必要な資格は「第二級陸上特殊無線技士(通称:二陸特)」です。この二陸特が事実上、“警察無線の資格”です。
警察学校での一括取得が標準
47都道府県警察本部のうち、警視庁が定める『警視庁警察官採用時教養実施要綱』によれば、警察学校の初任科に入校した者は、二陸特の取得を目指すことが標準的な教養課程のカリキュラムとされています。
警視庁の公文書を見ていきましょう。
柔道、剣道又は合気道及び逮捕術の段位又は級位、けん銃操法初級、救急法初級、情報処理能力検定初級並びに第二級陸上特殊無線技士の資格の取得を目標とする。
出典 警視庁警察官採用時教養実施要綱の全部改正について 通達甲(警.教.教 1)第 6 号 平成 24 年3月30日
現場配属前の警察学校での教養を学ぶ過程で、効率よく二陸特を取得するる体制が整えられているのがわかります。
二陸特は、警察無線の基地局を操作する際などに必要とされるもので、実務上の必須資格と位置付けられています。
警察官はなぜ「二陸特」なのか?─実は交通取り締まりに関係
ではなぜ、より取得しやすい「第三級」ではなく、二陸特が求められるのでしょうか。
実は単に「警察無線の資格」という理由ではない実情が見えてきます。
以下は警察庁公式サイトから引用した訓令です。
第4節 通信従事者 (固定局等の通信事業者の要件)
第19条
都道府県警察等の運用する固定局及び基地局の通信従事者は、電波法 施行令(平成 13年政令第 245号)第2条第3項第2号に掲げる第2級陸上特殊無線技士の資格を有する者をもつて充てるものとする。
[改正・・・昭和 61年訓令3 平成5年訓令9、平成 16年訓令7] (通信従事者の任務)
引用元:警察庁公式サイトhttps://www.npa.go.jp/laws/notification/kunrei/1965kunrei3-jouki.pdf
まず明らかなのは、警察本部の通信指令センターや各警察署の無線室など、固定局や基地局の通信設備を扱う業務においては、法律上「第二級」以上の資格が必要とされている点です。
こうした場合、送信出力の大きい無線設備を操作する必要があるため、より高い知識が必要です。
では、パトカーや白バイなど移動局側の警察官には、必ずしも二陸特は必要ないのでは、と思われがちです。
ところが実際には、移動局の警察官にも二陸特の取得が求められています。
その理由が、交通取り締まりに用いられる「速度測定装置」=レーダー装置です。
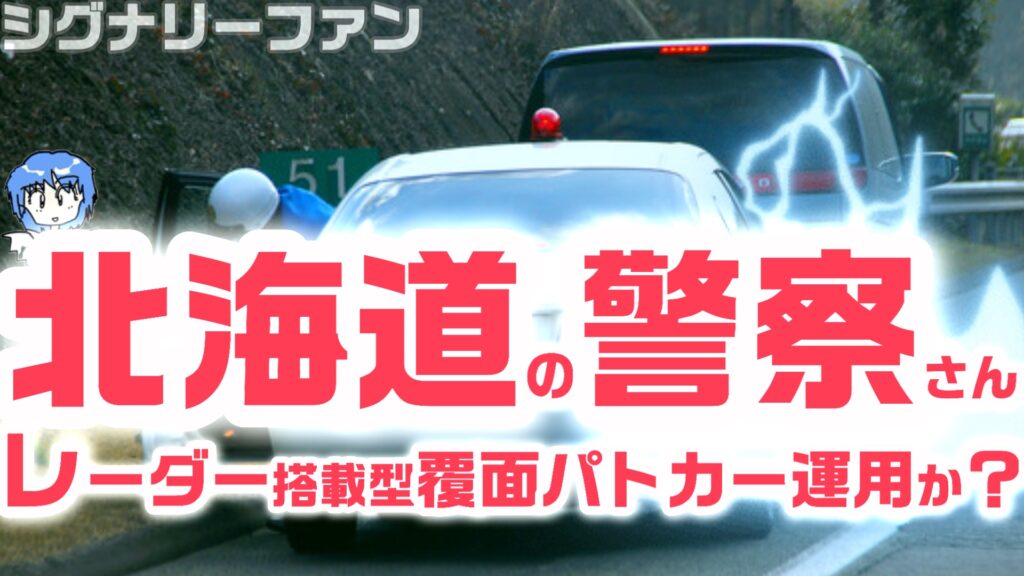
「マイクロ波レーダー」がカギ
速度違反の取り締まりに使われるレーダー装置は、マイクロ波という高周波電波を発信する無線機器に分類されます。
これらを取り扱うためには、法令により二陸特以上の資格が必要です。
つまり、交通取り締まりでレーダーを扱う警察官にとって、この資格は職務遂行上、必要不可欠なのです。
アナログ無線時代の「乙種」資格
警察無線がまだアナログだった時代、多くの警察官が取得していたのは「特殊無線技士(無線電話乙)」と呼ばれる旧区分資格でした。

特殊無線技士(無線電話乙)で、通常の警察無線は操作可能でしたが、ひとつ問題がありました。
それは、交通取り締まり用のレーダー機器を操作できなかったという点です。
当時、速度違反の取締りに使われていたマイクロ波を用いたレーダー式速度測定装置を操作するには、「特殊無線技士(レーダー)」という、さらに別の資格が必要でした。
しかし、この資格を有する警察官はごく少数にとどまり、全国でも10%未満という状況でした。
結果として、実際の取り締まり現場でレーダーを使える警察官は限られていたのです。
こうした状況を受けて、1989年(平成元年)に制度が見直され、「陸上特殊無線技士」という新区分の資格ができました。
これにより、第二級以上の陸上特殊無線技士であれば、レーダー取締り機器の操作が可能となり、運用体制が大きく変わることとなります。
したがって、警察官に求められる資格も次第に「二陸特」へと移行。
警視庁などは警察学校在校中に取得を目指していると説明している通りです。
資格取得後は警察学校で通信訓練も行われ、訓練と業務連絡を兼ねて通話コードを適切に使用し、警察本部とも定期的に交信しています。

現在の取り締まりでは「レーザー式」も登場。しかし、レーダー式も併用
なお、近年では従来のマイクロ波であるレーダーに代わって、光であるレーザー式速度測定器(レーザーパトカーなど)の導入が進んでいます。
レーザー式は対象を正確に捉えやすく、誤測定が起きにくいという利点があります。

しかし、2024年時点では旧式のレーダーと最新式のレーザーは並行配備されている状況です。
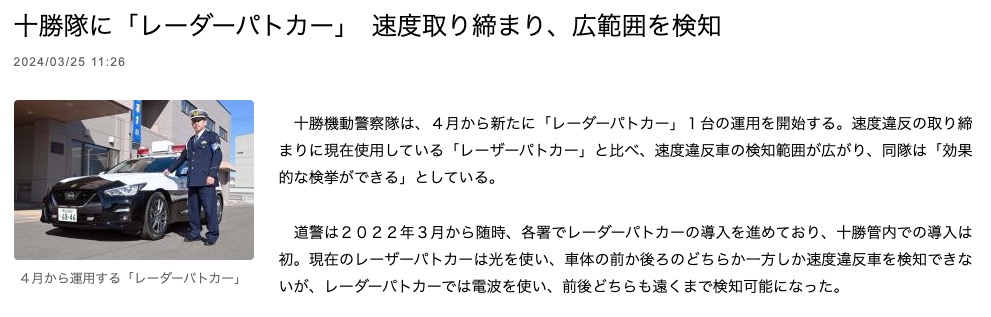
出典 十勝隊に「レーダーパトカー」 速度取り締まり、広範囲を検知 https://kachimai.jp/article/?no=605830
いずれの方式にも、一長一短があるようです。
高度資格「一陸技」を持つ技術者集団、警察庁情報通信局
一方で、二陸特よりもはるかに取得難易度が高いのが「第一級陸上無線技術士(通称:一陸技)」です。
この国家資格を保有するのが、警察庁の情報通信局に所属する技官です。
技官は、警察組織の基幹ネットワークの設計・構築・保守を担当するほか、無線や通信に関する専門知識を活かして、システムセキュリティや災害対策通信の支援にも従事しています。
技官の多くは、総合職(技術系)や一般職(技術系)情報通信職員として採用されており、物理・電子・情報分野における高い専門性を持つ人材として配置されています。
捜査にも関与──技術部門が担う“最前線”
情報通信局は内部ネットワークの運用だけでなく、犯罪捜査やサイバー攻撃への対応にも深く関わっています。
その中核をなすのが、技術対策課(現・情報技術解析課)に設置された「サイバーフォースセンター」です。
情報通信局は、サイバー攻撃に対して技術的な対応を行い、都道府県警察との連携や技術支援、さらにサイバー犯罪捜査におけるサポートも担います。
まさに日本版FBIのサイバーテロ対策センターとも言える存在です。
技官たちの極秘任務、「スパイ無線局ハンティング」
そして驚くべきことに、情報通信局の技官には、「スパイ無線局ハンティング」という極秘任務も存在します。
これは、不審な短波・超短波無線の発信源を特定し、北朝鮮による対日有害活動など、日本の国家安全保障に関わる不法な活動を摘発・監視する任務です。

機動警察通信隊──現場をつなぐ通信のプロフェッショナル
さらに、重大事件・災害時などにおいて、現場と警察本部を結ぶ通信機能を確保するのが、警察庁情報通信局の機動警察通信隊です。
彼らは、都道府県や管区警察局に編成され、臨時中継施設の設置や現場映像のリアルタイム伝送などを担っています。
配備されている衛星通信車やヘリテレシステムなどの特殊資機材を駆使した通信網の確保と指揮系統の維持が任務です。
重大事件では、警察官と共に技官も防弾チョッキとヘルメット姿で出動し、危険を伴う任務にあたることも少なくありません。
羽室英太郎氏のように技官出身から警察本部長にまで昇進した事例もあります。
毎日新聞の報道によれば、羽室氏は小学生の頃からアマチュア無線に親しみ、学生時代にはすでに警察無線を傍受するという“筋金入りの無線少年”であったそうです。
技官は本来、現場の指揮系統とはやや距離のある「裏方」の専門職とされがちですが、羽室氏のように通信・技術のプロフェッショナルとして警察行政の中枢に登りつめた事例は、異例であると同時に、警察庁がいかに情報通信の専門性を重視しているかを物語る証左ともいえるでしょう。
まとめ・警察官に必須の「二陸特」
このように、警察官の実務と二陸特は密接に関係しています。
出典一覧
-
無線従事者資格の種類一覧|日本無線協会
https://www.nichimu.or.jp/denpa/shikaku/ -
国家試験制度について|日本無線協会
https://www.nichimu.or.jp/kshiken/ -
無線従事者の資格とその種類について|総務省 電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/qualification/
他の関連記事もぜひご覧ください。



















































































































