事件が起きればパトカーが現れる──これはアニメでもドラマでも、もはやお決まりの展開ですよね。
でも今回は、いわゆる白黒ツートンの「ザ・パトカー」ではなく、ちょっと渋めな“覆面パトカー”が登場するアニメに注目してみたいと思います。
最近は「警察がテーマのアニメ」もすっかり珍しくなくなりましたし、正直、そういったジャンルにあまり食指が動かないという方も多いかもしれません。ぶっちゃけ筆者もそのひとりで、「もうそういうの観る年でもないしな……」なんて思ってたりもします。でも、いい歳こいてこんなテキスト書いちゃうのね。
ともかく、今回は銃ではなく、『覆面パトカーが登場するアニメ』が主旨です。でも、最近のアニメはご容赦ください。
覆面パトカーが登場するアニメ各種
名探偵コナン
◆ コナンくんと覆面パトカーの親和性について
「最近のアニメはご容赦ください」なんて言っておきながら、しれっとこれを持ち出すのかよ……と自分でもツッコミたくなるんですが、やっぱりこの作品は外せません。そう、1996年から放送され続けている由緒正しき警察プロパガンダアニメ──『名探偵コナン』です。
警察とアニメの関係を語る上で、覆面パトカーの登場頻度という点でも、この作品は頭ひとつ抜けています。
とはいえ、子どもが捜査現場に毎回しゃしゃり出てくるという時点で、もはやリアルな刑事ものではなくギャグアニメとして捉えるのが正解かもしれません。ただ、警察組織の描かれ方は意外にも真面目で、少年向けとは思えないほど掘り下げられていたりします。
公安警察まで普通に出てくるし……冷静に考えて、子ども向けアニメで公安が暗躍してるのって、プロパガンダも度がすぎるのでは?
ちなみに90年台初頭あたりのアニメでは、公安が未成年の子どもを逮捕していたり、自衛隊の戦車が強奪されたり、教育現場で日の丸・君が代をめぐる論争、89式の密輸、日本人として矜恃をモテない事を描いたりと、今だったら即炎上級のネタがさらっとフジテレビで放送されていたりもしました。もう二度とそんなアニメ描けないでしょうね(笑)
……話を戻しましょう。コナンにおける覆面パトカーの描写については、ファンでもない筆者が今さら語るのも野暮かなと思っていたんですが、2025年3月に放送された第1155話「追跡!探偵タクシー2」が、ちょっと無視できない内容だったのでご紹介します。
この回は原作にない『TVオリジナル』エピソードなのですが、なんと「毛利小五郎の熱狂的ファン」だというタクシー運転手・石川元気が、自分の車に赤色灯を搭載し、覆面パトカーに偽装するというトンデモ展開。
当然、作中のコナンくんも冷静にツッコミを入れます。「道路交通法違反」と。
この時点で充分ぶっ飛んでるんですが、さらに衝撃なのは──これが何かを仄かしているという事実。
実際にこのエピソードの放送の前年、2024年には福岡県で本物の“偽装覆面パトカー事件”が発生しているんです。ある男が自家用車に赤色灯を装着し、赤信号の交差点をサイレン鳴らして突破しようとした結果、タクシーと衝突するというもの。悪質きわまりない“警察マニア”による事件でした。

いやはや、現実がアニメに追いついたのか、それともアニメが現実を先取りしたのか……。どちらにしても、まさか『名探偵コナン』でこんな社会派ネタを突っ込んでくるとは。2020年代の空気感が反映されてるなあと、つくづく感じた一本でした。
いや、さすがにそれは深読みしすぎでしょう。いやいや、こっちが元ネタでしょう?NY市警のタクシー覆面。

筆者としては赤色灯で覆面パトカーに偽装するタクシーというプロットだけでもだいぶ怪しげで、「警察公認の警察プロパガンダアニメなのに、やってること大丈夫?」と思いもするのですが、ファンからはそれよりも、トリックが雑すぎる、セオリー無視といった批判も散見されるようです。
で、そんな“偽装覆面パトカー”の系譜、振り返ってみると、案外、アニメでは前例がありました。
逮捕しちゃうぞ
◆ 逮捕しちゃうぞと偽覆面の系譜
藤島康介原作の人気コミック『逮捕しちゃうぞ』。警視庁・墨東署を舞台に、交通課の女性警察官コンビが活躍するこの作品、アニメ化はもちろん、実写ドラマ化までされたほどのロングヒット作です。
……が、見ていると「いやいや、それ交通課の仕事じゃないよね?」とツッコミたくなる場面も多数。交通違反の取り締まりどころか、事件捜査、銃撃戦、果てはテロ対応まで、もはや何でもアリな勢い。実質、SATと白バイ隊のハイブリッド部隊です。
さてこの作品、アニメ版ではニューナンブM60(3インチモデル)の描写がしっかりしているだけでなく、覆面パトカーの内装や、助手席に装着されたカーメイト製の補助ミラーまで丁寧に描き込まれていて、マニア受けもかなり上々。細部まで愛を感じる作りになっているんですよね。
……で、ここでもやっぱり出てきます、「偽覆面」。すみませんね、さっきからモドキばかり扱ってて(笑)でもしょうがない、もうこれはブームなんですよ。乗るしかない、このカムリの覆面モドキに(笑)
特に印象に残っているのが、原作にあるエピソード「廻れ!炎の回転灯」。
パトカー整備士という裏方的な立場に甘んじていた男が、「現場で活躍する警察官たち」への嫉妬と、自分なりの正義感との間で暴走してしまい、自作の覆面パトカー──日産・Z32──に赤色灯を搭載して、勝手に交通違反の取り締まりを始めてしまうという、ちょっと切なくて狂気じみた回です。
(再)
特装車・消防車・部品の見本市行くとメーカーの技術者がブースで説明。コンパニオン雇うのは一部上場位。クルマの見本市は完成車メーカー主体だけど。こういう事態を予期し?『逮捕しちゃうぞ』「FILE.70 廻れ炎の回転灯」という整備士が警官に化け鬱屈を晴らす作品が35年前に上梓。偉大。 https://t.co/DaHL02fE3V pic.twitter.com/N2H0mV7mWi
— いわみこうぞう(💉P x7+MJ+他10種類) (@MasaruKoga1975) February 24, 2025
「自分が汗水流してパトカーを整備しても、それで違反者を捕まえて褒められるのは警察官だけ。こっちは誰にも評価されない。」
ところが、原作では私情まみれの“鬱屈と妄執の暴走”という小さな話だったものが、アニメ版になると様変わり。
第38話 廻れ! 炎の回転灯【後編】 あらすじ
墨東署全員の必死の調査と捜査で浮かび上がった実行者像。それは本庁内の一部エリートたちだった。警察のやり方に甘さを感じた彼らが独自に懲罰行動に走ったのだ。彼らのゆがんだ正義感に怒りをおぼえた夏実と美幸たち。墨東署員全開のパワーと知性で実行犯を追い詰めにかかる!
出典 https://www.videomarket.jp/title/174B84/A174B84038999H01
なんと、アニメ版では偽覆面を動かしていたのは、末端の「パトカーの整備担当職員」ではなく、本庁のエリート警察官たち──という大規模な陰謀に格上げされてしまいます。
しかもその動機がまたスゴい。「交通取締りの理想像を現実化したい」「暴力的な警察力による、抑止力としての交通管理を目指す」といった、妙に思想的で物騒な方向に……。
いえ、仮にもキャリア組がそんな理由で偽覆面(でもこの場合は本物かも?)やってる場合じゃないだろと。子どもか(笑)
たぶん彼らの中では「交通機動隊版ワイルド7」みたいな世界観を勝手に構築していて、それを現実にしようとしていたのかもしれません。あるいは、そういう部隊を本当に作るための“実績”が欲しかったのか……。
いずれにせよ、原作の“孤独なパトカー整備士さんの根暗な暴走”という人間ドラマから、アニメ版では“歪んだ正義を掲げる警視庁エリート官僚の陰謀”というスケールの大きな物語へと大バケしており、これはこれで見応えがあります。
でも、“孤独なパトカー整備士さん”ד歪んだ正義を掲げる警視庁エリート官僚さん”がコラボしたほうが面白いだろこれ(笑)
個人的には、原作のほうがしっくりくるというか、あのZ32が夜の闇の中を回転灯光らせてアスファルト切り付けて走ってるシーンは、今でも忘れられません。
機動警察パトレイバー(1989〜)
原案・ゆうきまさみ、原作・ヘッドギアの警察×ロボットアニメ。
1990年7月18日放送のTVアニメ第37話では、高速道路交通警察隊の覆面パトカーが登場。ようやく本物覆面出たわ。リアトレイの「パトサイン」までしっかり描写されており、さすがのこだわり。
一方で、主人公・後藤喜一警部補が乗るゲタ車は、軽自動車のミニパトという潔さ。それがまた、「ひねくれてて逆にかっこいい」と好評で、アニメにして唯一、黄色ナンバーがかっこいいと賞賛された伝説の1台となっております。
本作は、警察組織の内部事情や現場捜査のリアリズムを意識した設定で、当時としては非常に斬新で、コアなマニア層からはカルト的人気を誇っているのは説明不要です。
レイバー操縦士であり警察官である主人公の泉野明、篠原遊馬らが所属する「特車二課」は実際の警視庁警備部機動隊の中の特科車両隊の中の架空の大隊という設定がアツイ。
ちなみに、『踊る大捜査線』の本広克行監督も同作のファンであり、「踊る」は本作から多大な影響を受けたと公言しています。
……なるほど、どうりで体育会系特有の内輪ノリのような寒~い会話が延々と続くわけです。ちょっとついていけません(笑)熱かったり寒かったり、どっちなんだお前(笑)
未来警察ウラシマン(1983)
ロボットアニメにおける「変形」を「普通の車から覆面パトカーへの“変身”」に託した昭和の近未来警察アニメ!?
タイムスリップと近未来SFを合体させた、タツノコプロによる異色ポリスアクション。1983年を生きる少年「ウラシマリュウ」が、2050年の「ネオトキオ」にウラシマ効果で迷い込み、未来の警察官にスカウトされるという、「浦島太郎×警察×バディもの」です。
この作品においても、覆面パトカーがちゃんと登場。とはいえ、そこは未来世界の設定なので、乗り物デザインもひと味違うスタイルでした。
細部の演出に、当時のクリエイターたちの本気が垣間見えます。確か「アンモナイト」ってタツノコのデザイン班がやってたんだったかな。
そんで「よろしくメカドック」とか「光の伝説」とか「こち亀(1985年板)」も、どことなく「ウラシマン」風味なんだよな(笑)
――降りしきる雨がフロントガラスを叩く中、リュウは愛猫ミャアを助手席に乗せ、ひたすら逃げていた。
彼の背後には、赤色灯を回転させながら迫る無数のパトカー。
「俺はあんな大それたこと、やっちゃいねぇ!」
震える声を張り上げながら、ハンドルを握るリュウ。しかしカーラジオからは、あろうことか自分の指名手配情報が流れる。
「俺のほうが訴えてやる!」
根拠なき怒りをぶつけながらも、無免の彼に逃げ道はなかった(なお年齢設定は16歳)。
そして運命の分かれ道――リュウの愛車、1960年代式のフォルクスワーゲン・ビートルは工事中のバリケードを突破し、そのまま崖下へと転落。
瞬間、車体は謎の光の空間に飲み込まれ、時空を超える。
――たどり着いたのは、67年後の未来都市「ネオトキオ」。
時空のトンネルを抜けたビートルは、見知らぬ高速道路上に出現し、直後にエアカー型覆面パトカー「スポイラー」に追突。その相手こそ、後に相棒となる交通管制隊員・クロードだった。
そのままリュウは逮捕され、取り調べを受けるが、そこへ突然、謎の犯罪組織ネクライムの襲撃が起こる。
混乱の中、リュウは見事な身体能力と反射神経を発揮し、初対面の警官たちの目を見張らせる。
その能力を見込まれたリュウは、機動メカ分署『マグナポリス38』に預けられる。分署長は渋みあふれる叩き上げ、権藤警部。
配属されたチームは、元修道女のソフィア、そして例のクロードといった、クセの強い布陣。
こうして、リュウは未来世界の機動刑事として再出発を果たす。まぁ、やたら人員の少ない機動捜査隊ですなぁ。
そして忘れてはならないのが、リュウと共に時空を超えた彼の愛車――1960年代式ビートルの存在。
このクラシックカーはリュウの手により、未来技術と1980年代流のセンスが融合された「マグナビートル」へと超進化。
その仕様は以下の通り:
-
ルーフから自動展開する赤x青の警光灯
→ 現実の交通取締用覆面パトカー同様、ボタン操作で露出。 -
サイドドアに浮かび上がる“POLICE”マーキング
→ 通常走行時はマーキングが消えており、警光灯とともに表示。 -
通信装置、その他の装備など
→ 車載AIとのリンクポイント、他車両とのテレビ電話、偵察ドローン「アイポッド」とのリンク
この“旧車+未来技術”というギャップこそが、マグナビートル最大の魅力。
なお、リュウのやってきた2050年の未来社会では、もはやハイブリッドカーや電気自動車どころの話ではありません。
すべての車がタイヤのない「エアカー」となり、地上から数十センチ浮かんで走るうえ、自動運転が当たり前の、究極のハイテク・エコカー交通安全社会が実現していたのです。
もちろん、パトカーもタイヤがありません。しかし、リュウは「タイヤがついてない車は嫌だ」という個人的な理由から、エコ社会に逆行してタイヤのついたビートルに乗り続けています。
銃も、わざわざ骨董品博物館から偶然見つけたM36チーフスペシャルをカスタムし、自作の「マグナブラスター」として使用する超アナログなリュウ。
そんな時代でも、交通取り締まりは健在です。なにせ、未来社会でも覆面パトカーという概念がまだ存在するのです。
ただ、アメリカの一部警察のように、交通取り締まりに関しては覆面での活動が禁止されている地域もあるのかも。
さて、物語が始まって当初こそ、リュウの「マグナビートル」がパトライトを屋根に出すシーンが登場しますが、中盤以降になるとパトライトは常時設置状態に。
そのため、捜査上の秘匿を目的とした私用車を装った覆面パトカーとしての意味は失われ、単なるパトカーとして運用されていくようになってしまいます。
それでも第30話の「荒野の悪徳保安官」では私用車形態で潜入捜査も描かれたりもします。
とはいえ、リュウたちがほぼ毎回対峙する相手は、ネオトキオを支配しようと企む「ネクライム」という組織。そして、その精鋭集団であるスティンガーウルフ。
すでに彼らメカ分署の存在も顔も知られています。したがって、一般的な街頭犯罪にほぼ対応しない彼らは覆面パトカーに乗る必要が薄れていったのかもしれません。
ヒーロー作品における「変身」シーンが重要な見せ場であるように、車の「変形」もまた、作品の大きな魅力のひとつ。
『未来警察ウラシマン』は、当時の子どもたちをワクワクさせる、メカやギミック満載の近未来感覚アクションアニメだったものの、覆面パトカーならではの演出や活用を、もう少しだけ描いてほしかったという惜しさも残ります。
ところで、クロードのスポイラー、見た目はカウンタックっぽいシャープなデザインですが、浮いてる姿を見ると、ちょっと「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアンっぽい香りも。
それにしても、1980年代に制作された未来を舞台としたアニメ作品は数多くありますが、「ドローン(アイポッド)」のようなガジェットを先取りしていたのは、この『ウラシマン』だけかもしれません。
ちなみに、「(見ないと)逮捕しちゃうぞ!」という次回予告時のフレーズも、本作の次回予告が元祖なのです。たまげたなあ。
『ゴルゴ13 劇場版』(1983年)
劇場版では、アメリカの警察が使う覆面パトカーが登場しますが、日本式の反転式警光灯が取り付けられており、少し違和感があります。
当時のアメリカでは、着脱式の「コジャック灯」が主流で、その後、車内設置が主流になっており、米国警察において「反転式」は当時も現代も配備された実績はないと思われます。
『ルパン三世』シリーズ
80年代のテレビシリーズでは、銭形警部がアメリカ式の覆面パトカーで登場します。青い警光灯を自分の手で屋根に載せるという、お決まりの演出が。
『ライディング・ビーン』(1989年)
園田健一氏原作のOVA『ライディング・ビーン』でもアメリカの警察が描かれており、主人公を追う刑事たちの覆面パトカーには、ダッシュボードの上に警光灯があらかじめ設置されています。
『トランスフォーマー アニメイテッド』
アメリカ版『トランスフォーマー』シリーズに登場するオートボット「バンブルビー」は、覆面パトカーの形態を持つという設定です。
子ども向けおもちゃとしての見映えを意識してか、屋根にパトライトが載っており、アメリカの覆面パトカーとしては珍しく、日本の覆面に近い見た目になっています。
『ガジェット警部』(1983年)
最後にご紹介するのは、1983年に制作されたアニメ『ガジェット警部(INSPECTOR GADGET)』です。
ドタバタとハイテクが融合した世界観の中で、覆面パトカーの描写も独特でした。
『ガジェット警部(Inspector Gadget)』は、1983年にフランスと日本の共同制作で誕生したアニメ作品です。
まずはフランスなど海外で放送され、日本での放映はそれから3年後の1986年、NHK衛星第2テレビジョンの「衛星アニメ劇場」枠で行われました。
こうした放映経緯のため、日本国内での知名度はそれほど高くはありませんが、海外では根強い人気を誇る作品です。
実際に、1999年には実写映画化、2015年にはNetflixで新作CGアニメシリーズの『ガジェット警部の事件簿』が配信され、その国際的な支持の高さがうかがえます。
本作の主人公である「ガジェット警部」は、かつて一度命を落としたものの、サイボーグとして復活したロボット刑事です。
ただし、その事故の原因はといえば、映画『ロボコップ』の主人公・マーフィー巡査のような殉職ではなく、「バナナの皮で滑って頭を打つ」という非常にコミカルなもの。
こうした設定からも、本作のユーモアと脱力感のある世界観が伝わってきます。
ガジェット警部が乗車する車両「ガジェット・モービル」は、普段は私用車風のバン型車両として使用されていますが、事件発生時には車体が変形し、スポーツカータイプのパトカーへと変形。
変形後の車体デザインには諸説ありますが、Toyota Celica Supra P-Typeがモデルという説が有力で、1981年製のデロリアンをモチーフにしているという意見も存在します。
そういえば、先述の「ウラシマン」に登場するスポイラーにも似ていなくもありません。
変形後のガジェット・モービルは、車体サイドに「POLICE」の文字が現れるなど、まさに「隠れていたパトカー」が顕在化するギミック満載の仕様です。
こうした変形ギミックは、子ども向け作品としての演出だけでなく、覆面パトカーという存在の意外性やサプライズ感を視覚的に強調するための工夫と言えます。
なお、以下のリンク先には、この「ガジェット・モービル」についての詳細な解説が掲載されています。
https://thenewswheel.com/cartoon-car-spotlight-details-on-inspector-gadgets-gadgetmobile/
筆者自身、このアニメ作品の存在を長らく知らなかったのですが、ある外国人が日本の交通覆面パトカーを見て「まるでガジェット警部みたいだ」とコメントしたのをきっかけに、本作を知ることとなりました。
ちなみに、YouTubeで「SNEAKY UNDERCOVER JAPANESE COP CAR!!」という動画に登場する、反転式のパトライト付き覆面パトカーに対する外国人の反応は非常に興味深いものでした。

まとめ
いやぁー、ほんとにこのおじさん、萌えアニメ知らないんだねーってのがよくわかる記事ですね。
ほかにもアニメに関する記事を書いています。
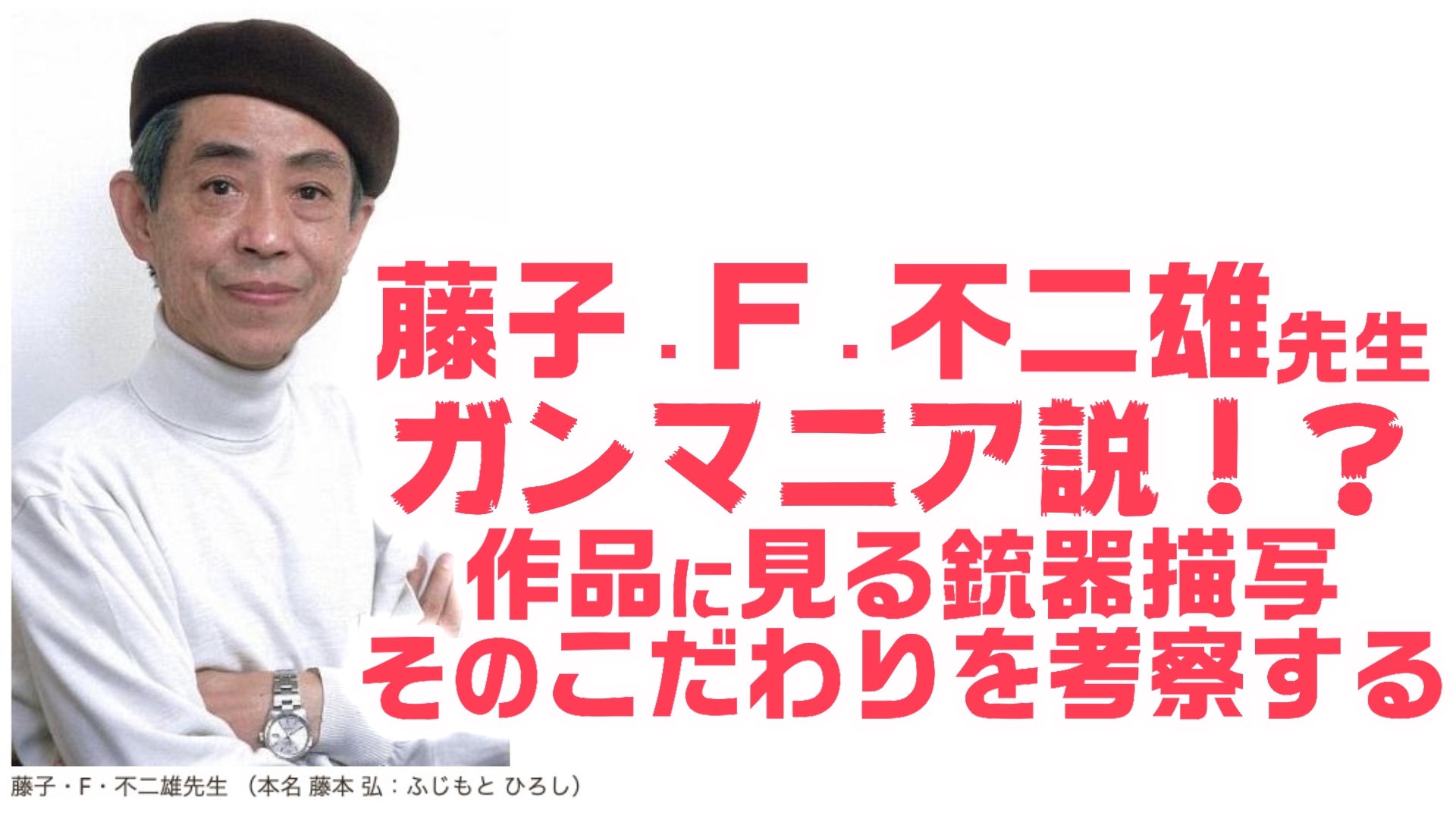



















































































































![RIDING BEAN [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CQJHEAY3L._SL500_.jpg)

