各都道府県警察本部の刑事部捜査一課には、身代金目的の誘拐事件や立てこもり事件など、重大かつ凶悪な事件に迅速かつ的確に対応するため、少数精鋭で構成された捜査班が設置されています。これが、いわゆる「SIT(エスアイティー)」、すなわち特殊事件捜査係です。
SITは、銃器使用による特殊犯事案や人質事件など、危険性の高い現場において、犯人の説得・確保などを刑事警察として担う役割を果たしています。
警察庁は以下のように特殊事件捜査係について公式に定義しています。
特殊事件捜査係とは、大規模な業務上過失事件、航空機・船舶等の不法奪取事件、爆破事件等、高度の捜査技術および科学的知識を必要とする事件捜査に即時の応援を行うための部署であり、警視庁およびすべての道府県警察本部に昭和56年3月までに設置された。
※出典:警察庁ウェブサイト : https://www.npa.go.jp/hakusyo/h20/honbun/html/kd100000.html
いわゆる「警察の最後のカード」とされる警備部の特殊部隊SATでは、報道公開された訓練映像や書籍(例:伊藤鋼一『警視庁・特殊部隊の真実』など)にも見られるように、警備警察として必要に応じて犯人のドタマを狙う即時無力化前提の射撃訓練が行われています。

対照的に、刑事部所属のSIT(特殊事件捜査係)は、交渉や説得による被疑者の確保を主な任務としています。警察庁の公式資料でも、SITは人命の保護を最優先とし、状況の安定化と早期解決を図るための部隊とされています。
SITは全国の警察に配備されており、法執行機関としての警察活動の中でも、特に緊迫した局面を担う部署となっています。

広島県警察特殊班HRTおよび大阪府警特殊班MAATの捜査員ら (出典:USAミリタリーチャンネル)
広島県警察の特殊班「HRT」や大阪府警の「MAAT」といったように、都道府県警察の中には、特殊事案に対応する専門班を独自に編成している例が見られます。
こうした部隊のうち、刑事部に所属する「特殊事件捜査係(SIT)」については、テレビドラマや報道映像で紹介される際に、濃紺やグレーの難燃性スーツを着用し、ベレッタ製自動式けん銃や防弾盾を携行、あるいはロープを使って垂直降下しながら建物に突入する、といった“特殊部隊”のような印象が強調されることがあります。

しかし実際には、このような重装備による突入任務は、警備部が所管する部隊――たとえば銃器対策部隊や、特殊急襲部隊(SAT)などが本来の担当として想定されており、SITの主な任務とは異なります。

SITは、刑事部門に属する少数精鋭の捜査班として、誘拐や立てこもり、人質事件などの重大事件に対処するため、交渉や情報収集、現場の安定化などを中心に活動しています。
近年では、テレビドラマや映像作品などの影響により、特殊事件捜査係(SIT)の名称は一般にも広く知られるようになっており、場合によっては警備部のSATよりも存在感が強く印象づけられている側面もあります。
ただし、これらの映像作品においては、演出上、実際の装備体系や部隊の役割分担とは異なる描写が見られることもあります。
たとえば、SATが実戦配備している連射仕様の短機関銃「MP5」を、SITの捜査員も使用する場面が登場することがありますが、実際のSITにおいては、単発射撃専用に仕様変更されたMP5であり、誤解を生む可能性があります。

今回は特殊事件捜査係(SIT)を構成する人員や配備される装備品の検証をしていきましょう。
SIT要員は兼務または専従
全国の警察本部に設置されている特殊事件捜査係(SIT)の要員には、捜査一課に所属する刑事が兼務または専従で配置されている場合が一般的です。なかには、過去に警備部の特殊部隊SATに所属していた隊員が転属して活動している例もあり、男性に限らず女性捜査員が任に就くこともあります。
SITは、立てこもり事件や誘拐事件などの凶悪事件への対応に加えて、業務上過失致死傷事件など、より広範な刑事事案にも柔軟に対応できる体制を特徴としています。
しかし、地方の小規模な警察本部では、人的資源の制約からSIT専任の部隊を編成することは困難な場合が多く、実際には機動捜査隊や他部門の職員が兼務する形で運用されている例が全国的に多く見られます。
一方で、警視庁においては、SITは完全な専従体制が敷かれており、人的・物的資源ともに比較的潤沢な予算に支えられた運用がなされているのが実情です。

特殊事件捜査係の名称は全国の警察で異なる
「特殊事件捜査係」という名称は必ずしも全国で統一されているわけではありません。
最も知られているのは、警視庁捜査一課に属する「SIT(エスアイティー)」です。この略称には複数の由来があるとされており、隊員の肩章には「Special Investigation Team」と英語で表記されていますが、実際には「Sousa Ikka Tokusyuhan(捜査一課特殊班)」の略であるという説が有力です。
「Special Investigation Team」は、あくまで後づけの解釈とされているのです。
東京MX公式チャンネルによるニュース配信
こうした命名慣行は他の都道府県警察でも見られ、白石光氏による『決定版 世界の特殊部隊100』などによれば、各都道府県警察で名称はさまざまで、大阪府警では「MAAT(Martial Arts Attack Team)」、埼玉県警では「STS」、青森県警は「TST」、千葉県警は「ART」、神奈川県警では「SIS」、広島県警では「HRT」といったように、多くが3文字の略称を使用しています。
なお、「SIT」という略称については、発音上の問題も指摘されています。英語圏では「シット(Shit)」と聞き間違えられるおそれがあり、これは英語では不適切な表現とされるため、国際的な場面での使用には配慮が求められます。このため、大阪府警が独自に「MAAT」という名称を採用した背景には、そうした国際的な事情があったとも考えられます。
このように、捜査一課の特殊事件捜査係は、任務や役割に共通点があるものの、名称や運用の一部には地域性が見られることが特徴となっています。
タスクフォース制度と特殊班派遣部隊
SITには、都道府県を超えて出動するケースもあります。一例として、2016年8月に和歌山市で発生した建設会社従業員銃撃事件では、和歌山県警のSITに加え、大阪府警のMAATも派遣されています。
また、2023年の長野県中野市で発生した銃撃事件では、犯人が猟銃で警察官と市民ら4名を殺害するという深刻な状況の中、警視庁や神奈川県警のSIT要員が深夜のうちに航空隊のヘリコで現地に急行しています。

このように、ある本部のSITが他の地域の事件に出動するケースが多いのは、警察庁が重大事件発生時に全国から即応できる体制として定めている「タスクフォース制度」によるものです。

栃木県内でM3913を被疑者の立てこもる家屋に向ける警視庁SITの捜査員。警視庁や大阪府警などの特殊捜査班は警察庁特殊班派遣部隊に指定されており、必要とあらば全国で法執行が可能な”FBI”的な部隊。 写真の典拠元「決定版 世界の特殊部隊100」著者: 白石光
現在、警察庁がタスクフォースとして特殊班派遣部隊に指定しているのは、北海道、警視庁、愛知、大阪、福岡の5警察本部の各特殊事件捜査係。
これらは、各警察本部からの要請や警察庁の指示により、事態解決のため速やかに全国へ展開する手筈となっています。
特殊捜査班の主な出動実績

全国の警察本部に編成されている「特殊事件捜査係」は、これまで地域の所轄警察官や武道枠で採用された屈強な刑事たちでも手に負えない、刃物や銃器を使用した立てこもりなどの凶悪事件に数多く対応してきました。
彼らは困難な現場で被疑者を確保し、実績を積み重ねることで名声と予算を獲得してきたのです。
たとえば、2015年2月に東京都内の高層マンションで発生した立てこもり事件では、警視庁捜査一課SITが未明に突入を敢行。エアガンを振り回して立てこもっていた男を公務執行妨害の現行犯で逮捕しました。
一方、立てこもり事件の多発地帯とされる愛知県では、より深刻な事案が相次いでいます。
- 2003年 愛知県名古屋市東区立てこもり放火自爆事件
- 2007年 愛知県刈谷市人質立てこもり事件
- 2007年 愛知県豊明市立てこもり事件
- 2007年 愛知県長久手町立てこもり発砲事件
- 2008年 愛知県岡崎市東名高速バスジャック事件(※犯人は山口県在住の少年)
- 2010年 愛知県一宮市立てこもり事件
- 2013年 愛知県稲沢市刃物立てこもり事件
- 2013年 愛知県豊川市豊川信金立てこもり事件
- 2015年 愛知県岡崎市コンビニ店立てこもり事件
- 2017年 愛知県名古屋市中村区立てこもり事件(※犯人はイタリア国籍)
2003年には名古屋市東区で被疑者が建物に放火し自爆。支店長らが命を落としたほか、出動した機動捜査隊員も殉職しました。
さらに、2007年の長久手町における立てこもり発砲事件では、出動した愛知県警のSAT隊員が銃撃され命を落とすという痛ましい結果となりました。
過去には被疑者検挙の際に撃たれ、意識不明の重体になったSIT隊員も……
立てこもり事件など危険性の高い現場で、説得と強制執行の両面から対処を行う刑事警察の特殊事件捜査係(SIT)。過去には隊員が被疑者の銃撃を受けて重傷を負った事例も報告されています。
代表的な事件として、2003年に東京都板橋区の都営住宅で発生した立てこもり事案が挙げられます。この事件では、散弾銃の所持が合法であった男性が、家族とのテレビのチャンネルをめぐる口論から激昂し、自宅に立てこもったものです。
警視庁はまず説得による解決を試みましたが、被疑者はこれに応じませんでした。最終的に、警視庁捜査一課のSIT突入班に強行突入の指示が出されました。隊員たちは出動服を着用し、M3913拳銃を携行して建物内に進入。しかし、被疑者はすでに銃を構えて待ち構えており、突入直後に発砲。警部補および巡査部長の2名が被弾し、そのうち1名は大量出血により意識不明の重体となりました。
被疑者の発砲に対し、隊員らは冷静に応射し、5発中3発が被疑者に命中。結果として、被疑者は殺人未遂容疑で現行犯逮捕されました。
この事件は、SITにとって過去に例を見ないほど深刻な被害が出た事例のひとつです。
特殊事件捜査係に配置される任務別の要員
立てこもり事案などにおいて、特殊事件捜査係の本来の任務とは、あくまで交渉を通じて速やかに事態を平和裏に解決することにあります。
「突入係」が濃紺の耐熱アサルトスーツに防弾ヘルメット、バラクラバを着用し、レーザー付きの“ベレッタ92 Vertec”を構えて冷たい目で突入——
そうした光景は確かに警察事象として象徴的で、映像的にも映える場面です。しかし、それがすべてではありません。
むしろ、花形の突入係を支える裏方こそ、現場の成否を左右する鍵となります。各任務に専従するプロフェッショナルたち──それが、いわば「裏方役者」と呼ばれる存在です。
張り込みや追尾チームの“トカゲ”

たとえば、身代金目的の誘拐や企業恐喝事件で、被疑者が金の受け渡し場所を指定した場合、まず現場に現れるのが「トカゲ」と呼ばれる斥候要員たちです。彼らは周辺の張り込みや追尾、偽装した監視活動を担当します。
“ネゴシエーター”:人質解放に賭ける交渉人
そして、事件の成否を最も左右すると言っても過言ではないのが、粘り強く説得を続ける交渉担当者──いわゆる“ネゴシエーター”たちです。
人質を取って立てこもる被疑者に対し、食料や水の差し入れと引き換えに人質の段階的解放を促す。
あるいは、親族を現場に呼び寄せ、被疑者のわずかな良心に訴えかける。
こうした「人質立てこもり事件説得交渉専科」としての専門教育が警察大学校で本格的に始まったのは2005年。
以来、ネゴシエーターは立てこもり事案の現場で不可欠な役割を担い続けています。
● だが、最終的には──
しかし、いかに交渉を尽くしても、被疑者が応じないケースも存在します。
そのときは、最終手段としての「突入」――
たとえば、近所のラーメン屋の出前持ちに化けた隊員が、岡持ちにラーメンとチャーハン、そしてけん銃を忍ばせて被疑者の元へ向かう(※そんな岡持ちは実在しません)。
あるいは、テレビでもおなじみの高校野球出身で体力とコミュニケーション能力を鍛え抜かれた突入係が、耐熱スーツで身を固め、ラッペリングで窓ガラスを蹴破って突入する。
そして、音響閃光弾がドンパン炸裂する中、現場は一気に終局へ──

特殊事件捜査係の装備品各種
ここで特筆すべきは、彼らにとっての“けん銃”の意味です。
特殊部隊にとってけん銃は通常「セカンダリ・ウェポン」、つまり主兵装が使えなくなったときの補助火器にすぎません。
しかし、警視庁SITをはじめとする特殊事件捜査係にとっては、むしろ“けん銃こそがプライマリ”。
その理由は、立てこもり現場など市街地・住宅街での戦術を前提にしているため、携帯性と制圧力のバランスを重視した装備体系が採られているためです。
特殊事件捜査係と“けん銃”の関係
かつて、1998年の東京証券取引所立てこもり事件の報道映像では、警視庁SITが使用していたのはP230でした。
その後も、各時代・社会情勢に応じてけん銃の機種は更新され続けているようです。
https://amateurmusenshikaku.com/security/kenjyuu/
P230の威力の低さはよく知られた話です。
https://amateurmusenshikaku.com/security/p230/
しかし現在、凶悪な武装犯と最前線で対峙するSITでは、より高い火力が求められるようになっています。
まず初期には、9mm口径のS&W M3913が選ばれ、その後、2006年頃からニュース映像などで登場し始めたのが、同じく9mmのベレッタ92 Vertecです。
このベレッタ92 Vertecは、イタリアの老舗銃器メーカー「ベレッタ社」が開発したダブルアクションの高性能拳銃で、世界各国の警察特殊部隊で採用実績があります。

日本でも警視庁、大阪府警、埼玉県警などがこれを実戦運用しており、レーザーサイト、ダットサイト、フラッシュライトを装着して活動していることが確認されています。
特に特徴的なのは、グリップと一体化したレーザーサイト。外見からはそれと分からないように巧妙に隠されており、まさに実戦仕様です。
さらに同時期、SITの装備として加わったのが、H&K社のサブマシンガンMP5(9mm)です。このモデルは、特殊急襲部隊(SAT)の主要装備として知られています。

「ついにSITにもサブマシンガンが…!」と思いきや、SITで配備されているのは連射機能を省いた単発(シングルファイア)仕様。
これは、米国の一部法執行機関でも同様に連射機能のないライフルを一般警察官(PRO /パトロール・ライフル・オフィサー)や特殊部隊などに配備する例があるため、日本だけの特例ではないと言えます。

非致死性の法執行装備も充実
SITの新装備「閃光弾発射機PGL-65&B&T GL-06」
SITの任務が「生きたまま被疑者を確保すること」である以上、非致死性装備(ノンリーサル・ウェポン)の存在が大きな意味を持ちます。
中でも注目されているのが、多用途ランチャーPGL-65およびB&T GL-06です。これらは通常の榴弾だけでなく、ゴム弾、催涙ガス弾、閃光弾などの発射が可能で、犯人の無力化に用いられます。
-
PGL-65:回転式拳銃と同じような構造を持つ多弾装填式
-
B&T GL-06:中折れ式の単発ランチャーで、ストック付き。レールシステム対応でカスタム性も高い
さらに、圧縮空気で作動する非致死性ランチャーFN 303も配備されています。
これらの装備は、警察庁が一括購入し、全国の警察本部に配布。しかし、県ごとの独自装備(いわゆる「ご当地SIT装備」)が存在する可能性もあります。
2020年7月に札幌で発生した立てこもり事件では、北海道警察のSITがアメリカ製のエアガンを携行していたことが報道されました。

防弾装備については、防弾チョッキ、バイザー付きヘルメット、盾など、SATに準じた高度なものが用意されています。
興味深いのは、警視庁が突入時に犯人を驚かせる目的で「かわいいクッション」を投げ入れるという工夫までしている点。
まさに「相手を傷つけずに制圧する」ための知恵が随所に見られます。
🛠 SITの装備品◎
| 装備品名 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| ベレッタ92Vertec | 制圧用 | 9mm、DA、レーザーサイト、ダットサイト、フラッシュライト搭載 |
| MP5(単発) | 制圧支援 | サブマシンガン型ながら単発運用 |
| PGL-65 | 同上 | 閃光弾・催涙弾発射、回転式、非致死性 |
| B&T GL-06 | 同上 | 単発中折れ式、ピカティニーレール搭載 |
| FN 303 | 同上 | ガス・ゴム弾発射、圧縮空気方式 |
| 防弾装備 | 個人防護装備 | バイザー付きヘルメット、防弾盾など |
移動手段や運用の違い
移動車両は、SATが警備部の所属であるため専用の車両を使う一方、SITは「SIT」と記されたマイクロバスを使用していることが報道で明らかになっています。
そして何より重要なのは、SITとSATの本質的な違いです。
特殊事件捜査係のまとめ
SITは、暴力的手段を最小限にとどめつつ、犯人を逮捕するための精鋭部隊です。火器から非致死性装備、ユニークな戦術グッズまで、あらゆる手段を駆使して、命を守る捜査活動にあたっています。
SITとSATの本質的な違いは端的に表すと以下の様になります。
SITとSATの違いとは?
-
SAT(特殊急襲部隊):任務は「排除・鎮圧・無力化」、必要であれば犯人の射殺も辞さない「最後の切り札」的存在
-
SIT(特殊事件捜査係):任務は「説得・投降促し・検挙」。交渉を重視し、自主的な降伏を狙う「検挙班」
つまり、SATの目的は警備警察として排除、鎮圧、その結果として犯人の射殺もやむを得ない任務の一方、SITの目的は刑事警察として犯人を生かして逮捕すること。事件の種類によっては、交渉係、突入班、追跡班などが適宜編成され、誘拐や立てこもりといった所轄では対応困難な案件に対処します。
良くも悪くも、SATが”最後の切り札”と呼ばれる非情な部隊の一方、あくまでSITは交渉からの投降呼びかけ、自主的な投降を促すのが前提の”検挙班”という運用です。
極端に言えばこうなります。
所轄では手に余る誘拐事件や武装立てこもりなどが発生した際に対応するのはもちろん、交渉係、突入班、追跡班など各種要員も配置され、対応できる事案の範囲は意外と豊富なのが特殊事件捜査係なのです。










































































































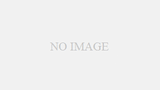
コメント
[…] 刑事部の『SIT』と警備部の『SAT』の違いはひとつだけ […]