アマチュア無線の免許を失効させたまま、無線機を車内に搭載し続けていたことで摘発され、処罰を受けた当事者自らの手記が注目を集めています。
出典は、月刊誌『ラジオライフ2020年2月号』に掲載された読者投稿「アマチュア無線緊急レポート」。
一般論として、アマチュア無線に関する法令違反があった場合、刑事処分の可否や量刑は検察と裁判所が判断し、行政処分については総務省が所管する形になります。そのため、総合通信局が発表する行政処分の情報だけでは、刑事処分の詳細までは把握できないのが実情です。
知らなかったでは済まされない“電波の責任”──。この事例は、無線運用のリスクと法の厳格さを改めて浮き彫りにしており、すべてのアマチュア無線愛好者にとって警鐘となることでしょう。
本件の詳細は、当該誌の投稿に基づくもので、当サイトでは個別の事案に対して法的判断を行う立場にありません。
「電波を発射していない」では済まされなかった法の壁
『アマチュア無線緊急レポート 』の投稿者(仮にAさんと呼びます)によれば、Aさんは1994年に従事者免許証を取得、正式に開局申請を行い、当時は交通事故の現場で無線を活用して救助要請を行うなど、積極的にアマチュア無線を活用していたとのことです。
しかし、年月の経過とともにアマチュア無線運用への関心が薄れ、5年後の1999年には再免許を申請せずに失効。ただ、その後も愛用していた日本マランツのハンディ機「C460」だけは車内にアクセサリー感覚で設置し続けていました。
Aさんによれば、「電波は一切発射していなかった」とのこと。しかし、これが捜査当局に受け入れられることはありませんでした。
その理由は、電波法の規定にあります。一般には見落とされがちですが、電波の実際の発射行為そのものよりも、「無線機が電波を発射可能な状態にあること」自体が問題視されるのです。電源が入っていなくとも、アンテナに接続され、容易に使用可能な状態であれば“運用”と見なされる余地があると、総合通信局では注意喚起をしています。
このケースでは、警察の職務質問から助手席に警察官を乗せたまま警察署へ出頭、書類送検後、検察官の取り調べを経て略式起訴。最終的には刑事罰としての罰金刑が科されました。
失効免許のまま無線機を車載──「元・モービル局」が摘発された一部始終
車載アンテナに警察官が注目、職務質問から摘発までの詳細な経緯
事件が発覚したのは2018年12月24日。クリスマスイブのこの日、Aさんは自宅付近の路上に駐車中の自家用車に戻ろうとしていたところ、自転車に乗った警察官から職務質問を受けました。
きっかけは、車両に取り付けられたアンテナでした。これを不審に感じた警察官が何度かその場を往復し、最終的に車内に設置された無線機を確認。声をかけてきたのです。
なお、モービル局は、警察官による職務質問と免許確認が避けられない存在であることを、改めて認識する必要があります。

警察官からの問いかけに対し、Aさんは「アマチュア無線機である」と説明。すると警察官は従事者免許証(従免)の提示を求めました。Aさんはかつて1994年に従免を取得していたものの、その携帯はしておらず、自宅を探しても見つけられず、すぐさま提示できる状態ではありませんでした。
おそらく本人には「運用していない=携帯不要」との認識があったと見られますが、実際には、無線機が設置されている状態である以上、警察官にとっては「運用の意思あり」と見なされる余地があります。
Aさんは過去に使用していたアマチュア局のコールサインを伝えましたが、警察官が本署経由で確認した結果、局免はすでに失効していることが判明。ほどなくしてパトカーが到着し、警察官3名が現場に加わりました。
「あなたの無線局免許状は失効していますよ」
その言葉に、Aさんは内心では「いや、それは知っています」と感じたかもしれません。しかし事態は深刻な状況です。
局免の失効状態で無線機を車両に備え付けていたことが警察官に現認されたことで、Aさんは警察官から詳細な事情聴取を受けます。最終的に総勢4名の警察官により任意同行を求められ、自らの車に警察官1名を同乗させたうえで、所轄警察署へ向かうこととなりました。
署に到着すると、さらに3名の捜査員が待機しており、無線機、アンテナ、ケーブルといった関連機材の撤去をその場で指示。これにより本件は、単なる確認で終わることなく、捜査対象として本格的な事件手続きへと進んだのです。
【続き】「運用していない」は通用せず──その決定的要因とは
2018年12月に摘発されたAさん(仮名)の事例について、Aさん自身は、「運用の意思はなかった」「電源は入れていなかった」と主張していましたが、その言い分は警察に通用しませんでした。警察が「無免許運用の疑いあり」と判断した根拠、それは何でしょうか。
その理由は、無線機が「いつでも電波を発射できる状態」で設置されていた状況です。
アマチュア無線機、電源接続とモービルアンテナ装着が決定的要因
Aさんの車は、外部電源とモービルアンテナに無線機が接続された状態で駐車されていました。これにより、たとえ運用の実態がなかったとしても、外形的には「常時運用可能な状態」と見なされ、警察官による現認の時点で「無免許での常習的な使用」の疑いを持たれる結果となりました。
この点について、通信行政を所管する総合通信局の見解は首尾一貫しています。
「電波がいつでも発射可能な状態で無線機を設置していれば、電波を実際に発射せずとも“運用”とみなされる」という判断基準です。
今回の摘発に至った直接的な現場状況については、『ラジオライフ2020年2月号』(184ページ)に写真付きで詳しく掲載されています。
記事によれば、警察官が確認したAさんの車の状態は以下のとおりです。
-
車両ルーフのドア付近に、ショートタイプのモービルアンテナを装着
-
車内の無線機は電源オフではあったものの、外部電源に接続済み
-
同無線機はモービルアンテナと接続されており、電波発射可能な構成
この状態が「運用していない」とするAさんの主張と矛盾していたため、Aさんは無免許状態での使用準備があったと判断されました。
アマチュア無線家にとって、運用の意図がなくとも、“いつでも電波を出せる”構成はリスク要因であることを、今回の事例は改めて浮き彫りにしています。
電波が発射できる状態の無線機に対して、総合通信局ではどのような見解を示しているのか、以下の記事で紹介しています。

「局免失効状態でアマチュア無線機を使用した」電波法違反容疑での取調べ
捜査員が従免・局免の区別も曖昧な中、被疑者は5か月間で3度の取調べに応じた
局免許を失効させた状態でアマチュア無線機を搭載していたAさん(仮名)は、その事実をもって電波法違反(無免許運用)容疑で警察の捜査対象となりました。
取調べは決して簡単なものではありませんでした。Aさんの証言によれば、5か月の間に3度呼び出され、仕事を休まざるを得ない状況に。しかも取調べを担当した捜査員の中には「従免(資格)」と「局免(開設許可)」の違いを理解していない者もいたといいます。
捜査の手法は通常の刑事事件と何ら変わりなく、誘導尋問に近い形での質問が繰り返されたとのこと。刑事が何をどのように問いただしたのか、詳しいやり取りも同レポートに記されています。
なお、Aさんが「逮捕された」との記述はなし。その理由としては捜査に協力的で、逃走や証拠隠滅の恐れがないと判断されたことが背景にあると考えられます。
しかし、事情聴取を経たAさんには、指紋採取、顔写真撮影といった通常の被疑者扱いがなされ、最終的に検察庁に送検されることとなります。
【検察編】「電源を入れたことは?」
女性検事の一言が流れを変えた可能性も
検察庁ではさらに厳しい取調べが行われました。対応したのは若手の男性検事とベテランの女性検事。人情派を装いながらも本質的には追い詰めていく「飴と鞭」の典型的な分担です。
中でも、女性検事は何度も「電波を発射したことがあるか」とAさんを問い詰めます。Aさんはこれを明確に否定。しかし、質問の角度が変わった瞬間、流れが変わりました。
「一度くらい電源を入れたことはあるでしょう?」
この問いに対して、Aさんは「あるかもしれない」と答えます。この一言が、起訴の決め手となった可能性も否めません。
さらに、押収された無線機器については「返還を希望しない」という文書への署名を求められ、Aさんはあたかも「応じれば不起訴の交換条件になるのではないか」と錯覚した可能性も。結果として、それが不起訴を意味するものではなく、略式起訴への流れを加速させただけでした。
【結末】罰金刑確定──略式命令書には「納付不能なら労役所収容」の文言も
こうして、Aさんは略式起訴により地裁から罰金刑を言い渡されます。略式命令書には、「○○円の罰金を科す。納付不能の場合は労役所に留置」とも明記されていたとのこと。
罰金の具体的な金額、さらに刑事記録に残る扱いとなった一連の流れについても、詳細は『ラジオライフ2020年2月号』にて紹介されています。
総合通信局による解説
東海総合通信局公式サイトでは取り締まりを受けた際の流れを以下のポイントごとに解説しており、刑事処分についても言及しています。
Q2-2 路上取締りで警察に捕まったらどうなるの?
警察官による取り調べが行われます。その間、身柄・車両とも拘束され、一定時間運行できなくなります。その後は検察庁に送致されて起訴され、裁判によって刑罰が決定されます。無線設備については、証拠品として司法警察員に押収されます。
Q2-3 電波法での罰則はどうなるの?
電波法の規定に基づき、“1年以下の懲役又は100万円以下の罰金”の罪に問われます。更に、重要な無線局に妨害を与えると、“5年以下の懲役又は250万円以下の罰金”に処せられることになります。軽い気持ちで始めると、大変なことになります。
引用元 東海総合通信局公式サイト https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/denpa/kansiqa/index.html
警察官による摘発から検察への送検、起訴と裁判、有罪判決により罰金刑と、上述の読者投稿の体験談と同じ流れになっています。
『自分の二の舞にならないように各自免許の期限を確認してほしい』と投稿者
いかがだったでしょうか。
発端は、ある日突然の職務質問。そのまま警察署へ任意同行──。女性検察官による執拗な追及の末に略式起訴。最終的には罰金刑が確定し、具体的な金額までもが詳細に綴られています。
このように、無免許(免許切れ)で電波が発射可能な状態の無線機を設置していた場合、「電波を出していない」「使っていない」「受信のみ」では済まされないのが、電波法違反の現実です。
免許の有効性、装備の状態、さらには“言質”としての一言が、法的な処分を決定づける材料となり得ることを、今回の事例は如実に物語っています。
知らぬ間に「無免許運用」という重大な違反に該当してしまうケースは、決して他人事ではありません。今回、ラジオライフ2020年2月号に掲載された読者投稿は、その“現実”を赤裸々に描いた貴重なレポートです。
総務省総合通信局が公表しているのは、あくまで行政処分に関する情報のみです。同局公式サイトや、そこから毎回転載しているウェブサイトを見れば、免許の取り消しや運用停止といった行政処分の内容は確認できますが、検察庁が科した刑事処分――つまり罰金や懲役といった刑罰の有無については、一切知ることができません。
刑事処分が明らかになるのは、報道機関による報道か、実際に裁判を傍聴する場合、または当事者による手記など、ごく限られたケースのみです。さらに、今回のように略式裁判で処理されたケースでは、裁判所での傍聴も事実上できないため、その全貌が公になることは極めて稀といえます。
過去には、アマチュア無線機を客引き行為に利用した大規模な事件が通常裁判となり報道された例もありますが、そうした事案は悪質で例外であり、多くのケースは報道する公益性が低いと判断されるのか、報道されることはありません。
そんな中、今回当事者による手記が公開され、大きな注目を集めました。Aさんは、自身にアマチュア無線を運用している認識がなかったとし、問題の無線機についても「アンテナにつないで車内にアクセサリー感覚で設置していた」と説明。電波を発射した記憶も明確ではなく、「一度電源を入れたかもしれない」という曖昧な状況でした。
結果的に、Aさんは電波法違反で起訴され、罰金刑の有罪判決が言い渡されました。
この事例から浮かび上がるのは、「実際に電波を発射したかどうか」よりも、「無線機が電波を発射可能な状態にあったかどうか」が判断のポイントになっているという事実です。これは見落とされがちな、重要な視点といえるでしょう。
今回のAさんの例とは少し異なりますが、無免許無資格の方が受信目的で、電波発射が可能な状態にあるアマチュア無線機を車に積むというケースがとくに初心者の方が陥りやすいと言えそうです。
なお、総合通信局では、摘発の際によく用いられる「言い逃れ」事例を公式に公表しており、これに関しては当サイト内の別記事で詳しくご紹介しています。
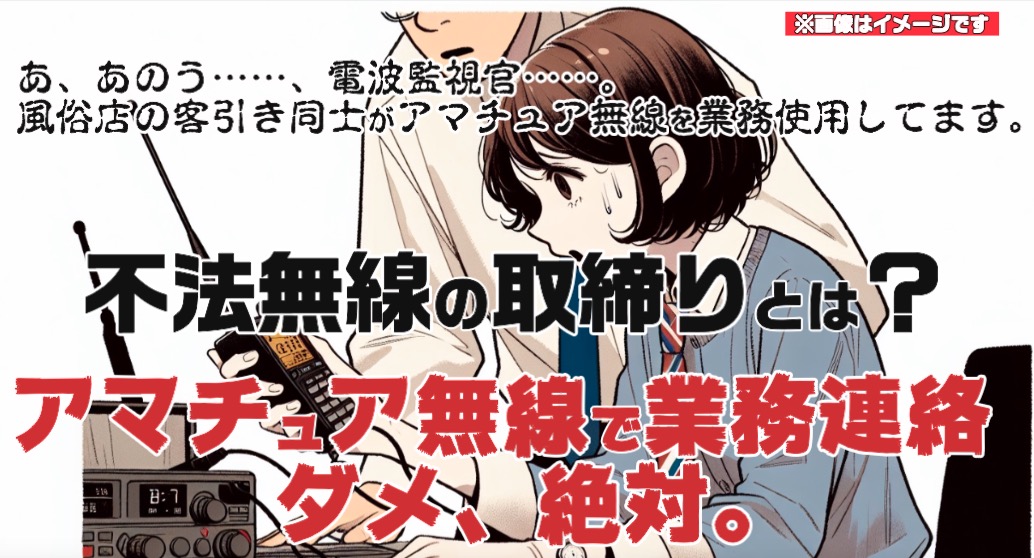
「このレポートが、無免許運用を実行しようとしている人、すでにしてしまっている人にとって反面教師となれば……」
そう語るのは、筆者ではなく、投稿者であるAさん本人です。今回の結果をすべて自身の責任として受け止めたうえで、最後には「自分のような事態にならないよう、皆さんも免許の期限を今一度確認してください」と呼びかけています。
違反の意図がなくとも、知らず知らずのうちに法を犯してしまうリスクがあるのがアマチュア無線の世界。今回のレポートは、その現実を知るうえで重要な資料となるでしょう。






















































































































