アンカバーとは何か
かつてアマチュア無線の世界には「アンカバー」と呼ばれる、正体不明の存在がいました。
彼らは正式なコールサイン(無線局免許)を持たず、自由勝手な名前を名乗って電波に乗っていた違法無線局です。
今のようにスマートフォンや衛星通信(例:スターリンク)が普及する前は、情報収集や交流、緊急連絡、承認欲求の発散すらもアマチュア無線に依存していた時代。
そのなかで突如現れる「謎の声」は、ある種の都市伝説的な存在でした。
本記事では、短波(HF)帯無線における違法な電波の利用事例を紹介しています。受信にあたっては法令を遵守し、違法な通信活動を行う個人や団体に協力することのないよう、十分ご注意ください。
■ 日本とアメリカにおけるアマチュア無線の初期事情
・アメリカでは大正3年(1914年)、ARRL(アメリカアマチュア無線連盟)が発足。
わずか3年後には会員数4000名を突破し、すでに文化として定着しつつありました。
・一方の日本では、大正4年(1915年)に「無線電信法」が施行されたものの、
当時はアマチュア無線に対する明確な免許制度が存在していませんでした。
そのため、この時代に個人で無線を運用していた者たちは、制度上はすべて「アンカバー」扱いとなります。
■ 免許制度の整備と合法化の分岐点
・日本で初めてアマチュア無線の免許が正式に交付されたのは昭和2年(1927年)9月。
この年が「合法なアマチュア無線」のスタートとされます。
したがって、「日本のアマチュア無線は大正4年から」とするか、「正式な制度が整った昭和2年から」とするかには、見解の分かれるところがあります。
■ 著名な“アンカバー”経験者たち
戦前期のアマチュア無線には、後に名を馳せる技術者も関わっていました。
・ソニー創業者の井深大氏
・放送局の技術スタッフ
など、後の日本の電波技術を支える人々が“アンカバー”の立場から出発しています。
■ 戦時中のアマチュア無線
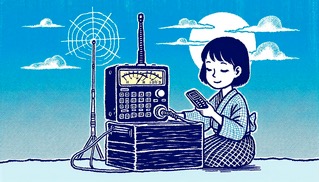
戦時下においては、アマチュア無線は全面的に規制されました。
・無線機器には政府の命令で封印が貼られ、個人の運用は禁止
・一方で一部の無線家は「国防無線隊」や「愛国無線隊」として徴用され、
軍の通信訓練に参加していた例もあります。
参考文献:アイコム公式サイト
https://www.icom.co.jp/beacon/backnumber/electronics/002.html
| 内容 | |
|---|---|
| アンカバーとは | 正規のコールサインを持たず、好き勝手な名前で電波を出す「正体不明」の違法無線局。承認欲求や情報収集目的で現れた。 |
| 当時の状況 | 現代のようなスターリンクやiPhoneの緊急通報は存在せず、アマチュア無線が情報収集・交流・緊急連絡手段だった。 |
| 米国の動向 | 1914年(大正3年)にARRL(米国アマチュア無線連盟)設立。1917年までに会員数4,000人以上に。 |
| 日本でのアマ無線の初期 | 1915年(大正4年)に無線電信法施行も、アマチュア免許制度は未整備。1927年(昭和2年)9月に初の免許が交付される。 |
| アンカバーの扱い | 昭和2年以前のすべてのアマチュア無線通信は、免許未整備のため「アンカバー」とみなされる。 |
| 著名なアンカバー経験者 | 井深大(ソニー創業者)、放送局関係者など、多くの技術者が関与していた。 |
| JARLの設立 | 1926年(大正15年/昭和元年)、日本アマチュア無線連盟(JARL)が発足。 |
| 戦時中の状況 | アマチュア無線は厳しく規制され、機材には封印。通信訓練として「国防無線隊」「愛国無線隊」に徴用された。 |
| 参考 | アイコム公式サイトの記事 |
📡 かい人21面相…! 「無線の怪人」現る!?
「かい人21面相」や「キツネ目の男」という言葉を聞いたことがありますか?
1984年から1985年にかけて、日本を騒がせた「グリコ・森永事件」。
当時、江崎グリコや森永製菓といった大手食品メーカーが、青酸入りのお菓子をばらまくと脅迫され、身代金を要求されたこの一連の事件は、今となっては若い人にはなじみがないかもしれません。
この事件の中心にいたのが、あの「かい人21面相」と名乗る謎の犯人です。
事件は、江崎グリコの社長誘拐に始まり、青酸入りお菓子のばら撒き警告、脅迫状と挑戦状の乱発など、まさに“劇場型犯罪”でした。
犯人の動機については今なお謎です。企業への金銭要求が主な動機に見える一方で、誰も殺していない、報道を巻き込んだ劇場型演出、挑戦状の数144通などを見れば、目立ちたいだけの愉快犯説(承認欲求)も否定できません。
あるいは、企業や警察への恨み、株価操作を狙った経済犯など、複数の動機の可能性も指摘されています。
実はこの事件、私たちアマチュア無線愛好者にとっても無関係ではありません。
というのも、当時の警察関係者や報道によると、警察無線が何者かによって妨害されたことが複数回あったとされ、その発信に改造されたアマチュア無線機が使われた可能性が高いと見られています。
当時の警察無線はアナログ方式で、受信そのものは簡単でした。しかし、妨害となると話は別。同一周波数でより強力な信号を発信するには、専門的な知識と設備が必要です。

加えて、発信元を特定されるリスク(逆探知)もあるため、かなり慎重に行動していたものと推測されます。
また、犯人とされる人物から報道機関に届けられた手紙の中に、自らを「無線マニア」と名乗る記述が残っています。実際に犯人グループは無線に関する高度な知識を有していた可能性が高いと見られています。
社会の反応と『ラジオライフ』バッシング
事件当時、報道はまさに過熱状態。犯人を義賊的に扱うような風潮すらありました。
なぜなら、1年半にわたって挑発や脅迫を繰り返しながら、誰一人として命を奪っていないという点があったためです(ただし、警察本部長が責任問題で命を絶っています)。
そんな中、マニア向け雑誌『ラジオライフ』が槍玉に挙げられる出来事がありました。事件に便乗した週刊誌の「とばし記事」によって、同誌が警察無線妨害を煽っているとレッテルづけられたのです。

そもそも、アマチュア無線機の「送信改造」と「受信改造」はまったく別物で、無線マニアの多くはその違いを当然知っていますが、一般人には区別がつきません。
この件では、マニア界隈でも「なんでそんな誤解を…」と呆れる声が多く上がっていました。
他にもアマチュア無線の販売店も迷惑を被っています。
犯人がライトバンに残していった遺留品にYAESU FT-208があり、これで滋賀県警察の無線である”滋賀1系”を傍受していたとしてテレビに取り上げられ、八重洲関係者がインタビューに答えていたそうです。
上述の無線機は『山本無線』で販売された一台で、同店やアマチュア無線家らは捜査当局側からの調べを受けるなど、無関係の関係者も困惑されたようです。
「かい人21面相」現る──7MHz帯の怪電波
興味深いのは、後に犯人から報道機関へ送られたとされる手紙の中で、自らを「無線マニア」と称していた点です。犯人たちは、相当高度な無線技術と知識を持っていたと見られています。
そして、それを裏付けるように事件の渦中にもうひとつ、無線界隈を震撼させる出来事が起きました。
1984年12月4日。アマチュア無線の世界で“オフバンド通信”と呼ばれる、許可された周波数帯域を逸脱した不正な通信が、7MHz帯で傍受されました。
そのやり取りはこうです。
「21面相、こちら玉三郎」
「クスリは用意できたか」
「ひと、ふた、ひと、ろく(12月16日を指すと推定)、航空券が往復確実に取れてR6へ行く場合は日帰りで必ずアシがつかないように戻ってくるように」
「不二家はやっぱり金払わんちゅうとんのけ」
「不二家あきらめたほうがええわなこりゃ」
──実はこの通信が傍受されたのは、不二家を標的にした脅迫事件が起きる直前のこと。不二家脅迫事件は1984年12月7日、不二家の労務部長宅に脅迫状が届き、青酸ソーダとカセットテープが同封されていた事件でした。
つまり、7MHz帯でのオフバンド通信があったのは、そのわずか3日前だったのです。まさに犯行の打ち合わせ。
この通信をキャッチしたのは、北海道や大阪など、当時の正規アマチュア局。7MHz帯はコンディションによっては全国的に通じる短波帯域で、普段から多くの無線家が常時ワッチしている人気バンドです。
そのため、少しでも異常な通信があると、すぐに不審がられます。実際、この「21面相」と「玉三郎」の通信も、すぐさま警察に情報提供されました。
犯人らがなぜ電話ではなくアマチュア無線を選んだのか、理由は不明です。無人島のように固定電話のない場所に潜伏していた可能性も考えられますが、彼らが自称「無線マニア」である以上、無線の利便性と匿名性を熟知していたと見るのが自然でしょう。
この一件が報道されて以降、「21面相」の電波を探して夜な夜なダイヤルを回す“電波探偵”も続出。緊張感と同時に、どこか漫画のようなコードネームに冷笑を交えながら、世間はこの謎に注目。
しかし結局は、誰も彼らの正体を特定できなかったのです。
グリコ・森永事件は未解決のまま、2000年に公訴時効が成立。犯人が誰だったのか、そもそも生存しているのかさえ、現在も不明です。
こうして見ていくと、「かい人21面相」と「玉三郎」は、単なる愉快犯ではなく、無線や情報戦に熟知した、非常に高度なスキルを持つ組織的な集団だった可能性が高いと考えられます。
犯罪者というより、「情報工作員」のような側面さえ感じさせます。
そう、彼らはまさに、電波と時代に消えた怪人 だったのです。
📡 オフバンドは無法地帯!?
というわけで、アマチュア局に正規に許可されている周波数帯から、ほんの少し外れた場所で行われた交信。
これが、総合通信局が言うところの「指定外周波数使用」、つまりいわゆる「オフバンド交信」。当然ながら、違法行為です。
では、もう少しだけオフバンドについて深掘りしてみましょうか。
まあ、当時の無線界隈って、今とは違って「監視の目」がだいぶゆるやかだったんですよ。
誤解しないでくださいね。「ゆるい」というより、今みたいにリアルタイムで発信源をピンポイントで探査できる技術や体制が、まだ整っていなかったという意味です。
だからこそ、「21面相」とか「玉三郎」みたいに、犯罪の打ち合わせとまではいかなくても、オフバンドで深夜ラジオばりのふざけた電波を平気で流すような連中が、当時はそこかしこに存在していたんです。
特に、電波の伝搬特性が非常に良好なHF帯の中でも、7MHzの指定外周波数ってのが、アンカバーにとっては格好の“遊び場”だったようです。
「この局、全然コールサイン名乗らへんけど、話の内容が妙に濃いぞ!?」
「おいおい、誰やねん!こんな場所で、さも当然みたいに深夜番組やっとる奴は!」
なんて反応が、普通に飛び交っていたような、そんな空気感の時代だったんですね。
もちろん、そんな行為が良いわけないってのは、当時の人たちもみんな分かってたと思います。
でも、中には妙に印象に残る“個性派アンカバー”がいて、その存在に引きつけられ、思わず聞き入ってしまう“ファン”みたいな人たちもいたんです。
ある種、時代が許した「異端の魅力」ってやつかもしれません。
「JA10」なんてコールサインを名乗る奴もいたらしいですよ。10エリアって、そもそも日本に存在してないエリアやないかい、って話です。
それから、レピーター妨害を常習的にやってた迷惑な奴らもいましたね。
あまりに悪質だったもんで、ついに業を煮やしたレピーターの運営者。町の電気屋さんだったらしいんですが、自ら怪しげなワゴン車で妨害電波を探査して、発信源を突き止め、ついには自宅まで乗り込んで「念書書け!」って迫ったとか……。
いやはや、怖い話ですよ。まるで“民間電波監視官(民間電監)”です。

今でこそ、総合通信局(当時は「電監」と呼ばれていました)がすぐに監視に入りますし、正規の周波数帯を外れて送信すれば、即座に発信源を特定されてしまいます。
しかし当時はというと、まさに「誰もが好き勝手にやっていた無法地帯」だったのです。
そして、時には「監視官」までもが自ら電波に出てくることがありました。
「こちら、電監です。違法電波は即時停止しなさい。」
「えっ、ワイは玉三郎ちゃんちゃいますう!」(とシラを切るアンカバー)
「いや、あんたや、あんた!」
「ワイこそが本物の玉三郎ちゃんや!」
「ワイは21面相や!」
──なんていう、本物の監視官か偽者かもわからない、「電波上の漫才劇」みたいなやりとりが、実際に繰り広げられていたのです。
そしてこちらが、1982年当時に実際に交信された、アンカバーたちの音声記録です。なんと、子どもまで出てきています。
この“ノリ”こそ、当時の7MHz帯に漂っていた空気感の一端を垣間見ることのできる、「歴史的な物証」のひとつと言えるかもしれません。
当時、1982年。まだ4歳の少女「アラレちゃん」はともかくとして、彼女より年上と思われる登場人物の誰ひとりとして、正規のコールサインを名乗ってはいませんでした。
そもそも、彼らが出ていたのは正規のアマチュアバンドではない周波数だったため、名乗れるはずもなかったのでしょう。
にもかかわらず、最低限のマナーとしてか、「メリット交換」だけは行われていたのが、なんとも不思議な“礼儀”を感じさせます。
さらに、彼らが使っていたニックネームには、当時の世相や流行が反映されており、文化的な側面から見ても非常に興味深いものがあります。
なぜ「オフバンド」が行われたのか?
オフバンドによるアンカバー通信が行われていた理由は、ひとつではありません。いくつかの背景が複雑に絡んでいたと考えられます。
まず、実際のところ当時のアマチュア無線は非常に活況で、免許された正規の帯域では利用者があまりにも多かったことが挙げられます。
特に7MHz帯は、現在よりも周波数幅が狭く、混雑状態にありました。
そのため、空きチャンネルを確保するのが難しかったうえ、他の正規局からの傍受を避けたいという動機も少なからずあったと思われます。
携帯電話やインターネットが存在しなかった時代、アマチュア無線はもっとも手軽な連絡手段のひとつでした。
特に「移動通信」としての役割も大きく、利用者が非常に多かったのです。そしてそれは同時に、第三者による傍受も多かったことを意味します。
もし正規のアマチュアバンド内で、電波法に違反するような通信を行えば、すぐに正規局が警察や当時の電波監理局(電監)に通報します。
それを避けるために、彼らはあえて許可外の帯域、すなわち「オフバンド」へと移動し、「アンカバー局」となった。これは一つの合理的な行動だったとも言えるでしょう。
もっとも、違法なアンカバー局と言っても、その実態はさまざまでした。
ちょうど我々がインターネット黎明期に「2ちゃんねる」などでアングラ的な楽しみ方をしていたように、当時のアンカバーたちも、電波という空間で“悪ノリ”を楽しむ者が多かったのです。
確かに電波法違反であることに変わりはありませんが、少なくとも営利目的の通信や、外国のスパイ活動、あるいは犯罪グループによる犯行の打ち合わせなどと比べれば、まだ“可愛げのある”レベルだったと言えなくもありません──いや、同じ違反に大小はないと叱られるかもしれませんが……。

なお、当時と現在では、取り締まりの精度が段違いです。今や総合通信局による監視体制は大幅に強化されており、全国に設置されたセンサー局が協調して発信源を探査することで、違法電波の発信地点は、ほぼ瞬時に特定されます。
また、現代では通信手段がスマートフォンの一択です。わざわざアマチュア無線のオフバンドを使って秘密の連絡を取る必要性も低下しています。今では「シグナル(Signal)」などの暗号化メッセンジャーが利用されるでしょう。
📡 まとめ:アンカバーは、もうおらんのか?
結局のところ、この記事の要点は──
「アマチュア無線を使ったオフバンド通信において、かつては犯罪者グループによる秘密のやり取りが本当に行われていた可能性がある」という事実と、それにまつわる考察にあります。
本来、アマチュア無線は免許された周波数帯域内でのみ運用するのが原則です。
許可されていない帯域での通信は電波法に反し、これを「オフバンド」と呼び、それを行う者を「アンカバー(アンカバー局)」と呼びます。
そして彼らは、法的にはれっきとした「不法無線局」として、摘発の対象となる存在です。
かつては、そうした謎のアンカバー局が「当たり前」のように存在していました。
しかし、時代の変化とともに監視体制は強化され、今ではほとんど見られなくなったのです。
それでも、ダイヤルをぐるぐる回していると──
たまに「妙に話のうまい翁」が、聞き慣れない周波数で喋っていることがあるかもしれません。
もしかしたら、それは伝説の「アンカバー」の生き残りかもしれませんよ?
とは言え、現在でもオフバンド通信が、北朝鮮をはじめとする工作活動や犯罪者による秘密通信の手段として使われるケースもあると言われています。
アングラな世界に足を踏み入れるには、それなりの覚悟と用心が必要です。
くれぐれも、ご注意を。





















































































































