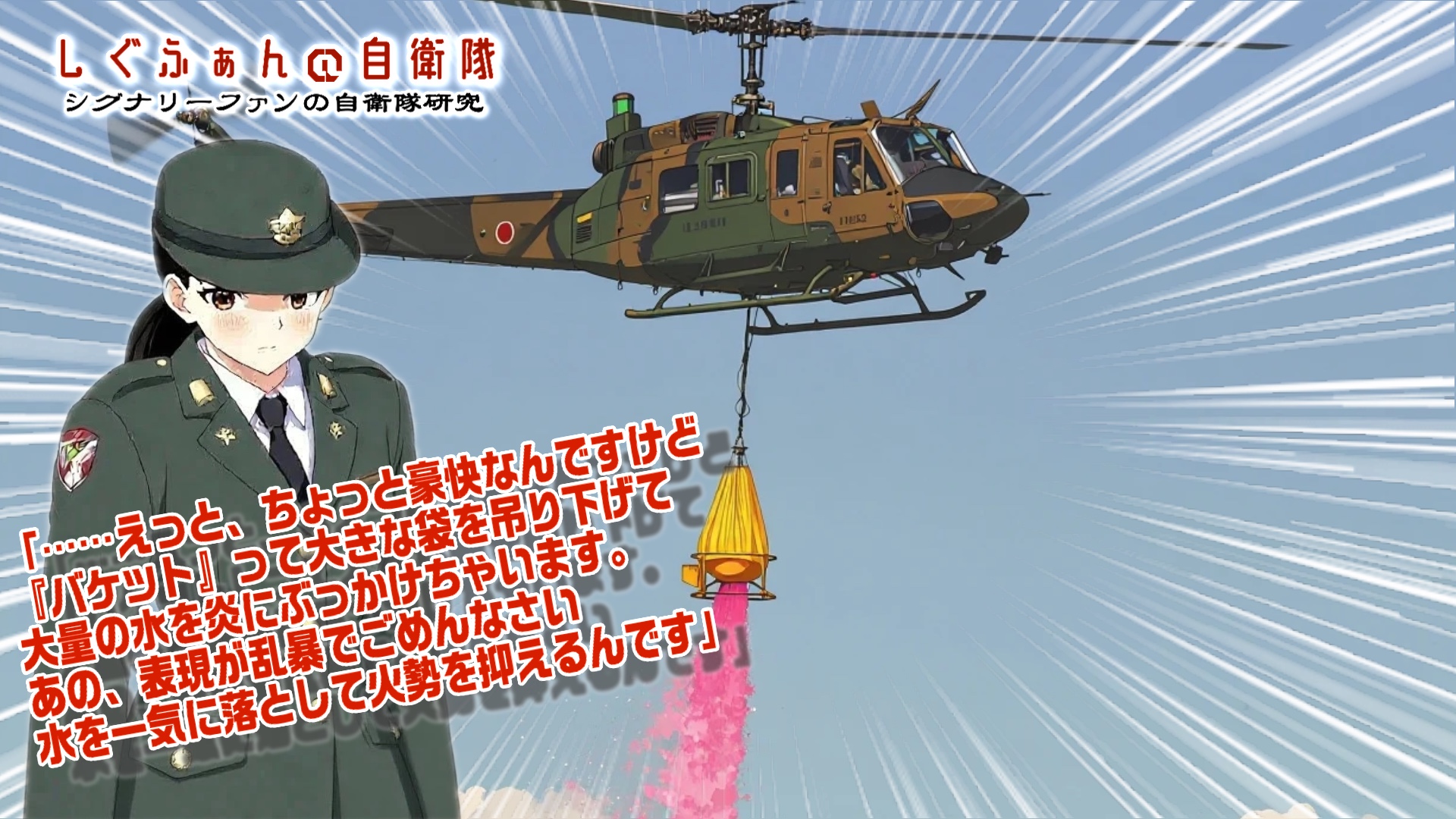地上戦では戦車は圧倒的な戦力を誇りますが、携行式をはじめとする対戦車ミサイルには十分に対応できません。
そのため、戦車の行動を支えるためには、敵の対戦車兵器を扱う歩兵を排除する役目を、味方歩兵が「護衛」として担う必要があります。
IFVというカテゴリと歴史
歩兵戦闘車(Infantry Fighting Vehicle:IFV)は、戦後の戦車と装甲兵員輸送車(APC)の発展の中で生まれたカテゴリーで、「歩兵を戦場へ運び、降車後も共に戦う」ことを目的として設計された車両です。

装甲兵員輸送車は歩兵を戦場まで安全に運ぶ手段として普及しましたが、単なる輸送にとどまらず、戦闘支援の火力も求められるようになりました。
こうした要求に応えて登場したのが歩兵戦闘車で、輸送機能を維持しつつ、大口径機関砲などの重火器を搭載し、事実上「準戦車」と呼べる存在となりました。
冷戦期には各国で開発競争が活発化し、アメリカのM2ブラッドレーのように対戦車ミサイルを装備した歩兵戦闘車が注目を集めました。
こうした国際的な動向を背景に、日本も歩兵戦闘車の開発に着手し、1980年代に初の国産車両として89式装甲戦闘車を配備しました。
以下に、その歴史的経緯を時代順に解説します。
■ 1. 第二次世界大戦後 ― APCの登場
第二次世界大戦での戦訓から、兵員が前線まで安全に移動できるよう、戦車に随伴して移動するための装甲兵員輸送車(APC:Armored Personnel Carrier)が登場しました。
代表的な初期の車両としては、
-
アメリカのM113(1960年代)
-
ソ連のBTR-60シリーズ
などがありました。これらは基本的に兵員輸送専用であり、兵士は戦闘時に車外へ降りて戦うことを前提としていました。搭載火器も7.62mm機銃程度で、攻撃力は限定的でした。
■ 2. 1960年代 ― IFV概念の誕生(BMP-1の衝撃)
1966年、ソ連がBMP-1を登場させたことで、IFVの概念が世界に広まりました。
BMP-1は、機銃ではなく73mm低圧砲と対戦車ミサイル(AT-3サガー)を搭載し、兵員輸送車でありながら戦車や軽装甲車を攻撃できる初の車両でした。
これにより、西側諸国も「歩兵戦闘車(IFV)」というカテゴリーを急速に整備し始めます。
■ 3. 1970〜80年代 ― 各国のIFV整備競争
BMP-1の登場は西側諸国に強い衝撃を与え、次のような車両が登場します。
-
西ドイツ:Marder(マーダー)
-
アメリカ:M2ブラッドレー
-
イギリス:FV510ウォリアー
-
フランス:AMX-10P
これらはいずれも、
-
20〜30mm機関砲を搭載
-
兵員6〜8名を搭載可能
-
一部に対戦車ミサイル搭載能力を持ち、APCより高い戦闘能力を有していました。
日本初のIFV ― 89式装甲戦闘車の登場
日本でも冷戦末期、ソ連の機械化歩兵部隊に対抗するため、陸上自衛隊が「89式装甲戦闘車(FV)」を開発。1989年に制式採用され、国産初のIFVとなりました。
主な特徴は以下の通りです。
-
35mm機関砲と74式戦車と共通の射撃統制装置
-
副兵装として同軸機関銃(7.62mm)と79式対舟艇対戦車誘導弾を装備
-
油気圧懸架装置による高い走破性
-
8名の普通科隊員輸送能力
しかし、コストの高さや冷戦終結により、生産数は約120両にとどまりました。
89式装甲戦闘車は空の脅威にも対応できる?
89式装甲戦闘車には対空能力も付与されています。87式の自走対空機関砲としての役割を一部補完しています。

89式装甲戦闘車は主要武器に35mm機関砲を搭載しています。
これは87式自走高射機関砲が使う口径と同じ系統の機関砲で、低空のヘリや無人機に対する射撃が技術的には可能です。
水平より上向きにもできるため、地対空装備としても機能します。
実務的には、装甲戦闘車(IFV)が機動中に自らの35mm砲で低空脅威に対抗することで、87式の近接防空を補う(=部隊レベルでの対空防護を強化する)役割を果たせます。
ただ、89式の砲塔はあくまで歩兵戦闘車の主砲であり、継続的な対空戦闘能力や87子に準じた高度な対空指揮管制は持ちません。
また弾種や管制装置、弾幕形成の機能(例えばAHEAD型の近接分散弾、専用レーダーとの統合など)についても、87式のほうが本格的であり、89式は“緊急対応的な対空能力”にとどまります。
あくまで一部補完であり、89式装甲戦闘車は35mm機関砲を備え低空の脅威に対処できますが、87式の専任的な近接防空能力(火器管制レーダー・弾種や探知能力など)を完全に代替するものではありません。
89式は87式を部分的に補完できるが、置き換えるものではない
戦術的には、装甲部隊のIFV群(89式等)が自衛的に低空脅威を排除しつつ、専任の87式や後継SHORADシステムが主要な近接防空を担うのが現実的運用です。
まとめ.歩兵戦闘車の現在と今後
21世紀のIFVはネットワーク化とモジュール化へ
現代のIFVは、単なる「歩兵支援車両」から情報共有・戦術指揮の中核へと進化しています。
-
スウェーデン「CV90」シリーズ
-
ドイツ「プーマ」
-
韓国「K21」
-
日本の新型装輪装甲車(改)および後継IFV構想
いずれも電子装備やセンサーを強化し、無人砲塔やリモートウェポンステーションの導入が進んでいます。
無人機(UAV)や対戦車ミサイルの発達によって、重装甲車両の生存性は低下傾向にあります。
そのため、各国は「装輪式IFV」や「遠隔操作型支援車両」などにシフトしつつあり、歩兵戦闘車は情報戦・機動戦の一翼を担う“戦術ノード”へ進化しています。
参考(抜粋)
-
防衛省(東千歳広報誌PDF 内の装備関連記事)
https://www.mod.go.jp/gsdf/nae/7d/hensei/team/i/07.ojiroshinbun/ojiroshinbun127.pdf -
87式自走高射機関砲(Wikipedia 日本語)
https://ja.wikipedia.org/wiki/87%E5%BC%8F%E8%87%AA%E8%B5%B0%E9%AB%98%E5%B0%84%E6%A9%9F%E9%96%A2%E7%A0%B2 -
Type 87 self-propelled anti-aircraft gun(Wikipedia 英語)
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_87_self-propelled_anti-aircraft_gun -
89式装甲戦闘車(Wikipedia 日本語)
https://ja.wikipedia.org/wiki/89%E5%BC%8F%E8%A3%85%E7%94%B2%E6%88%A6%E9%97%98%E8%BB%8A -
防衛白書(装備資料PDF の一節)
https://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2008/2008/pdf/20shiryo2.pdf -
防衛白書(別年・装備資料PDF)
https://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2011/2011/pdf/23shiryo2.pdf -
装備解説(87式/陸自装備まとめ) — 陸自調査団(解説記事)
https://rikuzi-chousadan.com/soubihin/zisouhou/type87kousya.html -
装備解説(89式/陸自装備まとめ) — 陸自調査団(解説記事)
https://rikuzi-chousadan.com/soubihin/soukousya/type89sentou.html -
89式装甲戦闘車(個別解説ページ / combat1)
https://combat1.sakura.ne.jp/89SHIKI.htm -
35mm弾・AHEAD(対無人機向け近接分散弾の説明) — DMRSC 技術解説
https://www.dmrsc.com/AAG/AAG_201x.html -
AHEAD / 近接分散弾 解説(技術系ブログ・補足)
https://seesaawiki.jp/w/namacha2/d/GDF002%2035mm%CF%A2%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%CB%A4 -
装備解説記事(一般向け解説:HARUKAZE/89式紹介)
https://harukaze.tokyo/2017/03/09/89sikifv/