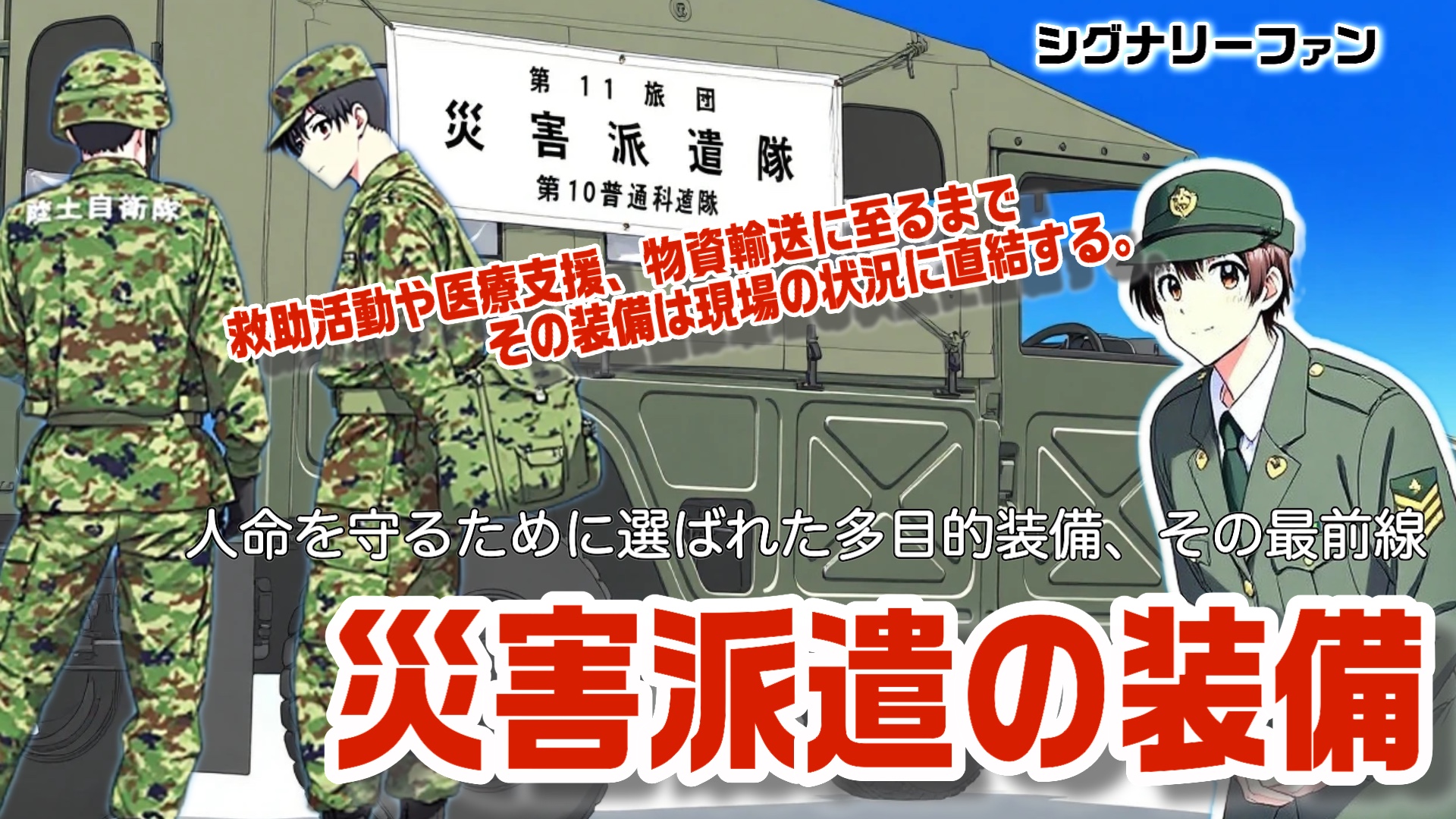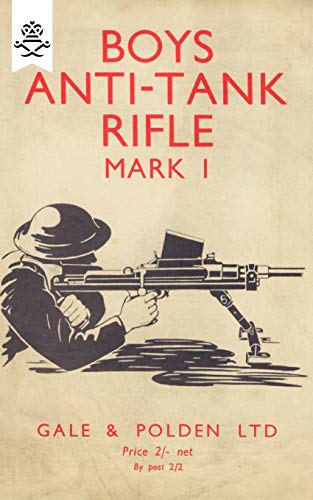ライフルを語るとき、「対戦車ライフル」「対物(アンチマテリアル)ライフル」「対人ライフル」を同列に扱ってしまいがちです。
混同が起こる原因のひとつは、現代の報道や一部の書籍で「対物ライフル=対戦車ライフル」と表現される場合があることです。
特に警察や特殊部隊での運用では、歴史的な対戦車ライフルを現代の標的や任務に合わせて改良・再分類しており、公式文書でも厳密に区別されないことがあります。
そのため、素人目には「大口径で強固な装甲を撃つライフル=対戦車ライフル」という理解で止まってしまいがちです。
しかし、これらは見た目や口径が似通う場合があるものの、歴史的な成立過程や想定される標的、技術的な設計意図において明確な違いがあることがわかります。
本稿では、それぞれの定義と用途、発展の経緯を整理して解説します。
詳しく見ていきましょう。
対人ライフルとは

対人ライフルとは、主に人間を対象に精密射撃を行うことを目的に設計された銃を指します。

陸上自衛隊でも「対人狙撃銃」という名称でM24 SWSならびにHK 28E2が配備されています。

一般に「狙撃銃」や「スナイパーライフル」と呼ばれる分類で、命中精度と弾道安定性を優先した設計が特徴です。
対人ライフルは単に「威力が強い」銃ではなく、銃本体の剛性、精密加工された銃身、照準器(高倍率スコープ)、バイポッドやチークピースなどの操作性向上装備、そして「マッチグレード」と呼ばれる高精度弾薬の組み合わせで初めて性能を発揮します。
装填方式も重要で、長距離で最高精度を狙う場面ではボルトアクション式が好まれる一方、複数の標的に対処したり迅速な追撃が必要な場面では半自動式が求められます。
現代の歩兵用ライフル(アサルトライフル)における国際的な標準弾は概ね5.56×45mm NATOであり、多くのNATO加盟国や日本を含む米国の同盟国で採用されている制式小銃(例:M16/M4系、日本の89式、20式など)はこの弾薬を基準に設計されています。

一方、対人ライフル(狙撃銃、スナイパーライフル)では、より高い射程と貫通力・弾道性能が求められるため、7.62×51mm NATOが広く用いられています。
7.62×51mm NATO弾の有用性
米軍のM14小銃は7.62×51mmを採用した旧世代の制式ライフルであり、日本の制式小銃であった64式も同様でした(※64式は弱装弾を使用)。
7.62×51mmは、戦後の冷戦期に各国で採用され、1950年代から1960年代にかけて歩兵用の主要な口径として広く使われてきましたが、1960年代以降に5.56×45mmの高速小口径弾を採用する国が増えたため、多くの軍で歩兵用小銃の標準口径は次第に5.56へと移行しました。
しかし、7.62mmは旧世代とはいえ、実効射程や弾道保持が5.56mmより優れるため、指定射手(DMR)や多くの汎用狙撃用途で今でも標準的なのです。
陸上自衛隊でもM24SWS対人狙撃銃が導入される以前は64式小銃の精度の良い個体を選び、狙撃銃に転用していました。

さらに任務や要求射程に応じて.338ラプアや.300ウィンマグのような、より大口径の弾薬が選択されることもあります。
一方で、designated marksman rifle(指定射手用ライフル、DMR)のように中近距離での即応性を重視して5.56mm系弾薬を用いる派生も存在します。部隊の運用コンセプトにより使い分けられているのが実情です。
対戦車ライフルとは
まず、対戦車ライフル(anti-tank rifle)とは、第二次世界大戦期に開発された大型ライフルで、当時の軽戦車や装甲車両を貫通することを目的としていました。
口径は一般に13mmから20mm級で、弾丸は鋼鉄装甲を貫通するために特化しており、現代の小口径ライフル弾とは比べ物にならない破壊力を持ちます。
ボーイズ対戦車ライフル
代表的な例が英国でH.C.ボーイズ(H. C Boys)大尉によって1937年に開発され、同軍が採用したボルトアクション方式の「ボーイズ対戦車ライフル」で、.55 Boys弾を用い、100ヤード付近で約23mmの鋼板貫通能を持っていました。
興味深いことに、ボーイズ対戦車ライフルの使用法を、あのウオルト・ディズニーがアニメ映画にしています。
これは「Stop That Tank!(別題:Boys Anti-Tank Rifle)」はウォルト・ディズニー・プロダクションが1942年に制作した教育・訓練用の短編(カナダ国防省/ナショナル・フィルム・ボードなど向け)です。
デグチャレフ PTRD‑41
デグチャレフ設計のPTRD-41は、1941年にソ連で大量生産された単発式の大口径対物・対戦車ライフルです。
高い運動エネルギーを持つ14.5×114mm弾を採用しており、ドイツ軍の軽装甲車や初期の装甲車両の側面・後部、車両の機関部やタイヤといった要所を無力化する用途で実戦投入されました。
設計は構造が比較的簡素で大量生産に適しており、戦争初期に対戦車火器を欠いていた赤軍(ソビエト連邦労働者・農民赤軍/Workers’ and Peasants’ Red Army)にとって即戦力となりました。
一方で、PTRD-41は単発式であるため再装填に時間を要し、銃本体と弾薬は大型で携行性に難があり、加えて戦車の装甲が厚くなる戦局の進展に伴い、正面装甲を確実に貫く能力は限定的になりました。
特に1943年以降に登場したドイツ軍の重量級戦車(Panther / Sd.Kfz.171、Tiger I / Sd.Kfz.181、Sd.Kfz.182)に対しては、射距離や射角次第で効果が左右されるため、対戦車任務は次第に対物的な用途や局地的な破壊工作へと性格を変えていきました。
設計の単純さと14.5mm弾の破壊力で戦争初期に有用だったPTRD-41ですが、装甲の進化と運用上の制約から役割は限定的に変化したと評価される兵器といえます。
現代において対戦車ライフルの実用性が急速に低下した背景
しかし、戦後に近代化された戦車に対しては、これらの対戦車ライフルの実用性は急速に低下しました。現代では戦車を直接破壊する目的で使用されることはほぼありません。
第二次大戦期の対戦車ライフルは、当時の軽戦車や装甲車の薄い装甲を貫通することを目的に開発されたのは上記の通りです。
ところが第二次大戦戦後、戦車の装甲は複合装甲やセラミック、反応装甲の採用などで著しく強化され、同じ運動エネルギーの弾でも総合的な防御力が大幅に増加しました。
加えて装甲の厚み自体が大きく増加し、往時の大型ライフルや大口径実包では現代の主力戦車(MBT)の正面装甲を破壊することは現実的でなくなりました。
こうして、初期の戦車や装甲車両には有効だった対戦車ライフルは、急速に実用性を失っていきました。
誘導ミサイルを含む対戦車兵器の一般化
さらに、対戦車戦闘における兵器も様変わりしました。
対戦車砲、ロケット弾(ロシアのRPGシリーズやアメリカのM72LAW)、対戦車ミサイル(JavelinやSpike、自衛隊の01式軽対戦車誘導弾など)といった個人携行型の強力な対戦車兵器に移行したのです。

これらは、従来の運動エネルギー弾よりも遥かに高い装甲貫徹能力を持つ成形炸薬弾(HEAT)を用いており、非常に優れた対戦車兵器です。
このような優れた次世代兵器の前では、大口径のライフル弾で対抗する合理性が薄れ、対戦車ライフルの役割は完全に置き換えられてしまったのです。
したがって「現代では近代的な軍隊が戦車を撃破する目的で対戦車ライフルを使う事例」は極めて限定的と言えます。
対物ライフル(アンチ・マテリアル・ライフル)としての再定義
このように歴史的に「対戦車ライフル(anti‑tank rifle)」として発展してきた大口径ライフルは、戦車装甲の強化や戦術の変化に伴って直接戦車を撃破する役割を失い、用途が再定義されました。
つまり「戦車を一撃で破壊する」道具としての有効性は低下したが、大口径ライフルが現代の戦場や特殊なテロ対策の現場でまったく役に立たないわけではなく、標的や目的を限定すれば有用なケースは残る、というのが実情です。
これが現代の対物ライフル(anti‑materiel rifle)という概念につながっています。
口径は12.7mm(.50BMG)前後が中心で、精密射撃と遠距離射撃に優れています。
特に遠距離狙撃では狙撃手が敵兵に対して射撃する事例もありますが、本来は装備や機材への攻撃が主眼であり、名称どおり「対物用」です。
これに代わって現代に運用される大口径ライフルは一般に対物(アンチマテリアル)ライフルと呼ばれ、用途が再定義されています。
対物ライフルは口径や弾薬(代表例:12.7mm/.50 BMG、14.5mm、さらに大きい20mm級など)で分類されますが、主な目的は戦車そのものの撃破ではなく、陣地やソフトスキンである非装甲のトラックや多目的車両といった標的を無力化することです。
日本での配備状況は?
なお、日本の国内事情についてですが、警察特殊部隊SATや自衛隊の特殊作戦群において大口径ライフルに関する訓練や導入の報道・証言が散見されます。
例えば、メディアによる元・SAP隊員へのインタビューなどから、SAP時代から対戦車ライフルを用いた訓練を行なっていたという証言があります。

陸上自衛隊での配備状況は以下の記事をご確認ください。

まとめ
整理すると、銃器を分類する際の本質的な違いは、想定される標的と歴史的経緯にあります。
対人ライフルは主として人間を標的とする狙撃任務に最適化された銃であり、弾薬や照準系もそれに合わせて設計されています。
一方、第二次世界大戦期に用いられた『対戦車ライフル』は、当時の軽装甲車両や初期戦車を想定して開発されたものでした。
しかし戦後、戦車装甲の複合化や反応装甲の導入、誘導兵器の発達により、これらの大型ライフルは主力戦車を直接破壊する手段としての実用性を失いました。
その結果、大口径ライフルは『対物(アンチマテリアル)ライフル』として再定義され、軽装甲車両のタイヤやエンジンといった目標を無力化する用途で運用されるようになっています。
関連リンク
- 対物ライフルで兵士を撃ってはいけないはウソ? —
(対物ライフルの法的・倫理的制約を論じた解説記事) - 陸上自衛隊、新たな対人狙撃銃:ヘッケラー&コッホ社製HK G28 E2を調達 —
(HK G28 E2 の導入を伝えるニュース/解説) - 陸上自衛隊はなぜ狙撃銃を導入してこなかったのか —
(狙撃銃導入の歴史的背景と理由を考察した記事) - 敵の恐怖心を煽り、進撃遅滞させるスナイパーの運用は心理戦でもある —
(狙撃運用の心理戦的効果を論じた考察) - 陸上自衛隊も配備する「バレット対物ライフル」シリーズの驚くべき実力 —
(バレット社製対物ライフルの性能解説と陸自導入の文脈) - 陸上自衛隊が導入した対人狙撃銃「M24 SWS」の実力 —
(M24 SWS の技術解説と運用評価)