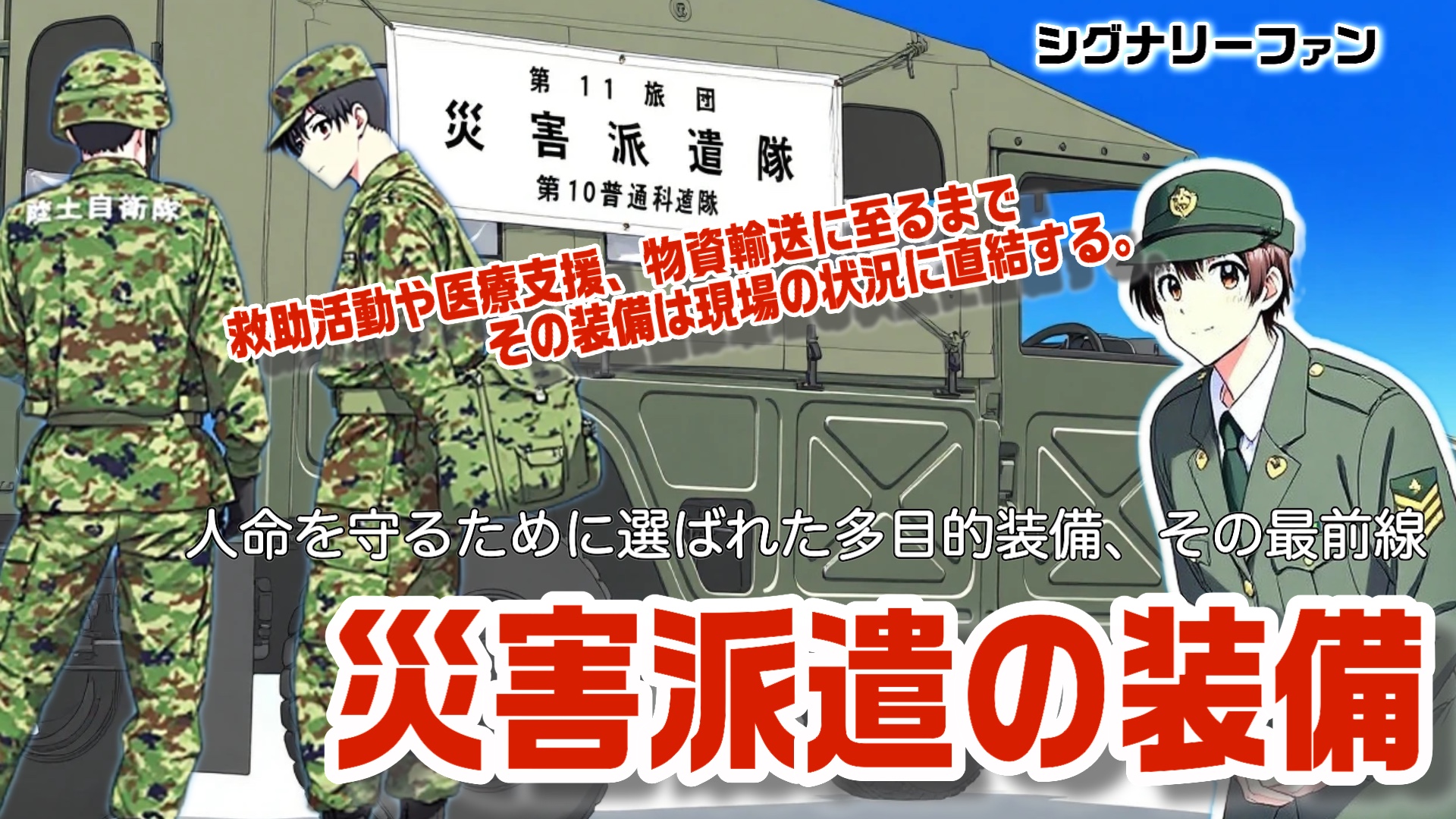現代の陸上自衛隊において、もはや狙撃は特殊任務だけの技術ではなく、部隊運用と切り離せない戦術の一要素になっています。
2000年代以降、対人狙撃銃としてM24SWSが各部隊に配備されてきたのに続き、2023年にはその光景となる7.62mm対人狙撃銃HK G28 E2が調達開始されました。

近年では対物(materiel)用途を想定した大口径対物ライフル「Barrett」の導入も公表されました。
ただし、現段階では一般部隊への配備は確認されておらず、特殊部隊のみの配備と見られています。
本稿では、陸上自衛隊が調達を開始したとされるバレット(Barrett)対物ライフルを中心に、その背景、性能的特徴、運用上の意味合いを整理します。
対物ライフル「バレット(Barrett)」とは
バレット(Barrett)は米国のBarrett社が製造する大口径対物ライフルのシリーズで、主に.50 BMG(12.7×99mm)弾を用い、遠距離から車両の機関部や通信・光学機器、強化ガラスなどの物的目標(materiel)を無力化する用途を想定して設計されています。
モデルには半自動式のM82/M107やボルトアクションのM95などがあり、設計様式や作動方式はモデルによって異なります。
また近年は.416 Barrett(10.4×83mm)など別口径の展開もあります。
対物ライフルについては以下の記事にて解説のとおりです。

バレットは高威力の弾薬と頑強な作りにより、遠距離から車両の機関部や通信・光学機器、強化ガラスといった「物的目標(materiel)」の無力化を主眼に設計されています。
バレット・シリーズと自衛隊での配備状況を詳しく見ていきましょう。
バレット社とシリーズの概略
バレット(Barrett Firearms Manufacturing)は、1980年代初頭にロン・バレット(Ronnie Barrett)によって設立された米国の小火器メーカーで、大口径の対物/狙撃銃で国際的に知られています。
創業以来、同社は.50口径(.50 BMG:12.7×99mm)弾を中心とした大口径ライフルの実用化と量産化を進め、軍・警察・民間双方で幅広い採用例を生み出しました。

MRAD Sniper Rifle 出典 New Zealand Defence Force
バレット・シリーズはバレット M82 (Barrett M82) として1982年に開発されました。
1986年に改良型のM82A1が開発され、M107(M82A1M)として、米軍で配備されています。
やはり配備の主体は軍隊です。米軍をはじめ複数国の陸軍・海兵隊でM82/M107等が採用され、車両無力化や長距離制圧、偵察支援などで運用されています。
一方で、対テロや重要施設防護の観点から、警察特殊部隊にも配備事例が多数あります。
民間向けにも民生モデルが販売され、スポーツ射撃やライフル収集での人気があります。
ただし多くの国・地域で使用・輸出に規制が存在します。
代表的なモデルと特徴
バレットにはサイズや発射方式で複数のモデルがありますが、標準的な運用弾は.50 BMG(12.7×99mm)です。
この大口径弾薬による、車両の機関部や通信装置、無人機、強化ガラスなどの破壊、または長距離での貫通力・打撃力を重視した設計です。
近年は高弾道係数弾(BCの高い弾)や、別口径での精密性向上に対する要求も高まり、弾種や口径の多様化が進んでいます。
Barrett M82 / M107(セミ・オート式)

出典 New Zealand Defence Force
半自動式の.50 BMGライフルで、車両や機材、軽装甲目標を遠距離から無力化する用途で広く採用されています。
対物狙撃と車載・固定座射の両面で運用され、米軍をはじめ複数国の軍隊で制式採用例があります。
半自動のため、再装填のボルト操作を必要とせず、引き金を引くごとに次弾を発射できるのが特徴です。
Barrett M95(ボルトアクション/ブルパップ型)
ボルトアクションの.50 BMG対物狙撃銃で、比較的軽量かつコンパクトに設計されたブルパップ方式です。

Model 95™ – Pfoto by Barrett Firearms
高い精度と耐久性を両立しており、固定射撃や狙撃任務で評価されています。
Barrett M99 / M98(ボルトアクション)
単発または単列マガジンのボルトアクション式対物ライフルで、精密性を重視した設計です。対人狙撃と対物撃破任務の双方で使われます

その他(.416 Barrett 等)
近年は.50 BMG以外の弾薬も選択肢が増えており、.416 Barrettのように弾道係数や風耐性を高めつつエネルギーを維持する口径を採用するモデルも開発されています。
ブルパップ方式の特徴
Barrett(バレット)の銃はBarrett M95など、一部のモデルがブルパップだというだけで、すべてがブルパップではありません。
特に有名なM82/M107は半自動式の.50 BMGライフルで、銃床~銃身が前方に伸びるオーソドックスなレイアウトであり、ブルパップではありません。M99 / M98もこの系統です。
その他、AR系のREC7もやはりブルパップではありません。
同社のラインナップにはブルパップ式と通常レイアウトの両方があります。
ブルパップの利点
銃器におけるブルパップ方式は、装薬室(ボルト)がトリガーの後方に配置されているため全長が短くでき、ライフルでもカービン並みのコンパクトサイズにできます。
これは携行性や取り回しに有利です。
ブルパップの欠点
反面、ボルト操作や装填時のスムーズではない操作、射手の頬付けや銃声・排莢の位置など運用上のトレードオフがあります。
陸上自衛隊での配備モデルはM95

画像の出典 https://x.com/JGSDF_HTS_pr/status/1139017072342515713
自衛隊公式アカウントがM95を含む映像を公開したことおよび調達文書の公開が、配備確認の根拠の一つとなっています。
これは陸上自衛隊高等工科学校の生徒が武器学校を訪れて研修を行っている時の様子のようです。
したがってこのM95自体は武器学校が保有している可能性が高いようです。
一方で、すでに陸上自衛隊特殊部隊である特殊作戦群では、対物ライフルを配備していることが防衛省が公表している文章から以前より推測されています。
したがって、このM95は特殊作戦群で配備されているものと強く推測されます。
バレットM95は本来、戦車正面装甲を撃破するための兵器ではなく、対物用途として設計されている点が重要です。
有効射程約1,800メートルを活かして、航空機の地上破壊、軽装甲車の機関部無力化、レーダーや光学機器の破壊、さらには長距離からの制圧射撃や偵察支援など、射程と貫通力を活かした任務で配備されていると見られ、それを担うのは特殊部隊である特殊作戦群です。

なぜボルトアクションなのか
軍事作戦で.50口径を高精度で使う任務では、1発の致命性を追求する運用が中心です。
連続的なセミオートよりも弾道の再現性や弾着の確実性を優先する場合、ボルトアクションを選ぶ合理性があります。
これはすでに一般部隊や特殊作戦群でも配備されているM24から得た知見が活かされ、統一性を持たせた可能性もあります。
また、半自動は射撃時にガスや機関部の作動音が出やすいのに対し、ボルトアクションは比較的静かです。
ステルス性が重要な狙撃任務では、発見リスク低減の観点から有利です。
ただ、米軍は実戦運用の結果、対物/長射程狙撃用途においてセミオート(例:Barrett M82 → 制式名称 M107)を採用する利点が大きいと判断し、M107を長距離狙撃・対物ライフルとして運用してきました。
しかし、精密性や射程を最優先する任務ではボルトアクションも依然重要であり、最近はマルチカリバーのボルト式採用(Mk22等)という流れも出ています。

ほかにも、M95はブルパップ様式で全長が比較的短いことから、狭い車内や装備の搭載、航空機・車両への搭載・空挺作戦などで取り回しが良い点があります。
短い全長を好む部隊運用に合致します。

とはいえ、主な理由は極めて長距離かつ精密射撃ではボルトアクションの優位が残るため、と推測します。
M95は対物狙撃や遠距離精密射撃を主眼に置く運用に適しており、「一撃で確実に仕留める」ことが重要な任務には合理的といえるでしょう。

まとめ
近年のバレットは軽量化・精密化・弾薬の高度化(BC改善、超音速/亜音速の最適化)が進んでおり、これまでの.50口径一辺倒ではない選択肢が増えています。
また米軍では新たな対人狙撃銃として、Mk22 MRADを導入しています。

そして、陸上自衛隊における対物ライフルの導入は、単に“強力な一丁”を増やすというより、任務環境の変化と戦術的選択肢の拡大を反映したものです。
長射程からの機材無力化、重要施設の防衛、そして味方のリスク低減に貢献する一方で、運用・整備・法的・倫理的な制約も伴います。
関連リンク
- 対物ライフルで兵士を撃ってはいけないはウソ? —
(対物ライフルの法的・倫理的制約を論じた解説記事) - 陸上自衛隊、新たな対人狙撃銃:ヘッケラー&コッホ社製HK G28 E2を調達 —
(HK G28 E2 の導入を伝えるニュース/解説) - 陸上自衛隊はなぜ狙撃銃を導入してこなかったのか —
(狙撃銃導入の歴史的背景と理由を考察した記事) - 敵の恐怖心を煽り、進撃遅滞させるスナイパーの運用は心理戦でもある —
(狙撃運用の心理戦的効果を論じた考察) - 陸上自衛隊も配備する「バレット対物ライフル」シリーズの驚くべき実力 —
(バレット社製対物ライフルの性能解説と陸自導入の文脈) - 陸上自衛隊が導入した対人狙撃銃「M24 SWS」の実力 —
(M24 SWS の技術解説と運用評価)