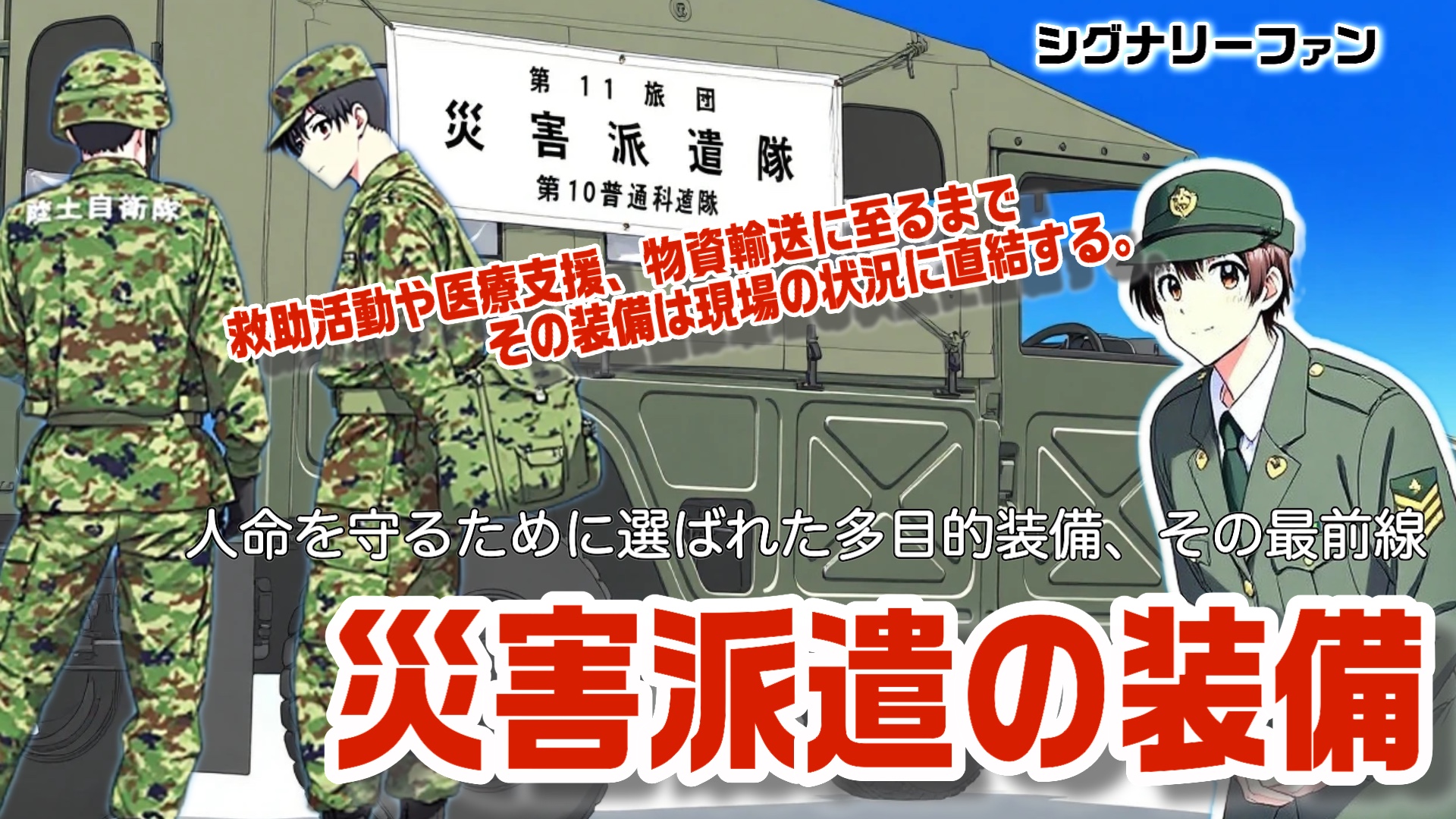軍事における狙撃手は、単なる射撃の専門家ではなく、戦場における重要な戦力として位置づけられます。
その存在は指揮官やエースパイロットと同様、戦況に大きな影響を与えることがあります。
戦闘が激化すると、戦意を高める目的で狙撃手の功績が称えられることもあります。
歴史的に見ると、正規の女性兵士のほか、ミリシア(民兵)として、一般市民の女性が自ら志願して戦争に参加する歴史がありました。
とくに第二次大戦でのソ連女性狙撃手たち(リュドミラ・パヴリチェンコら)は、戦術的・宣伝的に大きな存在になりました。
詳しく見ていきましょう。
1)1930年代〜第二次世界大戦前夜:社会的制約の中の前線参加
1930年代から第二次世界大戦前夜にかけて、女性兵の戦闘参加は社会的制約の影響を強く受けていました。
多くの国で戦闘任務は男性の専権とされ、女性は看護や補助、後方支援など非戦闘職に限定されるのが一般的でした。
それでも、政治的・社会的背景や戦力不足から、女性が戦闘に関与する例は史実として、多数散見されました。
スペイン内戦では女性ミリシアーナが前線に立ち、ソ連でも戦術的理由から女性狙撃手が任用されました。
これら激動の時代における女性兵らは「戦力」としての価値よりも、社会的規範との葛藤の中で行動していたのが実情といえます。
1)スペイン内戦の“ミリシアーナ(女性戦闘員)”たち
1936〜39年のスペイン内戦では、共和国側に多くの女性戦闘員(ミリシアーナ)が参加しました。
スペイン内戦では、フランシスコ・フランコ率いる反乱軍(ナショナリスト派)が、ドイツ・イタリアのファシズム勢力の支援を受け、それに対抗する共和国側の兵士と共に、ミリシアーナ(miliciana)」と呼ばれる民兵として、多くの一般市民の女性が戦場に立ちました。
当時、共和国側を構成していたアナーキスト、社会主義者、共産主義者などの左派勢力(反ファシスト主義)は、男女平等や女性解放を強く掲げていました。このイデオロギー的背景が、女性が戦場に参加しやすい土壌を作りました。

出典 https://en.topwar.ru/143134-vintovki-po-stranam-i-kontinentam-ispaniya-zhenschiny-i-mauzery-chast-19.html
特にアナーキスト、社会主義、共和派の背景を持つ女性たちは、志願による戦闘参加を通じて自己実現や解放を求めたとされています。
彼女たちミリシアーナが使った武器は様々ですが、その装備は流動的で「鹵獲品を含めて、使えるものを使う」が基本でした。
彼女たちミリシアーナは都市戦や山岳戦ではピストルのほか、旧式のスペイン制式小銃(Mauser Modelo 1893 等)、ソ連から供与されたモシン・ナガンといったボルトアクション式の小銃を構え、待ち伏せや突発的な戦闘に参加することがありました。
また、イギリス志願者のリー=エンフィールド(SMLE)、アメリカ系やその他が持ち込んだ小銃など、国際旅団を通じて多国籍の銃が混在しました。
拳銃類はAstra等のスペイン製拳銃、一般的な自動拳銃やリボルバーが使われました。
まだ「組織的な女性狙撃手」という枠組みはなく、個人の適性に応じて任務が割り当てられるケースがほとんどでした。
戦意を高める宣伝目的で女性兵士の写真や記事が使われたこともあります。
女性の前線参加はイデオロギーと人員需要が重なった産物で、以後の女性戦闘史に影響を与えました。

2)フランス・レジスタンスの女性戦士(例:シモーヌ・セグワン)
フランス抵抗運動にも女性戦闘員が多数おり、Simone Segouin(シモーヌ・セグワン)はその象徴的存在です。
1925年フランス、ティヴァール村に生まれたシモーヌは、1944年3月ごろ地元レジスタンス組織 Francs‑Tireurs et Partisans Français (FTPF) に加わりました。戦闘員としての彼女は主にニコル・ミネ”Nicole Minet”というコードネームで呼ばれました。
シモーヌのレジスタンス活動は当初、伝令・通信役として始められ、自転車を使ってドイツ軍占領地区でメッセージの輸送や監視を行っていたほか、活動中にドイツ軍から鹵獲したサブマシンガン MP 40 を所持・使用していたことが複数の史料で確認されています。

MP40とSimone Segouin
また、小型拳銃やライフルも使用訓練を受けており、訓練段階で「ハンドガン、ライフル、サブマシンガンの使用を学んだ」と本人・取材記録に記されています。
爆破工作(鉄道線路破壊・橋梁破壊)や待ち伏せ・敵兵の拘束・捕虜化など、戦闘行動にも従事しており、例えば「1944年7月14日、2人のドイツ兵を自転車で移動中にサブマシンガンで射撃・撃破した」とする記録があります。
当時「戦闘任務=男性」の定義が強かったフランスにおける女性の役割変化を象徴しています。彼女自身は「抵抗のために戦った。それだけだ。もう一度やり直すなら同じことをする」と述べています。
戦後、彼女は小児看護師として勤務し、レジスタンス運動における女性参加の記憶を語り継ぐ存在となりました。
レジスタンス文脈では「狙撃手」と明記されるケースは限定的ですが、前線で銃を扱った女性たちの実像を伝える重要な事例です。
2)第二次世界大戦:ソ連軍の大量動員
女性狙撃手が話題になる時、必ずと言っていいほど、当時のソ連軍の女性兵士ばかりが挙げられます。それはなぜでしょうか?
実は当時、女性兵士を戦闘員として動員していたのが赤軍だけだったからです
第二次世界大戦の戦場で、ソ連軍は意外な戦力を公式に養成・配置し、活用していました。それは女性の狙撃手。単なる戦術上の補助ではなく、前線で実際に敵兵を仕留める重要な役割を担っていたのです。
戦局が厳しくなる中、男性兵士だけでは戦力を補えず、射撃の腕に秀でた女性兵士が前線に送り込まれました。
1941年から1945年までに、少なくとも2,000名以上の女性狙撃手が前線で戦い、数千人の敵兵を戦果として記録しています。
女性狙撃手は小柄な体格や忍耐力を生かし、森や市街地の陰に潜みながら待ち伏せし、長距離射撃で敵兵や指揮官を狙う役割を果たしました。
ソ連では公式の訓練課程があり、記録上は数百人の女性狙撃手が戦場で活躍したことが確認されています。
ロシアの“女の死神”―リュドミラ・パブリチェンコ
若き歴史学徒が銃を手に戦場に立ったとき、予想だにしない伝説が始まりました。
リュドミラ・パブリチェンコは1930年代末に射撃を学び、独ソ戦勃発後に志願して前線へ。短期間で類稀なる命中精度を示し、最終的に公式記録で309名(諸資料で差はある)もの戦果を挙げ、「レディ・デス(死の女)」と呼ばれ恐れられました。
彼女の名は前線だけでなく、外交舞台でも知られ、米国や英国内でも戦時講演に招かれるほどの存在になりました。
若さと詩情の射手―ローザ・シャニナ
シャニナが17 歳だったときに戦争が始まり、彼女は志願兵として軍の登録および入隊局に自ら出頭するも、年齢を理由に拒否されました。
彼女はその後、執拗な要求を続け、どうにか、ポドリスクの狙撃兵学校で訓練を受けることが許されました。
彼女は正確な射撃技術だけでなく、敵の位置を見つけるスキルも高かったのです。
シャニナの銃とダブレット
シャニナは1944年のヴィリニュス(リトアニア)戦や東プロイセン攻勢などで戦闘に従事しましたが、彼女は主に当時のソ連標準のボルトアクション狙撃銃『モシン=ナガン(M1891/30)』狙撃兵仕様を愛用していました。
写真資料や狙撃手概説でも、彼女はソ連の狙撃兵に広く支給された代表的な狙撃光学機器『PU 3.5倍スコープ』を装着したモシン=ナガンを手にしています。
なお、モシン=ナガン系統の標準実包は7.62×54mmR(ロシア弾)ですが、狙撃用途では重装弾(B-32 など)が運用される事例もありました。
シャニナが好んで使った戦術が「ダブレット」です。
シャニナの戦死
彼女が20歳で戦死したのは、砲撃・砲弾の破片による負傷を負って救護中の指揮官を守ろうとした際とされます。
二人で守り抜いた誓い―ナターリヤ・コフショワとマリヤ・ポリヴァノワ
狙撃手は孤独だと語られがちですが、時に絆は最強の武器になります。
ナターリヤ・コフショワとマリヤ・ポリヴァノワはコンビで戦い、互いを補い合う「射手と観測手」の関係でした。
包囲され、弾薬を失った極限の局面で彼女たちは共に運命を選び、最後まで戦い抜いて名誉の称号を受けました。
中央女子狙撃学校 — ソ連が生んだ女性スナイパー養成校
第二次世界大戦中、ソ連の女性狙撃手を大量に育成する中核を担ったのが、モスクワ郊外に設置された中央女子狙撃学校です。
設立の背景
1942年、ナチス・ドイツの侵攻が続くなか、ソ連軍は兵力不足に直面していました。
男性兵士だけで前線を維持することは困難であり、女性の積極的参加が急務となりました。
特に小柄で隠密行動に適する女性の体格は、狙撃任務において有利と判断され、専門教育を行う学校が作られたのです。
教育内容
中央女子狙撃学校では、射撃技術の基礎から、精密射撃、観測技術、地形判読、潜伏行動まで、狙撃に必要なスキルを総合的に学びました。
教育課程はおおよそ数か月にわたり、屋外での実射訓練や野営訓練も取り入れられました。
例えば、射撃練習では静止標的だけでなく、動く標的や遠距離目標も設定され、風向や距離、気温などの条件を計算に入れた「実戦射撃」が日常的に行われました。
潜伏訓練では、草むらや森の中で長時間静止する方法や、敵に発見されにくい動き方を徹底的に叩き込まれました。
精神面の訓練も重視され、孤立した状況でも任務を遂行する忍耐力や冷静さを養うカリキュラムが組まれていました。
卒業後
この学校を経て前線に送られた女性狙撃手たちは、数百名の戦果を上げた者もおり、戦後に名を残した例としてリュドミラ・パヴリチェンコが知られています。
3)冷戦後〜21世紀初頭:特殊作戦と非正規戦への参加
冷戦後の地域紛争やゲリラ戦では、女性が狙撃任務に就く事例は散発的に現れました。
1990年代のフランス・レジスタンスの歴史研究や、ユーゴスラビア紛争の文献などでは、女性兵士が市街戦や待ち伏せで小銃を使用した記録がありますが、組織的な養成は限定的でした。
4)21世紀:現代の女性スナイパーの登場
現代戦ではインターネットを介した映像や報道で活動が可視化されることも多く、以前より社会的認知が高まっています。
1)クルドのYPJ(女性防衛部隊)―現代の女性スナイパー群
2010年代以降のシリア内戦では、クルドの女性部隊YPJが注目され、狙撃任務を含む前線任務で女性射手の活躍が度々報道されました。
彼女たちは狙撃技術を駆使して前線で戦うだけでなく、情報収集や敵陣偵察も担っています。
欧米出身の志願兵も現地で狙撃手として活動した例があり、従来の男性中心の戦闘構造に新たな役割を示しました。
映像や取材記事には、狙撃銃を構えるYPJの女性兵士や、接近弾をかわす場面が残されており、現代戦での女性スナイパーの実例として分かりやすい事例です。
ジャーナリストや国際機関の報告でもYPJの女性戦闘員の存在は繰り返し言及されています。
2)ジョアンナ・パラニ(Joanna Palani)―欧州出身の女性スナイパー例
デンマーク出身でクルド勢力に参加したジョアンナ・パラニは、ISIS と戦う過程で狙撃手として活動したとされる人物です。
欧州出身者が志願し、前線で狙撃任務に就いた稀な近現代の事例として知られています。
3)ミャンマー(ビルマ)抵抗:若き女性スナイパー(近年の事例)
近年のミャンマー内戦でも、民族防衛組織に女性スナイパーが現れているとの報道があります。
例として、若い女性が抵抗勢力の狙撃手として戦っているルポが国際紙に掲載され、現代の非正規戦での女性兵の役割を示しています。
総括
戦火の只中で「一発で状況を変える」技量が、いかに個人を戦争の象徴たらしめるかを示す女性狙撃手たち。
時代が進むにつれて、女性狙撃手の存在は偶発的・個人的な役割から、組織的・戦術的役割へと変化してきました。
ソ連のように国家単位で訓練・配置する例から、現代の非正規戦で専門スキルを生かすケースまで、多様な形が見られます。
上の例に共通するのは、戦争・紛争の様相(人員需要、イデオロギー、地域文化)と個人の適性・訓練機会が重なった結果として女性狙撃手が現れた点です。
共通して言えるのは、女性の小柄さや忍耐力、観察力が「待ち伏せ型狙撃」に適していた点で、戦術的価値が認められてきたということです。
しかしながら、「戦闘員としての女性兵士」は当時では普遍的な構図ではありませんでした。当時の諸外国軍では主にソ連(赤軍)のみが女性兵士の大規模・組織的な養成を行っており、当時のアメリカ軍やドイツ軍などでも戦闘員として女性兵士は動員しておらず、衛生や通信といった後方支援に限っていました。
これらについては以下の章で掘り下げています。

関連リンク
- 対物ライフルで兵士を撃ってはいけないはウソ? —
(対物ライフルの法的・倫理的制約を論じた解説記事) - 陸上自衛隊、新たな対人狙撃銃:ヘッケラー&コッホ社製HK G28 E2を調達 —
(HK G28 E2 の導入を伝えるニュース/解説) - 陸上自衛隊はなぜ狙撃銃を導入してこなかったのか —
(狙撃銃導入の歴史的背景と理由を考察した記事) - 敵の恐怖心を煽り、進撃遅滞させるスナイパーの運用は心理戦でもある —
(狙撃運用の心理戦的効果を論じた考察) - 陸上自衛隊も配備する「バレット対物ライフル」シリーズの驚くべき実力 —
(バレット社製対物ライフルの性能解説と陸自導入の文脈) - 陸上自衛隊が導入した対人狙撃銃「M24 SWS」の実力 —
(M24 SWS の技術解説と運用評価)