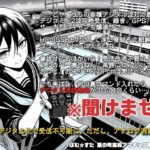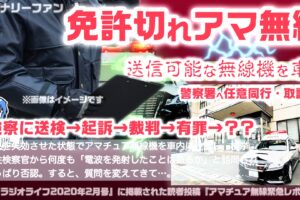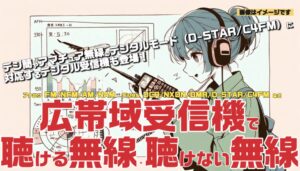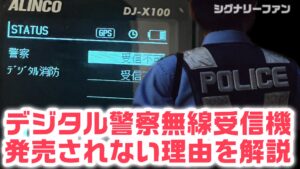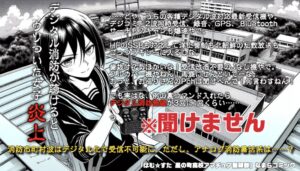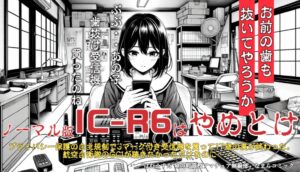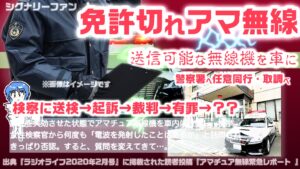日本では国家資格であるアマチュア無線技士の級は全部で4つ。
それぞれの級とアマチュアの『アマ』をつけて『○アマ』と略されるのが一般的です。
取得には国家試験と『養成課程講習会』があり、最上級の1アマ以外は養成課程講習会でも取得が可能です。
上級になるにつれ、使用できる周波数帯域と送信出力が拡大。
これは、アマチュア無線家がより高度な技術を学び、広範な通信を探求するための仕組みです。
それでは日本のアマチュア無線技士資格のそれぞれの級の違いをご説明いたします。
第1級アマチュア無線技士(1アマ)
第1級アマチュア無線技士(通称1アマ)は、アマチュア無線技士の中で最上級の資格です。試験レベルは短大卒以上とされていますが、時には小学生が挑戦することもあります。実際、1996年5月20日の朝日新聞によると、三重県四日市市に住む小学4年生が、9歳7ヶ月で1アマに合格したという話が紹介されています。それまでの最年少記録は12歳3ヶ月でしたが、この小学生の合格により、その記録は大幅に更新。

その小学生の試験対策は、「漢字や計算方法を丸暗記し、勉強した範囲以外の問題は諦める」という戦術だったそうです。
モールスの実技試験が廃止されてから、1アマの合格率は20%から40%に急上昇しています。
1アマの操作範囲は「アマチュア無線局の無線設備の操作」となり、これには「アマチュア局に許可されたすべての周波数とモード、最大1kWまでの操作」が含まれます。
1アマ以外で、同じ操作範囲を扱う資格には第1級および第2級総合無線通信士があります。
1アマの試験は、財団法人日本無線協会が年3回(4月、8月、12月)に実施しています。試験地は東京都、札幌市、仙台市、長野市、金沢市、名古屋市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、那覇市の10都市です。令和5年度の受験料は9,600円で、これは4つの級の中で最も高額です。
総務省の平成21年度「通信白書」によると、1アマの資格を持つ人はアマチュア無線技士全体の0.7%、約26,000人にあたります。
第2級アマチュア無線技士(2アマ)
-
- 第2級アマチュア無線技士の主な操作範囲
- アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作
- 第2級アマチュア無線技士と同等の操作範囲を免許される他の国家資格
- 第3級総合無線通信士
- 第2級アマチュア無線技士の利点
- 養成課程講習会での取得も可能
- 特定のアニメキャラに想いを重ねることができる
- 4アマと3アマでは免許を与えた者が『総合通信局長』だったが、2アマおよに1アマは『総務大臣』になり、日本人の大好きな権威主義を思う存分堪能できる
- 第2級アマチュア無線技士の主な操作範囲
工学の難易度は3アマ、4アマでできた暗記では難しくなりますが、旧試験と比較すると容易です。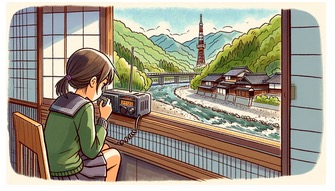 現在では1アマ同様に通信術の実技試験もなく、モールスの知識を確認することに主眼が置かれ、法規の中にモールス関連問題が出題されます。法規は4アマ、3アマと段階を踏んで合格してきた人ならば、暗記は容易。
現在では1アマ同様に通信術の実技試験もなく、モールスの知識を確認することに主眼が置かれ、法規の中にモールス関連問題が出題されます。法規は4アマ、3アマと段階を踏んで合格してきた人ならば、暗記は容易。
法で定める2アマの操作範囲は”アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作”です。周波数は1アマ同様です。なお、2アマの操作範囲を行える他の従事者資格には「第三級総合無線通信士」があります。
令和5年度時点で2アマの取得方法は年に3回行われる国家試験のほか、ついに2015年からは養成課程講習会も開始。なお、JARD主催の養成課程講習会の費用は7万円程度になっています。
試験地は1アマ同様です。受験料は令和5年度時点で、7,800円です。総務省の平成21年度版「通信白書」によれば、2アマの資格者数は75.000人。これはアマチュア無線技士全体の2.3%です。
なお、テレビアニメに登場する高校生の女性キャラクター『武部沙織』が2アマを取得し、無線の知識を部活動で役立てていることから「俺も2アマ取って彼女に想いを馳せたい」という成人男性が多くいたようです。
第3級アマチュア無線技士(3アマ)
-
- 第3級アマチュア無線技士の主な操作範囲
- アマチュア局の無線設備の操作(空中線電力50ワット以下で18MHz以上又は8MHz以下)
- 10MHzおよび14MHzの操作は不可
- モールス通信が可能
- 第3級アマチュア無線技士と同等の操作範囲を免許される他の国家資格
- 3アマの操作範囲のみに該当する他の国家資格はなし
- 第3級アマチュア無線技士の利点
- モービル運用が目的なら最大出力の50Wまで出せる
- モールス通信ができることで、より遠距離の交信(DX)が可能
- 第3級アマチュア無線技士の主な操作範囲
3アマから法規の中にモールスに関する問題が出題されます。つまり、モールスは3アマから初めて許可されます。4級を取得していれば、養成課程講習会にて3アマを取得することも可能です。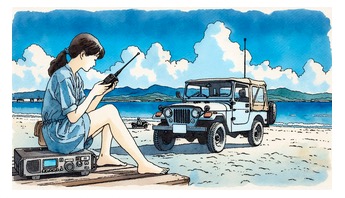
法で定める3アマの操作範囲は”アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18メガヘルツ以上または8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作”です。
最大で50Wまでの出力が許可され、モービル運用だけ楽しみたい方は3アマまで取得してしまえば、事実上なに不自由なく法で規定された『移動するアマチュア局』に許可される上限で運用可能。
令和5年度時点で3アマは全国各地にあるテストセンターにてCBT(Computer Based Testing)方式の国家試験により、年間を通じて実施されます。
受験者はPC画面上に表示された多肢選択問題に対してマウスを用いて正答の番号を選び、解答します。CBT国家試験についてはこちらをご覧ください。
または養成課程講習会で講習と修了試験を経て取得が可能です。国家試験の受験料は令和5年時点で5,400円です。
なお、総務省の平成21年度版「通信白書」によれば、3アマの資格者数は20万人と、全アマチュア無線技士の6%です。3アマ同等の操作範囲が行える他の従事者資格は現在のところ、ありません。
第4級アマチュア無線技士(4アマ)
- 第4級アマチュア無線技士の主な操作範囲
- アマチュア局の無線設備(無線電信を除く)の操作(空中線電力20ワット以下で30MHz超もしくは空中線電力10ワット以下で21MHz以上30MHz以下又は8MHz以下)
- 10MHz・14MHz・18MHzは操作不可
- モールス通信は不可
- 第4級アマチュア無線技士と同等の操作範囲を免許される他の国家資格
- 第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士、第4級海上無線通信士、航空無線通信士、第1級陸上無線技術士、第2級陸上無線技術士
- 第4級アマチュア無線技士の利点
- もっとも試験が容易
- 5.8GHz帯を使うFPV(First Person View)ドローン操縦が可能。※開局が必要
小学生でも楽に合格できるほど、やさしい国家試験になっていますが、さらに優しい養成課程講習会でも取得できます。
4つの級の中で唯一、モールス通信が免許されず、よってモールスに関する問題は出題されません。
法で定める4アマの操作範囲は”アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信を除く) 1 空中線電力10W以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまでまたは8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの 2 空中線電力20W以下の無線設備で30メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの”です。
144MHzや430MHzでもアンテナ次第で数百キロもの広範囲で交信可能です。また、4アマでは現在、3.5MHz、3.8MHz、7MHz、21MHz、24MHZ、28MHzの各HF帯バンドが許可されており、HFを楽しみたい方も4アマでOK。ただし、モールス通信は許可されず、CWを楽しみたい方は3級を目指しています。
令和5年度現在、4アマは3アマ同様、CBT試験または養成課程講習会で講習と修了試験を経て取得が可能です。国家試験の受験料は令和5年時点で5,100円です。
なお、総務省の平成21年度版「通信白書」によれば、4アマの資格者数は300万人です。これは実に全アマチュア無線技士の90%です。
4アマの操作範囲を行える無線資格は第1級海上無線通信士、第2級海上無線通信士、第4級海上無線通信士、航空無線通信士、第1級陸上無線技術士、第2級陸上無線技術士となっています。
なお、「特殊無線技士」の資格で、アマチュア無線を運用することはできません。
おまけ 国外のライセンス制度
記事の冒頭で『日本では』と断りを入れた理由はアメリカ、ドイツ、オーストラリアなど各国によってアマチュア無線の資格の分類数が違うからなのです。
例えばアメリカでは最も初級の「テクニシャン・クラス」、中間の「ジェネラル・クラス」、そして最上級の「エクストラ・クラス」の三つのみ。
また、日本と違って、はじめから最上級の試験を受けることはできず、下から順番に受験して合格しなければなりません。
さらに、アメリカのライセンスは包括免許のため、従事者免許証と無線局免許状が1つになっているのも特徴です。なお、日本人でも取得することが可能です。
参考サイト様 http://ja1yuu.blog.fc2.com/blog-entry-30.html
アマチュア局が免許を受けることができる周波数帯と、免許を受けることができる空中線電力、さらにアマチュア無線が運用できる業務用無線従事者資格、外国のアマチュア無線資格で操作できる範囲などについてさらに詳しくお知りになりたい方はJARL公式サイトでご確認ください。
http://www.jarl.or.jp/Japanese/6_Hajimeyo/shikaku.htm
最後に
各級において受験要項や受験料の改定が行われている場合があるため、受験に際しては必ず事前に日本無線協会の公式サイト等にて詳細をご確認していただけるようお願い申し上げます。