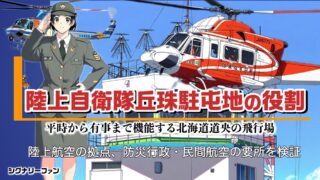陸上自衛隊は「対人地雷を戦術的に配備している」わけではなく、1999年の条約(オタワ条約)に基づきおおむね廃棄を完了した上で、除去訓練や探知技術の研究・教育目的に必要最小限の地雷を保持している、というのが事実です。
しかし、実は同様の装備は、今なお自衛隊で配備されています。
対人地雷の廃絶後、自衛隊は「対人障害システム」など、条約上の対人地雷には該当しない代替手段を整備しているのです。
「対人障害システム」は、簡単に言えば、リモコンで爆破できる遠隔式地雷です。
これは、人間が操作できるため、戦争終結後も無差別に民間人に被害を与える対人地雷の持つ危険性を排除するための装備です。
まずは、地雷が廃止された流れを見ていきましょう。
対人地雷の廃止と条約批准
冷戦期から1990年代にかけて、多くの国が対人地雷を備蓄していました。
日本もかつては大規模な在庫を保有していましたが、1997年に採択された対人地雷禁止条約(通称:オタワ条約)に参加し、1999年に批准しました。条約の要求に従って在庫の破壊を進め、2003年2月に主要な破棄が完了したと政府は発表しています。
政府記録や当時の報道でもその完了が報じられています。
地雷問題・対人地雷禁止条約(オタワ条約)の概要 | 外務省
この条約は、対人地雷の全面的な廃止を目的とする国際条約であり、締約国には対人地雷の開発、製造、保有、使用、他国への移譲などが禁じられています。
また、既存の対人地雷については、一定期間内に完全廃棄することが義務づけられています。
これに基づき、自衛隊が保有していた対人地雷も順次処分され、2003年にはすべての対人地雷が廃棄されました。同年、北海道美唄市にある日本油脂(当時)にて地雷の爆破処理作業が実施され、その様子は政府首脳にも中継されました。
当時の小泉純一郎首相は、「人道的見地から日本はアジア太平洋地域の中で率先して条約を締結した。本日の廃棄が世界全体の対人地雷撤廃の弾みとなることを期待する」と述べ、自衛隊の今後の防衛体制についても万全を期す姿勢を示しました。
アメリカもロシアも中国も批准していない
先進諸国や多くの途上国が批准して対人地雷の使用・生産・備蓄を禁止し、人道主義を体現したかのようなオタワ条約ですが、キューバ、エジプト、インド、イラン、イスラエル、ミャンマー、パキスタン、ロシア、韓国、シリア、米国は、1997年以来の毎年国連総会が実施するオタワ条約の普遍化と全面実施を呼びかけるための決議を棄権し、オタワ条約に参加するつもりのないことを表明しています。
このため、条約の枠組みに従う国と従わない国が混在する「不公平な国際環境」になっているのが実情です。
陸上自衛隊が教育・訓練目的でごく限定的に対人地雷や地雷模擬装置を保持している理由の一つは、国際条約を遵守している日本にとって、敵(具体的な国を言えませんが)が対人地雷を使用する可能性がある現実的リスクに備える必要があるためです。
陸上自衛隊の対人地雷廃棄と「対人障害システム」への移行
しかし、自衛隊では「地雷」に相当する武器が消えたわけではありません。ここでは、自衛隊の新たな「対人障害システム」について詳しく見ていきます。
条約の抜け道か?対人障害システムとは何か
オタワ条約により、自動的に作動する従来型の対人地雷は全面的に禁止されましたが、条文上の定義の範囲外とされる「遠隔操作型の爆発物」については、一定条件のもとで保有が可能とされています。
この条約の「抜け穴」に相当するのが、自衛隊が現在配備している「対人障害システム」です。このシステムは、アメリカ軍のM18A1クレイモア地雷と同様の構造を持つ、指向性散弾(FFV 013)を中核としています。
これらは、遠隔操作によって使用者の判断で起爆させる形式であり、オタワ条約に定義される「自動的に作動する地雷」には該当しないとされています。
FFV 013などの指向性散弾は、半円形の本体内部に多数の鋼球と爆薬が装填されており、前方一定範囲に殺傷効果を持つ散弾を放出します。陸上自衛隊では、これらを「地雷」ではなく「指向性散弾」や「対人障害装置」と呼称しており、通常の地雷とは区別しています。
M18A1クレイモア地雷本体には、誤って逆方向に設置した場合には自軍への被害の危険があるため、本体に「FRONT TOWARD ENEMY(この面を敵に向けよ)」などの警告表示が明記されており、訓練においてもその取り扱いは厳重に指導されています。
退役した兵器と現存する装備
条約による装備変更の具体例─87式地雷散布装置の一部廃止
自衛隊が保有していた87式地雷散布装置は、車両やUH-1などのヘリコプターから自動的に地雷を広範囲に散布できる装備であり、1980年代末から配備されていました。
特にヘリコプター搭載型の散布装置は、戦術的機動性に優れる一方、人道的観点から問題視される自動散布型対人地雷を搭載していたため、オタワ条約批准を受けて対人地雷散布用の機能は廃止・撤去されました。

「対戦車地雷」との混同に注意
対人地雷と対戦車地雷は法的にも運用上も異なります。対戦車地雷はオタワ条約の対象外であり、各国が異なる扱いをしています。
日本の装備や政策議論の中で、対戦車地雷や他の防御手段を巡る議論があるため、「地雷全般」の話と「対人地雷」の話を混同しないよう注意が必要です。
一方、87式地雷散布装置では「対戦車地雷」の散布能力は条約の対象外であるため、引き続き使用可能とされており、一定の改修を経たうえで現在も装備の一部として残されています。
敵地雷への対抗手段
地雷原に対応する自衛隊のカウンター装備
地雷は敵部隊にとって極めて効果的な防衛手段であるため、これに対処するためのカウンター装備も自衛隊に整備されています。
たとえば、戦車の車体前面に回転式のローラーを装着し、走行しながら地雷を物理的に爆破処理する「マインローラー」や、爆薬を巻いたロープをロケットで地雷原に射出して爆破することで人員や車両の通行できる道を開く「92式地雷原処理車」などが代表的です。
敵勢力が設置した地雷や即席爆発装置(IED)に対応するため、陸上自衛隊では以下のような装備を保有・運用しています。
| 装備名称 | 概要 | 主な用途 |
|---|---|---|
| マインローラー式処理装置 | 戦車の前方に回転ローラーを装着し、機械的に地雷を起爆させる | 行軍路・前進経路の安全確保 |
| 92式地雷原処理車 | 爆薬を装着したロープ(ラインチャージ)をロケットで地雷原へ射出し、地雷を誘爆処理する | 地雷原の通路開設(爆破開道) |
類似技術:アメリカ軍の非致死性兵器
参考までに、アメリカ軍ではクレイモア型の対人地雷に加えて、「機動阻止システム(Mobility Denial System)」と呼ばれる非致死性装備も存在します。これは、ヌルヌルした粘性のある液体を散布し、敵兵士や車両の動きを物理的かつ一時的に制限するもので、地雷や爆薬とは異なる非殺傷的な運用が可能とされています。
このような非致死的(ノンリーサル)兵器は、戦術的効果を保持しながら、戦後処理や捕虜対応の観点でも有用とされており、自衛隊でも将来的な導入が検討される可能性があります。
まとめ
「対人地雷を単に別の名称にして残しているのではないか」という疑問はよく出ます。これに対する日本と国際ルール上の立場は次の通りです。
-
オタワ条約は原則禁止だが、完全なゼロを強制するものではない
条約自体は対人地雷の使用・生産・備蓄・移転を禁止しますが、例外的に探知・除去・除去技術研究のための最小限の留保を認めています(Article 3)。これを各国は年次報告(Article 7)で透明性をもって報告することになっています。 -
日本は「大量備蓄」を破棄した上で、留保は教育・除去訓練など限定的な用途に限定している
日本の最新の年次報告(Article 7報告)でも「教育・訓練のために保有・使用している」と明記されており、保有数や用途は毎年見直す旨が記されています。
このように、自衛隊の地雷・障害装備は、国際条約を厳守しつつ、現実の戦術環境に即した形で進化を遂げています。
「地雷」という語が消えても、機能としての「対人障害」はなお存在し続けているというのが、現在の装備体系の本質といえるでしょう。
また、自衛隊内部では、演習中のトイレを暗語的に「地雷を埋めに行く」と呼ぶ慣用表現があります。