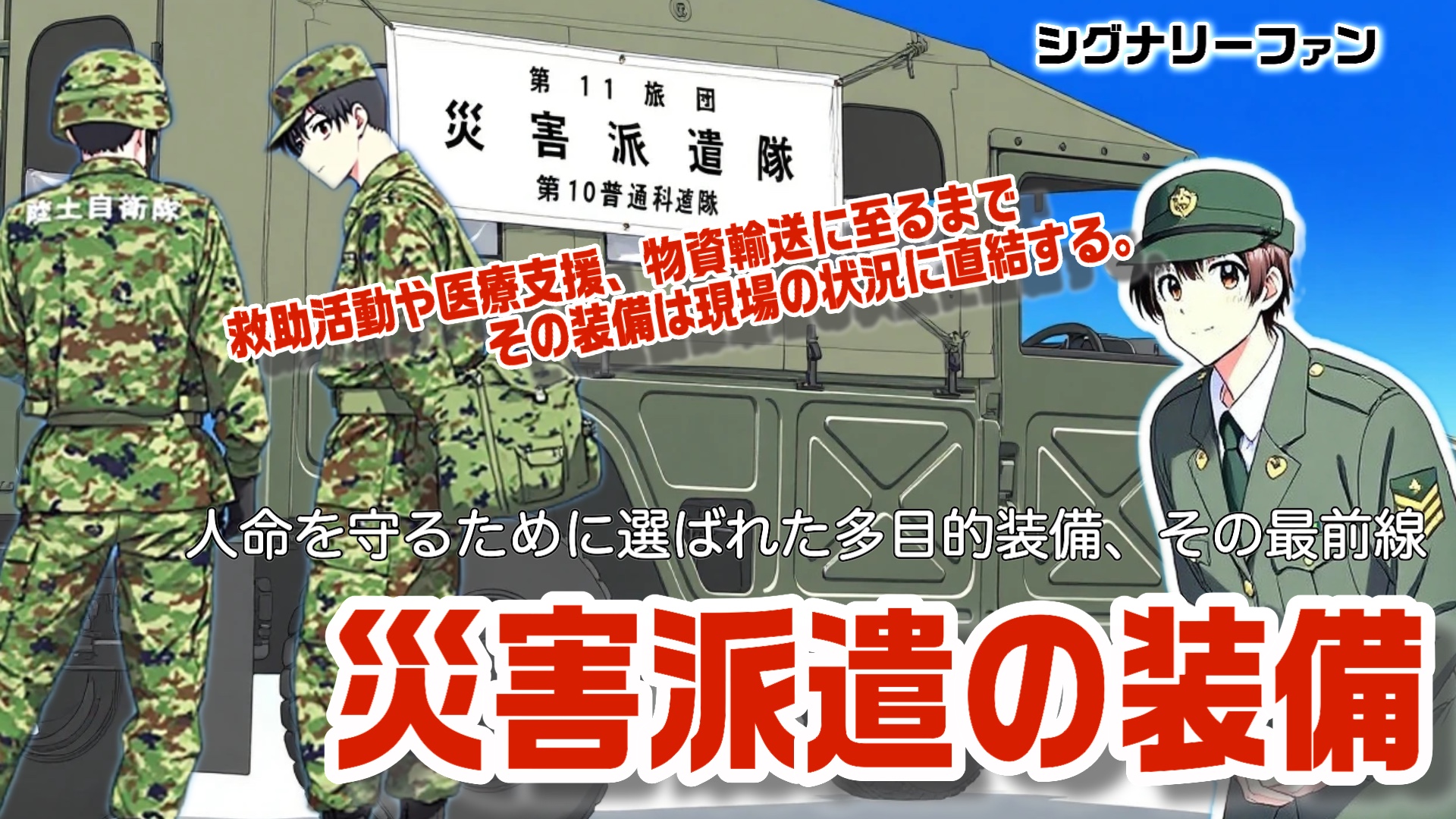航空自衛隊および海上自衛隊における操縦士養成制度の一つに、「航空学生」が存在する。これは、主に高校卒業(または卒業見込み)者、中等教育学校卒業(または見込み)者、高等専門学校3年修了(または見込み)者、あるいはそれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象に実施されている採用制度である。
航空学生制度に採用された場合、防衛省の教育課程に基づき、将来の自衛隊航空要員として必要な教育訓練を受けることとなる。養成後の配置先としては、戦闘機、輸送機、哨戒機など多岐にわたる航空機種が含まれている。
この制度は、自衛隊航空操縦士を養成する主要な経路の一つとされており、採用後は厳格な適性判定や段階的訓練課程が進められる。なお、操縦士としての適性が確認された場合に限り、操縦訓練課程が進行するが、操縦適性を満たさないと判定された場合は、他の職域に転換される制度上の運用も定められている。
操縦職以外の進路としては、たとえば固定翼哨戒機(P-3C、P-1等)における「戦術航空士(TACCO)」の職域があり、同乗して戦術情報の分析・指揮等を担当する要員としての養成も行われている。
航空学生は極めて高い水準の規律と訓練環境
航空学生制度の教育課程は、極めて高い水準の規律と訓練環境が設定されていることで知られている。教育課程中は上級学生への厳格な上下関係が維持され、教官の指導は制度上極めて重い権限を有して実施される。訓練期間中の規律違反や成績不良が認められた場合、制度上は退学処分(除隊措置)となる場合がある。身体的負傷等により航空訓練の継続が困難と判断された場合も同様に除外措置(エリミネート)が採られることが制度上明記されている。

このように航空学生課程は、操縦要員候補生としての適性を厳格に判定し、段階的に絞り込む養成制度となっている。他方、操縦適性を満たさないと判定された場合においても、自衛官としての身分は維持され、他職種への配置転換措置が講じられる制度運用が行われている。
なお、航空自衛隊および海上自衛隊の操縦要員養成制度は、航空学生制度以外にも複数存在している。たとえば、防衛大学校卒業後に航空要員として指定される経路、あるいは一般大学等を卒業後に一般幹部候補生として採用され航空要員適性検査を経て選抜される経路がある。いずれの制度においても、操縦要員として選抜されるには厳格な適性判定が課せられている。

陸上自衛隊においては、航空操縦士を初期募集時点で直接採用する制度は存在せず、陸曹航空操縦課程あるいは幹部操縦課程等に進む制度設計が採られている。これらの課程もまた、操縦適性や訓練成績に基づき選抜が進められる仕組みとなっている。
【航空学生出身の著名人】
航空学生制度の出身者の中には、一般社会においても活動している著名人が存在している例が報告されている。たとえば、漫画家のたなかてつお氏、軍事評論家の高部正樹氏などが挙げられている。これらの事例は、航空学生制度を経た後に多様な進路を選択した事例の一部として紹介されることがある。
【視力の壁にご注意を! レーシックはNG】
航空学生制度においては、航空身体検査基準の一部が平成20年(2008年)9月1日付で緩和された経緯がある。この緩和措置により、一部の身体条件については基準が見直されているが、視力に関する基準については依然として厳格な条件が定められている。
航空学生採用における身体検査基準では、「近視矯正手術(オルソケラトロジー等を含む)を受けていないこと」が応募資格要件に明記されている。これにより、レーザーを用いた角膜屈折矯正手術(いわゆるレーシック手術)を受けた者は応募対象外となる。
日本眼科学会によれば、レーシック(LASIK)手術とは以下のような医療行為である。
LASIKは、フェムトセカンドレーザーというレーザーを用いて角膜の表層に「フラップ」と呼ばれる薄い膜を作り、それをめくって角膜実質を露出させます。そこにレーザーを照射して角膜実質の一部を切除し、角膜の屈折力を変化させて視力を矯正する手術です。
(出典:日本眼科学会公式サイト https://www.nichigan.or.jp/public/disease/treatment/item08.html)
このように、レーシック手術は外科的な屈折矯正手術であり、航空学生採用制度では現行基準においてこれを受けた者の応募は認められていない。
【航空学生の受験概要案内】
航空学生制度における視力に関する応募基準(防衛省公式基準より)
防衛省が公表している航空学生採用試験における視力基準は、以下のとおり定められている(出典:防衛省公式サイト・FAQ)。
-
片眼の遠距離裸眼視力または矯正視力:0.7以上
-
両眼の裸眼視力または矯正視力:1.0以上
-
中距離裸眼視力または矯正視力:0.2以上
-
近距離裸眼視力または矯正視力:0.5以上
-
近視矯正手術(オルソケラトロジー等を含む)を受けていないこと
-
視力矯正手段としては眼鏡のみ使用可能であり、コンタクトレンズの使用は不可
これらは防衛省が公式に示している航空要員の身体検査基準の一部であり、レーザー角膜矯正手術(いわゆるレーシック手術)を受けた者は応募資格を有さないとされている。
また、オルソケラトロジー(特殊なコンタクトレンズを就寝時に装着して角膜形状を変化させる視力矯正手法)についても、同様に応募資格を制限する要件の対象となっている。
関連文献として、自衛隊が公式協力した宮嶋茂樹氏の著書『自衛隊レディース 空飛ぶ大和撫子』では、角膜手術後の眼圧検査における影響可能性についても記述されている事例がある。これにより、航空学生制度では屈折矯正手術歴の有無が厳しく確認対象となっている状況がうかがわれる。
(出典:宮嶋茂樹著『自衛隊レディース 空飛ぶ大和撫子』)
航空自衛隊パイロットの視力管理について
航空自衛隊の公式サイトには、戦闘機パイロットの視力維持および向上に関する記述が掲載されている。具体的には、天候の良い日には遠方を見るなど視力の維持に努めるよう推奨している。
(出典:航空自衛隊公式サイト)
また、航空自衛隊では、視力に良いとされるブルーベリージュースをパイロットに提供するなど、視力管理に関連した取り組みを行っている。
(出典:防衛省公式サイト)
以上のように、航空学生試験やパイロット養成において視力は重要な要素の一つとされている。
(出典:http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/omosiro/omosiro11.html)
航空学生の試験と身体検査
航空学生の選考試験には筆記試験と身体検査が含まれている。受験者は全国の進学校から選抜された優秀な学生が多く、基礎学力が特に重視されている。数学や英語などの科目において高い能力が求められる。
ただし、学力だけで合格が決まるわけではなく、パイロットとしての適性も重要視されるため、操縦の実技試験が実施される。
身体能力を測る警察や消防のような腕立て伏せや腹筋などの体力テストは課されないが、航空学生の3次試験においては、実際に練習機に搭乗しての飛行実技試験が行われる。
試験内容としては、離着陸は教官が担当する一方で、上空での基本的な操縦操作(上昇、旋回など)を受験者自身が行う。飛行試験は複数の段階(CP-1~CP-4)に分かれており、飛行手順の理解と正確な実行が評価される。
単に手順を暗記するだけでなく、限られた時間内にいかに正確に操縦できるかが重要とされる。
採用後の教育
航空学生として採用されると、正式な自衛官として約2年間の基礎教育が行われる。初期の期間は集団生活を送りながら、基礎的な教育や規律訓練を受け、その後に飛行訓練へと進む。飛行訓練はプロペラ機から始まり、次に亜音速ジェット機のT-4での操縦訓練が実施される。
パイロットにとって英語力は重要な要素であり、航空管制や米軍との共同訓練では英語でのコミュニケーションが求められる。航空自衛隊では英語教育を充実させているため、十分な英語能力が訓練の円滑な進行に寄与する。
Eチェック判定とエリミネート
訓練期間中、成績不良や学習意欲の不足が認められた場合、「Eチェック判定」が課されることがある。この判定は、合格に向けた最後のチャンスを示し、パイロットとしての適性が改めて試される。
努力を重ねてこの判定を乗り越える例の一つとして、こうした経緯は自衛隊がとくに好んで広報などで紹介されることもある。
一方で、Eチェック判定をクリアできない場合や怪我などで訓練継続が困難な場合は、「エリミネート」となり、パイロットコースから外れることを意味する。これにより、ウイングマークの取得ができず、パイロットとしての道は閉ざされる。
F転について
「F転」とは、戦闘機パイロットの候補者が救難機や輸送機のパイロットへと配属変更されることを指す。戦闘機パイロットの道は断たれるが、パイロット候補生としての資格は継続される。
航空学生の教育機関
航空学生の教育は山口県防府市にある第12飛行教育団を中心に行われている。ここでは約2年間にわたる基礎教育が実施され、「航空学生課程」や「地上準備課程」、初級操縦課程が含まれる。場合によっては、他の教育団での訓練も行われることがある。
約2年間、座学を中心とした基礎教育を受けて修了後、飛行幹部候補生として約2年間の飛行訓練を中心とした操縦教育を経て、パイロットの資格を取得します。その証として「ウイングマーク」を授与されます。さらにその後約4ヶ月から1年で、戦闘機、輸送機、救難機に分かれて教育訓練を受けて、各部隊に配属されます。「初級操縦課程」を修了した後、芦屋基地の第13飛行教育団での「基本操縦前期課程」、または美保基地の第3輸送航空隊での輸送機等の操縦士育成の「基本操縦課程」に進みます。
このようにして、複数のメソッドを用いた教育カリキュラムが行われている。
海上自衛隊における航空学生の教育
海上自衛隊の航空学生は、将来のパイロットや戦術航空士を育成するため、厳格な訓練課程を経て教育を受ける。特に、「幹部航空基礎課程」と「航空学生課程」の2種類の教育ルートが用意されている。

まず、「幹部航空基礎課程」は12週間の短期プログラムで、防衛大学校や一般大学の卒業者など、将来の幹部を対象に航空の基礎を集中して学ぶ内容である。
一方、「航空学生課程」は高校卒業者を主な対象とし、2年間にわたり基礎技術から計器飛行訓練など高度な技術まで幅広く教育が行われる。ここでの教育は、パイロットや戦術航空士として必要な能力を養成することを目的としている。
この教育過程は、将来の幹部としての資質も問われる厳しい環境であり、海上自衛隊の航空エリートを育てる基盤となっている。
海上保安庁パイロットの育成も
なお、海上自衛隊は海上保安庁のパイロット育成も行っており、小月には将来自衛隊のパイロットになる学生と、海保のパイロットになる学生が一緒に学んでいる。
射出座席の脱出訓練と落下傘降下訓練
戦闘機には、パイロットが緊急時に機体から脱出可能な「射出座席(イジェクションシート)」が備わっている。
非常時にパイロットがレバーを操作すると、まずキャノピー(機体の風防)が爆発的に吹き飛び、続いて座席の下部にあるロケットモーターが点火し、パイロットは座席ごと機体外へ射出される。射出後はパラシュートが展開し、安全に地上へ降下する仕組みだ。
しかし、この脱出方法は身体に大きな負担をかける。射出の瞬間には約6G(体重の6倍の重力)がかかり、体が耐えられず意識を失うこともある。
模擬訓練も実施されており、圧縮空気を用いて実際の脱出時に近い加速度を体験する。これも強烈なGを感じる過酷な訓練である。
さらに、海上に脱出した場合に備えて、射出座席には自動膨張式の救命いかだや非常食、救助信号発信装置が装備されている。
米軍の一部偵察機は自決用の毒薬が装備されているとの話もあるが、自衛隊にはそのような装備はない。

海上自衛隊のパイロットや戦術航空士は、陸上自衛隊の第1空挺団で「落下傘降下訓練」も受ける。
この訓練では、
-
高さ80メートルの降下塔から実際に飛び降りる
-
実戦に近い状況での空挺降下を模擬体験
-
恐怖心を乗り越える精神力が求められる
といった過酷な訓練内容となっている。
自衛隊のパイロットになりたい人のために、ガッツリまとめ
-
航空学生には2つのルート(幹部候補生コースと高校卒業コース)がある。
-
空自パイロットは徳島航空基地で計器飛行(計器による操縦)の訓練を受ける。
-
海上自衛隊は海上保安庁のパイロット育成にも協力している。
-
射出座席の脱出訓練は6Gという強烈な加速度を体験する、本物の試練である。
-
空挺降下訓練も必須で、高所からの落下に耐える覚悟が求められる。
- 陸自には航空学生制度がなく、陸曹(下士官)からの選抜か防衛大学校卒業後の航空要員任命によりパイロットを目指す。
つまり、「空を飛ぶ自衛官」になりたいのであれば、脱出・降下訓練を含めた厳しい訓練を乗り越える強い意志と体力が必要となっている。