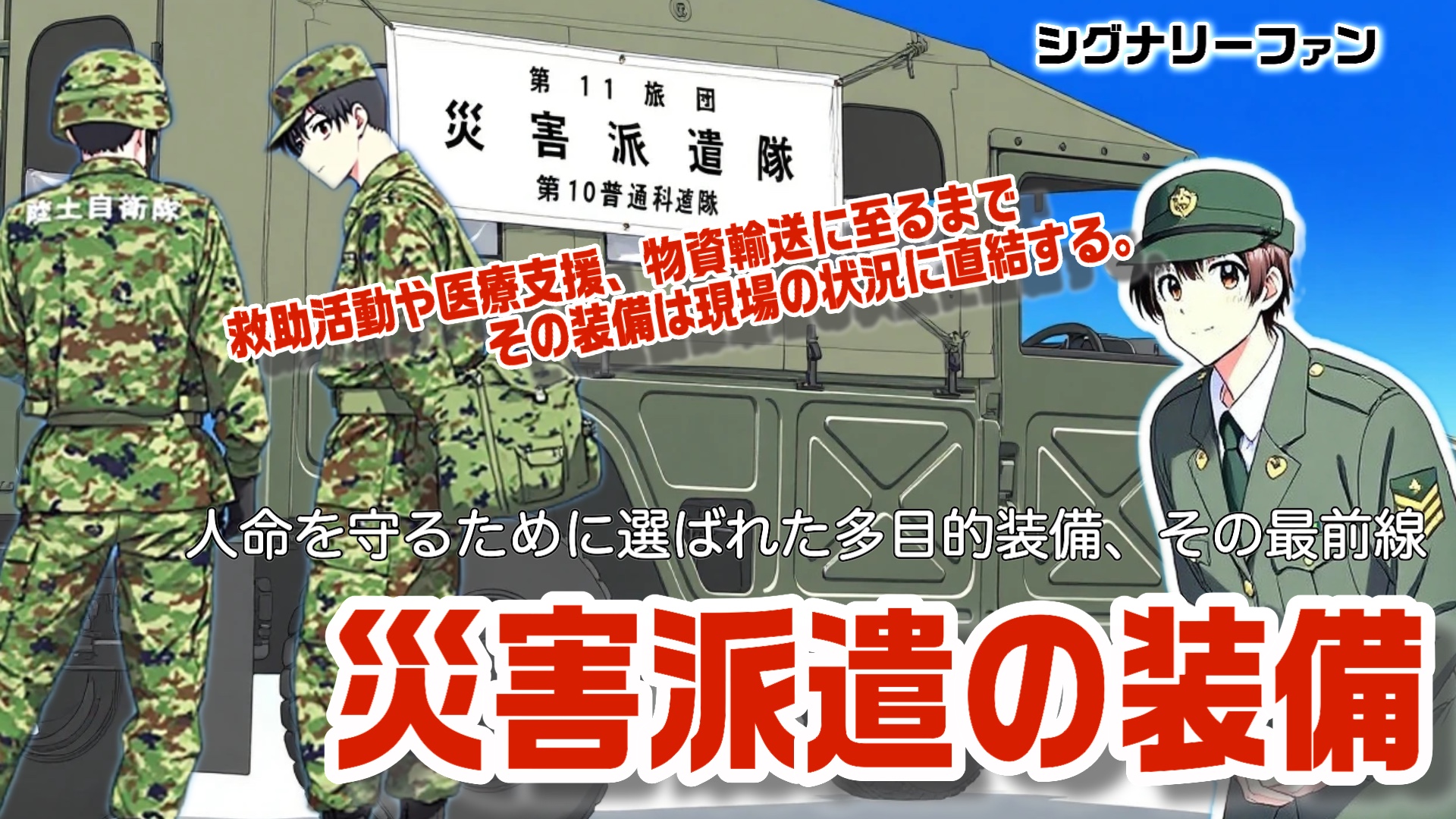アメリカ軍における「OPFOR(Opposing Force)」は、演習や訓練において“仮想敵”として行動し、実戦さながらの戦術状況を再現するために設けられた専門部隊である。
その中核が、カリフォルニア州フォート・アーウィンに設置された「国家訓練センター(NTC: National Training Center)」である。
1981年に正式に運用が開始され、アメリカ陸軍内の指定部隊が「仮想敵軍=OPFOR」として、訓練部隊と定期的に模擬戦闘を行うようになった。
日本でも陸上自衛隊に同種の部隊「部隊訓練評価隊」がある。

OPFORは単なる「敵役」ではない
OPFORは単なる「敵役」ではなく、敵国の兵器・戦術・思考様式を高度に再現し、実戦的訓練環境の提供を目的としている。
この高度にリアルな政治・軍事・社会構造を持つ国家モデルが、Decisive Action Training Environment(DATE)などの演習シナリオの中核となっており、高等軍教育から演習設計に至るまで一貫して使用されている。
ドノヴィア共和国とは
つまり、OPFORとは“敵国”そのものまで仮想的に配置している運用である。
その敵国こそがドノヴィア共和国である。

ドノヴィア共和国は、OPFORが演じる架空国家の代表格で、大規模~複合~電子領域まで取り込んだ統合脅威モデルである。そのモデルは明らかにロシアである。
米陸軍の公式訓練資料(TRADOC, Army University Press, CTC publications)などで、敵国としてのその世界観・地政学・軍事構造は実に詳細に設定されている。
ドノヴィア共和国の概要
ドノヴィア共和国は、長年の軍事的伝統を受け継ぎ、また経済的豊かさを活かして旧軍の残党を近代的な軍隊へと変貌させ、強力な軍事力を維持している。
その教義と戦術は複雑かつ現代的であり、アメリカにとって有能な敵となっている。
同国の軍事力は、民兵や民間軍事会社(PMC)から核兵器や対宇宙能力まで多岐にわたる。
ドノヴィア共和国は、戦術兵器から世界中のどこにでも攻撃可能な戦略大陸間弾道ミサイル(ICBM)まで、世界最大の核弾頭備蓄を保有している。
ドノヴィア共和国政府は、数十年前に両国際条約に署名して以来、化学兵器および生物兵器の保有を否定しているが、近年では高度な神経ガスを使用した政治暗殺事件や、軍の研究所から炭疽菌が漏れて100人以上が死亡した事件が発生している。
これらのことから、国際社会はドノヴィア共和国が依然として化学兵器および生物兵器の開発・保管を行っていると評価している。ドノヴィア共和国軍は、戦闘作戦を遂行しながら状況設定やナラティブ活用のためのマルチドメイン作戦(MDO)も遂行できる。
この強力な軍事力と、積極的な政治アジェンダが相まって、ドノヴィア共和国は世界有数の競争相手となっている。
ドノヴィア共和国は、友好国として親西側独裁国家であり石油と天然ガス資源を持つ豊かな「アトロピア(Atropia)」、中立国「ギャスタン(Gastran)」なども設定されている。
以上は、米国陸軍訓練教義司令部の決定的行動訓練環境(DATE )に記載されたものを筆者が要約した。
■ アメリカ陸軍における代表的OPFOR部隊:第11装甲騎兵連隊(ブラックホース連隊)
NTCにおけるOPFORの主力は、第11装甲騎兵連隊(11th Armored Cavalry Regiment, 通称“Blackhorse Regiment”)である。同連隊は、OPFORとして長年にわたり他部隊との模擬戦を担当しており、「ソ連軍風の編成・装備・戦術」を採用することで知られている。
冷戦終結後、仮想敵は旧ソ連軍だけでなく、多様な地域紛争や非国家主体も含むようになり、任務もそれに応じて多様化した。湾岸戦争やイラク戦争以降は、ゲリラ、反政府勢力、テロ組織といった非正規戦闘勢力への対応も訓練内容に組み込まれるようになった。また、アジア太平洋地域における演習では、中国や北朝鮮を念頭に置いたOPFORが想定されることもある。
-
駐屯地:ネバダ州フォート・アーウィン(Fort Irwin)内の国家訓練センター(NTC)
-
任務:演習に参加する実戦部隊に対し、架空の敵「ドノヴィア共和国軍」として立ちはだかり、本物の戦争のような戦場環境を作り出す。
- 兵員:OPFOR将兵は、敵国語(ロシア語)も喋るよう教育される。
-
装備:
-
米軍の正規配備車両(M1戦車やM113など)を敵国風に改装し、外観・塗装・装備配置にする。
-
例としてBMPに似せたM113に木製ERAブロックを載せて敵戦車として偽装し、戦術を体現する。
-
ホーエンフェルスでの演習ではスロベニア戦車部隊を招致して強化するなど、多国間・実装備型の訓練が実施されている。
- 電子戦や情報戦、ゲリラ的行動まで再現することもある。
-
■ OPFORの特徴
-
仮想国家の設定
-
NTCで用いられる「ドノヴィア共和国(The People’s Republic of Donovia)」は、ロシアや旧ソ連諸国を模した国家であり、部隊はその「軍隊」として行動する。
-
制服・装備・部隊編制までも仮想国家仕様とされている。
-
-
敵国戦術の徹底研究と実装
-
ロシア、中国、中東諸国の戦法を研究し、それをOPFORが再現。
-
例:縦深戦術、分散型ゲリラ戦術、電子妨害、サイバー攻撃の演習も行う。
-
-
演習のリアリティの追求
-
OPFOR部隊は“わざと負ける”のではなく、本気で勝ちにくる。そのため、演習部隊が敗北することも珍しくなく、実力が試される場である。
-
■ その他の主要なOPFOR拠点
-
フォート・ポーク(ルイジアナ州):統合即応訓練センター(JRTC)
-
小規模な戦闘や市街地戦に特化した訓練が行われる。
-
民間人役やNGO役まで用いて複雑な戦場状況を構築。
-
-
フォート・レナード・ウッド(ミズーリ州)などでも、規模の小さなOPFOR機能が存在。
-
OPFORは、第11装甲騎兵連隊以外にも以下の訓練センターで常設部隊として運用されている。
-
フォート・ジョンソン(ルイジアナ州):1‑509落下傘歩兵大隊(都市戦想定)
-
ホーエンフェルス(ドイツ):1‑4歩兵連隊第1大隊(欧州連合訓練センター)
-
■ 意義と目的
アメリカ軍のOPFOR部隊は、次のような訓練効果を生むために存在する。
-
兵士たちに“未知の戦術環境”を体験させ、即応力を鍛える
-
失敗を演習で経験させ、本番での生残率を高める
-
多国籍任務や市街地戦など、複雑化する現代戦への適応訓練
- 現場ではリアルな装備や言語、模擬戦術が重視され、兵站までOPFOR内部で完結する強固な訓練環境が構築されている