自衛官の制服は、まさに「国を護る者たち」の象徴として威厳と機能を兼ね備えている。
諸外国の軍服に引けを取らないデザインは自衛官の士気を高め、任務への決意を支える重要な役割を果たすという、れっきとした役割がある。
防衛省自衛隊に所属していても、すべての職員が制服を着用するわけではない
自衛官の恒常勤務においては、防衛省から貸与された制服を着用することが原則とされているが、これは戦闘員としての身分と任務を明確に示すと同時に、統制と規律の一環としても機能している。
制服の支給対象は「戦闘員として任務を遂行する自衛官および自衛官候補生」と、防衛大学校および防衛医科大学校、高等工科学校の学生のみである。
また、制服は多様な用途や性別に応じた仕様が整えられている。陸海空の各制服は色彩や意匠を変えており、公式式典では礼装、自衛隊音楽隊には特別デザインの演奏服が用意されている。

演奏服は著名な服飾デザイナー・三宅一生氏が手がけたもの。さらに、妊娠中の女性隊員には、1996年以降「妊婦服(マタニティ制服)」として制式の貸与が行われ、体調と安全に配慮した装いが供給されている。
階級によっても制服の着用形態に違いがあり、准尉・幹部自衛官には私服を含む追加制服の購入・着用が許されている。
これは、長く儀礼・公式行事などに出席する幹部のニーズに応えるための制度であり、売店(PX)で私物用制服の販売も行われている。
以上のように、自衛官が身に纏う制服群は、国防の誇り、任務への忠誠、そして多様な役割への対応を念頭に設計されたものである。
![MAMOR(マモル) 2011 年 07 月号 [雑誌] (デジタル雑誌)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61QdVW767uL.jpg)
また、正規の自衛官であっても、部外での捜査任務に従事する警務隊員や、身分を秘匿して情報収集活動を行う情報科職種の隊員など、一部の特殊任務従事者については、平素から制服を着用する必要がない場合もある。
3自衛隊の制服の特徴
陸上・海上・航空の3自衛隊においては、それぞれ任務の特性や組織文化に応じて異なる制服が用意されている。
陸上自衛隊は2018年、それまでの濃緑の91式から紫紺の16式へと変更している。
海上自衛隊は濃紺を中心とした海軍式の意匠を継承しており、儀礼性と伝統を重んじた装いとなっている。航空自衛隊はグレーやブルーを基調としたデザインが特徴で、航空業務に適した軽快さと機動性が考慮されている。
これらの制服はいずれも、単なる被服ではなく、任務に対する覚悟と責任を可視化するものである。任務の違いはあれど、国を護る者としての共通の精神が、その一着ごとに表現されているのだ。
陸上自衛隊の制服
陸上自衛隊の制服は、部隊創設以来たびたびのモデルチェンジを経て、現行の装いに至っている。陸自発足当時には、米軍から供与された生地を染め直した制服が用いられていた。
たとえば、1958年に採用された「58式冬服」は濃紺を基調とし、また1960年の「60式夏服」は明るいグレーのズボンとシャツで構成されていた。
1970年には茶灰色を基本色とした「70式制服」が登場し、これにより米軍の影響を色濃く残していた初期の制服から脱却。
「91式制服」
さらに1991年、自衛官の年齢層やファッション感覚の変化、そして日本の国土をイメージした色調を取り入れた「91式制服」が制式化された。

写真の出典 アメリカ海兵隊公式サイト「陸上自衛隊士官候補生、海兵隊に学ぶ」http://www.kanji.okinawa.usmc.mil/news/160121-jgsdf.html
若干明るい緑色を帯びた「オリーブドラブ(OD)」は、陸上自衛隊を象徴する色として定着。特に日差しの下では灰色に見えることもあるが、冬服はより濃い色調のODが採用されている。
新制服・16式

出典 https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq/mitinoku/cat4/181/index.html
防衛省は2018年3月22日、陸上自衛隊の新制服として「16式制服」を制定した。1991年に採用された「91式制服」に代わるもので、約27年ぶりの全面的な更新となる。新制服は2018年4月1日以降、各部隊に順次配備され、更新された。
16式制服は、従来の濃緑色から紫紺色を基調とするデザインに改められ、部隊の威容や規律を保持しつつ、機能性や着用性の向上を図っている。特に、式典などにおける着用を想定し、礼装的な要素を備えた仕立てとなっているのが特徴である。
参照;https://www.mod.go.jp/gsdf/news/press/2018/pdf/20180322.pdf
甲武装/乙武装
甲武装と乙武装という分類は、被覆の着用の種別を示す用語である。自衛官の装いに関して、公の儀式などでは「甲武装」、作業服には「乙武装」が規定されている。これは、防衛庁訓令第4号「自衛官服装規則」(昭和32年2月6日)第11条に明記された内容である。
甲武装は、儀式やセレモニー、礼式隊による警衛任務など、威厳を示す場面において適用される装備状態を意味する。具体的には、式典用の正装(第1種礼装など)の上に、白手袋、弾帯(あるいは拳銃帯)、脚絆、必要に応じて鉄帽などが装着され、小銃や拳銃を携行した状態で儀礼的かつ規律ある姿を維持し、行進や儀仗を行う。
参照:http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1956/ax19570206_00004_000.pdf
とくに陸上自衛隊の精鋭部隊である特殊作戦群(SFGp)では、甲武装に覆面という姿で編成式典に登場し、その存在感と異彩を放った。
日本の特殊部隊 2017年 03 月号 [雑誌]: ストライクアンドタクティカルマガジン 別冊
B01N5XYKF6 | SATマガジン出版 | 2017-02-16
一方の乙武装は、作業服(迷彩服)装において適用され、戦闘訓練や日常的な勤務に対応した、隊員としてより実務的なスタイルである。これには迷彩服や中帽、鉄帽などが含まれる。任務や訓練に際して多くの隊員が日常的に着用しているのはこの乙武装であり、機能性と動きやすさを優先した装いである。
したがって、自衛隊では服装規定に基づき、場面に応じて甲武装(儀礼・警衛等)および乙武装(戦闘・恒常勤務)を使い分けする。追号される装備や制服の種類に応じて、目的と機能が明確に反映された制度設計といえる。
2017年に陸自儀仗隊制服が52年ぶりに改正

旧制服と新制服の第302保安警務中隊員 (写真典拠元 時事ドットコムニュース)
典拠元 時事ドットコムニュース(2017/03/30-19:13)
http://www.jiji.com/news/kiji_photos/0170330at82_p.jpg
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017033001135&g=soc
2017年3月30日、防衛省は陸上自衛隊の警務科部隊である第302保安警務中隊および中央音楽隊の制服を52年ぶりに改定ししたと発表。新たな制服は、著名なデザイナーであるコシノジュンコ氏が監修した。
改定された制服の特徴は以下:
-
冬服の変更
従来のオリーブドラブ(オリーブ色)から、鮮やかなブルーへと一新されました。デザインは、かつての「盾の会」の制服を彷彿とさせるスタイル。 -
ネクタイから詰襟へ変更
ネクタイとブレザーのスタイルから、伝統的な詰襟のスタイルへ変更。これは、儀仗をより強調することを意図してのもの。 -
夏服の変更
夏服は白地に赤いラインを施し、日の丸をイメージしたデザイン。夏の暑さにも対応できる、清潔感ある印象を与える制服。
特別儀仗隊は、国賓来日時に第302保安警務中隊から臨時に編成され、重要な儀式や行事で特別な儀仗を行う部隊として活躍している。新しい制服は、そうした重要な任務を担う部隊にふさわしいデザインとして、伝統と現代性を兼ね備えたものとなっています。
一方、新しい制服については、賛否両論があるが、儀仗隊の制服には、デザイン以上に隊員の規律や統一感が重要だとする意見もある。
実際、第302保安警務中隊では、体格や規律の均整が重視されている。制服のデザインがどれほど優れていても、最も重要なのは、隊員一人一人が持つ規律の斉一性である。そのため、隊員の精悍な顔つきや姿勢、体格が統一されていることが、儀仗隊においてはより重要視されている。
この規律による「統制美」を守ることが、特別儀仗隊の使命において非常に大きな意味を持つ。
また、現在のところ特別儀仗隊には女性自衛官は選抜されておらず、伝統的な規律や体格に関する要求が厳しく、現時点で女性隊員の参加には制約があるという現実的な理由があるようだ。しかし、今後の変化や、性別に関係なく選ばれる隊員の条件が変わる可能性もあり、引き続き注目される問題と言える。
海上自衛隊の制服

海上自衛隊の制服制度には、隊員の階級や性別によって明確な違いが存在している。特に注目されるのは、男性海士が着用するセーラー服の存在だ。
セーラーカラーを特徴とするこの制服は、旧日本海軍の伝統を色濃く受け継いでおり、現行の海上自衛隊でも男性海士の象徴的な服装である。一方で、女性海士および海曹以上の男女隊員には紺色のブレザー型制服が貸与されており、セーラー服は支給されない。このように、階級の違いだけでなく性別によっても制服の形状が異なる点が、海自の特徴といえる。

かつては男性幹部に対し、幹部第1種夏服として灰色のブレザー型制服が支給されていたが、現在では白色のツメエリ型制服へと変更されている。こうした変遷は、機能性や視認性、儀礼性の面での見直しが進められてきたことを示している。なお、海上自衛隊の航空学生はセーラー服でもブレザーでもなく、紺色のツメエリ制服が着用されており、他の隊種とは異なる制服体系を持っている。
また、警務隊の男性隊員であっても、階級が士であれば通常の男性海士と同様にセーラー服を着用する。この際には拳銃やジストス警棒を装着したベルトを制服の上から着用し、警務任務にあたる。

セーラー服が海軍伝統の象徴とされる一方で、海自においてはその着用が男性のみに限られているのに対し、アメリカ海軍やドイツ海軍では女性兵士もセーラー服を着用できるなど、国によって制服制度の設計思想には大きな差異があることがうかがえる。
航空自衛隊の制服
航空自衛隊の制服制度は、昭和29年(1954年)の発足当初から、明確にアメリカ空軍の影響を受けて設計されている。創設当時、日本にはまだ自前の空軍装備や制服デザインに関するノウハウが乏しく、米空軍の制度や意匠を範として導入された。そのため初期の制服は、色味や裁断、装飾などの点で米空軍のブルー制服に類似していた。
その後、航空自衛隊は時代の変化や国内事情、任務形態の多様化に応じて制服のモデルチェンジを複数回行っている。特に2008年に実施された制服改定は大きな転換点で、それまでの明るめのブルーグレーを基調とした配色から、より落ち着いた濃紺(ダークブルー)を採用することで、儀礼性と威厳を高めた外観へと刷新された。この際、幹部自衛官の制服には袖に金線の飾線(モール)が加えられ、階級による識別性と格式が強調された。
空自の略帽として使用されるギャリソンキャップは、米空軍の伝統を色濃く受け継ぐ装備の一つである。これは正面に庁章を付し、着用時には額から斜め後方に流れる独特の形状が特徴で、米空軍の象徴的部隊「サンダーバーズ(Thunderbirds)」にちなみ、隊員の間では俗に「サンダーバード帽」とも呼ばれている。
また、空自の制服制度には用途に応じた細分化がなされており、常装(恒常的な勤務服)のほか、儀礼用の礼装や冬季と夏季で異なる季節制服、さらには航空機搭乗者向けのつなぎ型の飛行服(フライトスーツ)も制度上定められている。飛行服は戦闘機パイロットや整備員が任務中に着用し、耐火性や耐候性を重視した素材と設計がなされている。
階級章やネームプレートの装着方法にも明確な基準があり、襟元や肩章、胸ポケット上に配されることで、視認性と統制が保たれている。加えて、女性自衛官向けの制服も男女平等の観点から導入されており、スカート型の制服のほか、任務に応じてズボン型のものも支給される。
このように航空自衛隊の制服は、創設当初からの米空軍的伝統を保持しつつも、日本独自の実情とニーズに合わせて独自の進化を遂げてきた。
自衛官以外の制服
自衛隊においては、自衛官ではないものの、教育訓練機関に所属する者にも制服が貸与されている。防衛大学校、防衛医科大学校、高等工科学校などの生徒・学生たちがその例である。
防衛大学校においては、1992年に女子の入学が初めて認められたが、その際に制定された女子学生用制服は、冬季用として4つボタンの紺色スーツ型上着とスカート、夏季用にはベージュ色のスーツ型上着とシャツという構成であり、当時の女性自衛官と類似したスタイルであった。これらは長らく使用されたが、2003年より男子学生と同様に詰襟型の制服へと変更された。制服の変遷は、教育環境の平等化と任務意識の統一を図る試みの一環であったと考えられる。
一方、陸上自衛隊の付設教育機関である高等工科学校では、制度が少年工科学校であった時代、在籍する生徒も正式な自衛官であった。このため、生徒にもOD色(オリーブドラブ)のブレザー型制服が貸与されていた。だが、総人件費の圧縮や国際的な児童の権利に関する条約(いわゆる「子ども兵士」問題)への対応として生徒制度が改定され、以後は自衛官ではない防衛省職員と位置づけられるようになった。現在では詰襟型の制服が支給されており、制度上も従来とは異なる性格を有している。なお、同校への入校は男子のみとされている。
事務官・技官の服装
自衛隊には事務官・技官も多数勤務しているが、これらは非戦闘員すなわち文官であるため、自衛官のような制服は存在しない。勤務時は一般的にスーツやワイシャツ、ネクタイを着用しており、現場や技術系業務に従事する際には、支給された作業服やOD色のジャンパーなどを羽織ることもある。ただし、駐屯地や基地以外の一部自衛隊施設で守衛任務にあたる事務官については、例外的に警備員風の制服が貸与されている。

制服を着用しない自衛官
自衛官であっても、任務の性質によっては制服の着用が免除される場合がある。広報官がその一例であり、主に民間の対外活動に従事するため、スーツ姿での勤務が一般的である。さらに、警務官が犯罪捜査活動において張り込みや内偵などを行う際にも、任務の必要に応じて私服での行動が認められている。
また、近年新設された情報科職種においても、任務の秘匿性から私服での行動を前提とするケースがある。陸上自衛隊の特殊作戦群(SFGp)では、対テロ訓練の一環として、隊員がラーメン店員を装い、オカモチに発煙筒を仕込んで駐屯地へ侵入するという過激な抜き打ち警備訓練を行った事例もある。
仮装の内容がデルタフォースのようで大胆であるばかりか、意表を突く実行力の高さが示されており、特殊部隊の訓練とはいえ、まさに非日常の光景である。恐ろしい。
自衛隊の簡易服と略帽とは
自衛隊には、法令で定められた制式服以外にも、非公式ながらも一定の条件下で着用が認められている「簡易服」という分類が存在する。簡易服とは、正式な官給品ではなく、各自衛官が自費で購入する私物扱いの被服であり、一定の範囲内で制服と同等に扱われている。主に通勤時や軽作業時に着用されるジャンパーやセーターがこれに該当し、各自衛隊基地内の売店、通称「PX(Post Exchange)」で販売されている。

儀式等の威儀を正すべき場合は着用してはならないと決まっているが、規定に則ったものであれば、着用しても差し支えない。
各自衛隊ごとに配色が異なっており、陸上自衛隊ではOD色(オリーブドラブ)、航空自衛隊では従来の明るいブルーから2008年の制服改定を経て濃紺に変更、海上自衛隊ではブラックが用いられている。いずれも落ち着いた色調で精悍な印象を与え、左袖などには各自衛隊の部隊章が縫い付けられている。また、肩部にはエポレット(肩章取り付け部)が設けられており、階級章の装着が可能である。
自衛隊の略帽
一方、「略帽」も、簡易服として扱われるものの、正式な制服や戦闘服にも合わせて使用できる実用性の高い装備品である。一般に略帽とは、制帽に代わって用いられる簡便な帽子であり、日常業務や移動時、さらには式典などでも使用が認められている。
略帽は自衛隊の防寒ジャンパと同じく、私物で購入するもので貸与品ではない。隊員はPXで自費購入する。
略帽の形状と仕様は自衛隊の各種別によって異なっている。陸上自衛隊では、平成3年に制式化された「91式制服」にあわせて、「91式略帽」が採用された。これはクラシカルなスタイルのベレー型で、色は濃緑。欧州諸国の軍隊に見られるベレーとよく似た形状であるが、正面には自衛隊を象徴する「桜星」の帽章が装着されている。
海上自衛隊も陸自とほぼ同様のスタイルであるが、海上自衛隊の帽章になっている。
航空自衛隊においては、従来型のギャリソンキャップ型略帽が使われており、特に空自ではアメリカ空軍の影響を色濃く残したデザインであることから、「サンダーバード帽」と俗称されることもある。この略帽は、イギリスの空軍由来のデザインで、前後に折りたたむことができる簡便な形状が特徴である。
なお、諸外国軍、とりわけ米軍におけるベレー帽の位置づけは特別である。かつてアメリカ陸軍では、ベレー帽は特殊部隊やレンジャー部隊など、いわゆる精鋭部隊のみに着用が許されていた。その象徴とも言えるのが、「グリーンベレー」の名で知られる陸軍特殊部隊である。
しかし2001年、一般兵士の士気向上を目的に、黒のベレー帽がすべての兵士に許可される改革が行われた。これには歓迎の声があった一方で、特権性の喪失を懸念した特殊部隊からは強い反発も生じた。その後、方針は修正され、現在では指示があった場合のみベレーの着用が許可される体制となっている。
なお、自衛隊は国連の平和維持活動にも参加しているため、国連公式仕様のブルーベレーもある。
ベレー帽は、各国共通で「型出し」が重要視されており、被り方には明確な作法がある。自衛隊においても例外ではなく、隊員はお湯で帽体を柔らかくし、手で形を整える「プレス」の工程を経て、端正なベレーの形を作り出す。これは見た目の美しさとともに、規律と誇りを表す所作として位置づけられている。
自衛官の装具や被服類には、官給品と私物が混在しているという特有の実情があり、その使い分けには各自の裁量とともに、一定の職務規定が関わってくる。略帽や簡易服もまた、その象徴的な存在として自衛官の日常に密着しているのである。
自衛隊の制服のまとめ
自衛隊の制服の種類は3部隊で異なり、海上自衛隊のように階級や性差で異なる制服を着用する例もある。また、職種によっては必ずしも制服を着用するとは限らない場合もある。
以上、自衛隊の制服について簡略で概要を紹介した。なお迷彩服については以下の記事で解説している。






















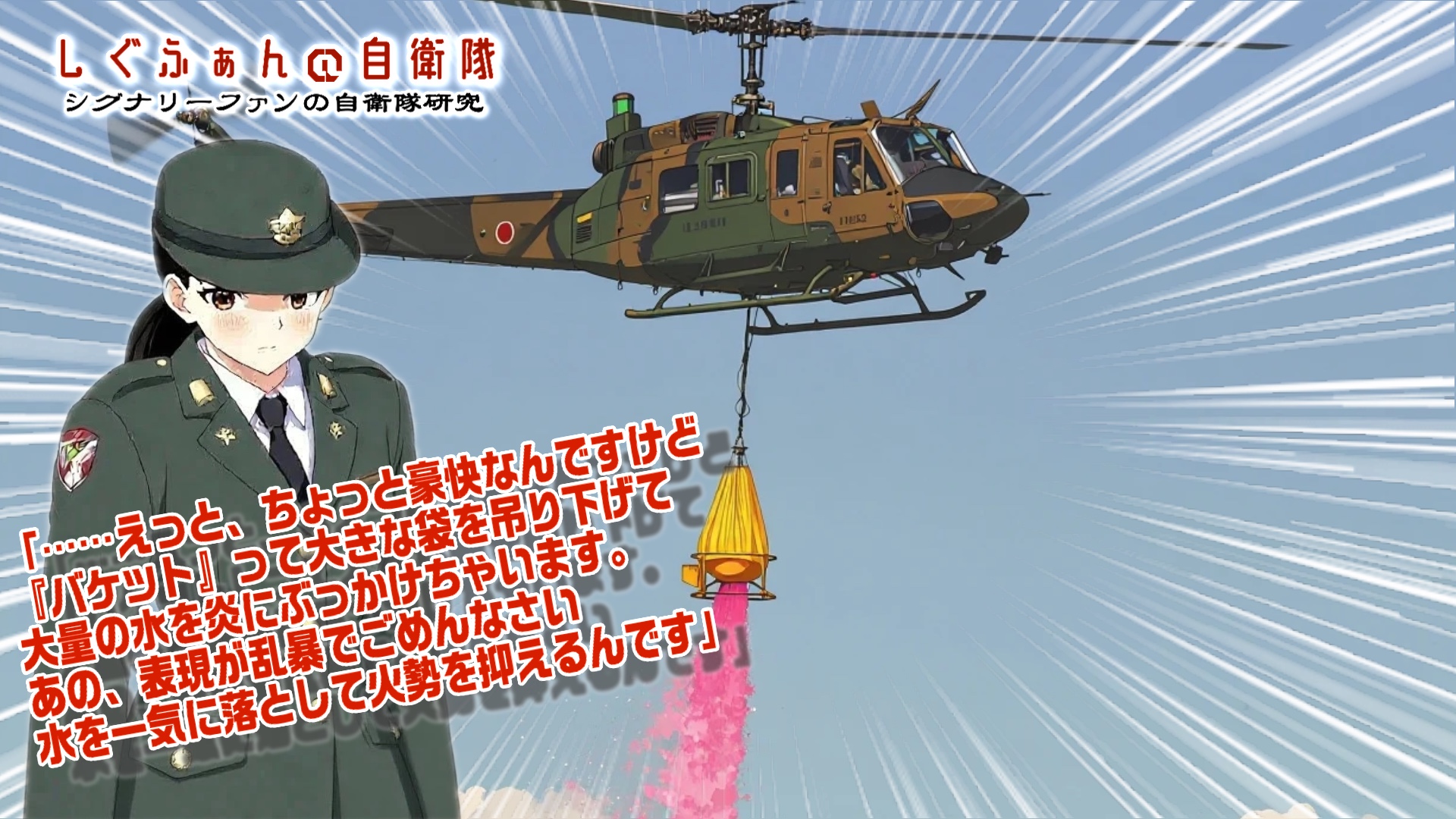

































































![ストライクアンドタクティカルマガジン 2020年 03 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51DPYFfjSvL._SL500_.jpg)
![日本の特殊部隊 2017年 03 月号 [雑誌]: ストライクアンドタクティカルマガジン 別冊 日本の特殊部隊 2017年 03 月号 [雑誌]: ストライクアンドタクティカルマガジン 別冊](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51IzUTm2mEL.jpg)


![[assy] 自衛隊グッズ 海上自衛隊 簡易 ジャンパー ネームベルクロ付 M【燦吉】](https://m.media-amazon.com/images/I/51ly5cezJlL._SL500_.jpg)
![[ロスコ] US. スペシャルフォース ベレー帽(G.I. Type Inspection Ready Beret)【ブラック/7.75インチ】](https://m.media-amazon.com/images/I/31zeQDW8iWL._SL500_.jpg)
