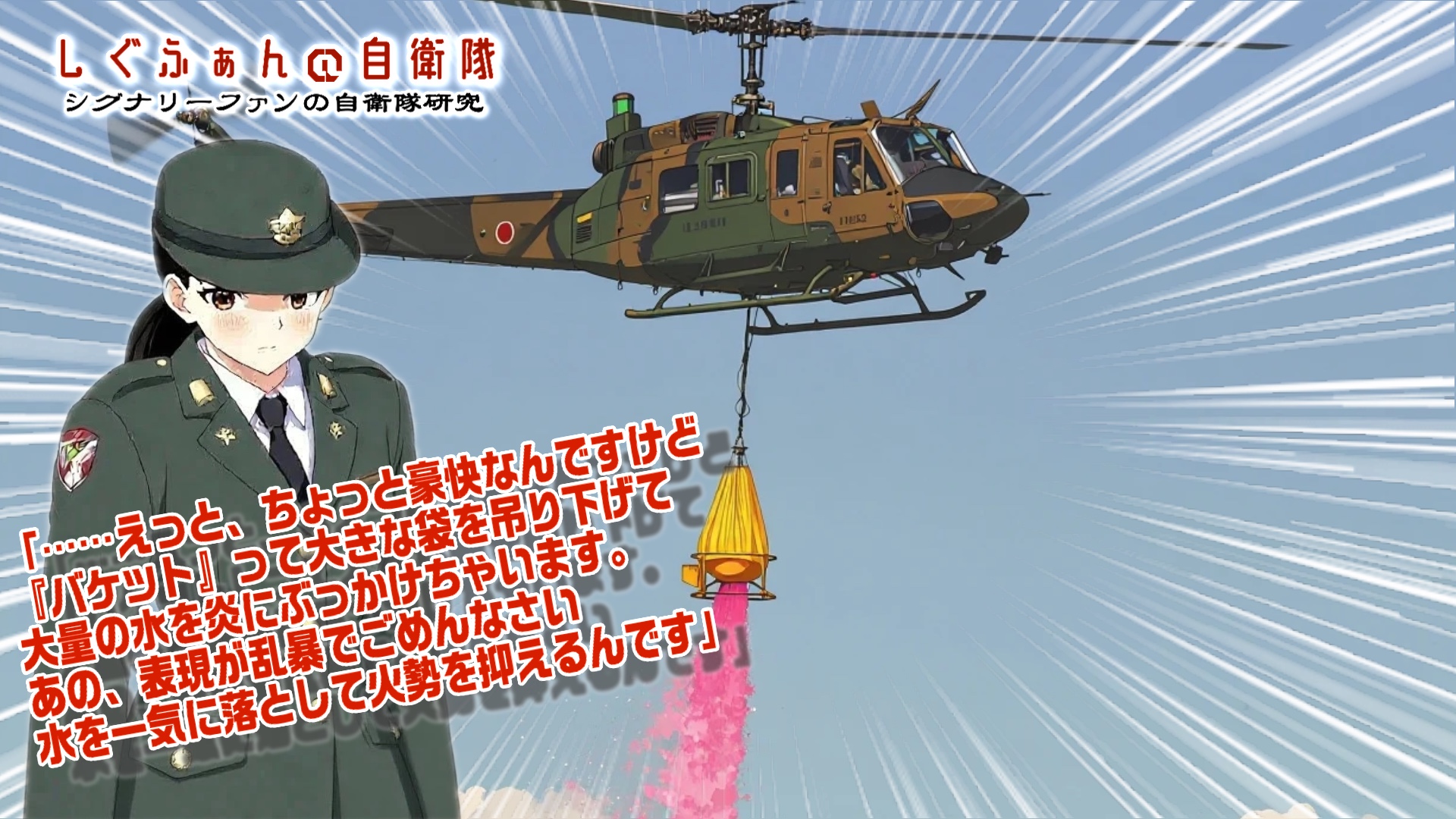陸上自衛隊のM24や、近年導入されたG28E2など、狙撃銃の設計には大きく分けて「ボルトアクション」と「セミオートマチック」の二種類があります。

引用元 水陸機動団@jgsdf_gcc_ardb
では、どちらがより優れているのでしょうか。
ここでは両方式の長所と短所、そして実際の運用での使い分けについて詳しく見ていきます。
狙撃銃の作動方式の違い
陸上自衛隊が2002年から長年使用している対人狙撃銃「M24」、さらに特殊作戦群において近年調達された「バレットM95」は、いわゆるボルトアクション方式の狙撃銃です。

一方で、陸上自衛隊が新たに導入した「G28E2」はセミオートマチック方式を採用しています。
この二つの機構の違いは単なる構造上の差にとどまらず、狙撃という任務そのものの考え方に関わる要素でもあります。
さらに詳しく見ていきましょう。
ボルトアクション方式とは

ボルトアクションとは、射手が手動でボルトを操作して薬室に弾を装填し、発射後は再び手動で排莢を行う方式です。
発射手順は単純で、弾を撃ち終えるごとに射手が手でボルト(遊底)を上げて後方に引くと薬莢が排出され、続けて前方へ押し戻すことで次弾が薬室へ装填され、ボルトを下ろして閉鎖することで装填が完了します。
この一連の動作がボルトアクションライフルの基本であり、機構の単純さと剛性が高いことが集弾性に影響する一方で、連射速度は犠牲になります。
また、ボルト操作時の後退量は機種ごとに異なりますが、操作動作は射手の頬付け位置や射撃姿勢に影響します。
右利き射手の典型的なレイアウトでは、ボルトが射手の顔側を通過する感触が生じ得るため、訓練では安全な操作姿勢と頬付けの工夫(ボルト操作時に頬を少し引く等)が徹底されます。
総じて構造が単純で剛性が高く、射撃時の部品移動が少ないため機械的精度が高く、命中精度に優れるのが特徴です。
また、弾倉構造が単純で、火薬ガスを再利用する機構を持たないため泥や砂に強く、整備も比較的容易です。
そのため長距離狙撃や静的な待伏せ型任務など、1発の命中精度を最重視する運用に向いています。
陸上自衛隊のM24もこの特性を生かし、遠距離での精密射撃を目的として採用されました。
ボルトアクション方式の長所と短所
長所は明瞭で、構造が比較的単純であるため信頼性が高く、剛性や集弾性(同じ狙点に対する弾のまとまり)に優れる点です。
動作部分が少ないぶん、発射時の銃本体の挙動が最小限に抑えられ、長距離での精度確保に有利になります。
これらの理由から「一発必中」が重視される精密狙撃任務ではボルトアクション式の優位性が今なお評価されています。

短所としては、セミオート式に比べて連射速度が遅く、発射と次弾発射までに手動の作業が入る点が挙げられます。
戦場や市街戦で迅速な連射や即応性が求められる状況ではセミオート式が有利になります。
海上自衛隊の特別警備隊(SBU)が半自動系のMSG90などを採用する背景にも、こうした連射性や即応性が関係していると考えられます。
自衛隊のボルトアクション方式銃の事例「M24」
陸上自衛隊では長らく、64式小銃を狙撃仕様に転用して簡易的な狙撃銃として運用してきました。

画像の出典 陸上自衛隊公式SNSアカウント
その後、89式小銃への更新などに伴い64式が退役したのち、陸上自衛隊が歴史上初めて大規模に調達した本格的な対人狙撃銃が「M24SWS」です。
M24はボルトアクション方式を採用し、長距離での精密射撃を主目的として配備されました。
自衛隊のボルトアクション方式銃の事例「M95」
要人警護や重要施設の防護といった任務に就く陸上自衛隊の特殊部隊である「特殊作戦群」では、限定的にバレットM95が配備されていると見られます。
現時点では一般部隊への広範な配備は行われていないと考えられます。

セミオートマチック方式とは
セミオート(半自動)方式では、発射の反動や火薬ガスを利用してボルトが自動的に後退し、次弾を装填します。
撃発→自動排莢→装填が自動で行われるため、複数射撃を素早く行えます。
例えば、陸上自衛隊が近年調達したヘッケラー&コッホ HK G28E2対人狙撃銃はセミオート方式のライフルです。

G28E2は、セミオート方式の狙撃銃の中でも精密射撃向けに設計されており、狙撃銃に近い性能を持つマークスマンライフルといえます。
引き金を引くたびに自動で次弾が装填され、複数目標への即応性を高めます。
現代の市街戦や対テロ作戦のように敵との距離が比較的短く、迅速な火力転換が求められる状況では有利です。
一方で、構造が複雑で部品点数が多く、発射時にボルトや内部機構が動作するためごくわずかな振動が命中精度に影響する場合があります。
そのため整備性や作動信頼性の確保には一定の技術力と教育が必要になります。
どちらが優れているのか
結論から言えば、どちらが優れているという単純な比較はできません。
任務と環境によって「適する方式」が変わるためです。
-
より長距離・より高精度射撃 → ボルトアクション
-
中距離・即応射撃対応 → セミオートマチック
つまり、狙撃の目的が「一撃必中」なのか、それとも「部隊支援の即応火力」なのかによって、求められる機構が変わります。
各国軍での運用における使い分けと近年の動向
この違いは、米軍でも明確に運用区分がされています。
狙撃手(スナイパー)は依然としてボルトアクションを使い、分隊射手(マークスマン)はセミオートを運用しています。

陸上自衛隊も同様に、G28E2の導入によって「狙撃銃=単一任務」から「階層的な射撃任務」へと発展を遂げつつあります。
運用側は任務特性に応じて使い分けを行っています。
具体的には「一発の精度」を重視する場面ではボルトアクションを選び、「即応性・連射性」を優先する場面ではセミオート式を選ぶ、という判断です。
アメリカ軍では現在なお単発のボルトアクション方式のライフルを新規導入することがあり、ボルトアクションの優位性が続いている面もあります。

まとめ 技術の進歩と今後の動向
このように、セミオート方式の狙撃銃は移動目標や状況が刻一刻と変わる場面で「一発で仕留められなかった場合」に即時に次弾を発射できる点が評価されます。
中隊規模での戦闘では即応射撃による直接支援など、セミオートの連続発射性はこうした用途で実用性を高めます。
とはいえ、ボルトアクションの優位点も残ります。
一般論ではボルト式は可動部が少なく、半自動に比べて故障箇所が少ないため砂塵・寒冷地など過酷な環境での稼働信頼性が高いのが特徴です。
また1発ごとの精度が出しやすい特性があります。
近年では、セミオート方式でもボルトアクション並みの精度を実現するモデルが登場しています。
先述のH&K社のG28E2などは、射撃精度と信頼性を両立させた“ハイブリッド型”と呼べる存在です。
日本のように複雑な地形と多様な任務を抱える部隊では、両方式を任務に応じて使い分ける形が今後も続くとみられます。
ボルトアクションは依然として精密射撃の象徴であり、セミオートは戦術機動下の火力維持に欠かせない存在となるのが、もはや世界の潮流です。
関連リンク
- 対物ライフルで兵士を撃ってはいけないはウソ? —
(対物ライフルの法的・倫理的制約を論じた解説記事) - 陸上自衛隊、新たな対人狙撃銃:ヘッケラー&コッホ社製HK G28 E2を調達 —
(HK G28 E2 の導入を伝えるニュース/解説) - 陸上自衛隊はなぜ狙撃銃を導入してこなかったのか —
(狙撃銃導入の歴史的背景と理由を考察した記事) - 敵の恐怖心を煽り、進撃遅滞させるスナイパーの運用は心理戦でもある —
(狙撃運用の心理戦的効果を論じた考察) - 陸上自衛隊も配備する「バレット対物ライフル」シリーズの驚くべき実力 —
(バレット社製対物ライフルの性能解説と陸自導入の文脈) - 陸上自衛隊が導入した対人狙撃銃「M24 SWS」の実力 —
(M24 SWS の技術解説と運用評価)