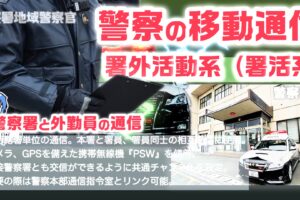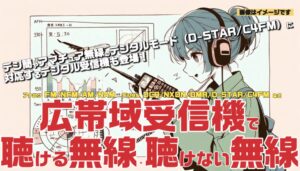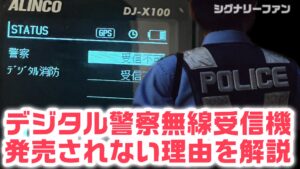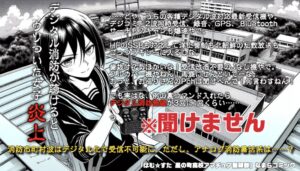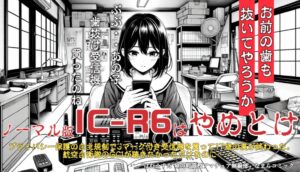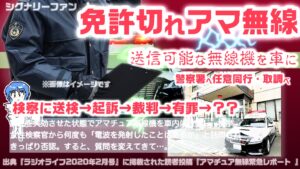警察官が緊急の現場に直面した際、腰に携行している無線(署活系)を使用せず、あえて自身の所属署を介さずに、その場から電話で直接110番通報を行うケースがあります。
このような対応が取られるのは、一体なぜなのでしょうか。
-
記事のポイント
この記事の内容は、警察通信システムの構造、緊急運用の現場ルール、通報経路の合理性と照らし合わせてほぼ正確です。特に「滑稽ではなく、合理的な判断である」と明示した点は、公表されている警察庁の内部ルールや実務的見地からも裏付けがあります。
各項目に飛べます
勤務中の警察官が110番を行った事例とネットの反応

例えば2016年に福岡県警本部に車が突っ込んだ事案に対応した警察官について、SNSを中心に以下のような反応が。
県警本部に車が突っ込んだと警察官から110番があったとはねぇ、110番は県警本部に繋がるのでは?理解に苦しむなぁ。 福岡県警本部に車突っ込む…男確保、けが人なし(読売新聞) – Yahoo!ニュース http://t.co/lrUJyw1tUs
— ふれっと (@okamelusian) October 5, 2015
何か笑える。県警本部に車が突っ込んで来て警察官が110番するんだ。。。福岡県警本部に車突っ込む…男確保、けが人なし(読売新聞) – Y!ニュース http://t.co/05RWq6pnYY
— dragon_ogawaアカ停解除中 (@dragon_ogawa) October 5, 2015
警察本部に車が突っ込んできたと警察官が110番したそうだ。目の前に大勢警察官がいるのになぜ110番が必要なのか。
福岡県警本部に車突っ込む…男確保、けが人なし(読売新聞) – Yahoo!ニュース http://t.co/aj2Fza0AYI
— すぐるちゃ【吉村裕基De復帰を求める会】 (@suguru0220) October 5, 2015
警察署に突っ込まれて警察官が110番するとは。笑
福岡県警本部に車突っ込む…男確保、けが人なし(読売新聞) – Yahoo!ニュース http://t.co/jldkCKg3aU— 芹澤 マクシム (@MAXIM_SIPKO) October 5, 2015
警察官の110番は「滑稽」なのか?――正当性を規則から読み解く

一般的な感覚では、「勤務中の警察官が110番通報をする」という行動には、上記に紹介したSNSの投稿で散見されるように、どこか滑稽さを覚える方も少なくありません。現場の警察官が、自分の組織である警察に対して通報するという構図に、違和感を抱くのも無理はないでしょう。
しかし、そのような見方が世間一般にある一方で、警察の内部運用においては、「警察官が110番すること」自体は決して誤った報告方法ではありません。
むしろ、緊急時においては通常の報告系統(署活系→所轄署→本部)を飛び越え、110番を通じて本部通信指令室に直接速報を入れることが「推奨されている手段」であるのです。
今回の記事では、この一見「滑稽」とも取られがちな行動について、その部内規則上の正当性と実務的意義を明らかにします。
なぜ警察は無線を2系統に分けているのか、そしてなぜあえて所属署を飛び越えた報告が必要とされるのか――。
その背景を探ることで、「警察官の110番」がいかに合理的かつ実務的な判断であるかが見えてきます。
外勤警察官の報告は所轄→警察本部へ吸い上げられる

ご説明の通り、地域警察官は無線警ら車向けの基幹系無線および、ミニパトや自転車移動の警察官向けの署活系無線の2系統を使用。
しかも警察官はわざわざ腰のベルトの署活系無線機とは別に、胸ポケットに”パトカー向けの基幹系を聴くためだけ”の『受令機』も入れています。
なぜ警察官が110番をするのか?――情報統制と迅速な初動対応のため
警察本部の通信指令室は、それぞれの都道府県全域をカバーするパトカー向けの無線「基幹系」を用いて、指令を下しています。これはいわば、県警における総司令部の役割を果たしている無線系統です。
一方で、「署活系」は通常、所轄署に所属する外勤警察官が使用する通信手段であり、本部とは直接つながっていません(ただし、本署の操作によって一時的に本部とリンクすることは可能です)。したがって、外勤警察官からの報告はまず所属する警察署の通信室を経由し、そこから本部へと情報が吸い上げられる仕組みとなっています。
また、署活系は運用範囲が狭く、その警察署の管轄内でのみ交信が行われるのが通常です。
では、なぜシステムを単一に統一せず、わざわざ「基幹系」と「署活系」の2系統に分けて運用しているのでしょうか?
その理由は、意図的に系統を分けることで情報統制を可能にしているからです。
情報が錯綜するからこそ、系統は分ける
重大事件が発生した際には、現場からさまざまな情報が同時多発的に寄せられるため、状況が錯綜する可能性があります。そのため、警察では平時から厳格な情報統制が求められています。
こうした状況において、署活系による「所属署経由」の情報吸い上げよりも、現場の警察官が本部に直接速報を送るほうが、正確で迅速な対応につながる場合があります。そこで、活用されるのが「110番通報」なのです。
警察官が110番通報を行う理由
一見すると「警察官が110番をかけるなんて滑稽だ」と思われがちですが、実際にはこれが正式な運用方針となっています。
たとえば、警視庁が平成7年に制定した『通信指令業務運営規程(平成7年4月26日)』では、以下のような主旨が記載されています。
「現場に臨場した勤務員は、速やかに状況を把握し、署活系無線などでリモコン指揮者(署通信室)およびその補助者を通じて指令本部に報告すること。ただし、急を要する場合にはこの限りではなく、把握した事項を直接指令本部に速報せよ。」
出典 『警視庁通信指令業務運営規程(平成7年4月26日)
このように、重大かつ緊急性を要する事案に限っては、署活系で段階的に報告するのではなく、現場から直接110番で本部に連絡する「飛び越え報告」や「飛び越え110番」が公式に認められています。
これは単なる例外ではなく、47都道府県警すべてにおいて共通して運用されている柔軟な対応の一つです。
県下一斉の緊急配備にも有効
さらに、署活系の通信範囲は狭いため、警察本部が全域に一斉指令を流すには不向きです。こうした事情もあり、県下一斉の出動や緊急配備には、広域をカバーする基幹系が使用されます。
つまり、警察官が緊急時に110番をするのは、正確かつ迅速な本部指令を得るための、合理的で有効な手段なのです。
現役警察官も実例として紹介
『現役警察官の事件現場ナイショ話』でも、緊急時にその場で110番通報を行う「飛び越え報告」が実例として紹介されています。
現在ではPSD(警察専用携帯電話)も活用
なお、現在ではすべての都道府県警察本部において、地域警察官には「PSD(Police Special Digital)」と呼ばれる警察専用の携帯電話が配備されています。これにより、署活系無線に頼らず、より簡便に本部との緊急連絡が可能となり、初動対応の柔軟性がさらに高まりました。
まとめ
「警察官の110番」は、一般的な常識では意外に思える行動ですが、実は警察が正式に定めた迅速な初動対応のための合理的な手段です。
以下に、結論と評価をまとめます。
-
✅ 緊急時に警察官が110番通報するケースもある
→ 警察運用上も事実であり、制度的にも合理性がある。 -
✅ 署活系無線より110番通報の方が迅速な場合がある
→ 実務上、状況によって成立しうる。特に無線が使えない場面で有効。 -
✅ 「警察官の110番」は滑稽ではなく、合理的対応である
→ 「飛び越え報告」として、通信指令運用や警察内部のルールに基づいた合理的対応である。
重大事案発生時には、署活系無線にこだわらず、直接本部へ報告する体制が整っていることこそ、現代の警察組織の強みであるといえるでしょう。