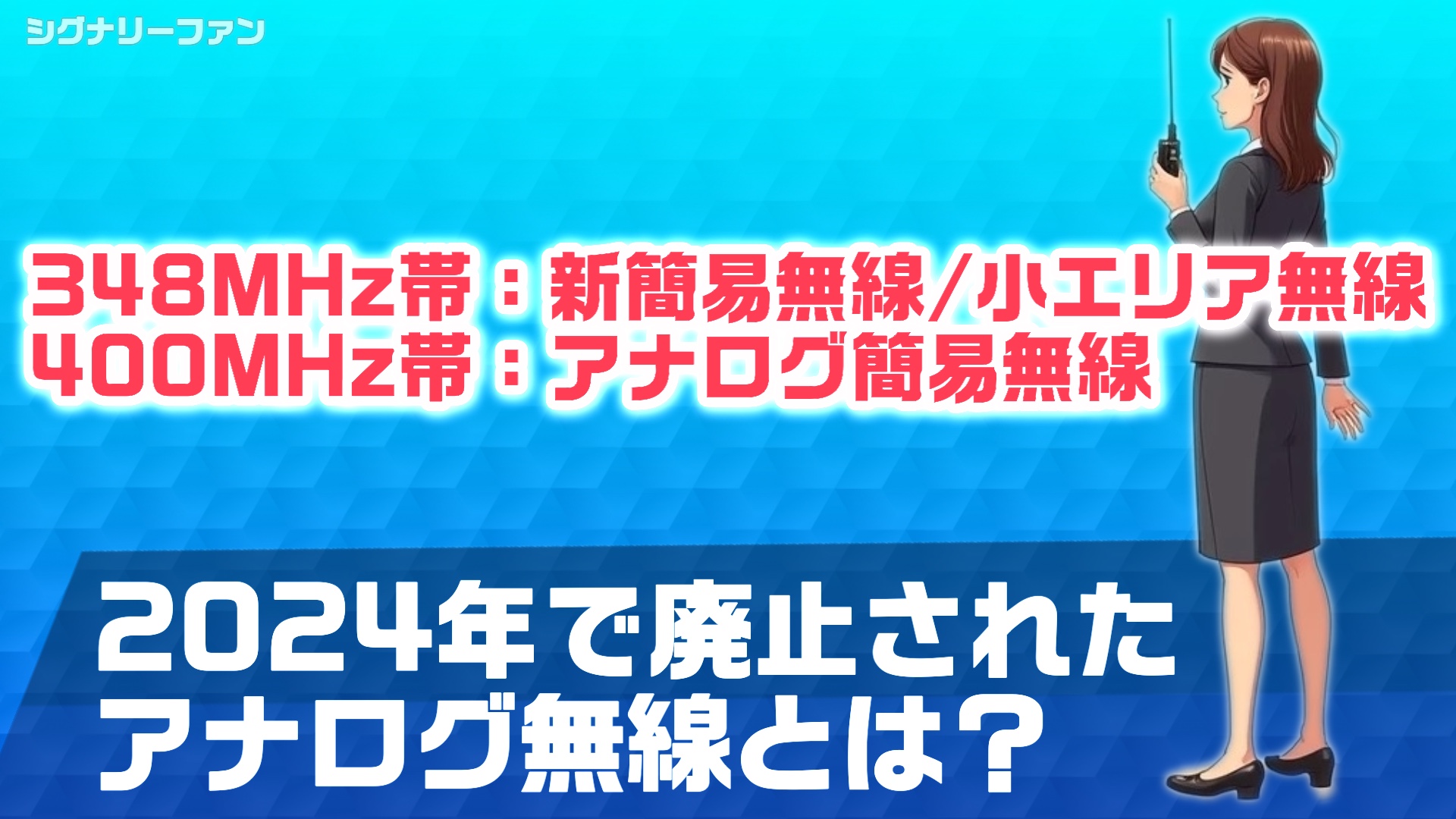日本ではかつて、さまざまな業務や地域連絡のためにアナログ方式の簡易無線が広く使われていました。
しかし、通信のデジタル化と電波資源の有効活用の観点から、348MHz帯と400MHz帯に割り当てられていた無線局が2022年から2024年にかけて廃止されました。
■ 348MHz帯:新簡易無線(陸上移動局)/ 小エリア無線【348MHz帯】
1990年代に登場した「新簡易無線」は、それまでの簡易無線機よりも高音質・小型化が進み、主に小規模事業者などで利用されていました。具体的な周波数帯は348.5625~348.8000 MHzで、20波以上が設定されていました。
-
用途:商業施設、建設現場、イベント業務など
-
特徴:全国免許制(どこでも使える)、通話内容は暗号化なし
-
廃止時期:2022年11月30日でアナログ新簡易無線の使用は完全終了
■ 400MHz帯:アナログ簡易無線
● アナログ簡易無線(陸上移動局)【400MHz帯】
業務用無線として古くから広く運用されていました。これらは主に、建設業、運送業、イベント運営などで用いられていました。
-
周波数:465.0375MHz~465.15MHzおよび468.55MHz~468.85MHz
-
民間事業者が多数使用していた
-
免許または登録が必要
しかし、総務省の方針により、400MHz帯のアナログ簡易無線も2024年11月30日をもって使用終了しており、以降はデジタル簡易無線(登録局/免許局)やIP無線への移行となっています。今後は465.0375MHz~465.15MHzおよび468.55MHz~468.85MHzで以前のアナログ無線機から電波を送信すると、電波法違反になります。
※415MHz帯のJR無線、466MHz帯の消防署活系無線は継続使用されています。
このような理由から、旧来のアナログ無線は「役目を終えた」とされ、2025年からは本格的にデジタル方式(DCRやIP無線など)に切り替わっています。
しかしながら、150MHz帯のアナログ無線など、かつての「おもしろ無線」王道周波数は多数残っているほか、次世代のデジタル無線で受信可能なものもたくさんあります。