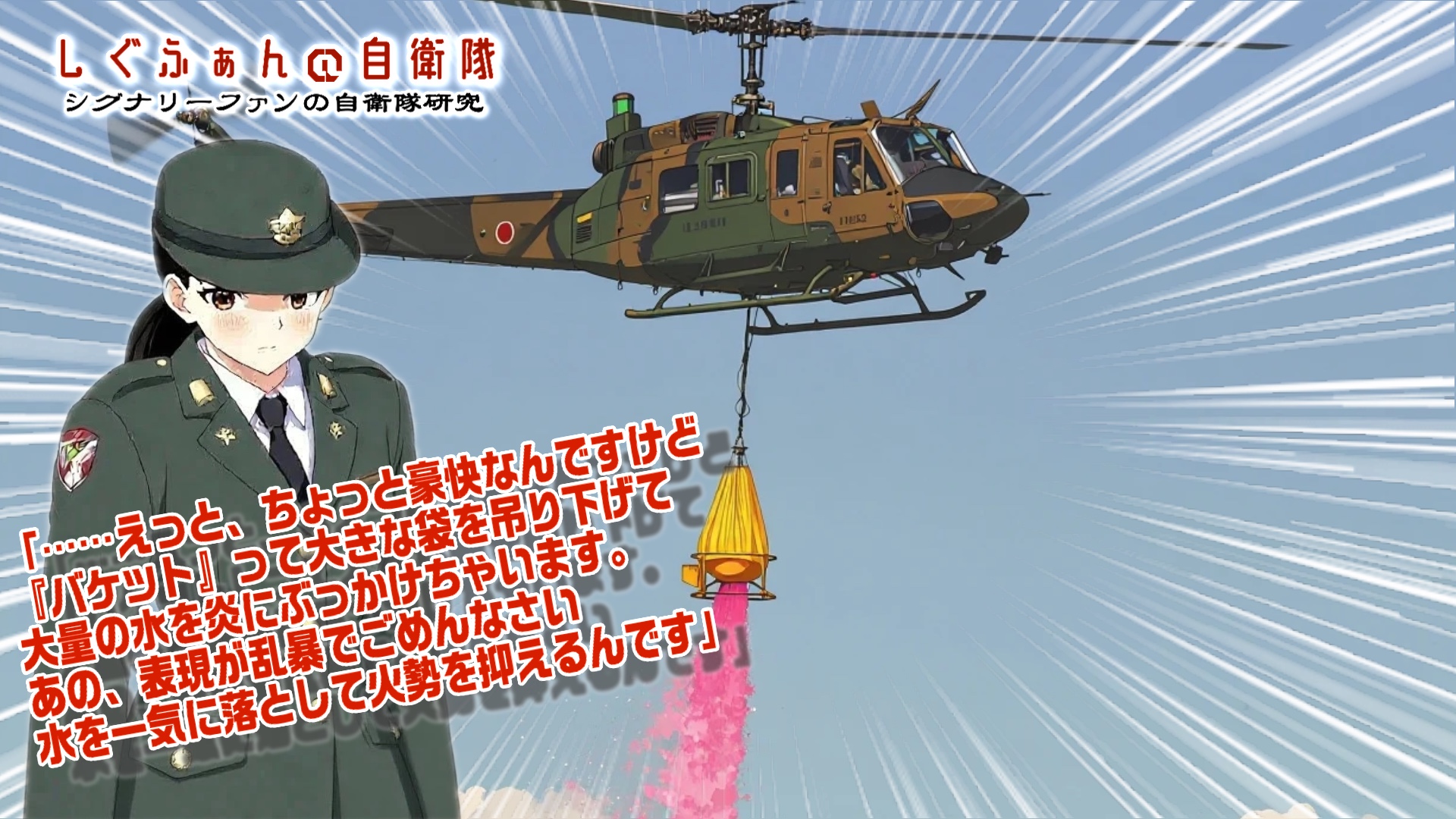陸上自衛隊が運用する「87式偵察警戒車(Type 87 RCV)」は、戦車や装甲車の陰で静かに動きながらも、部隊全体の作戦を左右する“情報収集の要”を担う車両です。
1980年代後半に導入されて以来、偵察部隊の中核装備として全国の師団・旅団に長らく配備されています。
詳しく見ていきましょう。
87式偵察警戒車の概要
偵察部隊の装備体系の一端を担っている車両
87式偵察警戒車は、陸自の偵察部隊において、敵情・地形・附随状況の把握を目的に展開される「偵察・警戒」任務を主たる機能とする装輪装甲車です。
陸上自衛隊北部方面隊第6師団公式サイトでは「偵察部隊に装備し、空地火力の脅威のなかで、主として路上機動により偵察警戒任務に当たるほか、側方警戒行動も行う」と明記されています。
つまりその任務は、敵情や地形、周囲の状況をいち早く把握し、上級司令部へ報告することです。
任務は偵察:戦うより、まず「見る」
つまりこの車両は、戦闘を始める前に「どこで、どのように戦うべきか」を見定めるための“先触れ”として機能します。
偵察部隊の役割
普通科や機甲科に編成された偵察隊は、有事や災害が発生した場合、師団や旅団の行動に先立って、先遣隊として展開します。
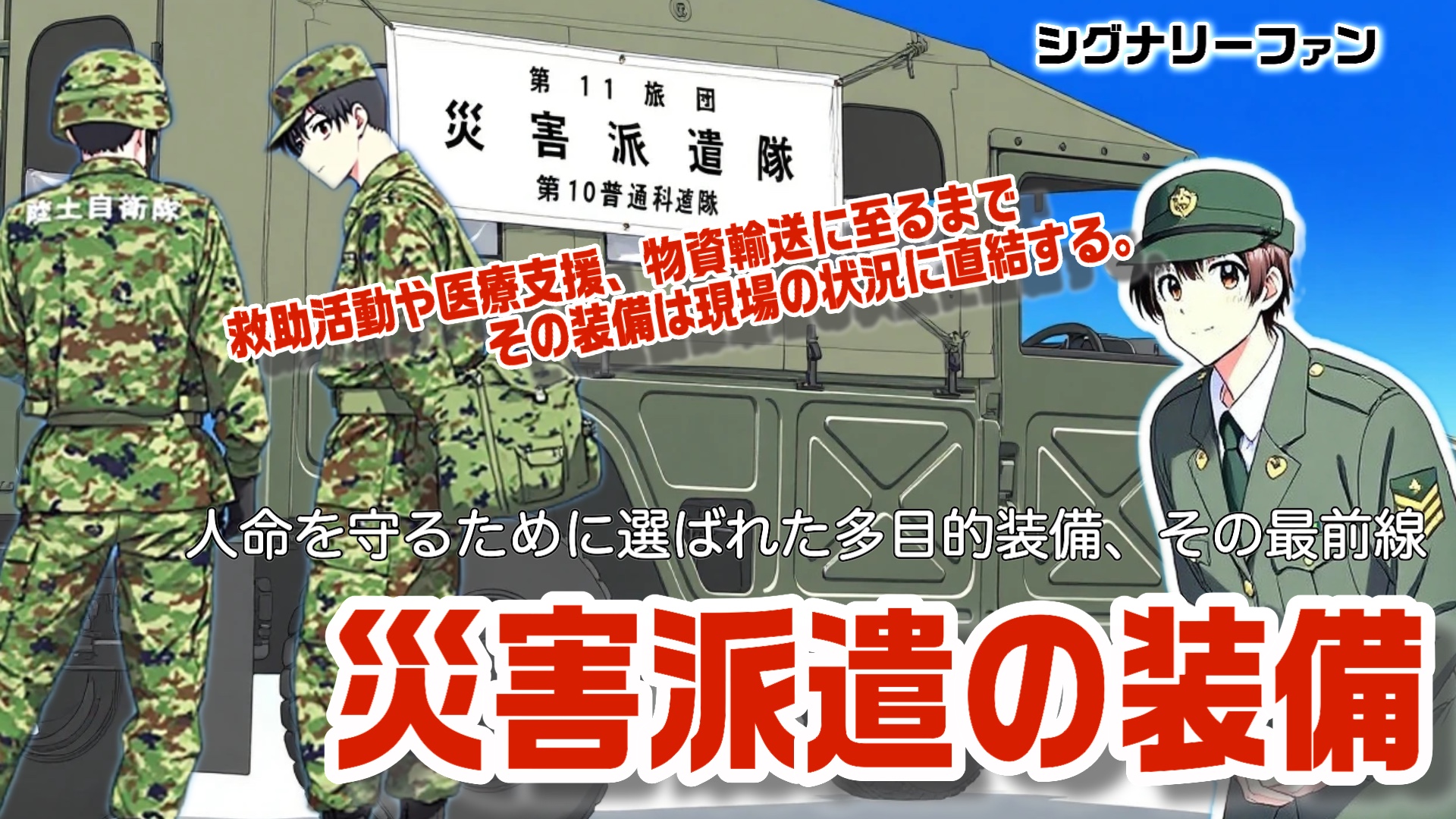
陸上自衛隊第2師団偵察隊の広報によれば、「87式偵察警戒車や偵察用オートバイを使用し、広範囲に展開して状況を把握する」とされており、これは単なる巡回ではなく、師団長の判断材料となる情報を確保する行動です。

偵察隊の87式偵察警戒車は、装甲で乗員を防護しながら、発達した現代の幹線道路、ときには未舗装の路上を中心に高速で進出し、現場で情報収集し、所属部隊や師団へ無線通信による情報伝達を行います。
装備・機能的特徴
87式偵察警戒車の主要仕様として、以下のような特徴が確認できます。
-
乗員:5名(操縦手、無線・観測要員、砲手、指揮者等)
-
全備重量:約15トン、車長約5.99 m、車幅約2.48 m、車高約2.8 m、最高速度約100 km/h。
-
装輪式6輪駆動(3軸6輪)仕様で「コンバットタイヤ」を使用し、舗装路・一般路における高機動を実現している旨記載があります。
-
武装:25 mm機関砲を主武装とし、74式車載7.62 mm機関銃を副武装として装備。
-
偵察・観測を支援するために、「操縦手・砲手用微光暗視装置」など視界・観測性能を補う装備を搭載。
これらの仕様から、装輪装甲車として「路上を迅速に移動しつつ偵察・警戒を実施できる」という設計意図が読み取れます。
また、軍用車両や陸上自衛隊の一部車両が装備し、小銃弾による銃撃を受けても一定の距離を走れるコンバットタイヤおよびランフラットタイヤについては、以下の記事にて解説しています。

運用上の役割と留意点
運用面においては、87式偵察警戒車は「偵察・警戒任務の実行プラットフォーム」として、師団・旅団級の偵察隊や偵察戦闘大隊に配備されていることが複数部隊の紹介文で確認されます。
例えば、陸上自衛隊最北の駐屯地・名寄駐屯地に駐屯する我々「第2偵察隊」では「主に夏季はオートバイ、軽装甲機動車及び87式偵察警戒車などを使用し…事態発生時は師団長の状況判断に資する情報を獲得するため、速やかに広範多岐に展開して情報収集活動を実施します。」と記されています。
このことから、87式偵察警戒車は「偵察用オートバイ・軽装甲機動車と併用されつつ、より防護力・機動力・火力を備えた偵察手段」として運用されていると整理できます。

一方で、公開されている情報から読み取れる留意点もあります。
偵察任務において「路上機動」を主たる行動形態としているため、未舗装路・山岳地帯・極端な悪路などでは制約を受ける可能性があります。
また「偵察警戒任務」「側方警戒行動」という表記から、必ずしも敵主力部隊に突入して戦闘を行うための車両ではなく、情報収集・警戒・監視を主体とした任務を担うことが想定されており、「戦闘車両」ではなく「偵察装甲車」という位置付けです。
装輪装甲車である意義
偵察・警戒能力は、軍事作戦において「敵の位置・状況・地形・部隊動向」を把握し、味方部隊の作戦行動を支える基盤となるものです。
87式偵察警戒車のような装輪装甲車がこの任務に適用されることで、以下のような意義が考えられます。
また、戦車に見られるキャタピラ式の装軌車両は地面との接地面積が広く、軟弱地や泥濘地などでの走破性能が高いため、戦車や装甲回収車などに採用されています。

このため、どんな悪路でも走破できると考えがちですが、自動車道路網の発達した日本国内においては、装輪車両を用いた機動偵察が有効です。
事実、防衛省や陸上自衛隊の公式資料(例:『防衛白書』『陸上自衛隊の装備』)にも、道路網を活かした機動展開能力(Mobility)の重要性が記されています。
特に本州・九州・四国のような舗装路が多い地域では、装輪車両の方が運用・整備の両面で効率的とされています。
このため、昨今の陸自では装軌車両よりも装輪車両を用いた機動偵察や部隊展開が有効とされており、8輪駆動の装輪車両「16式機動戦闘車」などを配備しています。
陸上自衛隊公式サイトにも「道路走行性を活かし、迅速な部隊展開を可能とする」旨が明記されています。
-
高速かつ広範囲な移動が可能であり、師団・旅団の行動域における偵察範囲の拡大に寄与。
-
相対的に自動車道路網の発達した日本国内において、装輪車両を用いた機動偵察が有効。
-
武装と防護を備えることで、偵察中の被威胁(敵火力・地雷・IED等)状況下でも一定の生存性を確保する構えを持つ。
まとめと今後の展望
このように、87式偵察警戒車は偵察部隊の戦術的選択肢を拡大させる機材として一定の役割を果たしています。
ただし、87式偵察警戒車の配備開始から数十年が経過しており、老朽化・陳腐化を指摘する報道も相次いでいます。
とくに自衛隊の作戦の要である情報装備・観測装備・ネットワーク化といった現代偵察任務の要件に対しては早急な更新が求められるでしょう。
87式が開発・配備された1980年代は、車両間で偵察情報や位置情報を自動的に共有するネットワーク化されたデータリンクシステムは一般的ではなく、現在配備される16MCVや10式戦車などが持つデータリンク能力・C4Iによって、部隊間の情報共有が底上げされています。
これに伴い、偵察戦闘大隊の装備体系もオートバイ・軽装甲機動車・装輪装甲車・監視センサーを含む多様化が進んでおり、87式偵察警戒車がその中でどのように位置付けられていくかが今後の注目点です。
戦車が「力」で前線を切り開くのに対し、偵察警戒車の役割は「情報」で味方を導くことです。
作戦の初動段階では、敵勢力がどの方角から侵入し、どの地形が危険かを探る。その情報が、戦車中隊や普通科部隊(歩兵に相当)の行動計画を決定づけます。
このように、87式偵察警戒車は「機動偵察/路上高速機動を活かした偵察・警戒行動」に位置付けられており、偵察部隊の装備体系の一端を担っています。
以上、87式偵察警戒車の任務・装備・運用について、公開資料をもとに整理しました。
参照URL一覧: