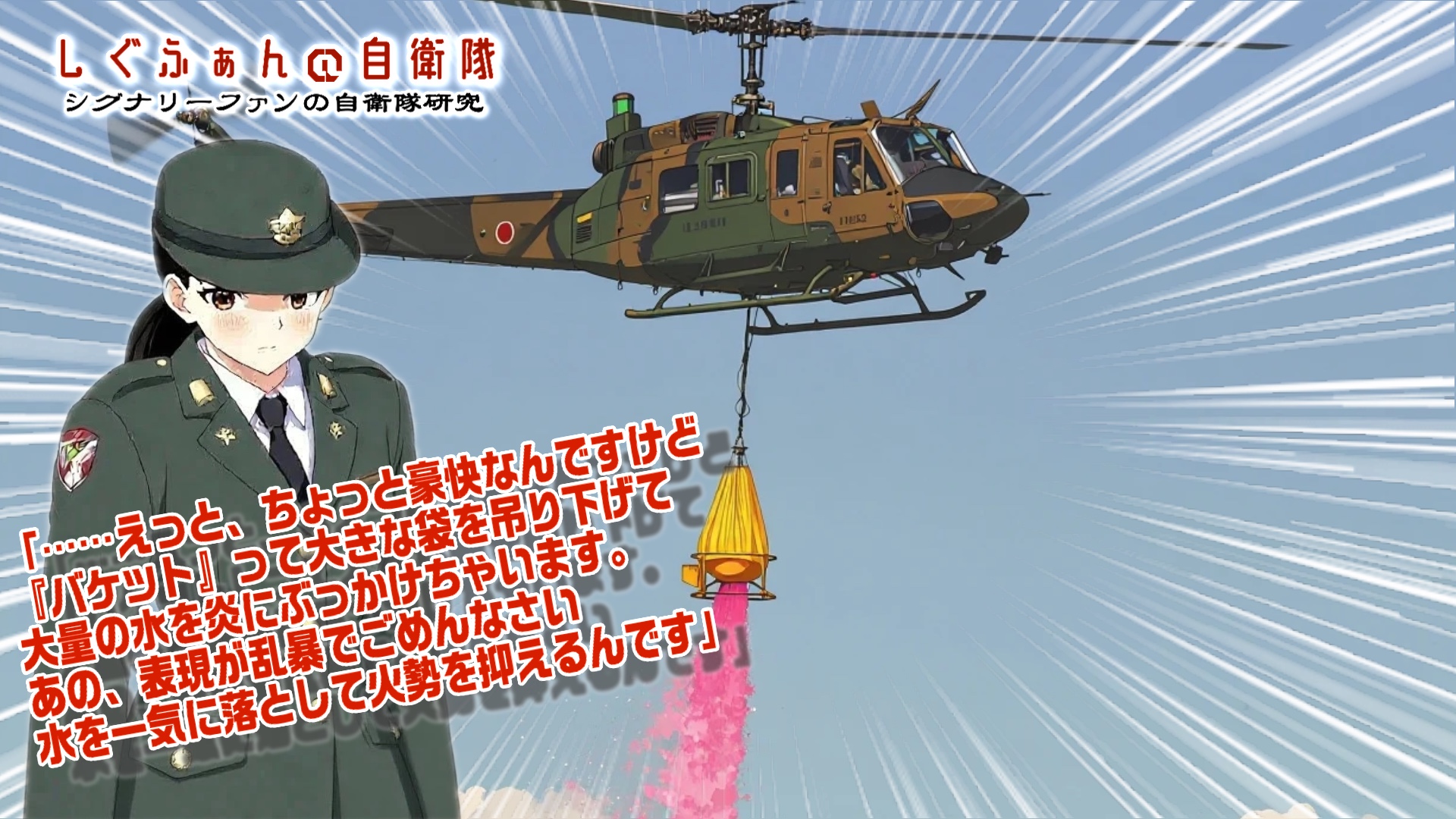自衛隊は、防衛や災害派遣など多様な任務に対応するため、各種の緊急車両を保有している。
警察や消防に準じた装備を独自に整備しており、その運用実態はあまり知られていないが、実に多岐にわたる。
たとえば、内部の秩序維持を担う「警務隊」が捜査活動に使用する覆面パトカー。
衛生隊が運用する野戦用救急車や、航空機事故に備えるための航空機用消防車。
そして、不発弾の処理に特化した車両も緊急車両に指定されている。
さらに、通常使用される自衛隊車両の一部にも、赤色灯とサイレンを装備し、緊急自動車の指定を受けているものがある。

陸上自衛隊が主に使用する73式小型トラックのうち、部隊長が乗車する車両は緊急時の指揮車両として運用されており、赤色灯と前面警光灯、サイレンを標準装備している。
そして、化学テロにも出動する化学部隊の車両にも赤色灯が装備されている。

これらの装備は、災害派遣などでの迅速な展開を想定したもので、警察による先導を待たずに部隊が独自の判断で展開可能となるように設計されている。
自衛隊の“パトカー” 秩序維持と緊急対応に活躍
自衛隊の警務隊は、自衛隊法に基づく司法警察権を持つ内部組織であり、その活動の一環としてパトカーと覆面パトカーを運用している。

警務隊のパトカーは自衛隊独自の白色塗装が施され、隊内の秩序維持、交通指導、犯罪捜査などに使用されている。

一方、覆面パトカーは秘密クラウンというわけではないが、ブルーバード・シルフィなどが配備されており、警察の交通用覆面パトカー同様、反転式赤色灯を備えている。


特に、部隊からの無断離脱、いわゆる「脱柵」が発生した場合には、最寄りの駅などに先回りし、緊急走行で隊員の身柄確保にあたる。
覆面車両は、一般車両と見分けがつかない外観で内偵活動にも用いられており、警務隊には白バイも配備されている。
駐屯地内外で稼働する自衛隊の救急車両 野戦でも対応
自衛隊の各部隊には、OD色や白色の救急車が配備されている。いずれも赤十字マーク、赤色灯、サイレンアンプを備え、必要に応じて駐屯地内や演習地、時には実戦想定の野戦環境でも負傷者の搬送にあたる。
野戦用としては、1トン半トラックのシャーシを活用した大型救急車があり、これは前線での応急処置や搬送を想定した構造となっている。
一方、駐屯地で使用される救急車は、主に業務隊が運用し、基地内の医療機関や地域病院との連携搬送を担っている。
赤十字のマークは国際人道法上、非戦闘車両の象徴とされており、軍用車両であっても攻撃の対象とすることは国際法上許されていない。
航空機事故にも即応 自衛隊の消防体制
自衛隊では、火災や航空機事故への対応能力を強化するため、駐屯地や基地に小型ポンプ車を配置している。特に航空部隊には、航空機火災や破損機の救助活動に対応するための大型救難消防車や化学消防車が導入されている。

たとえば陸上自衛隊でも飛行場を有する駐屯地では、救難消防車を備えており、航空自衛隊・海上自衛隊においてはさらに大規模な航空機を対象とした特殊車両を運用している。
基地によっては、海外製の破壊機救難車両を用いる例もある。
消防要員は専門教育を受けており、航空自衛隊芦屋基地の第3術科学校では初級消防教育が行われ、さらに上級課程に進む者もいる。
訓練は実践さながらで、完全防護装備での消火訓練では酸素欠乏により倒れる隊員が出ることもあり、その過酷さは消防吏員にも引けを取らない。
また、駐屯地周辺で民間の火災が発生した際には、地方自治体の要請に基づき「近傍派遣」として出動することもある。
任務に応じて独自の緊急車両を有する自衛隊。その配備と運用の実情は、多くの国民にとってまだ十分に知られていない。だが、それらはまさに国防と災害対応の現場で、確かに機能している。