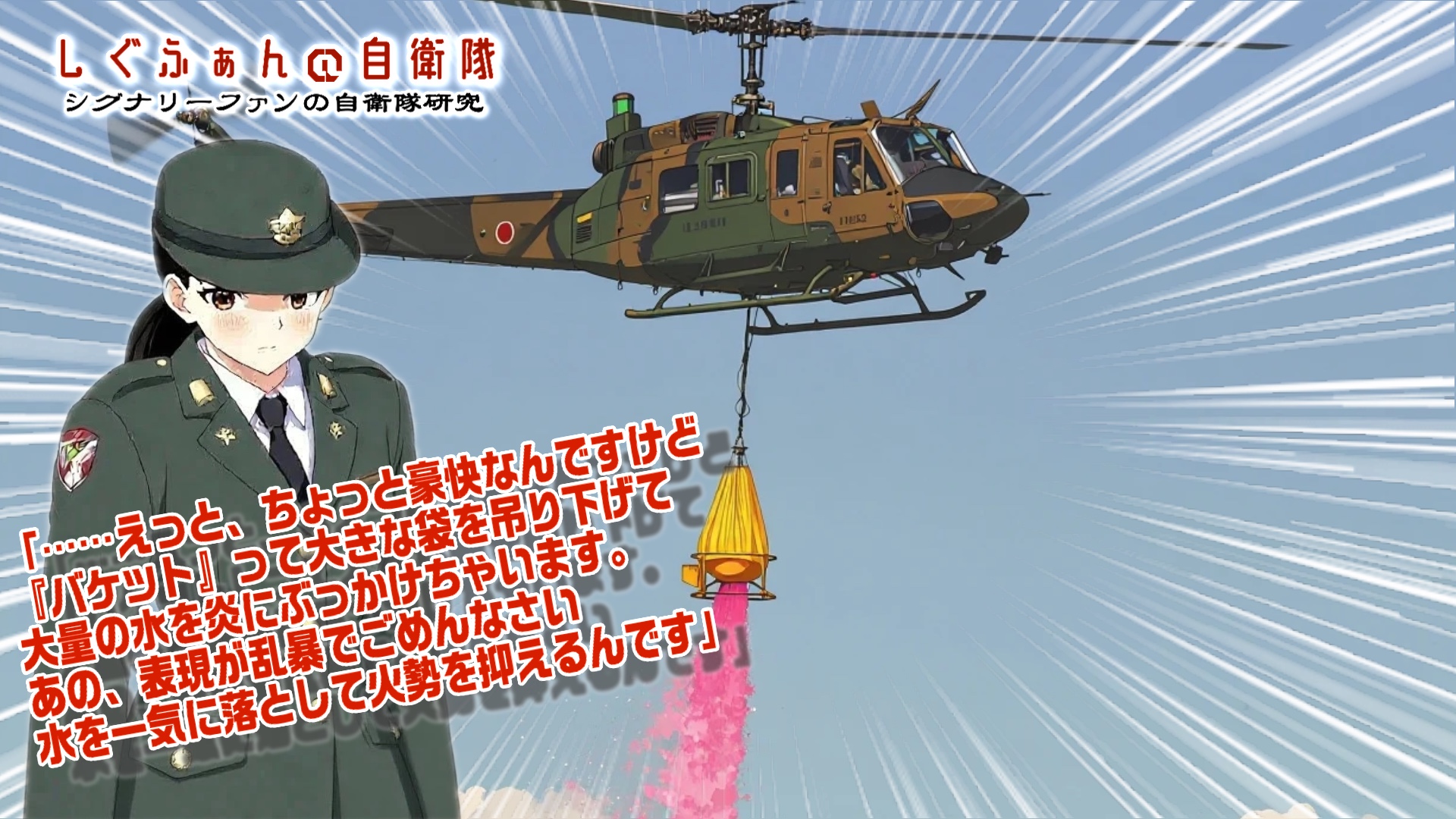自衛隊、「空薬きょう」1発も残さず回収 見つかるまで全隊員で捜索も
自衛隊では、実弾射撃訓練において使用した弾薬の空薬きょうを全て回収・返納する義務がある。
発射された弾丸の数と同数の空薬きょうが揃わなければならず、これが徹底されているのは、安全管理と弾薬管理の観点から、厳格なトレーサビリティ(追跡可能性)を維持するためである。
小銃などの火器には、通常「カートキャッチャー」と呼ばれる袋状の装置が取り付けられており、発射時に排出される薬きょうを自動的に収集する仕組みとなっている。
しかし、訓練中にこの装置が外れたり、気づかないうちに破損するなどして薬きょうが地面に散乱することもある。
その場合、薬きょう1発が不足しても、部隊全体での捜索が開始される。
演習地の草むらや泥地での捜索は過酷なものとなるが、それでも「見つかるまで終わらない」のが自衛隊の原則だ。
これは単なる規則ではなく、実際に過去、薬きょうの紛失が報じられた例もあり、部隊としての責任が問われる事案にも発展している。
この厳しい運用は、万一薬きょうが外部に流出した場合、事件や事故への悪用を防ぐ意味も含まれている。
自衛隊における弾薬管理は、組織全体の信頼性を支える根幹であり、「1発たりとも行方不明にしない」という姿勢が制度と文化の両面で徹底されている。
。
📝 自衛隊が空包を紛失した事例

自衛隊、薬きょう7発紛失で大規模捜索 最終的に1300人態勢に
熊本県で行われた陸上自衛隊の演習において、小銃弾の空薬きょうが紛失し、最終的に1300人規模の捜索態勢が組まれる事態となった。
発表によると、紛失が発覚したのは陸自第42普通科連隊による訓練中で、使用されたのは89式小銃用の5.56ミリ実包の薬きょうだった。

事案が発生したのは2015年4月25日午前、駐屯地から演習場へ薬きょうを運搬中の車両の荷台で、運搬用の木箱が倒れて薬きょうが散乱しているのが発見された。
直後の点検で、予定していた1万発のうち7発の薬きょうが不足していることが判明。自衛隊は直ちに捜索を開始し、同日午後10時までに6発を回収。うち3発は演習場内、残り3発は一般道上で発見された。
翌26日午前6時、自衛隊は態勢を拡大し、延べ1300人を動員して捜索を再開。最終的に残る1発も一般道で発見され、全ての薬きょうが回収された。捜索活動は約14時間に及んだ。
陸上自衛隊では、弾薬の厳格な管理が義務付けられており、発射した実包の薬きょうは一発ごとに確認・回収し、受領数と照合して返納する仕組みとなっている。
このため、薬きょうの紛失は管理上の重大な問題とされ、例外なく徹底的な対応がとられる。
過去にも、実弾1発の紛失が報告されている。1995年には帯広の第5師団が北海道鹿追町の演習場で行った実弾射撃競技会において、実弾1発が所在不明となり、連日1000人規模の部隊を投入した大規模な捜索が行われた。
しかし、この際の最終的な回収状況については公表されていない。
なお、国外の演習では、薬きょうの回収義務がない場合もあり、日米の運用文化の違いが現場で話題となることもあるという。
空薬きょう一発に至るまで厳しく管理される日本の姿勢は、国外の軍人からは「異例」と映ることもあるが、自衛隊としてはあくまで弾薬管理の信頼性を維持する上で必要な措置だとしている。
他にも以下のような事案がある。
① 2016年・新潟関山演習場で空包50発が一時紛失、全員で捜索
2016年7月、新潟県妙高市の自衛隊関山演習場において、機関銃用の空包50発が演習後にリュックから消失。
この際、約370名の隊員による大規模な捜索が行われ、翌朝には無事すべて回収されたと報じられた。
地元紙では「カラスが持ち去った可能性もあり」とされているが、演習後の安全措置が功を奏し、最終的に回収完了となった。
② 2024年・石川県志賀町で5.56mm空包リンク4発が紛失、一時捜索
2024年10月、石川県羽咋郡志賀町の旧小学校敷地で、第14普通科連隊所属の隊員が使用した5.56mm機関銃用リンク弾4発を紛失。

部隊は約100名体制で即座に捜索を開始し、翌日午前中に全て回収されたと防衛省によって公表された。
③ 番外編:大津駐屯地2等陸曹が空包を不法持ち帰り処分
2013年10月、高島市の演習場での共同訓練時に、当時の2等陸曹(30代)が米軍のライフル銃用空包を数発ポケットに入れて自宅へ持ち帰る事件が発生。
後に職場で紛失したことで発覚し、火薬類取締法違反として書類送検された後、減給1か月の処分を受けた。
※これは空薬莢ではなく「空包」であり、弾頭はないが、火薬が装填された実包の一種。銃刀法で規制されている。
④ 内部語り:大嵐訓練中、空包1発紛失で全員捜索も奇跡回収
ネット上には、実際に訓練中に空包を1発紛失し、全隊員による激しい捜索の末に2時間後に発見されたというエピソードもある。
悪天候の中で地面を這いつくばる姿に、多くの隊員が「これはまさに地獄だった」と当時を振り返る声も……。
厳密には空包射撃と実弾射撃ではやや違いあり
厳密には、空包射撃と実弾射撃では薬莢の扱い方がやや異なる。この違いは単に手順の問題ではなく、紛失防止や安全管理、後始末に直結する実務上の区別である。
自衛隊では空包(ブランク)射撃の場合、小銃右側に「カートキャッチャー」と呼ばれる袋状の回収装置を取り付ける。発砲され排莢された薬莢は、その場でキャッチャーに次々と収まっていくため、通常の演習など、屋外で多数の発砲を行う場面でも回収が容易で、薬莢紛失のリスクは低い利点がある。
これに対して実弾射撃では、状況が変わる。実弾では排莢の飛散角度が大きく、また安全確保の都合でキャッチャー装着が現実的でないことが多い。そのため、実射時には射手の後方に別の隊員が待機し、薬莢回収を担当する。回収用の道具は簡易な虫取り網である。後方の回収係が逐次薬莢を拾い集めることで、紛失を防止する。

にもかかわらず、薬莢の紛失は完全には防げない。強風や地形、発射角度、草むらや斜面への落下など、回収を困難にする要因は多い。紛失が発生すればその場で報告・捜索を行い、回収できなければ上申・記録の対象となる。薬莢は単なる金属片ではなく、訓練管理、環境対策、さらには第三者の手に渡った場合の安全上の懸念(誤使用や不安の種になる可能性)があるため、厳格な扱いが求められる。
実務上の運用ポイントを列挙する。
-
空包射撃ではカートキャッチャーを用い、射手側で回収完結を目指す。
-
実弾射撃では回収係を配置し、排莢経路を想定した配置・動線で拾い上げる。
-
射撃場は事前に風向き・地形を確認し、回収を容易にする整備を行う。
-
回収した薬莢は数を確認し、射撃記録と突合する。紛失があれば捜索記録と上申を残す。
-
環境への配慮(散乱金属の回収)と、地域住民への説明対応も運用上の必須項目である。
背後にある防衛理念:空包も「弾薬」として扱う厳格な管理
ニュースで報じられるこれらの事例からも分かる通り、自衛隊は空包1発の紛失でも見過ごさず、全力で回収する運用を徹底している。
これは規律面の扱いである。薬莢紛失は重大な管理不備と見なされる場合があるため、発見・報告・捜索といった初動対応の速さが問われる。
自衛隊では実包・空包を問わず「薬きょうは弾薬に準じた厳格管理」が義務付けられている。演習後には全数回収が原則で、1発でも不足があれば「大捜索」や「再出動」が命じられるほど。
その背景には以下の理由がある:
-
未回収の場合、実弾との混同や流出・悪用につながる可能性
- 国内外への安全と信頼性を損なうリスクを払拭
「たかが薬きょう、されど薬きょう」。一発の重みは、銃の先にある命の重みと同義である。そんな“鉄の規律”が、今日も自衛官たちの足元を支えている。
その厳しさは、戦闘力を支える裏方としての責任感と倫理感が根底にあるからだ。