受信機・無線・デジタル機器に命を懸けてきた筋金入りマニア御用達の雑誌「ラジオライフ」。言わずと知れたガジェット・裏技系の専門誌です。
そんな硬派なメディアが、かつてとんだ濡れ衣を着せられたのをご存じでしょうか。
1984年のグリコ・森永事件の報道合戦中、ある週刊誌の記者が無知と偏見から「ラジオライフは警察無線の妨害方法を指南している」と堂々とデマを掲載したのです。
これにはさすがの編集部も堪忍袋の緒が切れ、公式に反論。

ラジオライフの歴史、それは警察当局側と送信で暴れる過激派との果てしなき攻防、それを遠巻きに見守る受信者の記録とも言えましょう。
当時、警察波にちょっかいを出す“妨害行為”には、送信改造されたアマチュア無線機が使われていました。
アマ無線のVHF帯144〜145MHzに対し、警察などの“官波”は147〜149MHz付近。あとはお察しのとおり、改造なんて朝飯前。

確かに、ラジオライフ誌は警察装備や無線システムの特集と並んで、アマ機の改造ネタも多く取り上げておりました――そう、「受信改造」に限って、ですけどね?
にもかかわらず、「妨害指南雑誌」などと週刊誌が書き散らす始末。
あのさ、「受信マニアの情報誌」がいつ「送信マニア御用達」になったんですか? 違法送信を推奨?まさか。
つまり、ラジオライフが過去に掲載した「改造マニュアル」系の記事、あれ全部“受信改造”に限った話。
送信? 妨害? そんなもんは最初から御法度。編集部のスタンスは一貫して「妨害絶対NG」なのだから、それも頷ける。
言うまでもなく「警察無線」に関しては、筋金入りの受信至上主義のラジオライフ。
事実、同誌やその別冊が「警察無線を妨害するための送信改造法」を掲載したり、煽り立てたことはない。
なのに、そんな基本すら理解してない週刊誌の記者が、「おっ!こいつら警察無線のこと書きよる!きっと無線妨害の指南に違いない」とセンセーショナルに煽ったもんだから、あとはもうお決まりのコース。無知な週刊誌読者である一般大衆を騙くらかしたわけです。
これに堪忍袋の緒が切れたのが、当のラジオライフ1984年12月号。特集タイトルがまた最高、「THE・妨害 警察無線編」。沈黙を貫いてきた編集部が、ついに反撃の狼煙を上げた瞬間だったわけ。
ラジオライフ編集部、怒りの反論
これまで長年にわたり、「お門違いな批判」に対しては沈黙を貫いてきた(同誌編集部談)ものの、この時ばかりは無知と偏見にまみれた報道に堪忍袋の緒が切れたようです。
その抗議の意思を、明確かつ堂々と誌面で表明したのが1984年12月号の特集記事『THE・妨害 警察無線編』。
このタイトルだけ見たら、またどこぞの週刊誌が勘違いしそうだが、妨害された事例を紹介しているに過ぎない。
そもそもラジオライフという雑誌は、怪しげな陰謀雑誌でもなければ、電波で悪さを企てる不逞の輩のためのハウツー本でもありません。
電波と無線通信、受信機の性能、そして電子工作や盗聴防止技術に至るまで、いわば“周波数の世界を旅する人々”に向けた純粋な技術系情報誌です。
読者層もまた、それを裏付けています。アマチュア無線家、周波数フリーク、ガジェット愛好家、ミリタリーマニア、彼らは皆、知識と探究心を糧に、合法の範囲で受信を愉しむ“健全なオタク”たちです。
確かにラジオライフには、ちょっと変わった趣向もありました。全国から集まる「美人婦警さん」や「女性自衛官=公ギャル」の投稿写真、あるいは「覆面パトカー特集」など、読者サービス的要素もてんこ盛り。
毎号のように働く婦警さんが誌面を飾り、現場の空気感がバッチリ伝わる、読み応えのある投稿が掲載されていました。
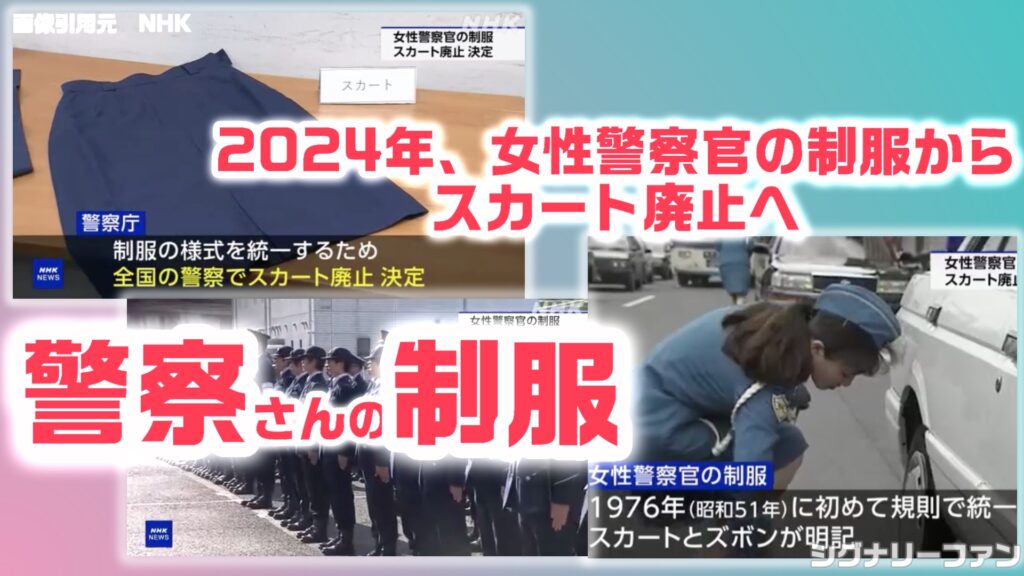
中でも覆面パトカーに関しては影響力が大きく、一部の車好きが「覆面っぽいカスタム」に手を出すほどに。
そうしたユニークな特集が話題になりすぎて、知らぬ者からすれば「なんだか怪しい雑誌だ」と誤解されたのも、ある意味では“お約束”だったかもしれません。
しかし、どれだけ誌面がバラエティに富んでいようとも、ラジオライフが一貫して貫いてきたのは“電波の正しい使い方”へのリスペクトです。
言うまでもなく、アマチュア無線の世界では「わいせつ電波」「妨害」「オーバーパワー」「オフバンド送信」などは、厳格にタブーとされる禁忌行為。
掲載された無線機の改造記事も、すべては電波法を遵守した「受信改造」の範囲内。つまり、送信を拡張する“違法改造”ではなく、あくまで受信の幅を広げる―それだけ。
それだけに、激怒したんですな。RLさんは。
『改造マニュアルは受信の本だ』
『送信の”そ”の字も載っていません』
『無知な記者はペンを握るな』
と、力強い行書体で各章の題を綴り、怒りを顕にしつつ正論パンチ炸裂してました。
しかも、単に技術だけではなく、法的な背景にもきちんと踏み込んでいたのが同誌の誠実さの証拠です。
電波法に関する専門家への取材や、弁護士による解説記事まで用意し、警察無線傍受がどのような法的位置づけにあるのかを、分かりやすく丁寧に解説してきました。
それを――ほんの見出しや一部の特集だけを抜き出して、「警察無線を妨害する改造法を載せている」と誤報をしでかした一部週刊誌の記者。いや、たぶん読んでないんでしょうな。
“あやしい雑誌”などと揶揄する前に、“事実かどうかあやしい記事”を書いているのはどちらだったのか。賢明なみなさんのご判断は?
送信改造はなぜいけないのか?
送信改造が問題視される理由は、端的に言えば「オフバンド送信」を可能にする違法な改造だからです。
こうした改造を施されたアマチュア無線機を持っているだけで、電波法違反による不法無線局開設罪に問われます。
ラジオライフ 1988年 12月号の「電波法違反事件を追う(第20回)」では、送信改造機を欲しがる人の心理も分析されています。
そこでは、人と違う無線機を持ちたい、同じ機種でも独自の改造がかっこいい、いたずら心や便利さ、周囲のマニア仲間からの影響など、動機は多岐にわたると分析されています。
そして共通するのは、「送信改造が重大な犯罪行為であるという認識の欠如」であると指摘しています。
当時の電波監理局でも完全に違法という認識を持って取り締まりに当たっていたことが記事からもわかります。
現在、一部のマニア間で「送信改造した無線機でも、アマチュアバンド外で送信しなければ違反にならないはずだ。現に時速200km出せる自動車に乗っていても、実際に時速100km以上出さなければ(高速道の場合)、捕まらないじゃないか」という論法がなされていますが、これは誤り。ある電監関係者はこうした風潮を「法知識に乏しい初心者を惑わし、不法行為を助長するような流言飛語は厳に慎んでほしい」と警告しています。
厳しい取締りが実際に行われている
電監当局はこの送信改造問題について「アマチュア無線用に製造、販売されている無線機を、わざわざアマチュア無線バンドを逸脱して送信できるように改造する行為に“正当な理由”があるとは認めがたい。もしこうした無線機を所持している場合、電波法110条1項に基づく「不法開設罪」として、厳正な対応をしていくことになる」と述べています。
引用元 ラジオライフ 1988年 12月号「電波法違反事件を追う(第20回)」
興味本位や虚栄心が、知らず知らずのうちに法律違反につながるという、警告めいた現実が浮かび上がります。
受信改造と送信改造を取り巻く当時の様相
とはいえ、『受信改造だからいい』というような、そう簡単な問題でもありません。
このグリコ・森永事件をめぐって、犯人自身が無線の知識を知り尽くし、アマチュア無線や警察無線の傍受を悪用したのが、グリコ・森永事件だったのです。

同事件において、犯人の遺留品からは受信改造された144MHz帯アマチュア無線機が発見されました。警察無線を傍受するために改造されたものだったのです。
ラジオライフ編集部は一線を守り、「送信改造」には一切触れず、合法的な受信改造のみを取り上げていたとはいえ、結局は受信改造も送信改造も悪用するユーザー側が問題でした。
また興味深い話ですが、ライバル誌はこの「タブー」を商機と見て、あえて踏み込んだ特集を組むという“危険な賭け”に出たのです。
1987年に創刊された『アクションバンド電波』誌です。
その経緯と顛末について、詳しくはこちらのサイト様を参照していただきたい。

まあ、このように当時複雑な様相を見せていたのもまた事実。
なんにせよ、頑なに守ってきたポリシーを一部マスコミに誤解され、面白おかしく書きたてられた当時のラジオライフ編集部さんの怒りは、相当なものだったに違いありません。
まとめ
以上、グリコ森永事件の報道合戦のさなか、無理解な一部マスコミにより色眼鏡で見られ『無線機を改造して警察無線を妨害する方法を指南している雑誌』と書き立てられ、それについて「事実と異なる」として激怒、反論した、とある専門誌のお話、いかがだったでしょうか。
それにつけても、マスコミのデマと扇動の恐ろしさ。そんなデマ報道がかつてのグリコ・森永事件の報道合戦で行われていたわけです。あ、今もか。

取材対象である警察に対して、深い愛と興味を持ち続けてきた雑誌だからこそ、ラジオライフが昭和から令和にかけてなおも刊行され続けている理由が、そこにあります。
「お巡りさんへのリスペクトとマニアとしての矜持を持て」―これが愛すべきラジオライフ編集部の警察ネタに関しての基本スタンスであり、我々読者への一貫したメッセージです。
今では、パトカーにカメラを向けただけで「Youtubeやめてくださーい」とPMに叱られる時代ですが、当時は「ラジオライフ送ったら、サンダースおじさん人形みたく道頓堀放り込むどアホ!」と真顔で怒鳴られる時代だったのです。
他の関連記事もぜひご覧ください。




















































































































