一般には知られていない“警察の言葉”─通話コードと専門用語の世界
街なかで警察官が無線を用いてやりとりしている場面を目にしたことのある方は多いのではないでしょうか。
しかし、そこで交わされている会話の内容は、なかなか理解しづらいものです。
たとえば、こちらの映像は愛媛新聞社が報じた「愛媛県警 通信指令技術競技会」の様子です。最前線の捜査員と通信指令室が無線で連携する様子が再現されています。
『至急、至急。松山北です、どうぞ!』、『なお救急はすでに手配済み!マルモクの確保に努めよ、どうぞ!』
こうした警察無線の交信では、通話コードや略語が次々と飛び交い、緊迫した現場の空気がそのまま伝わってくるようです。
「マル被(被疑者)」「マル暴(暴力団関係者)」といった表現はドラマなどで耳にすることもありますが、「サンマル」や「イチサンマル」など、数字による通話コードの存在については、あまり知られていません。
警察の内部では、無線通信の際に用いられる「通話コード」や、日常業務の中で使われる専門用語が多数存在します。これらの用語は、現場における迅速な意思疎通や、秘密保持に大きな役割を果たすのです。
本記事では、警察無線が報道現場でオープンソースとして、まだ傍受可能だった時代に実際に使われていた通話コードや警察用語について、その目的や具体的な表現例を交えながら詳しく紹介いたします。
どうぞ、目次から気になる箇所を選んでお読みください。
本記事は、かつて運用されていたアナログ警察無線の技術的変遷や制度背景について、公開情報や専門誌の報道に基づき解説するものです。現行の警察無線はデジタル暗号化されており、暗号通信の解読は不可能かつ違法です。本記事は違法な受信や行為を助長・推奨するものではありません。電波法等の法令遵守を前提としてご理解ください。
警察官が無線交信時に通話コードや略語を積極的に使う理由
まず、警察官が無線交信時に通話コードを積極的に使う理由は主に以下の二つ。
簡潔めいりょうな無線通信のため
本来、無線通信は警察無線に限らず、簡潔明瞭な交信が基本原則です。
なぜなら国際的に取り決められた国際電気通信条約附属無線通信規則の無線局運用規則第10条、無線通信の原則 (Principle of Radio Communication)で定められているからです。
簡潔な交信を行えば、一回の通話時間も短くでき、同じ周波数を共有する多数の無線局のリソースを奪いません。
長々しい言い回しより、適切に定められた通話コードや略語を用いた簡潔明瞭にテンプレ交信すれば、聞き間違いなども防げます。

第三者から交信内容を秘匿するため
もうひとつの理由は交信内容の秘匿。電波の拡散性を考慮し、常に交信内容は秘匿が必要です。
もっとも、お伝えしているとおり、わが国警察無線は高度なデジタル変調と暗号化により、外部の人間は受信できません。

したがって、通常は警察当局側が報道発表しない限り、交信が明らかになることはありません。
ただし、無線を使っている警察官の周囲の部外者や一時拘束した者に聞かれる恐れがあります。
従って、警察官の使う略語や通話コードは同時に暗号化になり、部外者に対しては適切に交信内容の秘匿が図られるというわけです。
これら「警察用語」の使用については、実際に各都道府県警察の無線運用規則により、その積極的な使用が定められています。
警察無線で暗号を使える法的根拠
暗号とは通信の当事者、すなわち同じ組織内に所属する相手方のみしか理解できない用語。まさに警察官が警察無線で使用する通話コードがそれに当たります。
電波法第58条では「実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない」と規定されています。
アマチュア無線で暗語を使用してはいけない理由はアマチュア局の通信の相手方が「不特定のアマチュア局であること」や「アマチュア業務に秘匿すべきものがない」ことなどが理由。
しかし、実験等無線局及びアマチュア無線局以外が暗語を使ってはいけないとは定められておらず、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、また民間では警備会社、タクシー会社など多くの業務無線で暗語、すなわち通話コードが使用されているのが現状。
変わったところでは漁師さんの使う漁業無線も秘話をかけたり暗号を使っています。これは漁獲高の無線報告で他の業者に良い漁場を悟られないためです。

一般的な警察用語と警察無線の通話コード
それでは警察無線で実際に使われる通話コードにはどのようなものがあるでしょうか。
警視庁のようなメジャーな警察本部が使うものが有名になりがちですが、警視庁の通話コードが全国標準なのかといえば、そうではありません。
本来であれば、通話コードは純粋に「数字」のみが使われます。ただし、都道府県が違えば通話コード/警察用語も違います。
警察用語としては、日本語、こじつけ、言い換えなどさまざまな手段を使って、元々の言葉を秘匿してる用語が多数です。意味がわかると、思わず唸ってしまうものも。
手元に資料として『ラジオライフ1988年11月号』がありますが、同誌に掲載されている各都道府県警察の通話コード表を参考に、用語ごとに各県警の違いを研究してみます。
もっとも、以下の通話コードは30年以上前のアナログ時代のものです。
「と呼んでいます」は「と呼ばれていました」と過去形になっているかもしれません。ご了承ください。
マルモク
目撃者。単に「モク」とも。
P系(PM、PS、PC、PB)
「POLICE」の頭文字であるPとそれに続く警察用語を組み合わせた使用法です。例えば、ポリスマンのPMは警察官/捜査員の意味。また、PSはポリス・ステーション、つまり警察署。PCはパトカーです。交番(ポリス・ボックス)はPBです。
パトカー関係
基本的にパトカーは『PC』ですが、警視庁では以前から単に『カー』と呼んでおり、先ごろ公開された地下鉄サリン事件当時の同庁の無線交信でも警察車両を『カーあれば向かってください』と呼んでいるのがわかります。
なお、1986年2月号のラジオライフ誌上にて“まれにカーというだけでパトカーを意味することがあります”と記載されているため、30年以上前から『カー』が使われているのは間違いないようです。
覆面パトカーの場合、大阪府警ではゼロパトと呼ぶ一方、マル覆と呼ぶ県警も。
パトカーの緊急走行を表す通話コードも各地方で違い、道警はRED、大阪府警は500、広島県警は200など。
母屋(おもや)
所轄警察署(員)から見た警察本部のことです。90年代に放映された、さる人気刑事ドラマの影響で所轄署員が警視庁を“本店”と暗語で呼ぶことが知られましたが、母屋は、分家や支店に対して本家や本店の意味があります。
至急報
母屋側、PCやPM側のどちらも送話の前に『至急、至急』と前置きすることで、扱いが最優先になります。

照会関係
その筋にはもっとも有名と言っても過言ではない『123』。これは警視庁の照会センターを意味する通話コードです。
各都道府県警察本部はそれぞれ、総務部情報管理課の中に『照会センター』を置いており、センターには個人の前科前歴、行政処分履歴、さらに失踪届けなどのセンシティブな情報がすべて電子データとして集積されて管理されています。
警視庁の場合は職務質問などで照会センターに照会を行う場合、『123願います』と発します。
123は厳密には”照会”そのものの意味ではありません。埼玉県警では単に『照会センター』、静岡県警、愛知県警では『0123』となっています。
職務質問で前科前歴照会をするにあたり、まずすべきことは無線で照会センターに繋ぐこと。所轄のPMの場合、本署のリモコンに要請し、リンク後、照会事項(総合、A号、L2などなど)が送られます。
かつてはPATシステムなど音声以外の照会方法もありましたが、現在は新型デジタル無線のIPRに統合。

職務質問を行う地域警察官や機動捜査隊などから123の要請を受けると、照会センター職員はただちに対象者の氏名生年月日、免許証番号から、蓄積されているデータとの突き合わせを行い、照会結果を通話コードで返します。
ラジオライフ2006年2月号の61ページによれば、照会時に返ってくる各コードについては全国共通。「01」が殺人、「02」が強盗、「03」が強姦、「04」が窃盗、「05」が公務執行妨害、「06」が暴行、「07」が銃刀法違反、「09」が凶器準備集合罪、「10」が放火。
対象者に何らかの犯歴があれば、照会センターから『ヒット』が返されます。
指名手配中ならB号、家出中で捜索願が出されていたならばM号などと、各種の通話コードで返ってくるわけ。
犯歴がない者は照会センターにそれらのデータがないので、該当がない場合は「00(ゼロゼロ)」あるいは「該当なし」と返されます。
かつては「パトカー照会指令システム(通称・PATシステム)」による照会も。
80年代に全国ネットで整備された警察専用の情報通信システムであるPATは、平成24年時点で全国3000台の警察車両に搭載。現在は新型無線システム『IPR』に統合、更新済みですが、自動車警ら隊などが対象者の身分証などから身元照会を行う際、警視庁の他、各警察本部で運用していました。
デジタル基幹系無線の搬送波にPAT用データ通信の電波を重畳させる方式で(現行のカーロケと似ている)、各都道府県警察の照会センターの大型コンピュータに蓄積されている情報データベースにパトカー端末からアクセスし、対象者の前科、指名手配など照会可能でした。
一方、徒歩やチャリで警らを行う外勤の地域課員が照会を行う場合はPSWと呼ばれる署活系無線を使います。
署活系無線でも照会できるシステムがありましたが、警視庁と大阪のみで全国整備はされませんでした。
反社関係
警視庁では暴力団をマルB、単にBと呼びます。北海道警や香川県警、大阪府警はマル暴。一方、佐賀県警では20、鹿児島県警では90、兵庫県警では520、奈良県警では801、京都府警では840などと数字コード。
暴走族関係
今や絶滅危惧種ですが、全国的に『マル走』が多いようです。
一方、京都府警では『マルS』『マルサ』のほか、4輪の場合はマル特、二輪の場合はヨコイチ。岡山県警は611。
佐賀県警は暴走族および同取締りを500と呼んでいます。
朝鮮人
警視庁では朝鮮人を『マル鮮』と呼び、大阪府警では『920(国マル)』、岐阜県警では『400』、兵庫県警では『680』と呼んでいます。
なお、”マルセン”の読み自体は北海道警察では有線連絡(電話)を意味する『マル線』と同じです。
有線連絡
緊急事態には警察官が無線ではなく電話(有線)連絡することも。有線連絡を表す通話コードは『マル有』が多いようです。
兵庫県警では『221』、道警では『マル線』。
この『マル有』には逸話も。街角で制服警察官が署活系無線で『マルユウ願います』と言った(あるいは本署から指示された)のを偶然、近くを歩いていた女性が聞き、郵便貯金の利子に対する非課税制度「ゆうちょマル優制度」と勘違いし、警察官が勤務中に無線で貯蓄を頼むって、どないやねん……と、大阪の新聞社に投書したそうです。
しかし言うまでもなく、それは有線連絡を表す警察の通話コード『マル有』のこと。投書を受けた新聞社のデスクは、これが有線連絡を意味する大阪府警の警察用語であることを紙面で読者に説明しました。折しも当時はマルサ(の女)やマル金、マルビ(貧乏)という言葉が流行語に。デスクはこれらを挙げ、『近頃はマルばかり。警察の世界にも”伝染”したのかな』と結んでいます。出典は昭和62年6月2日の毎日新聞大阪版『デスクです』より。
ホームレス、野宿者
大阪府警ではホームレスの人を「ヨゴレ」と呼んでいます。読売テレビでも紹介されています。
警察関係用語で、「ホームレス」や「浮浪者」のことを「ヨゴレ」と呼びますが、それと関連はあるのでしょうか?
出典 https://www.ytv.co.jp/announce/kotoba/back/2501-2600/2576.html
被害者
全国的には『マルガイ』、『害者(ガイシャ)』ですが、大阪府警では『330』と呼んでいます。
精神病
警視庁では精神病またはその可能性がある人を「マル精」のほか『精』の字のこめへんから「こめへん」や「マルコメ」と呼んでいます。愛知県警は『413』。
一方、大阪府警では『頭の330』。前述の“被害者”を意味する330に“頭”をつけるわけですから、ひどいスラングになります。
ところで北海道警察では『サイコ』なる言葉も。これはススキノの首切り娘のような人物ではなく、“妻子”を意味する用語だそうです。
変質者・露出関係
警視庁では男性の体の一部分を『センターポール』と呼んでいたのは有名です。
例えば『20代くらいの男がセンターポールを露出させながら駅前の路上を徘徊……』など。これぞ事実を覆い隠すと云う意味ではまさに警察無線を代表する通話コードです。
ただ、女性警察官は使わなかったとのことです。
任務解除
警視庁では「517」。とくに機動隊の警備において使われますが、転じて“警察官の退官”を指す場合も。
お食事
警察官の昼食、とくに弁当や出前を『マル食』と呼んでいたようです。これが使われたのは基幹系よりもゆるい署活系。

昼飯のメニューなどパトロールに出る前に決めておけばいいのに……という単純な問題でもなく、絶対服従の警察の上下関係の確認行為や無線の通話試験や訓練も兼ねていたようです。
なお、岐阜県警では肉まんを『290(ニクマル)』と呼んでいたようです。
まとめ
知れば知るほど興味深い、警察の“言語体系”の一端。いかがでしたか。これら、略語や通話コードは全国で統一されておらず、ところ変われば、がらりと変わるもの。
その都道府県警でしか使っていない、ご当地用語もあり、全国統一されていないところもポイントです。
したがって、一見同じ通話コードでも県警によっては全く別の意味になることがあり、注意を要することも。
例えば岐阜県警で『512』は『爆破予告』ですが、山梨県警では『ひき逃げ事案』です。また一般的にマルBは暴力団ですが、岐阜県警では秘話機能(もっとも、現在の警察無線はすべて暗号化されているので、この用語は廃止されているでしょう)です。
あるいは警視庁では照会を123と呼びますが、秋田県警などでは124、単に照会センターと呼ぶ警察本部も。
なお、無線でこのような通話コードを使用するのは警察だけでなく、消防も同様です。ラジオライフ2006年11月号によれば、消防の通話コードは少数ながら全国共通コードもありましたが、現在は組織ごとに違うコードを使用しているとされ、こちらも消防組織が違えば通話コードも異なるようです。

岡山県瀬戸内市消防本部の通話コード例 引用元 ラジオライフ2006年11月号 177ページより
例えば、ラジオライフ2004年9月号によれば、北海道の札幌市消防局の通話コードでは「死亡」をマルヨン、「爆破予告」をマルバク、「生活保護」をマルセイ、「伝染病」をハチマル、「放火」をヒトマル、「犯罪」をゴーマル、「警察(官)」をイチマルマルと紹介。一方、東京消防庁ではがらりと変わり、「警察(官)」が554、「組織暴力」は858、「死者」は954、「放火」は951など。
なお、機械警備大手でも警察と同様の通話コードを使用する場合が。
現在では第三者がデジタル警察無線の内容を復号できないため、通話コードや略語を使う必要性は薄れてはいるものの、警ら中の地域警察官が職務質問を行う際、署活系無線による身元照会などでは無線機から前科前歴がズラズラ流れてきたとたんに、目の前の対象者にダッシュで逃げられる恐れも。
そのため、照会担当者も『(前科前歴などが)複数ヒット。送ってよろしいか?』と、今まさに対象者の目の前にいるであろう警察官に対して配慮しています。
ただし、自動車警ら隊などはパトカー車載の端末によるデータ照会を行うため、音声での照会は行わない場合も。
というわけで、本来の意味を別の数字や語句に置き換えることで第三者に意味を悟られることを防いで、通信内容を秘匿するアナログ警察無線時代の名残りとも言えるのが、通話コードです。
警察官が使用する理由は簡潔明瞭な交信のため、そして第三者に対して意味を悟られにくくする暗号化のため、というわけです。
もっとも、本当に重要な警察用語は一般に知られては意味を成さなくなるので、公になることはないのでは。
なお、こうした通話コードといえば、アメリカの警察が使用する「テン・コード」が有名かもしれません。これは映画やゲームなどの影響もあり、広く知られるようになっています。
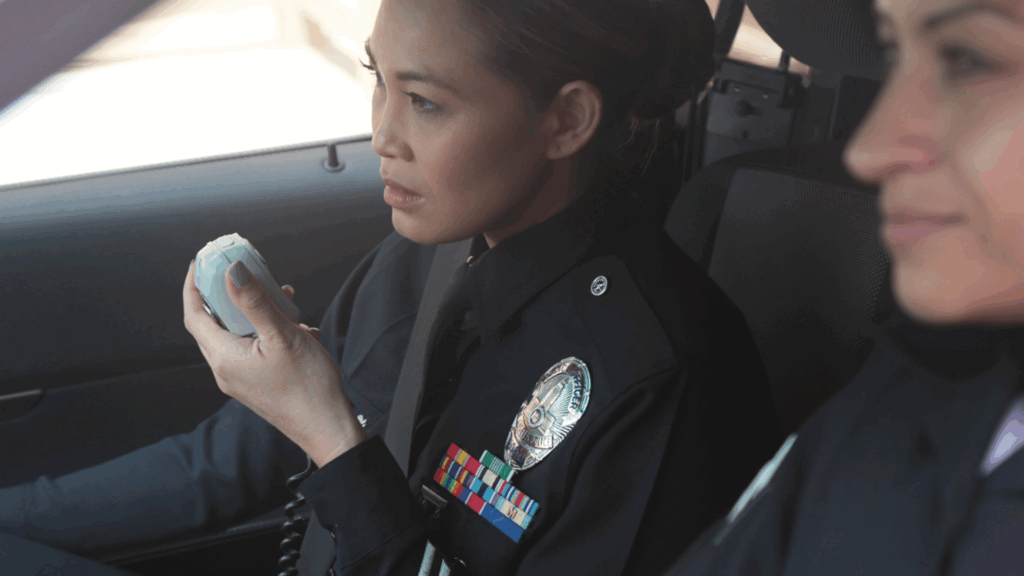
たとえば、人気ゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズでは、舞台となる「ロスサントス」がロサンゼルスをモデルにしており、同市警察(LAPD)を模した「LSPD(ロスサントス警察)」が登場します。
ゲーム内では、実際のLAPDと同様にテン・コードが使用され、リアルな警察無線の雰囲気が再現されています。
また、映画『ナイトクローラー』では、ロサンゼルスの街を夜通し車で走りながら、警察の出動情報を傍受して事件・事故現場にいち早く駆けつける“ストリンガー”という職業の主人公が描かれています。
彼は車内に搭載したスキャナー(広帯域受信機)を頼りに、無線から流れる事件情報を収集しています。

作中では、警察のディスパッチャー(指令担当者)から無線で発信される通報内容に耳を傾け、テン・コードやLAPDの独自コードを聞き取って即座に内容を解読します。
事件の種類や発生地域、さらにはどのニュース局が好みそうなネタかまで瞬時に判断し、迷うことなくアクセルを踏み込む姿は、まるで市場を見極める投資家のようです。
このように、通話コードや無線通信の言語体系には、映画やゲームを通しても触れる機会があり、私たちが普段意識していない“裏側の言葉”に興味を持つきっかけともなっています。
今では基本的に聴けない日本の警察無線。しかも、ただの数字の羅列にしか聞こえない通話コード。かつては日本でも、まさにアナログ警察無線を新聞記者やジャーナリストたちが一情報源としていたのです。


他の関連記事もぜひご覧ください。

















































































































