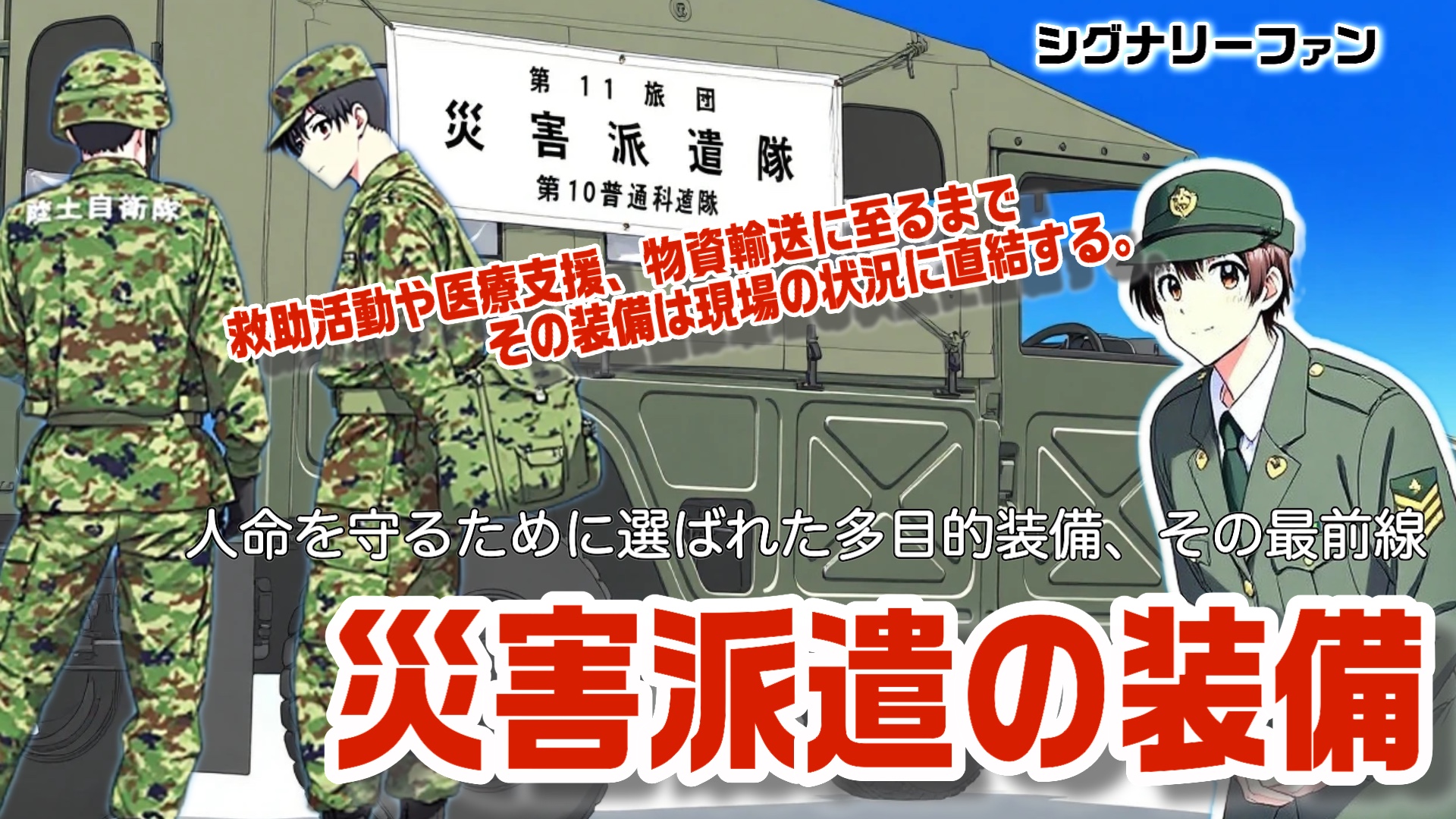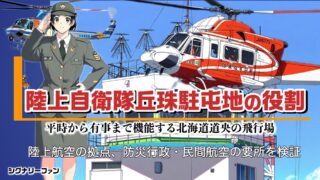いわゆる弾道ミサイルとは、通常弾頭に加えて、核、生物(ウイルス・細菌)、化学(毒ガス)といったさまざまな種類の弾頭を搭載し、1万キロ以上離れた敵国に着弾させて攻撃できる大量破壊兵器を指します。

日本が長年にわたって脅威にさらされているのは、中国や北朝鮮の高性能弾道ミサイル、特に北朝鮮によるミサイル発射実験です。
1998年には、北朝鮮政府が「人工衛星の打ち上げ」と称して、日本の東北地方上空を飛び越える形で弾道ミサイル『テポドン』を発射する事態が発生しました。
この際、日本政府は自衛隊や警察の情報収集活動により、発射前から一定の発射兆候を把握していたとされています。

こうした脅威に対応するため、日本は2004(平成16)年度から本格的にミサイル防衛(MD)システムの整備に着手。
しかし、その後も北朝鮮は弾道ミサイルの発射を繰り返し、緊張が続いています。
日本はこれらのミサイル発射に備え、航空自衛隊のペトリオットミサイル(PAC-3)を全国に展開させるとともに、海上自衛隊のイージス艦による迎撃態勢を敷き、不測の事態に備えてきました。
これまでのところ、実際に弾道ミサイルを迎撃する事態には至っておらず、発射されたミサイルはいずれも日本列島を飛び越え、太平洋へ落下しているため、人的被害などは発生していません。
それでは、周辺諸国における弾道ミサイル配備の状況、そして日本はどのようにして弾道ミサイルから国を守ろうとしているのか見ていきましょう。
新たな脅威・弾道ミサイル「北極星2号」
近年、北朝鮮政府の弾道ミサイル開発は目覚ましいスピードで進展しています。
特に2017年2月12日、北朝鮮は新型中距離弾道ミサイル「北極星2号」の発射を行いました。
このミサイルは、従来の液体燃料タイプではなく、個体燃料を使用することで発射プロセスを大幅に簡略化しました。
従来の液体燃料タイプのミサイルは、発射準備に数時間を要し、そのためアメリカ軍の軍事衛星によって発射の兆候を事前に察知することが可能でした。
しかし、「北極星2号」では燃料が個体化されたことで、発射にかかる時間はわずか数分に短縮され、事前に察知することが難しくなっています。
このため、従来の監視体制においては対応が困難となり、さらなる脅威となっています。
また、北朝鮮だけでなく、中国の弾道ミサイルも無視できません。
特に「東風21号」は、中国の戦略ミサイル部隊である第二砲兵隊が配備している核搭載中距離弾道ミサイルです。
このミサイルは、日本の主要都市を標的としており、250kt型水爆を搭載しています。この核弾頭は、広島型原爆約16発分に相当する威力を持つとされています。
そのため、東京をはじめ、札幌市、大阪市など全国の政令指定都市が照準にされている可能性が高いと考えられています。
2014年に外務省が委託した専門家による研究によれば、人口100万人の都市において1メガトン級の水爆が爆発した場合、その被害は長崎の50倍、広島の60倍に達し、約37万人が命を落とし、熱線による影響で14キロメートル先まで被害が広がり、さらに46万人が負傷するという試算が出されています。
水爆が一発直撃すれば、日本は甚大な被害を免れないとされています。
弾道ミサイル迎撃のための日本の防備とは
では、そんな脅威に対して日本の自衛隊はどのように立ち向かっているのでしょうか。
日本の防衛力と弾道ミサイル対策
自衛隊は普段から、他国の無線通信を傍受したり、航空自衛隊が各分屯基地に配置する高性能レーダー(FPS-5、FPS-3、FPS-7)を駆使しています。

また、情報収集衛星や自衛隊員によるヒューミント(人的情報収集)活動を行っています。

また、サイバー防衛隊のハッカーたちがネット上でその痕跡を探し、情報収集活動を行うことで、ミサイル発射兆候や飛来の監視を強化しています。
特に、2004年から日本はミサイル防衛(MD)システムの整備を始め、イージス艦に弾道ミサイル対処能力を持たせ、PAC-3の配備を進めることで、弾道ミサイルからの攻撃に対して自衛隊が対応できる体制を確立しています。

航空自衛隊の重要な役割
航空自衛隊においては、弾道ミサイルの探知、識別、追尾を行うための警戒管制レーダーが非常に重要な役割を果たしています。
日本全国には13箇所(令和元年現在)の航空自衛隊のレーダーサイトが設置されており、北海道から沖縄までの広範囲で、切れ目のない警戒監視活動が行われています。
これにより、特に中国や朝鮮半島からの弾道ミサイルなどに対して目を光らせており、ミサイル発射の兆候を早期に察知する体制を整えています。
ミサイル発射に備えて、24時間365日体制で全国各地のレーダーが収集した情報を一元的に処理しているのが『ジャッジ』と呼ばれる自動警戒管制システムです。このシステムは新バッジ(BADGE)とも呼ばれ、迅速な対応を可能にしています。
アメリカとの連携
一方、アメリカ軍は高性能な前方警戒レーダー「Xバンドレーダー」を配備しており、日本の航空自衛隊基地にも米軍の「Xバンドレーダー」が設置されています。
このレーダーはミサイルの発射をほぼ瞬時に察知し、着弾予測を即座に算出。
算出された情報は、洋上航行中の海上自衛隊のイージス艦に瞬時に伝えられ、迎撃命令が出される仕組みになっています。
また、弾道ミサイル発射後には、総理大臣の判断を待つことなく、現場の自衛隊指揮官が即座に迎撃指令を出せる体制が整えられています。
これにより、非常に迅速な対応が可能となり、日本の防衛力は着実に強化されています。
破壊措置命令と迎撃の手順
弾道ミサイルが日本に向けて発射された場合、最初に下されるのが「破壊措置命令」、つまり迎撃指令です。この命令は、防衛大臣によって出されます。
弾道ミサイルが発射されると、まずは「ブースト段階」に入ります。ここではミサイルが加速しながら宇宙空間へと飛び出します。
その後、「ミッドコース段階」を経て、大気圏に再突入する「ターミナル段階」に進み、最終的に目標へ着弾します。
自衛隊は、宇宙空間での迎撃を「ミッドコース迎撃」、大気圏内での迎撃を「ターミナル段階迎撃」とし、それぞれで対応します。
イージス艦による迎撃
迎撃の最初に出動するのは、海上自衛隊のイージス艦です。イージス艦には「SM-3ミサイル」が搭載されており、これを用いて宇宙空間での迎撃を行います。
イージス艦の特徴的な外見として、艦橋の側面に設置された八角形の盾がありますが、これが「フェーズドアレイ・レーダー」のアンテナ部です。
現在、SM-3ブロックIIAは日米共同で開発中であり、2017年2月にハワイ沖で行われた迎撃試験では、模擬弾迎撃に成功しました。
地上迎撃:PAC-3の出番
万が一、イージス艦によるSM-3ミサイルがミサイルを迎撃し損ねた場合、次に出動するのが地上に配備された航空自衛隊の高射部隊と「PAC-3ミサイル」です。
PAC-3は大型トレーラーを利用したシステムで、全国各地への迅速な展開が可能です。
以前の「PAC-2」は主に航空機を迎撃するためのシステムでしたが、「PAC-3」は弾道ミサイル迎撃に特化。
その射程は数十キロメートルに及び、大気圏内での最終迎撃を担当します。
北海道長沼町にある航空自衛隊長沼分屯基地には、第11高射隊と第24高射隊が駐屯しており、これらの部隊は湾岸戦争でその優れた能力を証明した「ペトリオットミサイル」を用いて、弾道ミサイルの迎撃を行っています。
他の迎撃方法
さらに、ミサイル迎撃の新たな手法として、アメリカ軍が開発中の「空中発射レーザーシステム」があります。
これは、メガワット級の酸素-ヨウ素化学レーザー(COIL)を利用して、ミサイルの燃料タンク付近をレーザー光線で加熱し、その爆発を誘発させるという技術です。
このシステムはボーイング747型機に搭載され、実際の迎撃実験も行われています。
核ミサイルは誘爆するのか?
弾道ミサイルがもし核ミサイルであっても、迎撃時に誘爆する可能性は低いとされます。
核ミサイルの起爆システムは精密かつ複雑で、迎撃による外部からの爆発で誘爆する可能性は極めて低いのが技術的な見方です。
ただし、上空で迎撃した場合、核ミサイルに搭載されているプルトニウムなどの核物質が広範囲に散らばる可能性は残ります。
ミサイル防衛のまとめ
中国や北朝鮮が配備する弾道ミサイルの標的とされている日本の主要都市。
これに対し、日本は弾道ミサイル防衛(MD)システムを構築し、さまざまな手段で対応しています。
具体的には、以下の対策が取られています。
-
レーダーサイトによる警戒監視
日本全国には、航空自衛隊のレーダーサイトが設置され、常に弾道ミサイルの発射兆候や飛来を監視しています。これにより、弾道ミサイルの発射を早期に察知し、迅速な対応が可能となります。 -
情報収集とスパイ活動
自衛隊は、他国の無線通信傍受や情報収集衛星を使って、日々の警戒監視を行っています。さらに、サイバー防衛部隊もネット上の痕跡を追い、ミサイル発射の兆候を探る活動を行っています。 -
SM-3迎撃ミサイル(上層迎撃)
海上自衛隊のイージス艦にはSM-3迎撃ミサイルが搭載されており、これを用いてミサイルが宇宙空間に出た後の「ミッドコース段階」で迎撃を行います。この迎撃は、弾道ミサイルがまだ大気圏に突入していない段階で行われ、最も早期に対応できる方法です。 -
PAC-3ペトリオットミサイル(下層迎撃)
万が一、SM-3で迎撃しきれなかった場合、今度は地上に配備された航空自衛隊のPAC-3ペトリオットミサイルが登場します。これは、大気圏内でミサイルが目標に接近した際の「ターミナル段階」において、最終的な迎撃を担当します。
これらのシステムは、24時間体制で監視と対応を行い、二段階で弾道ミサイルの迎撃を実現しています。こうした体制を整備することで、迅速かつ効果的な対応が可能となり、国民の安全を守るための重要な役割を果たしています。
参考文献 防衛省公式サイト https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/bmd/