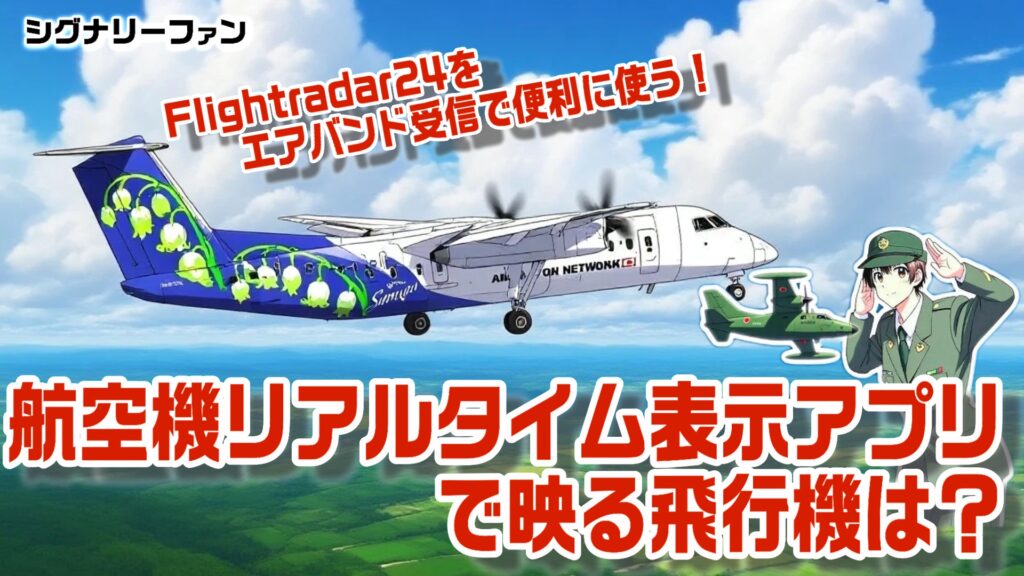実は2つある!自衛隊の「政府専用機」
政府専用機と聞けば、今でも長らく航空自衛隊が運用してきたボーイング747型機を思い浮かべる方が多いかもしれない。
【退役】旧型政府専用機(Boeing 747-400型)
政府専用機は、日本の外務・外交の現場で重要な役割を果たしてきた機体であり、特に初代モデルである Boeing (ボーイング)747-400 型 は、その象徴的存在だった。
主要スペックとしては、全幅約 64.9 メートル、全長約 70.7 メートル、高さ約 19.06 メートル。エンジンは4基搭載。巡航速度はマッハ約0.92、航続距離はおよそ13,000km 程度とされている。
陸上自衛隊の政府専用ヘリ ― EC225「スーパーピューマ」
しかし実は、陸上自衛隊にも「政府専用機」が存在する。こちらもヘリコプターによる要人輸送に特化した機体である。
日本の政府高官や皇族の国内移動を支える空の手段として、陸上自衛隊が運用する政府専用ヘリコプターがある。
運用母体は、千葉県の木更津駐屯地に司令部を置く第1ヘリコプター団・特別輸送飛行隊であり、この部隊は国の重要人物を迅速かつ安全に目的地へ移送するための専門部隊として編成されている。
この任務のために導入されたのが、フランスのユーロコプター社(現・エアバス・ヘリコプターズ)製のEC225「スーパーピューマ」だ。
かつて配備されていたAS332L1「シュペルピューマ」の後継機で、2005年以降、順次交代が進められた。
AS332は信頼性の高い中型輸送ヘリであったが、老朽化と性能向上の要請に応える形でEC225が採用された経緯がある。
内装と装備
この専用ヘリの内部には、革張りのシートと赤いカーペットが敷かれたVIP仕様のキャビンが設けられており、陸上自衛隊で多数配備される多用途ヘリとは明確に一線を画している。

外観こそ制空迷彩じみたグレーの塗装で軍用機らしさを備えているが、機内は空飛ぶ迎賓室とも言える仕立てで、政府要人や皇族の移動にふさわしい静粛性と快適性を提供している。
運用体制の特色
この政府専用ヘリは首都圏への即応性を重視して、陸自・木更津駐屯地に拠点が置かれている。
これにより、東京23区や官邸・皇居・赤坂御用地といった政治中枢との近接性が高く、短時間で要人の移動が可能となっている。
一例として、木更津・羽田の離着陸、あるいは立川駐屯地を経由した地方都市への中継移動など、多彩な運用パターンが確立されており、現代の日本における空の要人移送インフラの一翼を担っている。
航空自衛隊の政府専用機 ― ボーイング777-300ER型機
日本国政府の要人輸送に用いられる「政府専用機」は、航空自衛隊の特別航空輸送隊(Special Airlift Group)によって運用されている。
配備基地は北海道の航空自衛隊・千歳基地で、同隊は要人の輸送任務に加え、乗員の訓練や整備体制もすべて千歳で完結できるよう設計されている。
政府専用機は長年にわたり、ジャンボジェットの愛称で知られるボーイング747-400型機(通称:旧政府専用機)が用いられていたが、老朽化と整備コストの問題から2019年(平成31年)4月1日付でボーイング777-300ER型機へと更新された。
機体は日本航空(JAL)の技術協力のもとで整備・訓練が行われ、同社のノウハウも活かされている。
運用目的と実績
政府専用機の主たる任務は、内閣総理大臣や天皇・皇族の海外公式訪問における輸送である。これに加えて、国際緊急援助活動・国連PKO・緊急時の邦人輸送・遺体搬送など、多目的での運用が可能となっている。
この機体は単なるVIP専用機ではなく、有事や人道的危機に際して即応性の高い空中輸送能力を発揮する国家資産でもある。
実際、2013年1月にアルジェリアで発生した邦人人質事件では、犠牲となった日本企業「日揮」関係者の遺体搬送に旧型機は使用され、現地での厳しい運航条件下で迅速な任務遂行が行われた。
新型機(777-300ER)の特徴
現在の政府専用機であるボーイング777-300ER型機(2機体制)は、以下のような仕様を備えている。
-
全長:73.9メートル(ジャンボ機より長い)
-
航続距離:約13,650キロメートル(長距離直行便が可能)
-
最大乗員数:約140名(要人用キャビン、随行員席、報道席などを含む)
-
特別通信機器と専用医療スペースの装備
-
空中給油機能はないが、世界中の主要国にノンストップで飛行可能
また、維持整備費が747に比べて大幅に削減され、地上支援体制も簡素化されている。
これにより、運用効率と柔軟性が大きく向上している。
政府専用機は単なる外交儀礼の象徴ではなく、平時・有事を問わず国家としてのプレゼンスと責任を果たすための戦略的航空資産である。
特別航空輸送隊はその運用を一手に担い、地理的に日本の中枢から遠く離れた北海道にあって、今日も24時間体制で出動に備えている。
「空中輸送員」─政府専用機に乗務する自衛官のもう一つの顔
政府専用機に乗り込む乗務員も特別航空輸送隊員である。その中でも、特に機内での客室サービスを担っているのが「空中輸送員」と呼ばれる自衛官たちである。
彼ら・彼女らは制服姿の自衛官でありながら、機内ではエプロンを身につけ、総理大臣や皇族、閣僚に対して上質な接遇サービスを提供している。
民間水準を超える接遇訓練
空中輸送員に選抜される隊員は、いずれも一定の容姿・礼節・対応能力を備えた者であり、選抜後には民間航空会社、主に日本航空(JAL)などでの実地研修を受ける。
女性隊員にはメイクアップや立ち居振る舞いに至るまで指導がなされるなど、細部にわたる接遇スキルが求められる。
こうした背景から、彼女たちの機内サービスは、一般のLCC(格安航空会社)とは明確に一線を画すと評されることもある。
さらに、身だしなみや所作に関しては、儀仗隊や広報要員と同等の水準が要求されており、外見や姿勢も任務遂行能力の一部とされている点が特徴的だ。
だが彼らは“戦う自衛官”でもある
しかし、空中輸送員はただの「空飛ぶ案内係」ではない。そのもう一つの顔は、「戦う乗員(Combat-ready Crew)」である。
彼らは閉所戦闘(CQB)や護身術、拳銃射撃などの戦技訓練を定期的に受けており、特に女性隊員であっても9mm拳銃を用いた実戦的な訓練を欠かさない。

著名な報道カメラマン・宮嶋茂樹氏も、自身の著書やウェブサイトでこの事実を明らかにしている。
特に空中輸送員の中には、拳銃射撃技能上級の資格を持つ者や格闘技の有段者も存在し、万が一のテロやハイジャックといった緊急事態に際しては、即時に要人を護る戦闘要員としての役割も期待されている。
政府専用機という閉ざされた空間で、要人の至近距離で任務を遂行する以上、最終防衛ラインとしての能力を持っていることは不可欠であり、それゆえに空中輸送員は航空自衛隊の中でも選ばれた存在である。
なお、日常の任務において拳銃をどのように隠し持っているかは明らかにされていないが、「SFP9をどこに携行しているのか」という問いは、研究者の間でもしばしば話題になるほどである。
機内の食事と階層
政府専用機の機内では、上級国民、すなわち総理大臣や外務大臣、皇族といった要人には寿司や和牛ステーキ、高級ワインなどの豪華な食事が提供される。
一方、同行するSP、SAT、外務省職員、報道関係者などには、ハム、ソーセージ、目玉焼き、サラダなどのシンプルながら栄養バランスに配慮されたメニューが供される。
このような差別化は、乗員の役割と任務上の必要性に基づいており、軍用機としての機能性と国家の威信を両立させた体制の一端である。
宮嶋茂樹氏の撮影による政府専用機の内部写真は、以下の同氏公式ウェブサイトで確認できる。
▶︎ 政府専用機の機内写真(2008年) – 宮嶋茂樹公式サイト