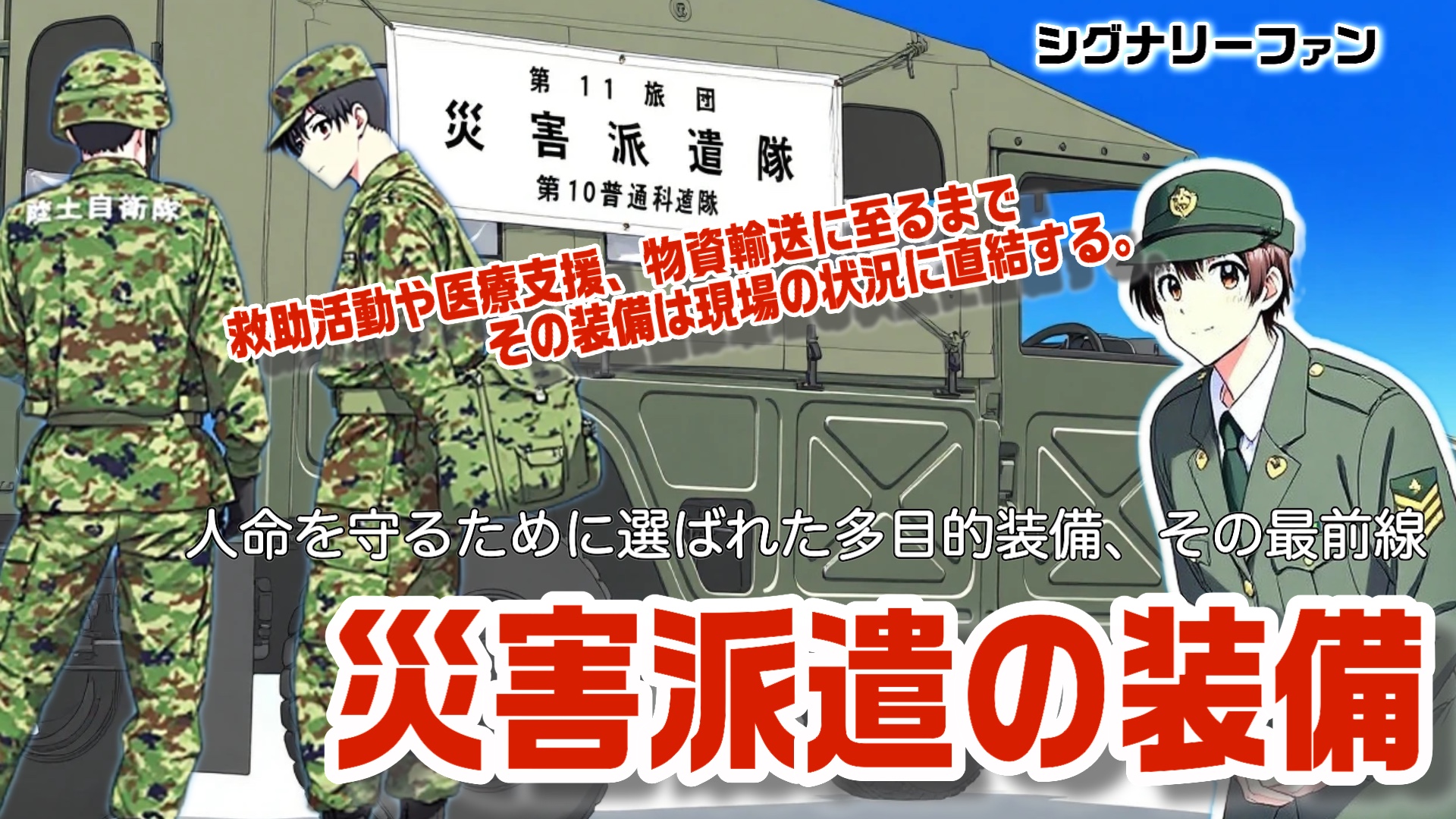陸上自衛隊が初めて本格的に導入した対人狙撃銃という装備品。
その導入の経緯について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

この記事では「M24」という高性能狙撃銃について、その実力に迫ります。
「M24 SWS」は“銃単体”ではなく“狙撃システム”
『M24 SWS(Sniper Weapon System)』
陸自に導入されたのはアメリカのレミントン社が開発したM24スナイパーウェポンシステム(M24 SWS)で、民間用モデル「Remington Model 700」を基に軍・法執行機関向けに調整された狙撃銃です。

US, Japan sniper teams strengthen partnership through friendly competition https://www.army.mil/article/226901/us_japan_sniper_teams_strengthen_partnership_through_friendly_competition
M24は7.62×51mm NATO弾を使用し、精度と信頼性の高さで広く知られています。
「M24 SWS」は単なるライフルではなく、スコープや二脚(バイポッド)、可変/調整可能な銃床など狙撃に必要な装備を一式で含む狙撃システムとして運用されます。
標準的な構成には固定倍率の光学照準器、二脚、そして射手の体格に合わせて長さや頬当て位置を調整できる戦術用ストックが含まれています。
光学照準器については、M24に用いられてきた実績の高い製品としてLeupold社のMark 4系(Mk 4 / M3など)が長く採用例として挙げられます。
Mark 4は耐久性と光学性能に優れ、軍用の狙撃運用に耐えうる仕様です。
二脚(バイポッド)はスナイパーライフルに必要不可欠なアクセサリーで、射手の姿勢安定に欠かせません。
Harrisなどの着脱可能な二脚が一般的に用いられます。

https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/939651/exercise-rising-thunder-japan-ground-self-defense-force-and-us-snipers-find-som/
ストック(銃床)は軽量で剛性が高く、長時間の運用や寒冷地での使用にも向いている合成素材(繊維強化プラスチック=ファイバー系)や複合素材を用いた伸縮・調整式のものが多く、HS PrecisionやMcMillanといったメーカー製のミルスペック仕様が使われることがあります。
M24 系列はその基礎が1962年に登場したレミントン Model 700 の設計に由来しており、民生用モデルの長年にわたる改良・実戦実績を吸収した信頼性が特徴です。
M24はその後も進化を続け、口径変更や近代化改修(例:7.62→.300 Winchester Magnum への改修や、XM2010 といった発展型)などが行われています。
M24 SWSはボルトアクション方式
M24 SWSは古典的なボルトアクション方式、つまり単発式であり、その操作様式が機能と命中率の双方に影響を与えます。

M24は7.62×51mm NATO 弾(.308 Winchester 相当)が標準弾薬で、「重厚なバレルと安定した動作」により中〜長距離で高い集弾性を発揮します。
狙撃銃は世界的に見て、ボルトアクションのほか、セミオート式(半自動式)のG28(M110)といった多様な狙撃プラットフォームが並存しており、各国が運用目的や環境に応じて採用・更新を進めています。

写真の引用元 https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/6d/equipment/sniper_rifle.html
陸自第6師団公式サイトにはストックに迷彩を施したM24SWSを構える狙撃手の写真が掲載され、同銃の説明には『陸自で初めて採用された米国レミントン社製の手動式(ボルトアクション)の対人用狙撃銃』とあります。
参照:https://www.mod.go.jp/gsdf/neae/6d/equipment/sniper_rifle.html
有効射程距離と最大射程距離
銃には、「有効射程距離」と「最大射程距離」という二つの基準がある
銃器には「有効射程(effective range)」と「最大射程(maximum range)」という二つの異なる基準が存在します。
有効射程は「実戦で目標を命中させ得る距離の目安」であり、最大射程は「弾が理論上到達し得る最遠距離(危険範囲)」を指します。
実射における再現性や風の影響などを考慮すると、この二つはまったく別の概念です。
M24 SWS(7.62×51mm NATO)に関しては、標準的な評価値として有効射程はおおむね800メートル前後とされるのが一般的です。
ただし、条件や弾薬、光学系、射手の技量によっては1,000メートルを超える命中例も報告されています。
したがって「メーカー保証の有効射程=絶対不変の限界」ではなく、運用実態では射手と装備次第で有効射程を伸ばすことが可能です。
一方、7.62×51mm弾の最大射程は理論上3,000メートル台(文献では約3,700メートル前後)とされますが、これは仰角を取って発射した際の弾道到達距離であり、「狙って当てられる距離」ではありません。
実戦的な狙撃では有効射程内での運用が原則であり、有効射程外からの狙撃は弾道・風・標高などの条件が極めて厳しく、通常は高度な技量と特別な弾薬(高BC弾)や改修を伴います。
結論として、M24の公称的な有効射程は約800メートル級ですが、熟練射手と適切な装備・弾薬の組み合わせにより1,000メートルを超える射撃が実行されうる、というのが実情です。
一方で「最大射程=有効射程」ではないため、最大射程の数値をそのまま「確実に当てられる距離」として扱うのは誤りです。
つまり・・・
- 有効射程距離(約1100m)
→ 「この距離なら狙えば確実に当たる」とメーカーが保証する範囲。 - 最大射程距離(約3700m)
→ 「弾はここまで飛ぶけど、狙ったところに当たるかは保証しません」という、いわば「最大危険範囲」。
一般的な歩兵部隊は有効射程距離内での運用ですが、特殊部隊のスナイパーともなると、自分の腕とカスタムした銃を駆使して、有効射程距離外からでも運用します。

高倍率のスコープを覗いて数百メートル先の標的を狙う場合、思った以上に小さく映ります。
十字のヘアラインを標的に合わせたとしても、訓練を受けていない限り、照準はブレてしまいます。
人間の心臓の鼓動や、ほんのわずかな身体の動きでも影響を受け、命中率に大きく左右します。
陸上自衛隊の運用構想
「東長崎機関」様の取材では隊員のコメントとして『陸自では指揮官を守るためにスナイパーを配置しており、映画のように積極的に敵地へ潜入して任務を行うなどの作戦構想はない』と報じられ、諸外国の狙撃手とは運用思想が異なるようです。
また陸自でも諸外国軍同様、通常は狙撃手1人に観測員が1人配置されますが、この観測員は周囲の警戒ではなく、あくまで目標の監視を行うとのことです。
自衛官:
狙撃手1人には観測1人がつきます。東長崎機関:
周辺警戒は、観測手1人だけですか?自衛官:
周辺警戒という考え方ではなく、ターゲットの観測です。東長崎機関:
その観測手は、狙撃手からどのくらい離れた位置ですか?自衛官:
狙撃手のすぐ隣です。東長崎機関:
観測手は、敵に先に発見される危険が高いと思うのですが、狙撃手の近くにいるのでは、狙撃手の位置も暴露されやすいのでは?観測手は、10メートル以上はなしたほうがよくないですか?
自衛官:
自衛隊では、敵を撃ちに潜行させるという形では狙撃手を使わず、味方部隊の指揮官を守るという戦術運用なので、そのような隠密行動はしません。典拠元:東長崎機関「自衛隊独特の狙撃戦術」
http://www.higashi-nagasaki.com/c2007/C2007_33.html
日本の陸上自衛隊は運用思想として、狙撃要員を「指揮官防護」や部隊戦術支援のために配備することが基調にあると公的報道や取材で説明されています。
一方で、米海兵隊などが採る「前線での偵察/斥候と狙撃を兼ねる」運用とは趣旨が異なり、法令・組織・運用方針等の制約を踏まえたうえでの運用がなされている点が指摘されています。
2016年に産経新聞でも以下の様に報じています。
陸自の狙撃手は指揮官を守ることで指揮命令系統の乱れを避けることを主任務としている。ただ、陸自は「指揮官防護だけに専従するわけではない」と説明する。
典拠元 あの国の特殊部隊を迎え撃つ、世界一の陸自スナイパーが手に握る「対人狙撃銃」
報道・解説材と一次取材の双方を踏まえると、陸自は他国のスカウト・スナイパー概念の技術や訓練を学ぶ一方で、日本の運用概念に合わせた限定的運用を取っていると整理できます。
最後に留意点です。狙撃・カウンタースナイパーの具体的な編成や戦術の詳細は、軍事組織にとって極めて厳重に扱うべき機密であり、安全保障の性質上、公開情報に限界があります。
報道で「公表された内容」であっても、真実か否か確認するすべはありません。
「推測・一般的な運用概念」を明確に区別することが信頼性確保の鍵となります。
狙撃要員選抜と課程教育
狙撃要員の選抜には、射撃技術とともに高い精神力・体力が求められます。
精密射撃を恒常的に遂行するには、射撃のセンスに加えて厳しい任務環境に耐える士気や持久力が不可欠です。
加えて、野外で長時間行動する任務が多いため、地図判読や航法、隠密行動といったフィールドクラフトの能力も重要視されます。
こうした要件は、レンジャー等の高難度資格保有者と同等水準の素養を求められる場合が少なくありません。
精神・行動面の適性検査も選抜の主要項目です。
自衛隊では情緒の安定性や社会適応性を評価するために各種の心理検査や作業検査を実施するのが通例であり、狙撃要員の選抜でも同様の適性検査が行われます。
公開されている範囲では、クレペリンによる知能・性格・作業素質など複数の項目を総合的に判断する仕組みが導入されているとされています。
ただし、具体的な検査名や合格基準(スコアの閾値やコード表記)については、部内資料として非公開扱いになっていることが多く、外部に公表されている情報は限定的です。
したがって「射撃技量・体力・フィールドスキル・心理適性の四点が選抜の核心である」という一般的傾向を示すにとどめます。
「対人狙撃課程教育」
2015年に新設された「対人狙撃課程教育」は、全国の部隊から射撃技術に優れた隊員を選抜して実施される上級養成プログラムです。
狙撃の基礎技能に加え、観測技術や地形判断、戦術の基礎といった実戦に直結する科目を体系的に学びます。
北部方面隊第11旅団隷下の第10普通科連隊(北海道滝川市・当時)では、狙撃要員養成の一環として、富士学校普通科が実施する特技課程「狙撃」を隊員に受講させるための入校前教育を行いました。
入校前教育の内容は射撃理論や観測技術など、狙撃任務の基礎にあたる項目が中心です。
受講生は数か月にわたり、実戦を想定した高度な訓練を通じて狙撃術と関連技能を習得します。
とりわけ重要視されるのは、狙撃手という職務の厳しさを自覚させることです。
野外での長時間行動や隠密行動、地形を読み切る能力などを求められるため、レンジャー資格者に匹敵する水準の身体・技能素養が必要とされます。
まとめ
陸上自衛隊で2002年から長らく配備されたM24 SWSですが、2023年にその後継として、「HK G28E2」の導入を決定しており、2025年現在、全国の普通科連隊において調達・配備が開始されています。

関連リンク
- 対物ライフルで兵士を撃ってはいけないはウソ? —
(対物ライフルの法的・倫理的制約を論じた解説記事) - 陸上自衛隊、新たな対人狙撃銃:ヘッケラー&コッホ社製HK G28 E2を調達 —
(HK G28 E2 の導入を伝えるニュース/解説) - 陸上自衛隊はなぜ狙撃銃を導入してこなかったのか —
(狙撃銃導入の歴史的背景と理由を考察した記事) - 敵の恐怖心を煽り、進撃遅滞させるスナイパーの運用は心理戦でもある —
(狙撃運用の心理戦的効果を論じた考察) - 陸上自衛隊も配備する「バレット対物ライフル」シリーズの驚くべき実力 —
(バレット社製対物ライフルの性能解説と陸自導入の文脈) - 陸上自衛隊が導入した対人狙撃銃「M24 SWS」の実力 —
(M24 SWS の技術解説と運用評価)