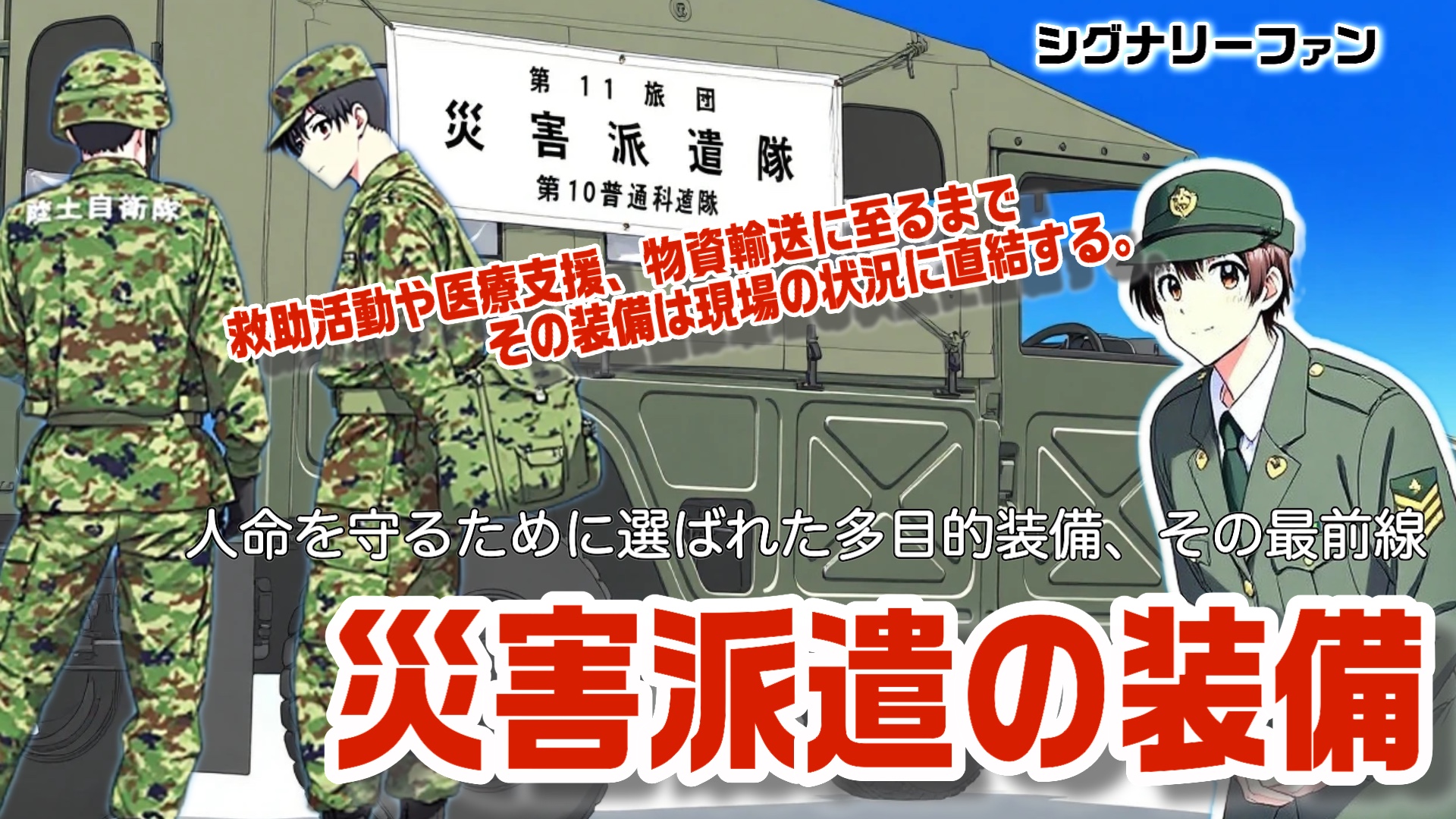軍用小銃の銃口下部に装着する短剣状の装備、それが銃剣―Bayonet(バイヨネット)である。
その名の由来は、17世紀にフランスのバイヨンヌ地方で考案されたためと言われる。
初期の火縄銃やマスケット銃は近距離戦闘に弱く、銃剣の装着によって槍のように機能させることで、この欠点を補った。
つまり、銃剣の本質は“火器と冷兵器のハイブリッド”だ。
自衛隊における銃剣

日本の自衛隊においても、銃剣は現役である。着剣装置が標準で装備された小銃に銃剣を装着することを「着剣」と呼び、訓練でもその技法が教えられる。
日本では銃剣は「刀剣類」に分類され、武器等製造法に基づく厳しい規制の対象となっているため、民間人が所持することはできない。
写真は真鍮製のレプリカ。
つまり、銃剣は銃器と同様にれっきとした“法定武器”であり、自衛官という職能にのみ許された装備である。
64式小銃には、いかにも「短剣」と呼ぶにふさわしい、刃長の長い銃剣が用意されていた。
美術品的にすら見えるこの銃剣は、冷戦期の陸自が想定していた「正面対峙戦」に対応する、まさに正統派の設計思想が感じられる。
だが、時代が下るとともに、軽量化と多用途化の流れが主流となる。
現在の主力である89式小銃に装着される銃剣は、「89式多用途銃剣」と呼ばれ、刃渡りは64式用よりも短めで、ナイフとしての使用も想定された構造となっている。

銃剣というよりは、むしろサバイバルナイフの延長線上にある。
この銃剣は鞘とセットで設計されており、組み合わせることでワイヤーカッターとしても機能する。鞘はベルトに吊るす。
また、少数ながら使用されている儀仗ライフル用の銃剣は、見栄え重視で光沢のある金属製。
こちらは“見せるための銃剣”であり、儀仗隊の行進や儀礼的な敬礼に使用される。見た目こそ美しいが、実戦用途ではない。

興味深いのは、陸自の精鋭部隊「特殊作戦群」に関する話だ。
元・米軍関係者によれば、同部隊ではアメリカ製のM4カービンが使用されており、それに対応するM9バヨネット、あるいはM7バヨネットなども導入されていると推測されている。
公式発表はないが、特殊作戦群はアメリカ特殊部隊との連携・訓練が多いため、その可能性は高い。M9は工具的要素が強く、まさに「マルチツールとしての銃剣」である。
自衛隊銃剣格闘
自衛隊では銃剣術や銃剣格闘が現在も訓練として運用されている。この画像は小銃を奪われそうになった場合、即座に銃剣に手を伸ばして引き抜き、対応する訓練の展示例。

出典・陸上自衛隊
一方、アメリカ陸軍では2010年に着剣状態の小銃を使った格闘訓練を廃止しており、代わりに銃剣を手持ちの武器として扱う訓練に切り替えている。
どちらの方がより実用的かということが考慮された結果だろう。
89式の銃剣は「多用途タイプ」
現代の銃剣には複合的な機能が付加されており、ワイヤーカッター、鋸、スコップ、栓抜きといった機能を兼ね備えた優れたサバイバル・ギアである。
かつては、多くの国の軍隊で缶切りを失った兵士が銃剣を突き立てて缶詰を開けていた。
やがてレーションには簡易缶切りが付属するようになり、兵士たちはそれを認識票のボールチェーンに通し、大切に携行するようになった。
現代では、缶切り機能やワイヤーカッター機能を備えた多用途銃剣が各国軍に配備されており、「89式用多用途銃剣」もその名の通り、鞘に缶切り・栓抜き機能を搭載し、刃部にはワイヤーカッター機能を備えている。
自衛隊の銃剣は「刃付け」されていない?
ところで、自衛隊で使用されている銃剣は通常、刃付けされておらず、いわゆる「刃引き」の状態である。有事や海外派遣の際に初めて刃を入れることになっている。
この点については、かのよしのり氏の著書『自衛隊89式小銃 日本が誇る傑作小銃のすべて』第4章「研いではならない『銃剣』」でも言及されている。
普段から先端は尖っているため、突く用途には使用できるものの、切断目的での使用は難しいというのが実情だ。
銃剣は官品かつ武器。紛失すれば大問題に
当然のことながら、銃剣は官給品である。また、前述の通り銃剣は法律上の「武器」に該当するため、これを自衛官が紛失すれば、報道機関にとっては報道価値のある自衛隊不祥事となる。
そうでなくとも、国民の税金で購入された大切な装備品であり、個人のアウトドアナイフや10徳ナイフのように気軽に扱ってよいものではない。
紛失すれば、部隊を挙げた大捜索が実施されることになる。薬莢の如く。

実際に、北海道の広大な島松演習場(恵庭市)で訓練中だった陸上自衛隊の士長が、さやに収めて携行していた銃剣を紛失し、750名の隊員が捜索に投入されたものの、発見には至らなかったという事例がある。2015年9月20日には滝川駐屯地の隊員も矢臼別演習場で銃剣を一時紛失し、問題となった例もある。
「そこが変だよ自衛隊」でも紹介されている通り、自衛隊では空薬莢ひとつの紛失でさえ、大捜索を行う。空薬莢であれば、ミリタリーサープラスショップで売っている米軍M4のカラ薬莢をポケットから出して「発見!」とやれば数は合うが、銃剣ではそれは通用しない。
もっとも、自衛隊の装備管理は米軍などと比べて厳しく、そもそも紛失が滅多に起きることではない。
自衛官と私物ナイフ事情
自衛隊では任務に必要な装備として、私物を用いることが意外に多く、その中でも代表的なのがナイフである。
野外活動では、支給された銃剣よりも、市販のアーミーナイフやサバイバルナイフの方が遥かに実用的であり、多くの隊員が私物としてそれらを所持している。
銃剣は支給されるが、汎用性の高いアーミーナイフは支給されないのが現実だ。
通信科では電工ナイフが支給される場合もあるが、普通科ではそのような配慮はない。
細かな作業には、ヴィクトリノックスやウェンガーの10徳ナイフが便利であり、使用が黙認されるという。
また、レンジャー訓練などで野生動物を獲ってさばく場面では、切れ味のよいサバイバルナイフが必須となる。またその話か……いい加減気持ち悪いからやめろっての。

まとめ
ただし、現代の戦争において、銃剣による白兵戦が想定される場面は極めて限られる。
実用というよりは、「武器の一体感」や「兵士としての所作」に関わる精神的な意味合いが強いとも言える。
事実、着剣の動作や銃剣突撃の号令は、訓練において士気高揚や集団行動の演練としても位置づけられている。
銃剣とは、武器としての合理性を超えて、兵士という存在を象徴する装具でもあるとも言えそうだ。
冷たい鋼の光沢の中には、兵の練度と覚悟が映っているのかもしれない。
銃剣が抜かれるのは訓練か、有事か、いずれにせよ“最後の手段”ということになる。