特殊部隊と聞けば、秘密裏に作戦地域へ潜入し、サイレンサー付きの小銃で目標を排除、人質を救出し、真夜中にヘリコプターで回収され帰還する――といった、いささかハリウッド映画的なイメージが先行しがちである。
特殊部隊とは、極めて高い能力を有する兵士のみを選抜して編成された、いわば「軍の中の軍」である。特別な訓練を受け、誇りと国家への忠誠心のみを頼りに、生還の保証なき困難な軍事作戦へ身を投じる者たちが、それである。
日本の陸上自衛隊にも、こうした任務に従事する特殊部隊が存在する。正式名称は「特殊作戦群」。日の丸と剣を背景に、鳶と榊の葉、そして桜星をあしらった意匠の「特殊作戦き章」を左胸に佩用することを許された選抜隊員で構成されている。
特殊作戦群は、2004年に陸上自衛隊初の本格的な特殊部隊として創設された。2018年4月には、中央即応集団の廃止に伴い、新設された陸上総隊の隷下部隊となり、現在は千葉県船橋市の習志野駐屯地において、戦闘要員およそ200名、後方支援要員約100名の規模で編制されている。
隊員は、隠密上陸に必要な空挺降下、水中浸透、特に遠距離潜水に優れた能力を持つ男性隊員によって構成されているとされる。ただし、これらは防衛省が公表したごく限られた情報に過ぎず、実態は極めて不明瞭である。
また、特殊作戦群は不正規戦に対応する能力――すなわち、対テロ作戦における極限状況への対応能力――も求められるとされ、私服で民間人に紛れ、都市空間において秘密裏に情報収集や偽装工作を実施するといった、米軍デルタフォースと同種の任務への従事も想定されている。
なお、海上自衛隊には同じく特殊部隊「特別警備隊(SBU)」が編制されており、自衛隊における公式な特殊部隊は、現時点でこの「特殊作戦群」と「特別警備隊」の二つのみ。
特殊作戦群の実際の任務は秘匿される
■ 陸自特殊作戦群、秘匿の「最後のカード」 — 2022年に一部初公開
陸上自衛隊の「特殊作戦群(SFGp)」は、日本国内で唯一、対テロ、人質救出、情報収集といった特殊作戦任務を担う部隊であり、防衛省においてもその実態は長年秘匿され続けてきた。関係者の間では「わが国防衛の最後の切り札」とも形容され、その訓練内容や装備体系についても原則非公開が貫かれてきた(※典拠元 防衛省・自衛隊公式資料)。
“防秘”で秘匿された自衛隊の「最後のカード」。元隊員が訓練や装備を口外することは違法?
だが、2022年、政策転換とも言える動きがあった。防衛省は同年、米国との共同訓練の一部として、特殊作戦群の隊員が訓練に参加する姿を初めて公式に公表し、部隊の存在と一部装備品の映像・画像が報道公開されたのだ(※典拠元 産経新聞2022年8月24日、NHK2022年報道)。

これまで「防衛秘密」に分類され続けてきた特殊作戦群の映像が一般公開されたのはこれが事実上初めてであった。
ただし、依然としてその詳細な部隊編成、装備体系、訓練手法、作戦ドクトリン等は防衛秘密に指定され続けており、元隊員らによる任務内容の外部口外は法令違反(自衛隊法第59条の秘密保持義務)に該当しうる(※典拠元 自衛隊法59条、防衛省資料)。
■ 過去に偶然撮影された装備情報の流出事例
特殊作戦群の装備情報が過去に偶然表面化した事例として、2000年代半ばに「H&K USP TACTICAL(特殊拳銃)」を装備していた可能性があると指摘された件がある(※典拠元 駐屯地来賓客による写真付きブログ投稿)。

ある著名人が駐屯地を訪問した際、消音器(サプレッサー)を装着したザ・ファブル臭いUSPタクティカルを携行する隊員を撮影し、その画像をインターネット上に公開したものが根拠だが、その背景には「特戦群」と書かれた陸自高機動車が写り込んでいた。当該ブログ投稿者によれば、「本物の銃を見せてもらいました」と記されており、当該の銃は実銃であると示唆している。ただし、来賓者に隊員個人の判断で秘匿された特殊拳銃を見せたのか、部隊側が正式に撮影許可を出したのかなど詳細は確認されていない。
こうした過去の断片的情報を除けば、特殊作戦群の実装備に関する詳細情報は2022年まで厳しく秘匿され、一般公開されたことはほぼ皆無であったのは事実である。
特殊作戦群の具体的な任務内容は現在も「防衛秘密」区分に属しており、現役隊員・退職者を問わず、内部情報の外部漏洩は法的に厳格に禁じられている(※典拠元 自衛隊法59条、国家公務員法守秘義務)。先述のように、近年では海外訓練が一部公開されることもあるが、その範囲は基本的な装備や訓練の一部に留まり、実際の任務・作戦内容については国民にも知らされていないのが実情である。
公にできない顔貌、眼差しのみが全てを語る特殊作戦群
■ 異様な「顔貌秘匿」の姿で登場した特戦群隊員たち
陸上自衛隊特殊作戦群(SFGp)は、2004年3月29日に東京都朝霞駐屯地で編成式典が行われた(※典拠元:防衛省発表、複数報道)。つまり、この式典が、特殊作戦群の部隊としての公式なスタートである。
この際、部隊指揮官は素顔を晒して式典に登壇した一方、作戦遂行の中核となる隊員たちは、顔面を覆うバラクラバ(目出し帽)を着用し、顔貌の秘匿を図っていた(※典拠元 産経新聞写真等)。こうした外観は従来の自衛隊部隊には見られなかった異様な光景であり、一般国民にも強い印象を与えた。
■ 顔貌秘匿の意味とは ― 対ゲリラ・コマンドゥ戦任務を暗示
こうした隊員個人の顔貌秘匿は単なる演出ではない。特殊作戦群は、日本国内のインフラ破壊工作、重要施設襲撃、都市型ゲリラによる破壊行為への対処任務を含む高度な不正規戦対処能力を想定して創設された経緯がある(※典拠元 防衛省中央即応集団時代の任務区分)。
仮に敵対勢力によるJR変電所、浄水施設、携帯通信網(NTTドコモ等)、電力鉄塔、警察機関施設等への破壊・攪乱・コマンドゥ攻撃が行われた場合、即応するのは警察力(特殊部隊SATおよび機動隊各機能別部隊)に加え、特殊作戦群が投入される可能性が想定されている(※典拠元 自衛隊統合運用教範②、2023年政府防衛白書③)。
そのため、こうした顔貌の秘匿は敵勢力による隊員の報復・特定化・親族への危険回避策として極めて実務的に重要視されていると考えられるのが妥当である。
■ 法的に極めて厳格な守秘義務
特殊作戦群に関する情報は、自衛隊法第96条の2「防衛秘密」に該当し、極めて高い秘匿義務が課せられている(※典拠元 自衛隊法96条の2条文⑤)。現職隊員のみならず、退職後も生涯にわたって基本的に部隊任務・訓練・編成・装備等の口外は禁じられている(※典拠元 防衛省内部通達⑤)。
■ 軽々に「知人が特戦群所属」と吹聴する危うさ
そのため、警察SAT等と同様に、特殊作戦群所属であること自体が同僚自衛官や家族間でも原則として口外されない(※典拠元 防衛秘密管理要領②)。SNSなどで「家族が特戦群所属である」などと投稿することは、事実であれば秘密保持違反に該当する可能性があり、内部調査となり得るだろう。
仮にSNS上で「配偶者が特戦群所属でSATとも合同訓練する予定だ」などと公言する投稿が出回った場合、それが事実なら極めて深刻な防衛秘密違反の可能性がある。他方、現実には「虚偽の自己顕示(俗に嘘松)」がネット空間では横行しており、情報の信憑性には極めて慎重な検証が必要である。
現在のところ、同部隊に関する断片情報は初代群長であった荒谷卓氏の著書などにより、少しずつ明らかになっていはいるものの、先述の事情から元隊員は口を閉ざしている。情報が乏しいため、軍事評論家の間でも特殊作戦群の装備や訓練は同盟国アメリカ軍の特殊部隊との比較から類推せざるを得ないのが現状である。
特戦群は外国のどの特殊部隊を手本としたか?
元・特殊作戦群(SFGp)初代群長の荒谷卓氏によれば、SFGpは、対テロや人質救出、不正規戦対応能力を重視し、アメリカ陸軍の特殊部隊「グリーンベレー(1st Special Forces Group)」および「デルタフォース(1st SFOD‑D)」をモデルに編成された部隊である(※典拠元 https://www.biglife21.com/society/11412/など)。
-
1998年からの部隊創設準備段階において、第一空挺団から選抜された隊員が米陸軍デルタフォースやグリーンベレーで訓練を受けた。
-
初代群長・荒谷卓氏は、米グリーンベレーで約1年間の実地訓練を経験し、その経験を日本の特殊部隊編成・訓練カリキュラム作成に活かした。
ただ、米軍のデルタフォースと比較した場合、特殊作戦群とは決定的な違いがある。それは日本政府および防衛省が特殊作戦群の存在を公式に認めている点で、非公式部隊ではないということだ。
特殊作戦群(SFGp)に女性隊員はいるのか?
SNSやブログで「特戦群の応募条件に性別不問と書いてある」などの投稿があっても、それが真実かは慎重に判断すべき状況と言えそうだ。2025年現在、特殊作戦群に女性隊員が配置されているという事実・防衛省からの公式発表は一切ないためである。
これまでの動きとして、防衛省では女性自衛官の戦闘職種配置制限を一部解禁する動きが目立っていた。

実際、すでに戦闘機・戦闘ヘリ・戦車・第一空挺団・レンジャー養成課程・普通科ナンバー中隊・潜水艦・海自特殊部隊(SBU)への配置制限は解除済みである。しかし、陸自特殊作戦群においては女性隊員任用解禁の発表はいまだ無いのが現状である。
ゆえに、現時点(2025年6月)では、特戦群に女性隊員が任用・配置されているという明確な根拠は存在せず、「不明」という状況と評価される。
イスラム国が日本人への明確な攻撃を表明。海外へ赴く日本人の安全は確保できるのか
2015年、過激派組織「イスラム国(IS)」による日本人拉致事件が国際社会を震撼させた。ジャーナリストの後藤健二氏と警備会社社長の湯川遥菜氏の2人がISに拘束され、安倍首相は自衛隊による人質救出の可能性を模索したとも一部報道されたが、作戦は実現せず、両氏は犠牲となった。
イスラム国はこれ以前から、日本政府がアメリカと連携してIS掃討作戦に関与していることに反発を強めていた。日本が近隣諸国に2億ドルの支援を表明したことも標的とされた背景にある。ISは「日本は明確な敵」と名指しし、日本人を標的にする姿勢を公然と打ち出していた。
2016年7月にはバングラデシュの首都ダッカでレストラン襲撃事件が発生し、日本人7人を含む20人が犠牲となった。実行犯のうち1人は日本国籍を持ち、日本の大学で教職に就いていた経歴も明らかになった。国内でもISに呼応する動きが確認されており、警視庁公安部や各都道府県警の公安部門が関係者の把握に努めている。山谷えり子国家公安委員長(当時)は、国内のシンパや連絡者についてリスト化を進めていると明らかにした。
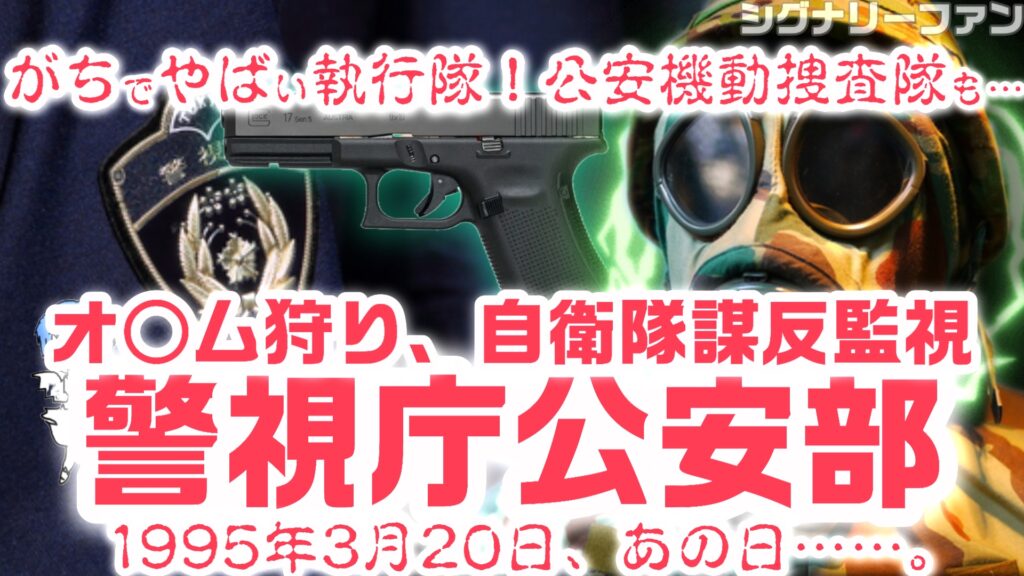
さらに米国当局の情報として、ISに参加した日本人戦闘員が存在し、実戦経験を経て帰国後に国内でテロを敢行する可能性も指摘されている。週刊誌報道では、愛媛の日本人女性が外国籍の夫とともにIS支配地域へ渡航したケースも伝えられた。
一方、こうした邦人の国外危機に対し、自衛隊の対応には限界があった。アルジェリア人質事件が発生した2013年当時、自衛隊法は海外での邦人輸送に厳しい制約を設けており、陸上での救出活動は認められていなかった。航空機や船舶での輸送に限定され、現地での陸上移動や装甲車による護送は不可能だった。政治部記者は「現行法では、隊員の安全が確保されている場合に限ってしか輸送ができず、陸上輸送も武器使用も厳しく制限されていた。根本的な法改正が必要だった」と指摘する。
この反省を受け、政府は同2013年、自衛隊法を改正。在外邦人保護のため、危険地帯での陸上輸送が可能となった。陸上自衛隊にはオーストラリア製の「輸送防護車」も新たに配備され、武装勢力の脅威下でも安全に邦人を移送できる体制整備が進められている。軍事フォトジャーナリストの菊池雅之氏は「特殊部隊が実戦投入できれば、過去のような惨事を防げた可能性もあった」と語る。「使用武器は銃身が短い小銃M4に夜間も使えるダットサイト(光学照準器)を装着したもの。
暗視ゴーグルつきのヘルメットをかぶり、全身を黒い服で固めた特殊部隊は、テロ組織を一掃したでしょう。自衛隊は『100人の人質がいたら、100人を助ける』という動きを意識している。今回のように犯人がトラックに人質を乗せて移動しようとしたら、当然トラックのタイヤを狙い移動を止めます」(菊池氏)
引用元 女性自身公式サイト
http://jisin.jp/serial/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/crime/6082
それでも、自衛隊による海外での人質救出作戦には依然として高い法的・政治的ハードルが残る。今後も邦人の安全確保が国家安全保障上の重要課題となり続けそうだ。
特殊作戦群はヤバイ現地の情報収集も任務とする
つまり、陸上自衛隊の特殊作戦群は、対テロ・人質救出などの直接戦闘任務のみならず、海外活動に際しての現地情報収集任務も担っている。派遣部隊の安全確保には、事前の治安状況の把握が不可欠だからである。
2004年からのイラク復興支援活動では、陸自部隊がサマワに本格展開する前段階として、特殊作戦群の隊員が先行して現地入りし、周辺地域の治安情勢や潜在的脅威の把握に当たったとされる。このような極秘の事前偵察は表に出ることがほとんどないが、海外任務の現実を物語っている。
また、近年のアデン湾海賊対処行動でも、ソマリア沖に展開する海上自衛隊のジブチ基地を警備するため、陸自から第1空挺団の隊員約50名が派遣された。その際にも、現地治安の情報収集や警備計画立案にあたり、特殊作戦群が裏方で活動していた可能性は高いと見られている。
自衛隊施設のテロ警備チェックも任務
特殊作戦群の任務は国外だけに限らない。日本国内の自衛隊駐屯地に対するテロ警備チェック(模擬襲撃訓練)も行われている。安全保障評論家で株式会社危機管理総合研究所代表取締役の小川和久氏は、特殊作戦群が出前持ちに変装して基地に侵入する訓練例を紹介している。オカモチ(出前箱)内部に発煙装置を仕掛け、内部から発火させるなど、奇抜な方法で警備網の盲点を突く訓練を実施していたという(典拠元:国際変動研究所 2011年5月19日記事 http://sriic.org/backnumber/20110519.html)。
戦闘力のみならず、情報収集や偵察・治安状況の事前察知、さらに自衛隊内部のセキュリティホールの点検まで担う特殊作戦群は、防衛省内でも極めて特異な存在となっている。
特殊作戦群の装備に特殊火器の名称多数
公開情報から浮かぶ実像
陸上自衛隊特殊作戦群が他部隊とは異なる特殊な火器を保有していたというこれまでの可能性が、今事実となっている。公開資料や元米軍関係者の証言から徐々に明らかになりつつあるのだ。本来秘匿されるべきこれらの装備品だが、一部が防衛省が入札公告などで一般公知され、不特定の人が公然と知りうる状態となっているためだ。
それによれば、特殊作戦群では一般部隊が使用する89式小銃や9mm拳銃、M24狙撃銃、MINIMI機関銃といった標準装備に加え、アメリカ製のM4カービンが配備されている可能性が高い。米国防総省が行う対外有償軍事援助(FMS)プログラムの公開情報によれば、日本政府はコルト社製M4カービンと共に、M203グレネードランチャーやQDSS-NT4サプレッサー(サイレンサー)を含むパッケージで購入している(典拠元:米国防総省 DSCA 発表資料、Defense Security Cooperation Agency, 2012年10月通知)。
これはあろうことか、特殊作戦群隊員と現役の米軍兵士とによる「あるやり取り」によって、結果的に裏付け補強がされている。

さらに、平成21年度の防衛省装備品契約希望募集要項には、“ドイツHeckler & Koch社製”の「4.6mm短機関銃」の導入記載が確認できる。この口径から推測すると、H&K社が製造するMP7短機関銃が候補と見られている。現状、陸上自衛隊の通常部隊にMP7が配備された例は確認されておらず、特殊作戦群など特殊用途部隊への限定配備と考えられる。

参考画像:MP7サブマシンガン
また、同じ募集要項には米ウィルソン・コンバット社の名が記載されており、同社が改修したM870ベースの戦闘用ショットガンが調達されている可能性がある。さらに対物ライフルの欄には「バレット」社製品と推定される内容も含まれている。
また、装備する可能性のある火器の中には、対人用途を超えた対物ライフルも含まれると見られている。
平成21年度の防衛省契約希望募集要項には、米国バレット社製と推測される対物ライフルが調達対象として記載されている。バレットM82(現行型はM107など)は対物狙撃銃(アンチ・マテリアル・ライフル)と呼ばれ、装甲車両や防御陣地といったハードターゲットの破壊を目的とした大型火器である。自衛隊ではM24SWSなどの対人狙撃銃の存在は公式に公開されているが、対物ライフルの配備状況は現時点で正式発表されていない。
さらに、CQB(Close Quarters Battle=近接戦闘)能力の向上も特殊作戦群の訓練における重要要素である。CQBは、建物内や市街地の室内戦闘における特殊技能で、米国警察のSWAT、日本警察のSATでも重視されている。こうした近接戦闘訓練では、閃光発音筒(スタングレネード/フラッシュバン)が使用されることもあり、自衛隊でも同種の装備が導入されていると推定されているが、防衛省は詳細を公表していない。
陸自におけるCQB訓練は、普通科部隊が旧陸軍由来の化学工場跡地や各地の市街地型訓練施設などで実施している。また、航空自衛隊の基地警備教導隊や基地警備隊でも同様の近接戦訓練が行われている。
こうしたCQB技術は、民間でも教育ビジネスとして注目されている。埼玉県の「田村装備開発」はその代表例であり、同社代表の田村氏は元埼玉県警察の特殊部隊「ラッツ」隊員だった経歴を持つ。教官には元警察特殊部隊員や元自衛隊特殊作戦群の出身者も在籍しているという。現職自衛官や警察官も訓練を受けに訪れる一方で、同社の本格的なCQB訓練はサバイバルゲーム愛好者にとっても人気の高い存在となっている。
特殊作戦群の任務特性上、特殊火器の配備は想定しうるが、防衛省は正式な装備体系について公表しておらず、詳細は依然、防秘の範疇にある。こうした特別装備の存在は、訓練や模擬テロ対処演習で「岡持ちに仕掛けた発煙装置」といった奇抜な訓練エピソード(※小川和久氏証言)と相まって、特殊作戦群の秘匿性を象徴している。
特殊作戦群まとめ・いまも顔を隠す現代の「サムライ」たち
日本政府は2015年、イスラム国(IS)がSNS上で「東京の悪夢が始まった」と挑発的な声明を発したことを重く受け止めた。2020年の東京オリンピックを控え、警察庁ではSAT(特殊急襲部隊)の訓練映像を公開するなど、対テロ能力の向上と抑止を国内外に示す必要に迫られた。
一方、防衛省も2022年、2025年と特殊作戦群に関する映像を初めて公式に公開した。これにより、覆面を着用し特殊小銃を駆使する特殊作戦群の姿が世間に初めて明らかになった。ただし、2022年の一部画像については外国軍のウェブサイトによって先行して公開された経緯があり、当の防衛省が、出さざるを得なかったという見方もある。
創設から20年近くが経過した現在もなお、特殊作戦群の実態は秘匿が維持されており、隊員たちは任務の特性上、公の場では一切顔を見せない。防衛省が「現代のサムライ」とも称される彼らにマスク(小銃へのモザイク含む)を外させる日は、まだ遠い先の話になりそうだ。
仮に特殊作戦群が出動する事態が発生するならば、それは日本が深刻なテロ脅威や国家的危機に直面していることを意味する。こうした事態の発生を未然に防ぎ、国際社会の安定と平和を維持することこそが、自衛隊の使命であり、また特殊作戦群の存在意義に他ならない。
【主な典拠一覧】
-
初代群長・荒谷卓氏の著書
-
防衛省公式発表(防衛省公式SNS、各種入札情報)
-
法令(自衛隊法、防衛秘密指定関連)
-
信頼性の高い一次報道(産経、NHK、時事通信などが配信した関連記事)
- 来賓として自衛隊駐屯地に招かれた個人ブログの写真付き投稿記事
-
防衛省「平成21年度 装備品等(火器車両関係)契約希望募集要項」
http://www.epco.mod.go.jp/kokok/27-350/announcement20120919204553.pdf
http://www.mod.go.jp/gsdf/gmcc/hoto/hkou/11hk039.pdf -
Defense Security Cooperation Agency (DSCA), U.S. DoD FMS通知資料, 2012年















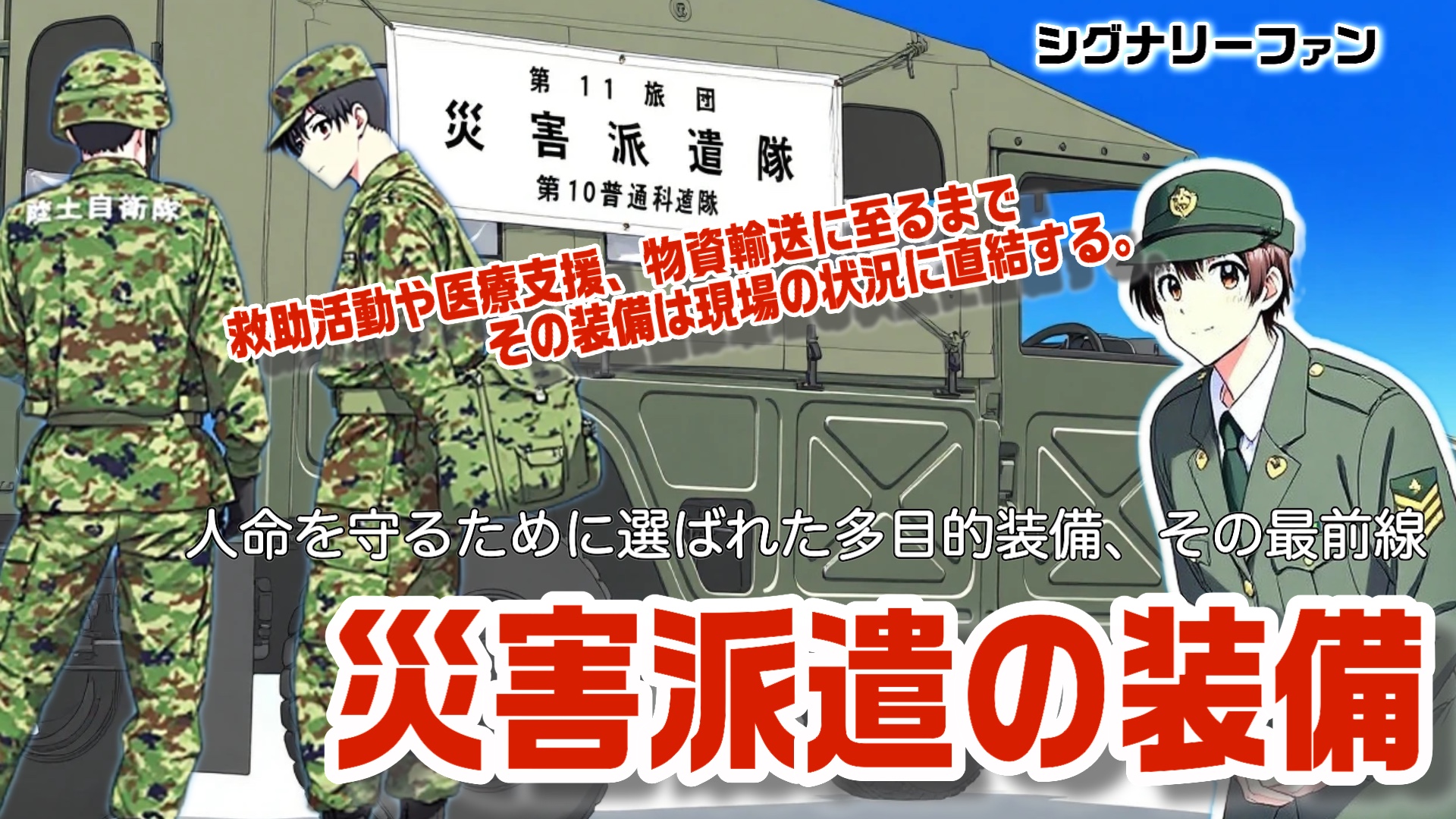



































































![日本の特殊部隊 2017年 03 月号 [雑誌]: ストライクアンドタクティカルマガジン 別冊 日本の特殊部隊 2017年 03 月号 [雑誌]: ストライクアンドタクティカルマガジン 別冊](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51IzUTm2mEL.jpg)





