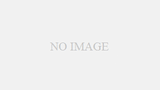今回は、ATFの歴史と法的位置づけ、主な任務、そして銃をめぐる議論の中での役割について掘り下げる。
ATF(酒・タバコ・火器・爆発物取締局:Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)は、その名のとおり、アルコール・タバコ・銃器・爆発物に関する法の執行を担う米国の連邦機関であるが、その設立は一度に成立したわけではなく、19世紀から20世紀を通じた段階的な制度発展の末に現在の姿に至っている。
起源は1791年のウイスキー税法(Whiskey Tax)にまでさかのぼる。当初は財務省(Department of the Treasury)に設けられた内国歳入局(Internal Revenue Service, IRS)の一部門として、酒類製造業者から税を徴収する任務が与えられていた。
これが後に違法な密造酒(ムーンシャイン)を取り締まるための武装部門へと発展し、やがてアルコール・タバコ関連の違法取引の捜査も担うようになった。
1920年代の禁酒法時代(Prohibition)には、アルコールの密造・密売が全米で急増し、これに対応するためアルコール税部(Alcohol Tax Unit, ATU)がIRS内に設置される。
禁酒法の廃止(1933年)後も、課税対象としての酒類やタバコの取締は継続され、この分野の法執行体制は恒常化された。
さらに、1934年の国家火器法(National Firearms Act)や1938年の連邦火器法(Federal Firearms Act)の制定により、銃器の製造・流通に対する規制が始まり、ATUの機能に「火器」の取り締まりが加わった。
その後、1968年の銃規制法(Gun Control Act)は、ATUの法的責任を大幅に拡大し、銃販売業者の登録制度や購入者の規制強化などが導入されることとなる。
こうした機能拡大を経て、1972年、IRSの一部門であったアルコール・タバコ・火器取締部(ATFD)は独立機関となり、「Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms(ATF)」として正式に設立された。この時点で、財務省の管轄下にあり、酒税・たばこ税の徴収と密造摘発、銃器犯罪の捜査を中心に活動していた。
その後、2001年の同時多発テロ事件を契機に、米国政府は法執行機関の再編を行い、2003年にはATFの爆発物・火器関連の法執行業務を司法省(Department of Justice)に移管し、現在の名称である「Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives(ATF)」が正式に用いられるようになった(略称は維持)。
なお、税務関連業務は一部が財務省のアルコール・タバコ課税貿易局(TTB)に分離された。
このように、ATFは財務官庁の税務執行機能から始まり、時代ごとの社会問題──禁酒法、銃規制、爆発物のテロ対策──への対応の中で、法執行機関としての性格を強めていった、極めて独特な発展史を持つ機関である。
今日では、爆破事件、連続銃撃事件、違法銃の流通、テロリストへの火器供与などに対して、FBIや地元警察と連携しながら積極的に捜査を展開している。
https://amateurmusenshikaku.com/security/fbi/
連邦制が規定するアメリカの法執行構造― 州政府と連邦政府の「二重構造」が生む捜査権限の境界線とは
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/us_renpou/
関連機関別 解説記事リンク一覧
-
FBI(連邦捜査局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/fbi/ -
USマーシャル(連邦保安官局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/united-states-marshals-service/ -
DEA(麻薬取締局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/dea/ -
ICE(移民・関税執行局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/ice/